2013年2月アーカイブ

イリアとオクタヴィアン 『イドメネオ』のユリナッチは文句なしに素晴らしい。その声の美質を遺憾なく発揮している。役と声の間にここまで親和性を感じさせる例も珍しい。このイリアがいれば、ほかのイリアはいらない、といいたくなるほどだ。音質は1956年に録音されたものの方が良いが、ジョン・プリッチャードの指揮が緩いのが難点である。 ユリナッチの美質は、『蝶々夫人』(1...
[続きを読む](2013.02.25)
ウィーンのプリマドンナ セーナ・ユリナッチの歌声は、豊かで深みがあり、あたたかく、声域全体のトーンが安定している。そこには作品のエッセンスを聴き手の耳の奥、心の奥にまで確実に届ける恩寵のような力も備わっている。何度繰り返し聴いても飽きることのない声、安心してどっぷり浸ることが出来る声である。 1921年10月24日、ユリナッチは医師の娘としてトラヴニクに生ま...
[続きを読む](2013.02.23)
デペッシュ・モード『ヴァイオレーター』1990年作品 もちろん、ほかにもエレクトロニック音楽の進化に深く関与したパイオニアは大勢いるけど、マシーンで鳴らす音楽をスタジアム・ロックの域へと昇華させたアーティストと言えば、やっぱりデペッシュ・モード(以下DM)だ。彼らにとっての決定的瞬間? 全米ブレイク作『ミュージック・フォー・ザ・マスィズ』(1988年)に伴う...
[続きを読む](2013.02.18)
その昔、YOKOHAMA BLACK CINEMA CLUBなる好事家の集まりがあり、筆者自身もメンバーのひとりで、不定期ながら、横浜某所で行われていた〈レアなブラック・ミュージックの映像を鑑賞する会〉に必ず参加していた。また、都内某所において、1980年代半ば頃、早稲田大学のサークル〈ブラック・ミュージック研究会(サークル名:ギャラクシー)〉の集まりがあ...
[続きを読む](2013.02.16)
アンジェイ・ムンクは1921年に生まれて戦争を生き延びたポーランドを代表する映画監督の一人である。ポーランド映画の奥深さを静かに知らしめるグレイトな企画だった〈ポーランド映画祭2012〉の中でも、ムンクの作品群はぼくの心臓に最も深々と刻まれた。 39歳で亡くなり、遺した長編映画は4本だけ。それにもかかわらず、『アンナと過ごした4日間』の監督として知られるイ...
[続きを読む](2013.02.14)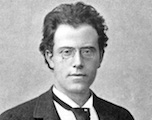
「悲劇的」を超えて 一番最初に聴いたマーラーの交響曲は第7番だった、という人はどれくらいいるのだろう。おそらくそこまで多くないのではないか。私の場合、誰にいわれたわけでもなく、何のガイドブックを読んだわけでもなく、結果的に第7番を最後に聴いた。そして、大袈裟にいえば、これまでほかの交響曲に親しんできたのは、第7番の世界に入るための準備であったかのような気持ち...
[続きを読む](2013.02.12)
多くのコーヒーショップで使われている小さな穴のあいた蓋を見たことがない、という人は少ないだろう。トラベラーリッド、ドリンキングリッドと呼ばれているやつである。かつてこの小さな穴を通してホットコーヒーを飲むことに抵抗を示す人が周りに沢山いた。今もいるかもしれないが、「いつ熱い液体が口に流れ込んでくるか分かりづらい」という不満をよく聞いたものである。しかし、ト...
[続きを読む](2013.02.09)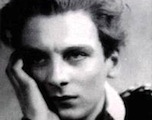
イギリス演劇史に名を残す名優、ジョン・ギールグッドが録音した『ハムレット』のレコードがある。何種類かあるようだが、私が持っているのは1957年に吹き込まれたもの。当時、ギールグッドは53歳。さすがに若々しさはないが、その音楽的な声(「絹にくるまれた銀のトランペット」と称えられた)を聞いていると、自然と『ハムレット』の世界に誘われる。ほかの俳優には模倣できな...
[続きを読む](2013.02.02)