2016年10月アーカイブ

今月会社を辞めた。私が担当していたフリーペーパーでは、ハロー!プロジェクトの連載やKEYTALKの連載のページを作ったり、『マッドマックス 怒りのデス・ロード』で巻頭記事を組んだりと、個人的にやりたかったこともいくつかできた。急遽企画したハロプロの新しい連載を最後まで見届けられないのは心残りだが、自分がしてきた仕事そのものには何の悔いもない。 いろいろあっ...
[続きを読む](2016.10.29)
ヘヴン17『ペントハウス・アンド・ペイヴメント』1981年作品 いわゆる「タイムレスネス」は、しばしば良質な音楽の条件に挙がる要素だ。しかし「(We Don't Need This)Fascist Groove Thang(こんなファシストのグルーヴはいらない)」と題された名曲が、リリースから35年も経った今もまるで昨日書かれたようなリアリティを醸すという事...
[続きを読む](2016.10.26)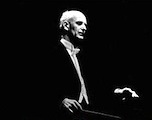
一回勝負に賭ける演奏 ヴィルヘルム・フルトヴェングラーが没入を重んじた指揮者だったことは、遺された録音や映像に接すればすぐに分かる。その手記にも、集中と没頭なき芸術が「芸術全般の悲劇の始まり」であると書かれている。彼にとって、単に楽譜に忠実なだけの演奏は非創造的であり、個性的な審美観を振り回す指揮は疑わしいものであった。「私にとって重要なのは、魂に訴えるか否...
[続きを読む](2016.10.19)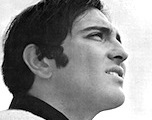
ミシェル・ローラン「サバの女王」(1967年) レイモン・ルフェーヴル楽団の「シバの女王」は1969年に日本でシングル・カットされ、同楽団の代表曲として知られるようになり、それと同時に、ムードミュージック界を象徴する名曲の一つになった。そのため、レコードを買うまで、私はレイモン・ルフェーヴルが作曲したものと思い込んでいた。 原曲は1967年にフランスで流行っ...
[続きを読む](2016.10.08)
山村聰は俳優として多くの映画に出演しただけでなく、一時は監督としても注目を浴びていた。その点で、歳の近い佐分利信と比較されることもあったが、2人を並べて語るのは難しい。佐分利は戦前から硬派の大スターだった人であり、キャリアの面でも、持ち味の面でも、山村とは異なる。 山村は1910年生まれ。東京帝国大学独文科を卒業後、大阪で演劇の道に進み、「二年足らずで、井...
[続きを読む](2016.10.01)