2012年7月アーカイブ

『狭き門』や『チボー家の人々』の翻訳で知られる仏文学者、山内義雄のエッセイ集『遠くにありて』の中に、「書籍の周囲」と題された短い文章がある。自身の読書愛を吐露した内容で、それによると、疎開先が空襲で焼けて書物を失い、4日間読書することなく過ごしたことがあるという。その「外から強いられた、何とも抗いようのない空白」について、山内は次のように書いている。「私は...
[続きを読む](2012.07.28)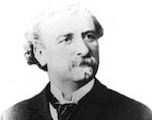
大作曲家も惚れたCMソング 口ずさんでいるだけで楽しい気分になる歌がある。その歌があれば、殺風景な道を歩いている間も、ピクニックで野山を闊歩しているような心持ちになってくる。「フニクリ・フニクラ」とは、まさにそんな歌である。 民謡のように親しまれている「フニクリ・フニクラ」だが、元々は1880年にヴェスヴィオ山に登山電車が敷設された時、観光客を呼ぶために作ら...
[続きを読む](2012.07.21)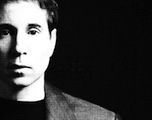
ポール・サイモン『グレイスランド』1986年作品 〈グレイスランド的〉という言い回しが音楽的ヴォキャブラリーの一部と化して、すでに久しい。西欧米のロック/ポップとその圏外の音楽のミクスチュアをざっくりと括るこの表現、そういう手法をとる若手アーティストが増えているせいか最近ますます頻繁にメディアで目にするのだが、リリースから四半世紀を経て本家本元が先頃再発され...
[続きを読む](2012.07.17)
9期と10期のメンバーは、2011年に加入したばかりなので、その才能には未知の部分が多い。私自身、ほぼ知らないに等しい状態にある。ただ、ある舞台を観て、個々の表現力の片鱗をうかがうことはできた。大槻ケンヂ原作の「ステーシーズ 少女再殺歌劇」である。話の山場が分散しているため、一度観ただけでは流れが掴みにくかったものの、各メンバーが頼もしい存在感を発揮し、あ...
[続きを読む](2012.07.14)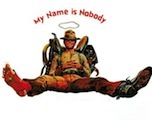
『荒野の用心棒』(1964年)によって始まったマカロニ・ウエスタン・ブーム。しかし、1960年代末頃から人気は翳り始める。「滅茶苦茶にリンチされてボロボロになった主人公が、最後に華麗なガンプレイで大逆転する」「争い合っている2大勢力を主人公が上手く操って共倒れさせ、大金をせしめる」、といったワンパターンな内容に観客が飽きてしまったのだ。そんな状況を受けて、...
[続きを読む](2012.07.13)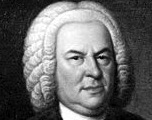
メロディー・メーカーとしてのバッハ バッハの4つの管弦楽組曲がいつ書かれたのか、はっきりしたことはわかっていない。ケーテン時代(1717年〜1723年)の作という説が有力ではあるが、第1番や第4番に関しては、それより後に作曲されたのではないかとみる人も多い。 また、「管弦楽組曲」というのも正式名称ではなく、当時は「序曲」と呼ばれていたらしい。なぜ「序曲」なの...
[続きを読む](2012.07.10)
2012年5月18日、モーニング娘。の新垣里沙と光井愛佳の卒業コンサートが日本武道館で行われた。あのタイミングで2人が一緒に卒業するという展開には驚かされたが、セレモニー自体は感動的なものだった。歌唱面でも、それまで本調子とはいい難かった田中れいなのコンディションが良かったこともあり、満足できる内容になっていた。とはいえ、グループ内で後輩たちを指導する立場...
[続きを読む](2012.07.07)
バロックの「疾走する悲しみ」 ストラヴィンスキーはヴィヴァルディのことを「同じ協奏曲を400曲も書いた」と評した。どれもこれも同じにしか聞こえないという皮肉である。たしかに、作品3『調和の霊感』、作品4『ラ・ストラヴァガンツァ』、『四季』を含む作品8『和声と創意への試み』、作品9『ラ・チェトラ』を目隠しで聴いて、どの曲がどの協奏曲集の何番目の作品の何楽章かい...
[続きを読む](2012.07.01)