
ウィリアム・カペル 〜ホロヴィッツを超えて〜
2012.01.30
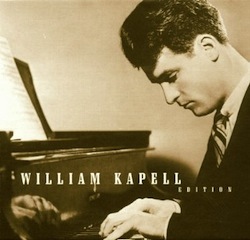
ウィリアム・カペルは1922年9月20日、ニューヨークに生まれた。彼にとっての最初のピアノ教師はドロテア・アンダーソン・ラフォレット。その後、フィラデルフィア音楽院でオルガ・サマロフに師事した。サマロフはストコフスキー元夫人。アメリカ人女性として初めてパリ音楽院に入学したピアニストで、フィラデルフィアで教鞭を執り、ロザリン・テューレック、ユージン・リスト、アレクシス・ワイセンベルクなどを指導した。彼女のもとで実力を開花させたカペルは、1941年にフィラデルフィア・ユース・コンクールで優勝、さらにナウムバーグ賞を受賞し、ニューヨークでリサイタル・デビュー。そのシーズン中に最高の演奏を行った30歳未満の音楽家に与えられるタウン・ホール賞も受賞した。
1942年は転機の年となった。夏、ニューヨーク・フィルの演奏会でハチャトゥリアンのピアノ協奏曲の独奏者に抜擢されたのである。この難曲でめざましい演奏を披露したカペルはセンセーションを巻き起こす。しかし、そのままコンサート活動に専念することなく、ジュリアード音楽院に入学し、研鑽を積んだ。1946年にヨーロッパ演奏旅行で成功、1948年に南米でも喝采を浴び、「ホロヴィッツの再来」と呼ばれる。1946年からRCAで録音活動も行われ(ライヴ録音なら1946年以前の演奏も残っている)、その人気と知名度は一気に上昇。1948年には結婚し、2人の子供に恵まれた。
当時の第一級ピアニストで、生まれも育ちもアメリカという人は少なかった。また、その恵まれたルックスが女性ファンを虜にしたこともあり、純アメリカ産の大ピアニストとして将来を期待されていた。が、1953年10月29日、オーストラリアで行われたリサイタルを終えてアメリカへ帰国する途中、カペルの乗っていた飛行機がキングズ・マウンテン山脈に激突。31歳の若さで落命した。
カペルの打鍵は岩盤を打ちつけるような強靭さを持ち、音色は明瞭な輪郭線を帯びて、曖昧さがない。その完璧な技術と輝かしい音色は、精神の美というよりアポロン的な肉体美を思わせる。たとえば、彼の代表的な録音であるハチャトゥリアンのピアノ協奏曲やラフマニノフの「パガニーニの主題による狂詩曲」。ここにはそういうアメリカン・ピアニズムとでも呼びたくなるような豪壮さと爽快さが横溢している。だから、ついテクニックに耳を奪われ、細やかなニュアンスを聴き落としてしまう。
しかし、カペルのアダージョの表現に惹かれてからは、私の見方はすっかり変わった。きっかけとなったのは、モーツァルトのピアノ・ソナタ第16番の第2楽章である。カペルはこのアダージョに執着していたようで、なんと3種類の録音(1種類はライヴ録音)が存在している。いずれも内なる声に耳を傾け、孤独に沈潜していくようなピアノだ。こんなにもセンシティヴな演奏をするピアニストだったのか、と目から鱗が落ちた私はあれこれ録音を探して聴くようになった。
その後、ショパンのマズルカ集と出会った。「マズルカはショパンの真髄」などといわれているが、それをカペルはまるで自分のために書かれた曲であるかのように弾く。無心に、そして自在に奏でられる、孤独なつぶやきのようなピアノ。まるでレコーディング・スタッフがいないスタジオで一人で録っているかのようだ。そこには輝かしい音色もなく、主張も、雄弁さも、色気もない。ただ音を自分の心の動きに寄り添わせるようにして弾いている。作品17-4、作品50-3はとくに絶品。それこそ多くのピアニストが録音している名曲だが、カペルの演奏はその中でもかなり上位に位置する名演ではないだろうか。私はこの「マズルカ集」を聴いていると、ホロヴィッツが録音したスカルラッティのソナタ集をどうしても思い出してしまう。切実な自己表現欲求と孤独な魂が透けてみえるのだ。
亡くなる1週間前に演奏されたショパンのピアノ・ソナタ第2番も、カペルの真価を知る上で聴き逃せない。純粋に、演奏として、圧倒的な重量感があり、美しい。その輝かしい音は、アメリカの太陽の明るさではなく、暗いところから不意に燃え盛る炎のような明るさを持っている。輝かしさの中にも漆黒の翳りがある。皮肉なことに、これは彼にとっての「葬送行進曲」になってしまったが、そういう悲劇と結びつけて考えるには、このピアノはあまりに力強く、生命力に溢れている。カペルが意識していたホロヴィッツを超えようとする迫力を感じずにはいられない。
カペルの録音の大半は、音質が古い。RCAなので当時の音としては良好だし、短い期間にこれだけ残してくれたことにまずは感謝すべきなのだが、これがもっと優秀な録音だったら、彼の音色の素朴な美しさやそこに含まれたニュアンスも、きちんと捉えることができただろう。直角に腕を振り落としているようなパワフルな演奏が割れ気味の音で炸裂しているのを聴いていても、このピアニストの才能が正確に伝わるとは思えない。1998年に出た9枚組のウィリアム・カペル・エディションは、リマスタリングによってだいぶ音質が向上しているが、これでもまだ不十分である。ラフマニノフのピアノ協奏曲第3番の嵐のように激しいライヴ演奏や、ミトロプーロスと組んだブラームスのピアノ協奏曲第1番の灼熱ライヴも、音質に難がある。という以前にカタログから消えてしまっている。これらの遺産が可能な限り高音質でよみがえることを希望してやまない。
(阿部十三)
【関連サイト】
William Kapell(英語)
ウィリアム・カペル(CD)
月別インデックス
- June 2024 [1]
- February 2024 [1]
- April 2023 [2]
- February 2023 [1]
- November 2022 [1]
- June 2022 [1]
- April 2022 [1]
- January 2022 [1]
- August 2021 [1]
- April 2021 [1]
- January 2021 [1]
- September 2020 [1]
- August 2020 [1]
- March 2020 [1]
- November 2019 [1]
- July 2019 [1]
- May 2019 [1]
- January 2019 [1]
- November 2018 [1]
- August 2018 [1]
- May 2018 [1]
- January 2018 [1]
- July 2017 [1]
- March 2017 [2]
- December 2016 [1]
- October 2016 [1]
- May 2016 [1]
- March 2016 [2]
- October 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- March 2015 [2]
- December 2014 [1]
- October 2014 [2]
- July 2014 [1]
- April 2014 [2]
- March 2014 [1]
- January 2014 [1]
- December 2013 [1]
- October 2013 [1]
- July 2013 [2]
- May 2013 [1]
- April 2013 [1]
- February 2013 [2]
- January 2013 [1]
- November 2012 [1]
- October 2012 [1]
- September 2012 [1]
- August 2012 [1]
- May 2012 [1]
- April 2012 [1]
- March 2012 [1]
- January 2012 [1]
- December 2011 [1]
- November 2011 [2]
- October 2011 [1]
- September 2011 [2]
- August 2011 [2]
- July 2011 [2]
- June 2011 [3]
- May 2011 [3]
- April 2011 [3]
- March 2011 [3]
- February 2011 [3]