
ルドルフ・ケンペ 〜真に精彩を放つもの〜
2019.07.04
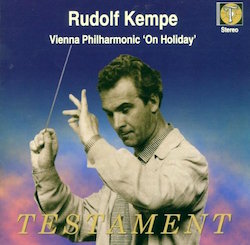
過剰でないからといって穏健というわけではない。楽器の音色は生き生きとしていて、色彩感があり、ほかの指揮者が強調しないフレーズを大胆に浮き上がらせることもある。その精彩の豊かさに接したら、穏健なんて言葉は出てこない。ただ、そういう演奏をオーケストラから自然に引き出している印象があり、強引な感じがしないのである。重たい強音ひとつとってみても、指揮者によっては威嚇的なポーズのように感じられることがあるけれど、ケンペの場合はわざとらしさがない。
こういった音楽性ゆえ、ケンペは様々なオーケストラに愛された。どこで指揮をしても楽団員の信頼を得て、観客や評論家からは好意的に迎えられていたようである。ドイツ以外ではイギリスで人気が高かった。
ルドルフ・ケンペは1910年6月14日、ドレスデン郊外に生まれ、まずオーボエ奏者としてスタートし、1934年に指揮者としてデビュー。ケムニッツ歌劇場(1946年〜1948年)、ワイマール国立歌劇場(1948年)などで研鑽を積んだ後、ドレスデン国立歌劇場(1949年〜1952年 音楽監督)、バイエルン国立歌劇場(1952年〜1954年 音楽監督)、ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団(1961年〜1963年、1966年〜1975年 首席指揮者)、チューリヒ・トーンハレ管弦楽団(1965年〜1972年 首席指揮者)、ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団(1967年〜1976年 首席指揮者)、BBC交響楽団(1975年〜1976年 首席指揮者)の顔として、重責を担っていた。さらに1950年代から1960年代前半にかけてベルリン・フィル、ウィーン・フィル、バンベルク響の指揮台に立ち、メトロポリタン・オペラやコヴェントガーデンでオペラを振り、1960年から1963年まではバイロイト音楽祭で『指環』を指揮していた。国際的にも華々しいキャリアだ。
ケンペの音楽は、いかにもドイツのカペルマイスターらしく造型がしっかりとしていて、響きが厚い。しかし、磨かれた音色でフレーズを美しく響かせ、オーケストラの自発性を促しながら音を躍動させる術を心得ている。鈍重な響きや病的な深刻さとは無縁だった。病気で活動を中断していたこともあるが、その前後の時期に録音された演奏を聴いても病の翳りを感じさせない。癌を患っていた晩年も、その芸格を崩すことはほとんどなかった。1976年5月12日、65歳の若さで世を去ったことが惜しまれる。
録音は豊富にある。ケンペといえば、まずはリヒャルト・シュトラウスだろう。メトで指揮した『薔薇の騎士』(1956年ライヴ録音)はこのオペラにふさわしい美演。リーザ・デラ・カーザがマルシャリンを歌っているのも好ポイントだ。コヴェントガーデンで指揮した『エレクトラ』(1958年ライヴ録音)は、過激になりがちなフィナーレであえてテンポを遅くして緊張感を持続させ、フレーズの生々しいうごめきを感じさせる。
シュターツカペレ・ドレスデンとの『ナクソス島のアリアドネ』(1968年録音)、同オーケストラとの「英雄の生涯」(1974年ライヴ録音)、ミュンヘン・フィルとの「メタモルフォーゼン」(1968年録音)は極上の名演で、ケンペが紡ぐ音楽には硬直したところが無く、旋律が息づくというのはこういうことかと思わされる。
誰もが知る作品も、ケンペの手にかかると精彩を帯びる。ドヴォルザークの「新世界」は、私はわりと苦手な作品で、くどいと感じることが多いのだが、ロイヤル・フィルによる1963年の録音は、緩急のつけ方が巧いだけでなく、強調するフレーズの選択も確かで、私には新鮮で感動的な演奏だった。
私がケンペに惹かれたのは、シューベルトの「ザ・グレイト」を聴いてからで、1950年にシュターツカペレ・ドレスデンを指揮した演奏に驚かされ、興味を持った。大好きな作品なので60種くらい録音を聴いているが、ケンペ盤の魅力が埋もれることはない。フレージングがしなやかで、颯爽としていて、みずみずしさと力強さを備えている。
ケンペの美点は小品集からもうかがえる。十八番だったレハールの「金と銀」は、ウィーン・フィルとシュターツカペレ・ドレスデンを指揮した録音があり、甲乙つけがたい。ウィーン・フィルを指揮したシューベルトの『ロザムンデ(抜粋)』、オッフェンバックの『天国と地獄』序曲(ともに1961年録音)は文句なしの名演で、この指揮者のこまやかさとユーモアを今日の聴き手に伝える。シュターツカペレ・ドレスデンを指揮した「ウィーンの森の物語」、「天体の音楽」(ともに1972年〜1973年録音)は、ウィーン・フィルと組んだものよりも音がきらきらしていてノリが良い。「ワルツは単調だ」と思っている人に聴いてほしい。
ミュンヘン・フィルとのブルックナーの交響曲第5番(1975年録音)、ロイヤル・ストックホルム・フィルとの交響曲第7番(1975年ライヴ録音)、チューリヒ・トーンハレ管との交響曲第8番(1971年録音)、ベルリン・フィルとのブラームスの『ドイツ・レクイエム』(1955年録音)、ミュンヘン・フィルとの「ハイドンの主題による変奏曲」(1975年録音)も素晴らしい。無理なく柔軟にクライマックスへと達する際の密度の濃いフォルテ、精妙に織り上げられた和音の連なりと、叙情性を重んじた豊かな音楽の流れに魅せられる。
プロムスで指揮したマーラーの「復活」(1972年ライヴ録音)の音源もある。オーケストラはミュンヘン・フィル。フィナーレでテンポをかなり速めるところがあるのだが、それが劇的な効果へと繋がっている。普通は、ここまでうまく行かない。ベルリン・フィルを指揮したベルリオーズの幻想交響曲(1959年録音)は遅いテンポで弦と木管の音色を丁寧に扱っているのが印象的だ。煮え切らないところもあるが(第4楽章)、不思議な魅力を持つ演奏だと思う。亡くなる3か月前にBBC響を指揮したブラームスの交響曲第4番(1976年ライヴ録音)は烈しい演奏。冒頭の啜り泣くような弦の響きは悽愴なほどで、万感胸に迫る。
ワーグナー関連の音源も充実している(ライヴ録音を含む)。特に有名なのは『ローエングリン』(1962年〜1963年録音)だろう。品のある表現で、ウィーン・フィルの響きがとにかく美しい。ただ、私がそれよりもお薦めしたいオペラの録音は、ドイツ語歌唱によるスメタナの『売られた花嫁』(1962年録音)。序曲の演奏から抜群の出来で、ワクワクさせられる。歌手も生き生きしている。ワクワクといえば、ウィーン・フィルを指揮したモーツァルトの序曲(1955年録音)があるのだが、これも心底楽しめる演奏になっていて、『フィガロの結婚』などは、軽快な序曲が終わった後、「なぜ続きが入っていないのだろう」と思ってしまうほど、これから始まるオペラへの期待を抱かせる。
ケンペは、己の美学を押し付けることなくオーケストラを導き、作品に本来あるべき精彩を与えることができた。その指揮は、ひたすら音楽に麗しい生命を吹き込もうとする誠実さと献身性を感じさせる。ケンペ自身の言によると、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管のオーボエ奏者だった期間に、最も印象的だった指揮者はオットー・クレンペラーだという。なるほど、木管を美しく響かせる術はクレンペラー譲りなのかもしれない。でも、それだけではない。ブルーノ・ワルター、ヴィルヘルム・フルトヴェングラー、フリッツ・ブッシュといった大指揮者からも多くのことを学んだのである。こういった偉大な先人たちの美点を、己の音楽性に合わせて抽出し、磨きをかけたものが、現在私たちが録音を通じて味わうことのできるケンペの芸術なのだ。
(阿部十三)
【関連サイト】
月別インデックス
- June 2024 [1]
- February 2024 [1]
- April 2023 [2]
- February 2023 [1]
- November 2022 [1]
- June 2022 [1]
- April 2022 [1]
- January 2022 [1]
- August 2021 [1]
- April 2021 [1]
- January 2021 [1]
- September 2020 [1]
- August 2020 [1]
- March 2020 [1]
- November 2019 [1]
- July 2019 [1]
- May 2019 [1]
- January 2019 [1]
- November 2018 [1]
- August 2018 [1]
- May 2018 [1]
- January 2018 [1]
- July 2017 [1]
- March 2017 [2]
- December 2016 [1]
- October 2016 [1]
- May 2016 [1]
- March 2016 [2]
- October 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- March 2015 [2]
- December 2014 [1]
- October 2014 [2]
- July 2014 [1]
- April 2014 [2]
- March 2014 [1]
- January 2014 [1]
- December 2013 [1]
- October 2013 [1]
- July 2013 [2]
- May 2013 [1]
- April 2013 [1]
- February 2013 [2]
- January 2013 [1]
- November 2012 [1]
- October 2012 [1]
- September 2012 [1]
- August 2012 [1]
- May 2012 [1]
- April 2012 [1]
- March 2012 [1]
- January 2012 [1]
- December 2011 [1]
- November 2011 [2]
- October 2011 [1]
- September 2011 [2]
- August 2011 [2]
- July 2011 [2]
- June 2011 [3]
- May 2011 [3]
- April 2011 [3]
- March 2011 [3]
- February 2011 [3]