2011年10月アーカイブ

大学時代の僕の遊び場と言えばライヴハウスであった。知らない人が沢山集まるコンパは苦手で、テニスやスキーの浮ついたムードにも馴染めず......という、我ながらキャンパスライフに不向きの性質の持ち主であった当時の僕にとって、唯一居心地の良さを感じられる空間がライヴハウスだったのだ。初めて行ったライヴハウスは、まだ小滝橋通り沿いにあった頃の新宿ロフト。そこは大...
[続きを読む](2011.10.29)
アンソニー・マンという名前は、せいぜい西部劇ファンが『ウィンチェスター銃'73』や『西部の人』の監督として記憶しているくらいではないだろうか。たしかにフィルモグラフィーを見ると西部劇が目立つ。ただ、このジャンルが縄張りというわけではない。フィルム・ノワールの名品『横丁』、グレン・ミラーの伝記映画『グレン・ミラー物語』、戦争映画の傑作『最前線』、スペクタクル...
[続きを読む](2011.10.25)
蒼井雄は昭和10年代に話題になった推理作家である。本名は藤田優三。1909年に生まれ、1975年に亡くなった。作家として独り立ちすることなく、関西配電の技師としてサラリーマン人生を送り、数えるほどしか作品を残さなかった。代表作は『船富家の惨劇』。1936年、これが春秋社の書き下ろし長編募集に一席で入選し、注目を集めた。蒼井を推した審査員は江戸川乱歩である。...
[続きを読む](2011.10.22)
理想主義者としてのドン・ファン 伝説のプレイボーイ、ドン・ファンの名が文学史に刻まれたのは、1630年に出版されたティルソ・デ・モリーナの『セビリアの色事師と石の招客』からである。ここに描かれているドン・ファンは、「俺の心の中にある最大の喜びは、何よりもまず女を誘惑して、相手の名誉を台無しにして棄てるってことさ」と言い放ち、欲望の赴くまま次々と女たちをたぶら...
[続きを読む](2011.10.20)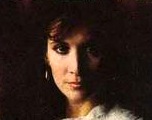
シャーリーン「愛はかげろうのように」(1982年/全米No.3、全英No.1) 〈一発屋〉を英語では〈One-hit wonder〉と表現する、ということを教えてくれたのは、米『ビルボード』誌のトップ40ヒットをデータ化した洋書だったと記憶している。日本語の〈一発屋〉にはどことなく嘲笑めいた響きを感じられるが、英語のそれは実に巧いことをいうものだ、と思った。...
[続きを読む](2011.10.17)
『女囚さそり』や『修羅雪姫』シリーズの存在だけでなく、梶芽衣子の歌も、僕はクエンティン・タランティーノの『キル・ビル』(2003年)を通じて知った。『キル・ビル』の劇中で、梶芽衣子の「修羅の花」(1973年)と「怨み節」(1972年)が使用されていたのだ。《死んでいた朝に とむらいの雪が降る》という、不吉な一節で始まる「修羅の花」、匕首を喉元に突きつけるか...
[続きを読む](2011.10.15)
僕はクエンティン・タランティーノと非常に気が合う。彼と会ったことはないのだが、絶対に仲良しになれると勝手に思っている。なにしろ彼の作品の元ネタは、僕の好みに合うものばかりなのだから。彼が映画を撮る度に挙がる元ネタは、僕にとって最高の映画ガイドとなっている。『女囚さそり』シリーズとの出会いも、タランティーノによってもたらされた。「『キル・ビル』の元ネタだから...
[続きを読む](2011.10.14)
ジネット・ヌヴーのヴァイオリンは胸を突き刺すような鋭い音で聴く者をとらえて離さない。フレーズのどこを切っても鮮血が飛び散りそうなほど熱い情熱が脈打っている。ただし、エモーショナルで尖った音だけがヌヴーの個性というわけではない。彼女の演奏家としての特性はむしろ、火を噴くような荒々しいパトスの奔出、集中力に支えられた逞しい造型感、油絵のような色彩感が統合された...
[続きを読む](2011.10.10)
夏に会社を移ってから生活サイクルが変わった。始業時間がこれまでより2時間早くなり、家から会社の距離も遠くなったので、7時には起きなければならない。一般的には、7時なんて早いうちに入らないのだろうが、20年近く夜型生活を送ってきた身には馴染みのない時間帯である。それでも、今のところは緊張感のおかげで起きている。夜も遅いので、体力がもつかどうか不安だ。 ある日...
[続きを読む](2011.10.08)
恍惚と狂気の果てに バッハを聴いても、モーツァルトを聴いても、ベートーヴェンを聴いても、あるいはマーラーやバルトークを聴いても、全く心が満たされないことがある。音楽が、というより、音楽を聴くという行為自体が、自分の心理状態とあまりにかけ離れているためである。そんな時はたいていどんな種類の音楽を聴いても満足できない。かといって、無音でいるのも物足りない。 そこ...
[続きを読む](2011.10.07)
一目見たら決して忘れられない俳優、それがリー・ヴァン・クリーフだ。僕が初めて彼の存在を知ったのは、小学生の頃にTVで観た『続・夕陽のガンマン』(1966年)だった。これはセルジオ・レオーネ監督とクリント・イーストウッドによるマカロニウエスタン3部作、通称「ドル三部作」の最後を飾った作品だ。リー・ヴァン・クリーフ演じる冷酷な殺し屋・エンジェルは、とにかく強烈...
[続きを読む](2011.10.05)
ジーザス・アンド・メリー・チェイン『サイコ・キャンディ』1985年発表 炸裂するフィードバック・ギター・ノイズと、甘美なメロディの融合ーーこの音楽スタイルの開拓者として、シューゲイザーからグランジ/オルタナまで、後に続くムーヴメントや数々のバンドに影響を与えてきた、ジーザス・アンド・メリー・チェイン。「キリストと聖母マリアとを結ぶ絆」という、意味深な宗教的冒...
[続きを読む](2011.10.03)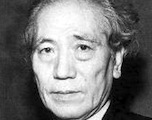
徳川夢声は大正から昭和にかけて活躍したマルチタレントである。マルチタレントというと「とりあえず何でもこなすけれど仕事の質は大して高くない」というイメージを持たれるかもしれない。が、この人の場合、それは当てはまらない。弁士としても、「対談まわし」としても、俳優としても傑物。小説の分野でも他に類を見ない独自の個性を発揮し、多くの作品を発表した。 元々は活動写真...
[続きを読む](2011.10.01)