2014年7月アーカイブ

ザ・プリテンダーズ『愛しのキッズ』1979年作品 「っつーか、男どもが、嫁がどうした子供がどうしたとかって言って、全然スケジュールを調整できなくて、待ってらんないし、しょーがないから独りでアルバム作ったってわけよ!」 このところ、御年62歳にして初のソロ・アルバム『Stockholm』を先頃発表したクリッシー・ハインドのインタヴューを、海外のラジオ番組などで...
[続きを読む](2014.07.31)
音による表現のエッセンス アントン・ヴェーベルンの「弦楽四重奏のための5つの楽章」は1909年に作曲された。作品番号は5。アルノルト・シェーンベルクのもとで研鑽を積んでいた頃、オペラの作曲計画が頓挫した後に起こった創作意欲の爆発を示す傑作である。まだ20代半ばだったヴェーベルンはここで調性的な世界から離れ、音の配列、強弱、音響、そして演奏法を徹底的に吟味し、...
[続きを読む](2014.07.25)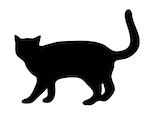
素人探偵、仁木兄妹の登場 仁木悦子の推理小説には、謎解きの面白さや緊迫感だけでなく、微笑ましい明るさ、軽快さがある。おどろおどろしさで背筋をぞくぞくさせる作風とは一線を画し、端正な文体で物語をテンポよく進行させ、しこりを残さず、あたたかい余韻で読者を包み込む。「探偵役」を務める人物たちも、犯罪者を捕らえてやるという正義感より、隠された謎を知りたいという好奇心...
[続きを読む](2014.07.19)
マライア・キャリー『バタフライ』1997年作品 筆者はマライア・キャリーのファンなので、彼女に対しては採点が甘いのかもしれないが、ただそんな贔屓目を抜きにしても、先頃登場した最新作『ミー。アイ・アム・マライア』は、どこかノスタルジックな気分にさせるいいアルバムだった。そう思った理由のひとつは、本人も認めている通り同作が自身の音楽的な歩みを辿るような内容で、特...
[続きを読む](2014.07.13)
指揮者の中の王 アルトゥーロ・トスカニーニは19世紀後半から20世紀半ばにかけて君臨したイタリアの大指揮者である。彼の登場により指揮者の地位、オペラの上演スタイル、オーケストラの演奏表現の在り方は大きく変わった。かのオットー・クレンペラーが「指揮者の中の王」と呼ぶほどその影響力は絶大だった。トスカニーニは単に指揮棒を振るだけの人ではなく、音楽監督ないし芸術監...
[続きを読む](2014.07.08)
観る者の目に焼きつくショット カメラの配置に関して、オーソンは天性の勘に恵まれていた。ピーター・ボグダノヴィッチによるインタビューでは、次のように語っている。「変幻自在が好きな私だが、カメラの位置に関してだけは唯一無二の場所があると思うし、それがどこかを即座に決めることができる。もし、即座に決められないとすると、それは撮るべきシーンの解釈、あるいは取り組み方...
[続きを読む](2014.07.03)
情熱はあくまでも監督業に オーソン・ウェルズの監督作には権力者の破滅や没落を描いたものが目立つ。『市民ケーン』(1941年)や『偉大なるアンバーソン家の人々』(1942年)はもちろんのこと、シェイクスピア原作の『マクベス』(1948年)や『オセロ』(1952年)、日本未公開の『秘められた過去(Mr. Arkadin)』(1955年)、ハリウッド最後の作品とな...
[続きを読む](2014.07.01)