2014年9月アーカイブ

ロジェ・マルタン・デュ・ガールの長編小説『チボー家の人々』のクライマックスをなす『1914年夏』は、市民が戦争の波に押し流されるまでの過程を鋭い目線でとらえているだけでなく、一つの大戦を成立させるメカニズムを心理的側面から生々しく浮き彫りにした文学として、今日の読者にも強い印象を与える。私たちは登場人物たちの言動を他人事とは思えないだろうし、自分ならどうす...
[続きを読む](2014.09.27)
溝口作品が置かれた状況 溝口健二監督の作品は半分以上現存していないと言われている。初期の『813』(1923年)や『血と霊』(1923年)はもちろん、サイレント時代に高く評価された『紙人形春の囁き』(1926年)も『狂恋の女師匠』(1927年)も観ることはできない。同時代人による論評とスチル写真から、どんな映画だったのか想像をふくらませるほかないのだ。サイレ...
[続きを読む](2014.09.20)
パルプ『コモン・ピープル』1995年作品 その感覚を「違和感」、もしくは「居心地悪さ」と評するべきなのか、パルプは枠からハミ出がちなバンドだった。間違いなく純英国的なセンスを備え、一般的にはブリット・ポップに括られることが多いものの、スウェードやブラーの面々と比べると世代的には少しばかり先輩。フロントマンでありリリシストのジャーヴィス・コッカーが前身バンドA...
[続きを読む](2014.09.15)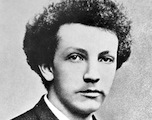
彼女が踊るとき、エロスと暴力は解放される 1891年にフランス語で書かれたオスカー・ワイルドの『サロメ』は、翌年サラ・ベルナール主演で上演される予定だったが、検閲官から上演禁止令が出て封印された。初演されたのは1896年になってからのことである。当時ワイルドは男色の罪で獄中にあった。 原作者が亡くなった翌年の1901年、マックス・ラインハルト演出による舞台が...
[続きを読む](2014.09.11)中将姫の伝説で知られる當麻寺に行くと、仁王門近くの梵鐘わきから美しい二上山を拝むことができる。以前私が訪れたときは曇天で、その愁いを帯びた空模様がまた二上山にはふさわしいように感じられたものである。この山に大津皇子が眠っている。 私が大津皇子に関心を抱いたのは、学生の頃、保田與重郎の「大津皇子の像」を読んでからである。これは毀誉褒貶甚だしい保田が遺した作品...
[続きを読む](2014.09.06)
バーバラ・スタンウィックの演技はひとつの理想である。常に軽々と役にフィットし、どんな難役であっても、気構えやストレスを微塵も感じさせない。むしろ難役であればあるほど輝きを増すのである。一例だけ挙げても、『ステラ・ダラス』(1937年)のステラ、『レディ・イヴ』(1941年)のジェーン、『群衆』(1941年)のアン、『教授と美女』(1941年)のオ・シェイ、...
[続きを読む](2014.09.01)