
ディヌ・リパッティ 〜ルーマニアから来た聖者〜
2012.05.23
「ディヌ・リパッティには聖者のような風格があった」ーーこれは有名なリパッティ論の冒頭を飾る一文である。執筆者はEMIの大プロデューサーであり、文筆家としても知られたウォルター・レッグ。その文章からは、リパッティの才能と人間性に対する敬愛の情が強い調子で伝わってくる。原稿は1951年に「追悼文」として発表されたが、今でもしばしばライナーノーツに使われており、リパッティのイメージ形成に影響を与えている。
そのイメージをまとめると、おそるべき天才で、人徳もあったが、あまりに病弱で、度々コーチゾンの注射を打ちながら奇跡のような録音を残し、夭折したピアニスト、という風になる。だが、私は初めてリパッティのピアノを聴いた時、このライナーノーツを読みながら一種違和感のようなものを覚えた。その時かけていたのは、1947年に録音されたグリーグのピアノ協奏曲イ短調。本当にこれが病人のピアノなのだろうか、と思った。とくに第1楽章のカデンツァ。氷山が眼前に迫ってくるようなその迫力、のけ反るような音圧を前に、私は知らず知らず息をひそめていた。第3楽章のフィナーレも力強く、輝かしい。鑑賞後、私はリパッティのことを病人として見ることができなくなっていた。
病気であるという情報は、時に、聴き手に冷静な判断力を失わせるものだ。実際以上の感動を誘うこともあるし、その芸術を認めないことがあたかも罪であるかのように思わせる場合もある。しかし、リパッティには元々そんなものは不要だったのだ。ディヌ・リパッティは天才だった。それだけで十分である。師ナディア・ブーランジェも次のように語っている。「彼(リパッティ)が病気であったためにいや増す憐憫の情は、切り捨てるべきだと思います」
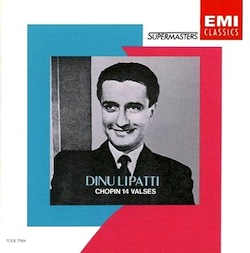 リパッティは、1917年3月19日、ルーマニアのブカレスト生まれ。病弱のため学校に行けず、家庭教師から必要な教育を受けた。フロリカ・ムシチェスクにピアノを習い、1934年、ウィーン国際コンクールで2位を獲得。この時リパッティを1位にしなかったことに抗議し、審査員を降りたのがアルフレッド・コルトーである。この事件は大きな話題となり、リパッティの名は世に広まった。コルトーの招きでパリに来てからは、指揮法をシャルル・ミュンシュに、作曲をポール・デュカス、ナディア・ブーランジェに学んだ。戦争勃発後はルーマニアに帰国するが、1943年にジュネーヴへ逃れる。戦後、ピアニストとして名声を確立。しかし病気のため活動に制限がかかり、思うようにリサイタルを開けなかった。1950年9月16日、ブザンソンで最後のリサイタルを開いた後、病状が悪化。同年12月2日、33歳で亡くなった。妻はピアノ教師のマドレーヌ・カンタキュゼーヌ。ベーラ・シキは弟子である。
リパッティは、1917年3月19日、ルーマニアのブカレスト生まれ。病弱のため学校に行けず、家庭教師から必要な教育を受けた。フロリカ・ムシチェスクにピアノを習い、1934年、ウィーン国際コンクールで2位を獲得。この時リパッティを1位にしなかったことに抗議し、審査員を降りたのがアルフレッド・コルトーである。この事件は大きな話題となり、リパッティの名は世に広まった。コルトーの招きでパリに来てからは、指揮法をシャルル・ミュンシュに、作曲をポール・デュカス、ナディア・ブーランジェに学んだ。戦争勃発後はルーマニアに帰国するが、1943年にジュネーヴへ逃れる。戦後、ピアニストとして名声を確立。しかし病気のため活動に制限がかかり、思うようにリサイタルを開けなかった。1950年9月16日、ブザンソンで最後のリサイタルを開いた後、病状が悪化。同年12月2日、33歳で亡くなった。妻はピアノ教師のマドレーヌ・カンタキュゼーヌ。ベーラ・シキは弟子である。
録音は少ないながらも名演揃いである。ただし、音質が良くない。本物の名演には音質の良し悪しなど関係ない、時代を超越して人の心に響くものだ、という声もあるだろう。私も音質にうるさいタイプの人間ではない。どちらかといえば、「そんなに文句をいうなら古い録音を聴かなければいい。私は聴くけど」というタイプだ。そんな私でも残念に感じてしまうほどの音質である。ピアニストにはそれぞれの音色がある。その音色が個性になる。ホロヴィッツにも、ギレリスにも、リヒテルにも、ミケランジェリにも、グールドにも、彼らの音色がある。それがリパッティの録音からは判別しにくい。輪郭がぼやけていたり、割れ気味だったり、ノイズがきつかったり、どこかに瑕がある。真の音色が曖昧である以上、ピアニストとしての特性を完璧に論じきるのは難しい。戦後間もない頃のEMIの録音なので仕方ないといってしまえばそれまでだが、実に大きな損失だと思う。
音質面を抜きにして、演奏の素晴らしさ、解釈の深さ、テクニックの鮮やかさを味わう分には何の問題もない。救いなのは、1950年9月16日に行われた最後のリサイタル(ブザンソン音楽祭)の録音が比較的良好な音質で残っていることである。これはリパッティという神々しい才能に恵まれたピアニストが、その才能をすり減らすことなく、ひたすら純化させていたことがよくわかる感動的な一枚である。音で詩を書くというのがどういうことなのか、このピアニストは教えてくれる。
J.S.バッハのパルティータ第1番の録音は、リパッティの美質を語る上でしばしば引き合いに出される名演である。演奏は2種類存在する。ひとつは1947年の録音、もうひとつはブザンソン音楽祭のライヴ録音だ。個人的には、ライヴ盤の方が聴き手の肌に迫ってくるような響きがあって好きだが、1947年の録音も「スタンダード」といいたくなるような名演である。スヴャトスラフ・リヒテルも、リパッティの弾いたパルティータ第1番を偏愛し、手記にその感想を記している。「この演奏で聴くパルティータは本当に驚くべきものだ」(1973年4月4日)
実際、ディヌ・リパッティの凄さは、独創的な解釈、斬新なビジョンを持ちながら、それを練り込めるだけ練って、自然な音楽の流れへと昇華し、いかにもそれがスタンダードであるかのように聴かせてしまうところにある。アゴーギクといい、フレージングといい、絶妙を通り越して必然の域にまで持っていく。バッハのパルティータに関しても、ピアノでこんな風に明瞭かつエレガントに音像化した例はあまりない。にもかかわらず、作為的なものや奇異さを感じさせない。かつてレオン・フライシャーは、第2次世界大戦後のピアニストで最も明確なビジョンを持ち、個性的な表現に秀でた人物として、ディヌ・リパッティとグレン・グールドの名を挙げていたが、それぞれの「個性的な表現」が目指したベクトルはさておき、解釈の清新さという意味でいえば、鋭い指摘である(ちなみにグールドを見出したのは、次世代のリパッティを探していたプロデューサー、デイヴィッド・オッペンハイムである)。
J.S.バッハの「主よ、人の望みの喜びよ」(マイラ・ヘス編)、ラヴェルの「道化師の朝の歌」、ショパンの「舟歌」と「14のワルツ」、グリーグとシューマンのピアノ協奏曲、モーツァルトのピアノ・ソナタ第8番、ピアノ協奏曲第21番......代表的な名演を挙げていったらきりがないが、私が一番鬼気迫るものを感じたのは、モーツァルトのピアノ協奏曲第21番である。暗い影と対峙するような第1楽章の決然たるピアノの響きに胸が熱くなる。リパッティの特性のひとつでもある、各声部を完全に独立した指で弾き分けるテクニックは、ラヴェルの「道化師の朝の歌」で十二分に堪能できる。これを聴いた後、ほかのピアニストでは満足できなくなるほど、耳に焼きつく鮮烈な演奏である。エネスコのヴァイオリン・ソナタ第3番の伴奏も秀逸。リパッティの代父だったエネスコの美しいヴァイオリンの音色と絡み合い、神秘的な雰囲気を漂わせている。
最後に、作曲家としてのリパッティにもふれておく。私が所有しているのは1995年にarchiphonから出た2枚組の録音集。このDISC2の方に、リパッティの作品が収録されている。その中の「古典派の様式によるピアノ小協奏曲」が良い。まどろみの美しさと洗練された構成が共存する佳作で、清潔な響きが心地よい。これは一時、私の目覚めの音楽だった。リパッティ自身の演奏しか聴いたことはないが、もっといろいろなピアニストに弾かれていい作品だと思う。
【関連サイト】
DINU LIPATTI(CD)
そのイメージをまとめると、おそるべき天才で、人徳もあったが、あまりに病弱で、度々コーチゾンの注射を打ちながら奇跡のような録音を残し、夭折したピアニスト、という風になる。だが、私は初めてリパッティのピアノを聴いた時、このライナーノーツを読みながら一種違和感のようなものを覚えた。その時かけていたのは、1947年に録音されたグリーグのピアノ協奏曲イ短調。本当にこれが病人のピアノなのだろうか、と思った。とくに第1楽章のカデンツァ。氷山が眼前に迫ってくるようなその迫力、のけ反るような音圧を前に、私は知らず知らず息をひそめていた。第3楽章のフィナーレも力強く、輝かしい。鑑賞後、私はリパッティのことを病人として見ることができなくなっていた。
病気であるという情報は、時に、聴き手に冷静な判断力を失わせるものだ。実際以上の感動を誘うこともあるし、その芸術を認めないことがあたかも罪であるかのように思わせる場合もある。しかし、リパッティには元々そんなものは不要だったのだ。ディヌ・リパッティは天才だった。それだけで十分である。師ナディア・ブーランジェも次のように語っている。「彼(リパッティ)が病気であったためにいや増す憐憫の情は、切り捨てるべきだと思います」
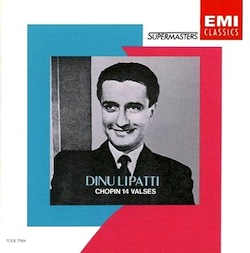
録音は少ないながらも名演揃いである。ただし、音質が良くない。本物の名演には音質の良し悪しなど関係ない、時代を超越して人の心に響くものだ、という声もあるだろう。私も音質にうるさいタイプの人間ではない。どちらかといえば、「そんなに文句をいうなら古い録音を聴かなければいい。私は聴くけど」というタイプだ。そんな私でも残念に感じてしまうほどの音質である。ピアニストにはそれぞれの音色がある。その音色が個性になる。ホロヴィッツにも、ギレリスにも、リヒテルにも、ミケランジェリにも、グールドにも、彼らの音色がある。それがリパッティの録音からは判別しにくい。輪郭がぼやけていたり、割れ気味だったり、ノイズがきつかったり、どこかに瑕がある。真の音色が曖昧である以上、ピアニストとしての特性を完璧に論じきるのは難しい。戦後間もない頃のEMIの録音なので仕方ないといってしまえばそれまでだが、実に大きな損失だと思う。
音質面を抜きにして、演奏の素晴らしさ、解釈の深さ、テクニックの鮮やかさを味わう分には何の問題もない。救いなのは、1950年9月16日に行われた最後のリサイタル(ブザンソン音楽祭)の録音が比較的良好な音質で残っていることである。これはリパッティという神々しい才能に恵まれたピアニストが、その才能をすり減らすことなく、ひたすら純化させていたことがよくわかる感動的な一枚である。音で詩を書くというのがどういうことなのか、このピアニストは教えてくれる。
J.S.バッハのパルティータ第1番の録音は、リパッティの美質を語る上でしばしば引き合いに出される名演である。演奏は2種類存在する。ひとつは1947年の録音、もうひとつはブザンソン音楽祭のライヴ録音だ。個人的には、ライヴ盤の方が聴き手の肌に迫ってくるような響きがあって好きだが、1947年の録音も「スタンダード」といいたくなるような名演である。スヴャトスラフ・リヒテルも、リパッティの弾いたパルティータ第1番を偏愛し、手記にその感想を記している。「この演奏で聴くパルティータは本当に驚くべきものだ」(1973年4月4日)
実際、ディヌ・リパッティの凄さは、独創的な解釈、斬新なビジョンを持ちながら、それを練り込めるだけ練って、自然な音楽の流れへと昇華し、いかにもそれがスタンダードであるかのように聴かせてしまうところにある。アゴーギクといい、フレージングといい、絶妙を通り越して必然の域にまで持っていく。バッハのパルティータに関しても、ピアノでこんな風に明瞭かつエレガントに音像化した例はあまりない。にもかかわらず、作為的なものや奇異さを感じさせない。かつてレオン・フライシャーは、第2次世界大戦後のピアニストで最も明確なビジョンを持ち、個性的な表現に秀でた人物として、ディヌ・リパッティとグレン・グールドの名を挙げていたが、それぞれの「個性的な表現」が目指したベクトルはさておき、解釈の清新さという意味でいえば、鋭い指摘である(ちなみにグールドを見出したのは、次世代のリパッティを探していたプロデューサー、デイヴィッド・オッペンハイムである)。
J.S.バッハの「主よ、人の望みの喜びよ」(マイラ・ヘス編)、ラヴェルの「道化師の朝の歌」、ショパンの「舟歌」と「14のワルツ」、グリーグとシューマンのピアノ協奏曲、モーツァルトのピアノ・ソナタ第8番、ピアノ協奏曲第21番......代表的な名演を挙げていったらきりがないが、私が一番鬼気迫るものを感じたのは、モーツァルトのピアノ協奏曲第21番である。暗い影と対峙するような第1楽章の決然たるピアノの響きに胸が熱くなる。リパッティの特性のひとつでもある、各声部を完全に独立した指で弾き分けるテクニックは、ラヴェルの「道化師の朝の歌」で十二分に堪能できる。これを聴いた後、ほかのピアニストでは満足できなくなるほど、耳に焼きつく鮮烈な演奏である。エネスコのヴァイオリン・ソナタ第3番の伴奏も秀逸。リパッティの代父だったエネスコの美しいヴァイオリンの音色と絡み合い、神秘的な雰囲気を漂わせている。
最後に、作曲家としてのリパッティにもふれておく。私が所有しているのは1995年にarchiphonから出た2枚組の録音集。このDISC2の方に、リパッティの作品が収録されている。その中の「古典派の様式によるピアノ小協奏曲」が良い。まどろみの美しさと洗練された構成が共存する佳作で、清潔な響きが心地よい。これは一時、私の目覚めの音楽だった。リパッティ自身の演奏しか聴いたことはないが、もっといろいろなピアニストに弾かれていい作品だと思う。
(阿部十三)
DINU LIPATTI(CD)
月別インデックス
- June 2024 [1]
- February 2024 [1]
- April 2023 [2]
- February 2023 [1]
- November 2022 [1]
- June 2022 [1]
- April 2022 [1]
- January 2022 [1]
- August 2021 [1]
- April 2021 [1]
- January 2021 [1]
- September 2020 [1]
- August 2020 [1]
- March 2020 [1]
- November 2019 [1]
- July 2019 [1]
- May 2019 [1]
- January 2019 [1]
- November 2018 [1]
- August 2018 [1]
- May 2018 [1]
- January 2018 [1]
- July 2017 [1]
- March 2017 [2]
- December 2016 [1]
- October 2016 [1]
- May 2016 [1]
- March 2016 [2]
- October 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- March 2015 [2]
- December 2014 [1]
- October 2014 [2]
- July 2014 [1]
- April 2014 [2]
- March 2014 [1]
- January 2014 [1]
- December 2013 [1]
- October 2013 [1]
- July 2013 [2]
- May 2013 [1]
- April 2013 [1]
- February 2013 [2]
- January 2013 [1]
- November 2012 [1]
- October 2012 [1]
- September 2012 [1]
- August 2012 [1]
- May 2012 [1]
- April 2012 [1]
- March 2012 [1]
- January 2012 [1]
- December 2011 [1]
- November 2011 [2]
- October 2011 [1]
- September 2011 [2]
- August 2011 [2]
- July 2011 [2]
- June 2011 [3]
- May 2011 [3]
- April 2011 [3]
- March 2011 [3]
- February 2011 [3]