
ヘルベルト・フォン・カラヤンについて
2014.10.02
相反する評価
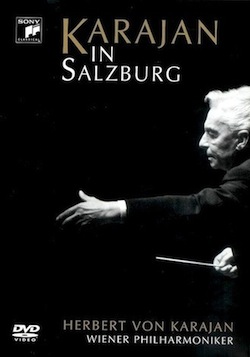 ヘルベルト・フォン・カラヤン生誕100周年の折、仕事の関係で、私は可能限り伝記や評論に目を通した。この指揮者に関する資料は多すぎるほど多く存在する。賛美に徹したものもあれば、批判に徹したものもある。しかし、そこに記されている評価のポイントは大体において同じである。それを肯定するか否定するかの違いが溝を生んでいるのだ。その最大のポイントは、性格的な面と音楽的な面それぞれにある。前者はカラヤンの権力志向と自己演出、後者は快楽原則に従ったような演奏のなめらかさ、美しさである。
ヘルベルト・フォン・カラヤン生誕100周年の折、仕事の関係で、私は可能限り伝記や評論に目を通した。この指揮者に関する資料は多すぎるほど多く存在する。賛美に徹したものもあれば、批判に徹したものもある。しかし、そこに記されている評価のポイントは大体において同じである。それを肯定するか否定するかの違いが溝を生んでいるのだ。その最大のポイントは、性格的な面と音楽的な面それぞれにある。前者はカラヤンの権力志向と自己演出、後者は快楽原則に従ったような演奏のなめらかさ、美しさである。
あまり指摘されないことだが、今日のカラヤン批評の周辺にはどのように批判しても許容される雰囲気がある。ほかの大指揮者に対して言おうものなら、どんなしっぺ返しが待っているか分からないことでも、カラヤンに対しては言えるのだ。これはフェアではない。たしかにカラヤン賛美には盲信的なものも存在するが、アンチが図に乗ってカラヤンを批判するのを目の当たりにすること以上に不快なものはない。
カラヤンの評価をめぐるズレの発端は、この指揮者を万能人に仕立てるような奇妙な演出から生じているのではないか、と思うことがある。彼がスキーやテニスを得意とするスポーツマンであったこと、スポーツカー、オートバイ、ヨット、ヘリコプター、ジェット機を操るアクティヴな人物であったこと、そしてヨガに凝り、その呼吸法を修得していたらしいことは、ほとんどの伝記に書かれている。これらの要素が、カラヤンの指揮法に影響を及ぼさなかったとは言わない。しかし、そのような観点から論じれば論じるほど、ただでさえルックスに恵まれ、目を閉じて指揮をするカラヤンのカリスマティックなイメージに、モダンな要素やミステリアスな要素を過度に付加し、音楽の核について語るスタンスから遠ざからせていくような危惧を抱くことが、少なくとも私にはある。カラヤン自身は明らかにそういった自己演出を好んでいたが、後世に生きる我々がそこに乗っかる必要はない。
カラヤンの録音
かくいう私は、中学2年生の時にカラヤンが指揮する第九(1962年録音)を聴いてファンになり、しばらくしてから距離を置き、また好きになり、距離を置き、やはり凄い指揮者だと思い直す、ということを何度か繰り返している。ただ、そんな風に流動的なカラヤン観を持ちながらも、これだけは誰がなんと言おうと変わらぬ価値を持つ遺産だと断言できる録音を知っている。それは「スケーターズ・ワルツ」「トリッチ・トラッチ・ポルカ」等を収録した『プロムナード・コンサート』(1953年〜1955年録音)、モーツァルトのホルン協奏曲集(1953年録音)、プロコフィエフの『ピーターと狼』(1956年〜1957年録音)、チャイコフスキーの『白鳥の湖』の抜粋(1959年録音)、ホルストの『惑星』(1961年録音、1981年録音)、ハイドンの交響曲第104番の第2楽章(1963年録音)、リムスキー=コルサコフの『シェへラザード』(1967年録音)、新ウィーン楽派管弦楽曲集(1972年〜1974年録音)、R.シュトラウスの『4つの最後の歌』(1973年録音)、『ツァラトストラはかく語りき』(1973年録音)、シベリウスの交響曲第5番(1976年録音)、ショスタコーヴィチの交響曲第10番(1981年録音)、ブルックナーの交響曲第7番の第3楽章(1989年録音)である。ここに、オペラやコンサートのライヴ音源、映像作品を加えると、およそ倍の数になる。
それでもカラヤンの厖大なディスコグラフィからすれば、僅かな数である。あれが入っていないのはおかしい、これが入っていないのもおかしい、と言われることは予想できる。しかし、ここに挙げた録音は、カラヤンを否定する人でも認めざるを得ない名演ないし秀演である。これらを否定する人は、カラヤンを否定するために識別力まで失っていると言わざるを得ない、その最小限のラインナップである。
カラヤンの音楽性
カラヤンは進取の人だった。レコード、デジタル録音、CD、映像メディアをいち早く重視し、これらを最大限活用することに情熱を注いだ。総売上枚数が1億枚を超えると言われてからすでに久しい。彼のレコードが受け入れられた要因としては、「鉱脈占い師的な本能」(ウォルター・レッグ)を発揮し、どんな作品からも美しい旋律線を紡ぎ出すことができたこと、スタイリッシュな流線型サウンドが大衆の耳をひきつけたことなどが挙げられるが、それと同時に、お抱え記者やお抱えカメラマンを使った「カラヤン・ブランド」のイメージ戦略が助けになったことも間違いない。皮肉ではなく、彼はそのイメージに見合うだけの内容を持つ音楽を提供してきたのである。
ここで避けておきたいのは、カラヤンをスタンダードとする過ちである。人は売れているもの、人気のあるものに判断基準を置きたがるが、忌憚なく言って、カラヤンは伝統的なカペルマイスターの系譜に連なりながら、自己流の音楽をやった人である。スタンダードとするには、あまりにもレガートが過剰であり、リズムやアンサンブルの細かいズレに(意外なほど)鷹揚である。いや、鷹揚と評するのは正確ではないかもしれない。おそらくカラヤンは、自分の体にしみ込んだ拍節感と後天的なレガート志向の噛み合わせから時折生じるズレを、音楽の大きな流れの中でダイナミズムや高揚感に還元させることができると考えていたのだろう。そうでなければ何度でも録り直したに違いない。そういうやり方は、たしかに多くの成功例を生んだが、モーツァルトのいくつかのシンフォニーのように気持ちが入っているとは到底思えない演奏を生むこともあった。
目を閉じて指揮をするスタイルも異様である。好意的にそのメリットを挙げることができたとしても、実践的なものとは言えない。つまるところ、カラヤンは己の手や腕の動きから放たれる伝播力に絶対の自信を持っていたのだ。これは神秘主義の態度に近いと言える。一方で、作品から微妙な陰影やゴツゴツした角を取り去り、重厚でどっしりとした低音を保ちながら、聴きやすいものに仕立てる合理主義的な面も備えていた。この特異な美意識を持つ、合理主義と神秘主義のアマルガムのような存在を指揮者のスタンダードとみなすことには無理がある。
カラヤンとクラウス
カラヤンは、自身の目指す音楽的境地について、「私が常に到達したいと望んでいたのは、フルトヴェングラーの夢想とトスカニーニの厳密さを結びつけた境地だった」と語っていた。刺激を受けた指揮者として、ヴィクトル・デ・サバタやヴァーツラフ・ターリヒの名前を挙げていたこともある。しかし、若き日のカラヤンがひそかに憧れ、現実的な意味で目標としていたのは、おそらくクレメンス・クラウスである。ウィーン・フィル最後の常任指揮者であるこの人物は、カラヤンが学生だった頃、昇り龍のような存在だった。そして、ナチス時代にウィーン国立歌劇場、ベルリン国立歌劇場、バイエルン国立歌劇場の総監督のポストを歴任した。リヒャルト・シュトラウスから信頼を寄せられ、『カプリッチョ』の台本を共作したことでも知られている。
レパートリーの面でも、気質の面でも、キャリアの築き方の面でも、クラウスとカラヤンには似ているところが少なくない。まず2人ともリヒャルト・シュトラウスの作品を最も得意としていた。そして、すぐれたワーグナー指揮者でもあった。大作ではないポピュラーな小品を指揮して聴き手を十分満足させる腕も持っていた。貴族意識を持ち、自尊心が高く、取り澄ました外見のイメージを保つ反面、時折コンサートで鬼気迫るような激しい指揮をしてみせた。聴衆からの人気も高かったし、ナチス時代に重用されていたことも共通している。カラヤンがベルリン・フィルの首席指揮者になり、天下人となったのが、クラウスが亡くなった後であったことを考えると、世代交代の配剤というものに思いを馳せずにはいられなくなる。
【関連サイト】
HERBERT VON KARAJAN
ヘルベルト・フォン・カラヤンについて [続き]
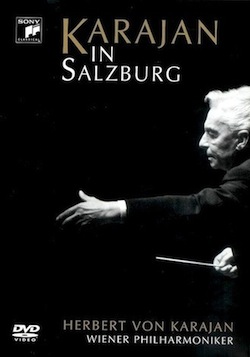
あまり指摘されないことだが、今日のカラヤン批評の周辺にはどのように批判しても許容される雰囲気がある。ほかの大指揮者に対して言おうものなら、どんなしっぺ返しが待っているか分からないことでも、カラヤンに対しては言えるのだ。これはフェアではない。たしかにカラヤン賛美には盲信的なものも存在するが、アンチが図に乗ってカラヤンを批判するのを目の当たりにすること以上に不快なものはない。
カラヤンの評価をめぐるズレの発端は、この指揮者を万能人に仕立てるような奇妙な演出から生じているのではないか、と思うことがある。彼がスキーやテニスを得意とするスポーツマンであったこと、スポーツカー、オートバイ、ヨット、ヘリコプター、ジェット機を操るアクティヴな人物であったこと、そしてヨガに凝り、その呼吸法を修得していたらしいことは、ほとんどの伝記に書かれている。これらの要素が、カラヤンの指揮法に影響を及ぼさなかったとは言わない。しかし、そのような観点から論じれば論じるほど、ただでさえルックスに恵まれ、目を閉じて指揮をするカラヤンのカリスマティックなイメージに、モダンな要素やミステリアスな要素を過度に付加し、音楽の核について語るスタンスから遠ざからせていくような危惧を抱くことが、少なくとも私にはある。カラヤン自身は明らかにそういった自己演出を好んでいたが、後世に生きる我々がそこに乗っかる必要はない。
カラヤンの録音
かくいう私は、中学2年生の時にカラヤンが指揮する第九(1962年録音)を聴いてファンになり、しばらくしてから距離を置き、また好きになり、距離を置き、やはり凄い指揮者だと思い直す、ということを何度か繰り返している。ただ、そんな風に流動的なカラヤン観を持ちながらも、これだけは誰がなんと言おうと変わらぬ価値を持つ遺産だと断言できる録音を知っている。それは「スケーターズ・ワルツ」「トリッチ・トラッチ・ポルカ」等を収録した『プロムナード・コンサート』(1953年〜1955年録音)、モーツァルトのホルン協奏曲集(1953年録音)、プロコフィエフの『ピーターと狼』(1956年〜1957年録音)、チャイコフスキーの『白鳥の湖』の抜粋(1959年録音)、ホルストの『惑星』(1961年録音、1981年録音)、ハイドンの交響曲第104番の第2楽章(1963年録音)、リムスキー=コルサコフの『シェへラザード』(1967年録音)、新ウィーン楽派管弦楽曲集(1972年〜1974年録音)、R.シュトラウスの『4つの最後の歌』(1973年録音)、『ツァラトストラはかく語りき』(1973年録音)、シベリウスの交響曲第5番(1976年録音)、ショスタコーヴィチの交響曲第10番(1981年録音)、ブルックナーの交響曲第7番の第3楽章(1989年録音)である。ここに、オペラやコンサートのライヴ音源、映像作品を加えると、およそ倍の数になる。
それでもカラヤンの厖大なディスコグラフィからすれば、僅かな数である。あれが入っていないのはおかしい、これが入っていないのもおかしい、と言われることは予想できる。しかし、ここに挙げた録音は、カラヤンを否定する人でも認めざるを得ない名演ないし秀演である。これらを否定する人は、カラヤンを否定するために識別力まで失っていると言わざるを得ない、その最小限のラインナップである。
カラヤンの音楽性
カラヤンは進取の人だった。レコード、デジタル録音、CD、映像メディアをいち早く重視し、これらを最大限活用することに情熱を注いだ。総売上枚数が1億枚を超えると言われてからすでに久しい。彼のレコードが受け入れられた要因としては、「鉱脈占い師的な本能」(ウォルター・レッグ)を発揮し、どんな作品からも美しい旋律線を紡ぎ出すことができたこと、スタイリッシュな流線型サウンドが大衆の耳をひきつけたことなどが挙げられるが、それと同時に、お抱え記者やお抱えカメラマンを使った「カラヤン・ブランド」のイメージ戦略が助けになったことも間違いない。皮肉ではなく、彼はそのイメージに見合うだけの内容を持つ音楽を提供してきたのである。
ここで避けておきたいのは、カラヤンをスタンダードとする過ちである。人は売れているもの、人気のあるものに判断基準を置きたがるが、忌憚なく言って、カラヤンは伝統的なカペルマイスターの系譜に連なりながら、自己流の音楽をやった人である。スタンダードとするには、あまりにもレガートが過剰であり、リズムやアンサンブルの細かいズレに(意外なほど)鷹揚である。いや、鷹揚と評するのは正確ではないかもしれない。おそらくカラヤンは、自分の体にしみ込んだ拍節感と後天的なレガート志向の噛み合わせから時折生じるズレを、音楽の大きな流れの中でダイナミズムや高揚感に還元させることができると考えていたのだろう。そうでなければ何度でも録り直したに違いない。そういうやり方は、たしかに多くの成功例を生んだが、モーツァルトのいくつかのシンフォニーのように気持ちが入っているとは到底思えない演奏を生むこともあった。
目を閉じて指揮をするスタイルも異様である。好意的にそのメリットを挙げることができたとしても、実践的なものとは言えない。つまるところ、カラヤンは己の手や腕の動きから放たれる伝播力に絶対の自信を持っていたのだ。これは神秘主義の態度に近いと言える。一方で、作品から微妙な陰影やゴツゴツした角を取り去り、重厚でどっしりとした低音を保ちながら、聴きやすいものに仕立てる合理主義的な面も備えていた。この特異な美意識を持つ、合理主義と神秘主義のアマルガムのような存在を指揮者のスタンダードとみなすことには無理がある。
カラヤンとクラウス
カラヤンは、自身の目指す音楽的境地について、「私が常に到達したいと望んでいたのは、フルトヴェングラーの夢想とトスカニーニの厳密さを結びつけた境地だった」と語っていた。刺激を受けた指揮者として、ヴィクトル・デ・サバタやヴァーツラフ・ターリヒの名前を挙げていたこともある。しかし、若き日のカラヤンがひそかに憧れ、現実的な意味で目標としていたのは、おそらくクレメンス・クラウスである。ウィーン・フィル最後の常任指揮者であるこの人物は、カラヤンが学生だった頃、昇り龍のような存在だった。そして、ナチス時代にウィーン国立歌劇場、ベルリン国立歌劇場、バイエルン国立歌劇場の総監督のポストを歴任した。リヒャルト・シュトラウスから信頼を寄せられ、『カプリッチョ』の台本を共作したことでも知られている。
レパートリーの面でも、気質の面でも、キャリアの築き方の面でも、クラウスとカラヤンには似ているところが少なくない。まず2人ともリヒャルト・シュトラウスの作品を最も得意としていた。そして、すぐれたワーグナー指揮者でもあった。大作ではないポピュラーな小品を指揮して聴き手を十分満足させる腕も持っていた。貴族意識を持ち、自尊心が高く、取り澄ました外見のイメージを保つ反面、時折コンサートで鬼気迫るような激しい指揮をしてみせた。聴衆からの人気も高かったし、ナチス時代に重用されていたことも共通している。カラヤンがベルリン・フィルの首席指揮者になり、天下人となったのが、クラウスが亡くなった後であったことを考えると、世代交代の配剤というものに思いを馳せずにはいられなくなる。
続く
【関連サイト】
HERBERT VON KARAJAN
ヘルベルト・フォン・カラヤンについて [続き]
月別インデックス
- June 2024 [1]
- February 2024 [1]
- April 2023 [2]
- February 2023 [1]
- November 2022 [1]
- June 2022 [1]
- April 2022 [1]
- January 2022 [1]
- August 2021 [1]
- April 2021 [1]
- January 2021 [1]
- September 2020 [1]
- August 2020 [1]
- March 2020 [1]
- November 2019 [1]
- July 2019 [1]
- May 2019 [1]
- January 2019 [1]
- November 2018 [1]
- August 2018 [1]
- May 2018 [1]
- January 2018 [1]
- July 2017 [1]
- March 2017 [2]
- December 2016 [1]
- October 2016 [1]
- May 2016 [1]
- March 2016 [2]
- October 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- March 2015 [2]
- December 2014 [1]
- October 2014 [2]
- July 2014 [1]
- April 2014 [2]
- March 2014 [1]
- January 2014 [1]
- December 2013 [1]
- October 2013 [1]
- July 2013 [2]
- May 2013 [1]
- April 2013 [1]
- February 2013 [2]
- January 2013 [1]
- November 2012 [1]
- October 2012 [1]
- September 2012 [1]
- August 2012 [1]
- May 2012 [1]
- April 2012 [1]
- March 2012 [1]
- January 2012 [1]
- December 2011 [1]
- November 2011 [2]
- October 2011 [1]
- September 2011 [2]
- August 2011 [2]
- July 2011 [2]
- June 2011 [3]
- May 2011 [3]
- April 2011 [3]
- March 2011 [3]
- February 2011 [3]