
オットー・クレンペラー 〜大器の音楽〜 [続き]
2016.03.21
クレンペラーの音楽
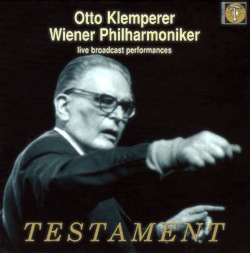 木管を強調させるやり方は、クレンペラーが意識して行っていたことである。何しろ「木管がきこえるということがもっとも重要なのです」とまで言い切っているのだ。その傾向が昔からあったことは、1928年に録音されたR.シュトラウスの「7つのヴェールの踊り」を聴くとわかる。これは極めて貴重な音源だ。録音年代を忘れるほど音質が良いこともあり、ぞくぞくするほど官能的な木管の音色が、悩ましい光沢と曲線の幻像となって聴き手を刺激する。
木管を強調させるやり方は、クレンペラーが意識して行っていたことである。何しろ「木管がきこえるということがもっとも重要なのです」とまで言い切っているのだ。その傾向が昔からあったことは、1928年に録音されたR.シュトラウスの「7つのヴェールの踊り」を聴くとわかる。これは極めて貴重な音源だ。録音年代を忘れるほど音質が良いこともあり、ぞくぞくするほど官能的な木管の音色が、悩ましい光沢と曲線の幻像となって聴き手を刺激する。
むろん、クレンペラーは木管だけでなく弦楽器の響きを際立たせる術も心得ている。ヘンデルの合奏協奏曲、モーツァルトの「アダージョとフーガ」、先に挙げたベートーヴェンの交響曲第7番第2楽章、「大フーガ」、ワーグナーの「ジークフリート牧歌」、R.シュトラウスの「メタモルフォーゼン」など、弦の響かせ方はそれぞれ異なるが、ここまで美しい演奏はなかなか聴けるものではない。余計な表情をつけず、楽器そのものが持つ響きをドラスティックに追求しているかのようだ。そこに荘厳な声楽が加わると、J.S.バッハの『ミサ曲ロ短調』のごとき大演奏になる。
1960年代以降、とくにフィルハーモニア管がニュー・フィルハーモニア管に改名してからの演奏では、テンポの遅さが目立つようになるが、クレンペラー自身は「わたしは前よりも遅いとは思いません」と言っている。1955年、1960年、1968年に録音されたベートーヴェンの交響曲第7番を聴き比べるまでもなく、この言葉を額面通りに受け取ることはできない。彼は同じような演奏を繰り返すことに意味を感じておらず、タイムウォッチで計測できる速度にも興味がないのである。おそらく作曲家でもあった自身の立場から(交響曲も書いている)、楽譜に記された音符をより吟味し、強調する方向性を選んだのだろう。この時期には、マーラーの交響曲第7番のような録音も登場している。これは音符の妖精たちが標本にされた陳列棚。聴いていて不安になるほど遅くて不気味だが、音楽を連続写真で見るような面白さがある。いずれにしても、私たちはこの指揮者の存在を介して、ほかの指揮者とは(作品によっては過去の彼自身とも)全く異なるテンポで、作曲家の世界に迫ることができるのである。
大器の録音
クレンペラーの録音は多い。そして、その全部とは言わないまでも、大半が特筆すべき名演奏である。モーツァルトとベートーヴェンの作品だけでも、少なからぬセッション録音が遺されているが、駄演は存在しない。台詞のない『魔笛』も、ジングシュピールという感じではないが、天才の書いた音楽の構造が透けて見えるようで鳥肌が立つ。『ミサ・ソレムニス』の言語を絶する偉容も、就中、「クレド」と「アニュス・デイ」に顕著である。メンデルスゾーンの交響曲第3番「スコットランド」やチャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」もため息が出るほど美しい。作品のイメージに一石投じるようなソノリティーがこれらの演奏にはある。ストラヴィンスキーの「プルチネルラ」組曲も超名演。セレナータでは「クレンペラーの木管」をほとんど耽美的な感覚で味わえる。協奏曲の録音だと、アラン・シヴィルとのモーツァルトのホルン協奏曲、ダヴィッド・オイストラフとのブラームスのヴァイオリン協奏曲などがあり、名演奏として知られている。
得意としていたワーグナーのオペラの中では、『さまよえるオランダ人』と『ワルキューレ第一幕』をまとまった形で聴くことができる。いずれも同作品を代表する録音だ。『トリスタンとイゾルデ』の前奏曲と愛の死も濃密で良いが、これは全曲録音を遺してほしかった。
ライヴ録音では、1968年にウィーン・フィルを指揮したときの一連のプログラムが魅力的で、中でもブルックナーの第5番は神々しい。音楽が巨大すぎて、表情を読めない怖さがある。1957年6月7日にケルン放送響を指揮したときの第8番は、全体のバランスが良い演奏で、クレンペラーらしくないと言う人もいるかもしれないが、指揮者が何をやりだすか分からない怖さがない分、とっつきやすく、それでいて迫力にも格調にも不足はない。
ブラームスの作品を取り上げたライヴも外せない。1957年2月7日にアムステルダムで演奏された、木管が味わい深い「ハイドンの主題による変奏曲」、1957年9月27日にミュンヘンで演奏された、激しい感情の波濤を思わせる交響曲第4番、1969年1月28日にロンドンで演奏された、重厚かつ壮大なピアノ協奏曲第2番(ウラディミール・アシュケナージ独奏)は、「これぞクレンペラー」と言いたくなる折り紙付きの名盤として記しておく。
頻繁に指揮していたマーラーの「復活」のライヴ録音もある。私がよく聴いているのは、1951年7月12日にオランダ音楽祭で指揮したもの、1963年6月21日にウィーン・フィルを指揮したもの、1965年1月29日にバイエルンで指揮したもの。気迫のこもった演奏で小細工なし。ここぞというときにフレーズを持続させ、もったいぶることなく直線的に高揚させていくやり方も素晴らしい。クレンペラーが気に入っていたエルンスト・ブロッホの言葉を借りれば、音楽が「これほど正確に燃えあがることはない」。
私がクレンペラーのファンになったのは、ワーグナーの『リエンツィ』序曲を聴いてからである。この演奏では、トランペットが高らかに主題を奏でるところで打楽器の波が打ち寄せる。その整然としていない微妙なズレに興奮を覚えたことを今でも覚えている。いささか大袈裟に言えば、瞬間的な混濁から輝かしいフレーズが飛翔していくような効果が生まれているのだ。これと似た現象は、ブルックナーの交響曲第4番「ロマンティック」の第3楽章でも起こる。こういうのは凡百の指揮者が計算してできることではない。完璧に整ったアンサンブルは、ひとつの理想ではあるが、クレンペラーは隙のない完璧さにこだわる人ではなかった。それでも巨大な音楽をコントロールし、劇的な効果を生み出すことができる、という大器としての自負が彼にはあったのである。
[主な参考文献]
ピーター・ヘイワース/佐藤章訳『クレンペラーとの対話』(白水社 1976年7月)
ウォルター・レッグ、エリザベート・シュヴァルツコップ/河村錠一郎訳『レッグ&シュヴァルツコップ回想録 レコード うら・おもて』(音楽之友社 1986年9月)
エーファ・ヴァイスヴァイラー/明石政紀訳『オットー・クレンペラー あるユダヤ系ドイツ人の音楽家人生』(みすず書房 2011年9月)
【関連サイト】
オットー・クレンペラー 〜大器の音楽〜
『クレンペラーとの対話』(白水社)
『オットー・クレンペラー あるユダヤ系ドイツ人の音楽家人生』(みすず書房)
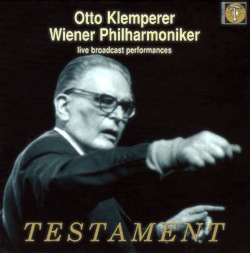
むろん、クレンペラーは木管だけでなく弦楽器の響きを際立たせる術も心得ている。ヘンデルの合奏協奏曲、モーツァルトの「アダージョとフーガ」、先に挙げたベートーヴェンの交響曲第7番第2楽章、「大フーガ」、ワーグナーの「ジークフリート牧歌」、R.シュトラウスの「メタモルフォーゼン」など、弦の響かせ方はそれぞれ異なるが、ここまで美しい演奏はなかなか聴けるものではない。余計な表情をつけず、楽器そのものが持つ響きをドラスティックに追求しているかのようだ。そこに荘厳な声楽が加わると、J.S.バッハの『ミサ曲ロ短調』のごとき大演奏になる。
1960年代以降、とくにフィルハーモニア管がニュー・フィルハーモニア管に改名してからの演奏では、テンポの遅さが目立つようになるが、クレンペラー自身は「わたしは前よりも遅いとは思いません」と言っている。1955年、1960年、1968年に録音されたベートーヴェンの交響曲第7番を聴き比べるまでもなく、この言葉を額面通りに受け取ることはできない。彼は同じような演奏を繰り返すことに意味を感じておらず、タイムウォッチで計測できる速度にも興味がないのである。おそらく作曲家でもあった自身の立場から(交響曲も書いている)、楽譜に記された音符をより吟味し、強調する方向性を選んだのだろう。この時期には、マーラーの交響曲第7番のような録音も登場している。これは音符の妖精たちが標本にされた陳列棚。聴いていて不安になるほど遅くて不気味だが、音楽を連続写真で見るような面白さがある。いずれにしても、私たちはこの指揮者の存在を介して、ほかの指揮者とは(作品によっては過去の彼自身とも)全く異なるテンポで、作曲家の世界に迫ることができるのである。
大器の録音
クレンペラーの録音は多い。そして、その全部とは言わないまでも、大半が特筆すべき名演奏である。モーツァルトとベートーヴェンの作品だけでも、少なからぬセッション録音が遺されているが、駄演は存在しない。台詞のない『魔笛』も、ジングシュピールという感じではないが、天才の書いた音楽の構造が透けて見えるようで鳥肌が立つ。『ミサ・ソレムニス』の言語を絶する偉容も、就中、「クレド」と「アニュス・デイ」に顕著である。メンデルスゾーンの交響曲第3番「スコットランド」やチャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」もため息が出るほど美しい。作品のイメージに一石投じるようなソノリティーがこれらの演奏にはある。ストラヴィンスキーの「プルチネルラ」組曲も超名演。セレナータでは「クレンペラーの木管」をほとんど耽美的な感覚で味わえる。協奏曲の録音だと、アラン・シヴィルとのモーツァルトのホルン協奏曲、ダヴィッド・オイストラフとのブラームスのヴァイオリン協奏曲などがあり、名演奏として知られている。
得意としていたワーグナーのオペラの中では、『さまよえるオランダ人』と『ワルキューレ第一幕』をまとまった形で聴くことができる。いずれも同作品を代表する録音だ。『トリスタンとイゾルデ』の前奏曲と愛の死も濃密で良いが、これは全曲録音を遺してほしかった。
ライヴ録音では、1968年にウィーン・フィルを指揮したときの一連のプログラムが魅力的で、中でもブルックナーの第5番は神々しい。音楽が巨大すぎて、表情を読めない怖さがある。1957年6月7日にケルン放送響を指揮したときの第8番は、全体のバランスが良い演奏で、クレンペラーらしくないと言う人もいるかもしれないが、指揮者が何をやりだすか分からない怖さがない分、とっつきやすく、それでいて迫力にも格調にも不足はない。
ブラームスの作品を取り上げたライヴも外せない。1957年2月7日にアムステルダムで演奏された、木管が味わい深い「ハイドンの主題による変奏曲」、1957年9月27日にミュンヘンで演奏された、激しい感情の波濤を思わせる交響曲第4番、1969年1月28日にロンドンで演奏された、重厚かつ壮大なピアノ協奏曲第2番(ウラディミール・アシュケナージ独奏)は、「これぞクレンペラー」と言いたくなる折り紙付きの名盤として記しておく。
頻繁に指揮していたマーラーの「復活」のライヴ録音もある。私がよく聴いているのは、1951年7月12日にオランダ音楽祭で指揮したもの、1963年6月21日にウィーン・フィルを指揮したもの、1965年1月29日にバイエルンで指揮したもの。気迫のこもった演奏で小細工なし。ここぞというときにフレーズを持続させ、もったいぶることなく直線的に高揚させていくやり方も素晴らしい。クレンペラーが気に入っていたエルンスト・ブロッホの言葉を借りれば、音楽が「これほど正確に燃えあがることはない」。
私がクレンペラーのファンになったのは、ワーグナーの『リエンツィ』序曲を聴いてからである。この演奏では、トランペットが高らかに主題を奏でるところで打楽器の波が打ち寄せる。その整然としていない微妙なズレに興奮を覚えたことを今でも覚えている。いささか大袈裟に言えば、瞬間的な混濁から輝かしいフレーズが飛翔していくような効果が生まれているのだ。これと似た現象は、ブルックナーの交響曲第4番「ロマンティック」の第3楽章でも起こる。こういうのは凡百の指揮者が計算してできることではない。完璧に整ったアンサンブルは、ひとつの理想ではあるが、クレンペラーは隙のない完璧さにこだわる人ではなかった。それでも巨大な音楽をコントロールし、劇的な効果を生み出すことができる、という大器としての自負が彼にはあったのである。
(阿部十三)
[主な参考文献]
ピーター・ヘイワース/佐藤章訳『クレンペラーとの対話』(白水社 1976年7月)
ウォルター・レッグ、エリザベート・シュヴァルツコップ/河村錠一郎訳『レッグ&シュヴァルツコップ回想録 レコード うら・おもて』(音楽之友社 1986年9月)
エーファ・ヴァイスヴァイラー/明石政紀訳『オットー・クレンペラー あるユダヤ系ドイツ人の音楽家人生』(みすず書房 2011年9月)
【関連サイト】
オットー・クレンペラー 〜大器の音楽〜
『クレンペラーとの対話』(白水社)
『オットー・クレンペラー あるユダヤ系ドイツ人の音楽家人生』(みすず書房)
月別インデックス
- June 2024 [1]
- February 2024 [1]
- April 2023 [2]
- February 2023 [1]
- November 2022 [1]
- June 2022 [1]
- April 2022 [1]
- January 2022 [1]
- August 2021 [1]
- April 2021 [1]
- January 2021 [1]
- September 2020 [1]
- August 2020 [1]
- March 2020 [1]
- November 2019 [1]
- July 2019 [1]
- May 2019 [1]
- January 2019 [1]
- November 2018 [1]
- August 2018 [1]
- May 2018 [1]
- January 2018 [1]
- July 2017 [1]
- March 2017 [2]
- December 2016 [1]
- October 2016 [1]
- May 2016 [1]
- March 2016 [2]
- October 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- March 2015 [2]
- December 2014 [1]
- October 2014 [2]
- July 2014 [1]
- April 2014 [2]
- March 2014 [1]
- January 2014 [1]
- December 2013 [1]
- October 2013 [1]
- July 2013 [2]
- May 2013 [1]
- April 2013 [1]
- February 2013 [2]
- January 2013 [1]
- November 2012 [1]
- October 2012 [1]
- September 2012 [1]
- August 2012 [1]
- May 2012 [1]
- April 2012 [1]
- March 2012 [1]
- January 2012 [1]
- December 2011 [1]
- November 2011 [2]
- October 2011 [1]
- September 2011 [2]
- August 2011 [2]
- July 2011 [2]
- June 2011 [3]
- May 2011 [3]
- April 2011 [3]
- March 2011 [3]
- February 2011 [3]