2012年8月アーカイブ

シンディ・ローパー『シーズ・ソー・アンユージュアル』1983年発表 『シーズ・ソー・アンユージュアル』は、当初日本では『N.Y.ダンステリア』というタイトルで発売された。カラフルでポップなLPジャケットは最初のヒット「ガールズ・ジャスト・ワナ・ハヴ・ファン」(これも「ハイ・スクールはダンステリア」と名付けられていたので、そちらで馴染んだファンが多いはずだ)の...
[続きを読む](2012.08.28)
「俺はいま不意に不可思議な恐怖に襲われた。冷たい汗がにじみ出し、手足がぶるぶる震えている。俺の心は目に見える以上の何かを感じている」 これはシェイクスピアが書いた最も残虐な悲劇といわれる『タイタス・アンドロニカス』の第二幕第三場、タイタスの息子クインタスが発する台詞である。初めてこの戯曲を読んだ時、私は森の場面のページを繰る直前に、クインタスと同じような心境...
[続きを読む](2012.08.25)
自分を押しつぶそうとする運命に抗して 最初に第6番「悲愴」を聴き、次に第5番を聴いて、それからしばらくして第4番を聴く。チャイコフスキーの交響曲を知る際、私だけでなく、おそらく多くの人がこの順番を辿っているのではないかと思う。圧倒的にポピュラーな第5番や第6番に比べると、第4番は同列に並べられるほど人気があるとはいえない。ただ、チャイコフスキーの交響曲を知れ...
[続きを読む](2012.08.20)
先頃閉幕したばかりのロンドン五輪、筆者が一番楽しみにしていたのは何を隠そう、開会式だった。音楽が大きな役割を果たすに相違ないと思って。映画監督のダニー・ボイルがディレクターに就任してからは尚更のこと、ボイル監督と度々コラボしているアンダーワールドが音楽スーパーバイザーを務めるというのだから、期待せずにいられるだろうか? 実際、英国近現代史を紐解くようにして...
[続きを読む](2012.08.18)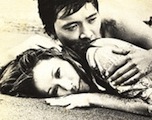
藤田敏八監督の『八月の濡れた砂』は1971年8月25日に公開された。同時上映は蔵原惟二監督の『不良少女魔子』。この2本を最後に、日活がロマンポルノに移行したことは周知の通りである。それを意識したのか、『八月の濡れた砂』の舞台は湘南。その美しく広大な海を背景に、若者たちが〈太陽族〉も顔負けの暴走ぶりをみせる。しかし、いうまでもなく、彼らは〈太陽族〉ではない。...
[続きを読む](2012.08.14)
それは、朝からうららかに晴れた、ある春の日のこと。国際線に乗るために新東京国際空港(現成田国際空港)のある成田市には何度も足を踏み入れたことはあるが、同市を擁する千葉県の県庁所在地、千葉市には一度も行った経験のなかった筆者は、今から遡ること16年前の1996年4月17日、生まれて初めてJR千葉駅に降り立った。千葉市の空もまた、筆者の住む横浜と同じように抜け...
[続きを読む](2012.08.11)
ローラ・ニーロ『イーライと13番目の懺悔』1968年作品 その紙は今も机の上にある。そのスペースでもう何年も無くならずにちゃんと残っているのはなぜだろう。1997年4月8日に彼女が卵巣癌のために世を去ったことを告げるインフォメーションだ。たしか日本のレコード会社が送ってくれた。引用する。「アメリカにおける最も影響力を持つシンガー・ソングライターの一人であるロ...
[続きを読む](2012.08.09)
キリル・コンドラシンの名前は、ダヴィッド・オイストラフやエミール・ギレリスといったソ連の名演奏家たちの協奏曲録音で知った。彼らの伴奏指揮者として必ずといっていいほどコンドラシンの名前が記されていたのである。そのため、私はしばらくの間、コンドラシンに対して「すぐれた伴奏指揮者」というイメージしか抱いていなかった。それが変わったのは、だいぶ経ってからのことであ...
[続きを読む](2012.08.05)
生まれることも、死ぬことも 1960年の『笛吹川』は戦国時代を舞台にした映画だが、話の中心人物は武将ではなく、農民である。戦が当たり前のように繰り返されている日常。功名心にはやる農民は、家を捨てて戦場へ向かい、武勲を立て、束の間慢心するが、良い時は続かず、まもなく戦死する。時が経てば、今度は次世代の若者が戦場へ行き、同じように武勲を立て、そして殺される。さら...
[続きを読む](2012.08.03)
『二十四の瞳』の涙 社会生活を送っていく中で、意思と行動を一致させるのは容易なことではない。いいたいと思ってもいえない、怒りをぶつけたいと思ってもぶつけられない、復讐したいと思っても復讐できない、逃げたいと思っても逃げられない、という人が大半である。欧米では合理性を以て筋を通せることも、日本で同じようにできるとは限らない。木下惠介監督は、そういう日本人の環境...
[続きを読む](2012.08.01)