
チャイコフスキー 交響曲第4番
2012.08.20
自分を押しつぶそうとする運命に抗して
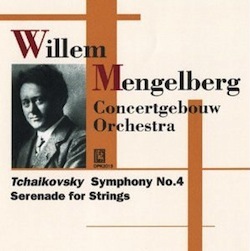 最初に第6番「悲愴」を聴き、次に第5番を聴いて、それからしばらくして第4番を聴く。チャイコフスキーの交響曲を知る際、私だけでなく、おそらく多くの人がこの順番を辿っているのではないかと思う。圧倒的にポピュラーな第5番や第6番に比べると、第4番は同列に並べられるほど人気があるとはいえない。ただ、チャイコフスキーの交響曲を知れば知るほど、第4番の存在がどうしようもなく気になってくる。この作品が持つ真摯さ、烈しさに惹かれずにいられなくなるのだ。冒頭で放たれる耳をつんざくような金管の咆哮からしてちょっと苦手、と思っていた私も、今では第5番、第6番以上に第4番を聴いている。
最初に第6番「悲愴」を聴き、次に第5番を聴いて、それからしばらくして第4番を聴く。チャイコフスキーの交響曲を知る際、私だけでなく、おそらく多くの人がこの順番を辿っているのではないかと思う。圧倒的にポピュラーな第5番や第6番に比べると、第4番は同列に並べられるほど人気があるとはいえない。ただ、チャイコフスキーの交響曲を知れば知るほど、第4番の存在がどうしようもなく気になってくる。この作品が持つ真摯さ、烈しさに惹かれずにいられなくなるのだ。冒頭で放たれる耳をつんざくような金管の咆哮からしてちょっと苦手、と思っていた私も、今では第5番、第6番以上に第4番を聴いている。
作曲時期は1877年。この年、チャイコフスキーの人生にとって大きな出来事が2つあった。ひとつはアントニーナとの結婚と破局、もうひとつはフォン・メック夫人による経済的援助のはじまりである。
アントニーナ・ミリュコーヴァがチャイコフスキーに恋文を送ったのは同年3月末頃のこと。チャイコフスキーはその熱心なアプローチに気圧される形で7月6日に結婚した。しかし、2人の同居生活はまもなく破綻。チャイコフスキーは妻から逃れ、9月27日に離婚希望を伝えた。その後、アントニーナは愛人の子供まで生むものの、離婚は成立せず、チャイコフスキーは断続的に支援を続けざるを得なかったという。破局の原因については諸説あり、チャイコフスキーにも、アントニーナにも非があったとされる。手の施しようのない性格不一致という表現が妥当だろう。
フォン・メック夫人は、長年にわたってチャイコフスキーを金銭面で支えていた富裕な未亡人。一度も会うことなく、厖大な手紙のやり取りを通じてチャイコフスキーの相談相手になっていた友人でもある。1881年以降、フォン・メック夫人は財政難にあったが、支援を打ち切ったり、返済を求めたりすることはなかった。この関係は1890年まで続いた。ちなみに、夫人が支えたのはチャイコフスキーだけではない。若きドビュッシーの援助もしていたことが知られている。
また、1877年といえば、ロシア・トルコ戦争が起こっていた時期とも重なる。チャイコフスキーの手紙には、この戦争に対する憤り、不安などが綴られていて、こんな時に「自分のことで涙を流すのは恥ずかしいことです」とまで書いている。交響曲第4番は、このような精神的、物理的状況下で生まれた。芸術家が生み出す作品に、実生活と分けて考えるべきものと分けては考えられないものがあるとすれば、交響曲第4番は間違いなく後者だろう。これはチャイコフスキーが当時抱え込んでいた真情がもろに噴出した作品といっていい。
この交響曲は、ベートーヴェンの交響曲第5番にヒントを得て書かれた。つまり、暗い運命との闘争から勝利へ、という図式に則っている。音楽に込められた意味も、チャイコフスキー自身によって明らかにされている。フォン・メック夫人のためだけに、「私たちの交響曲」の各楽章について手紙で説明しているのだ。
例えば、第1楽章の冒頭には次のようなテーマが込められているという。
「これは『運命』です。すなわち、幸福の追求を妨げる運命の力。平和と慰安が満ちあふれ晴れ渡らないように嫉妬深く監視している力です。そしてダモクレスの剣のように頭上に垂れ下がり、つねに魂に毒をもたらします」
悲劇的な暗さ、真摯な烈しさ、そして複雑な構成を持った第1楽章を書くにあたり、チャイコフスキーはかなり苦しんだようだが、最終的にその苦しみは凄絶な輝きに変容している。圧巻なのは、第2主題が現れてから「運命」の主題が復帰する第191小節まで。その筆運びには、構成という言葉も使いたくなくなるような閃きと、冷徹で強靭な意思の力がみなぎっている。
第2楽章は憂いに満ちた甘いメロディーが魅力的。チャイコフスキーは一人の詩人となり、こう綴っている。
「交響曲の第2楽章は、悲哀のもうひとつの相をあらわしています。仕事に疲れ、夜半にただ一人家の中に座っている時、彼を包み込む憂鬱な感情です。読もうと思っていた本が、手からすべり落ち、多くの思い出が湧いてきます。こんなにも多くのいろいろなことが、みんな過ぎ去ってしまったというのは、なんと悲しいことでしょう」
第3楽章のスケルツォは、弦楽器のピッツィカートに彩られ、独特の音楽的効果をもたらしている。
「ここにあるのは気まぐれな唐草模様。酩酊の最初の段階で、われわれの脳裏にすべりこんでくるぼんやりとした姿です」
このピッツィカートはトリオで中断され、今度は木管が活躍するが、まもなく金管による軍隊の行進曲が聞こえてくる。最後はピッツィカートが再現され、木管、金管も一緒になってささやかなクライマックスを形成する。巧みな音の配色とリズムの展開で魅せる楽章である。
第4楽章は強烈なffではじまる。第2主題はロシア民謡の「野に立つ白樺」をモチーフにしたもので、この美しいメロディーが様々な形にほぐされ、絡まりながら進行する。緩むことのない緊張感、めまぐるしく変転する喜怒哀楽。その果てに、嵐のような大団円を迎える。この楽章についてチャイコフスキーは、「民衆の祭りの日の描写」という言葉を残している。祭りの日に、その喜びを民衆と共にすることができるか。その一体感を味わうことができるか。
「あなたが自分自身の中に歓喜を見出せなかったら、ほかの人々をごらんなさい。民衆の中に入りなさい。民衆がどんなに生を楽しみ、歓びの感情に浸っているかをご覧なさい」
むろん、作曲者の語る言葉が全てではない。作品の解釈は自由である。標題性を抜きにして、音楽的内容の濃さ、音楽的効果のめざましさを味わうだけでも良い。第5交響曲や第6交響曲のような語り口の巧さとはまた違う、自分を押しつぶそうとするものに抵抗し、逆巻き、燃え上がる創作意欲の発露がここにはある。
これはチャイコフスキーが己の全存在を賭して書いた、彼の作品中でも屈指の力作である。「これまで自分の作品で、こんなに苦心したことはありませんが、これほどの愛情を感じたこともありません」という言葉も、そのことを裏付けている。
録音では、ウィレム・メンゲルベルク指揮、アムステルダム・コンセルトヘボウ管による1929年の演奏が、抜群に素晴らしい。楽譜に込められたニュアンスの細かいところまで、丁寧かつ大胆に紡ぎ出し、豊饒な旋律のドラマを形成している。ほかの指揮者では聴き流してしまうようなところも、この人はおろそかにしない。メンゲルベルクというとデフォルメ指揮者のようにいう人もあるが、少なくともチャイコフスキーの第4番に関してはその評言はあたらない。かつてこれほどの理解を以て、しかも美しく演奏された第4番があっただろうか、といいたくなるほどの指揮ぶりだ。録音状態も、年代から考えるとかなり良好である。
 それにしても録音が古いという人には、ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー&レニングラード・フィルのロンドン・ライヴをお薦めする。演奏の燃焼度が尋常ではないが、しっかりとした造形感を持っているので、音楽の流れが崩れない。鉄壁といわれたアンサンブルが人間味のある喜怒哀楽を見せ、存分に精彩を放っている。観客の盛り上がり方も度を越している。映像も存在するのだが、当時(1971年)の若者たちが前のめりになって、いささか目障りなほどリズムにのっている。
それにしても録音が古いという人には、ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー&レニングラード・フィルのロンドン・ライヴをお薦めする。演奏の燃焼度が尋常ではないが、しっかりとした造形感を持っているので、音楽の流れが崩れない。鉄壁といわれたアンサンブルが人間味のある喜怒哀楽を見せ、存分に精彩を放っている。観客の盛り上がり方も度を越している。映像も存在するのだが、当時(1971年)の若者たちが前のめりになって、いささか目障りなほどリズムにのっている。
1960年に録音された、エフゲニー・ムラヴィンスキー&レニングラード・フィルの演奏も、昔から名盤として知られてきたもの。贅肉のない引き締まったアンサンブルで、感傷の介入を拒みながら、作品の核心にぐいぐい迫ろうとする。体を貫くような冒頭の金管には恐怖すら覚えてしまう。厳格すぎて近づきがたいと感じる人もいるだろう。ただ、個人的には、ムラヴィンスキー盤の真の魅力は第2楽章の高潔な表現にこそあるように思われる。私は何度聴いても、この第2楽章で寒気にも似た感動に襲われる。
カラヤン盤、バーンスタイン盤、マルケヴィチ盤、ザンデルリンク盤、アルヘンタ盤、ドラティ盤など人によって評価の高い演奏を挙げはじめたらキリがないが、先に紹介した3種の録音を超えるものではない。ヴィルヘルム・フルトヴェングラー&ウィーン・フィルの1951年盤は別格。フルトヴェングラーらしい熱狂よりもむしろ格調を感じさせる演奏である。ピエール・モントゥー&ボストン響の1959年盤も不滅の名演。覇気を漂わせながらも感情に流されず、旋律を歌わせながらも骨格を崩さない。その匠の技に魅了され、聴き飽きることがない。
【関連サイト】
チャイコフスキー:交響曲第4番
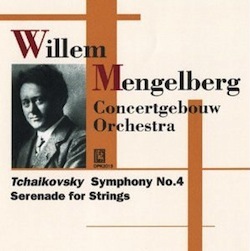
作曲時期は1877年。この年、チャイコフスキーの人生にとって大きな出来事が2つあった。ひとつはアントニーナとの結婚と破局、もうひとつはフォン・メック夫人による経済的援助のはじまりである。
アントニーナ・ミリュコーヴァがチャイコフスキーに恋文を送ったのは同年3月末頃のこと。チャイコフスキーはその熱心なアプローチに気圧される形で7月6日に結婚した。しかし、2人の同居生活はまもなく破綻。チャイコフスキーは妻から逃れ、9月27日に離婚希望を伝えた。その後、アントニーナは愛人の子供まで生むものの、離婚は成立せず、チャイコフスキーは断続的に支援を続けざるを得なかったという。破局の原因については諸説あり、チャイコフスキーにも、アントニーナにも非があったとされる。手の施しようのない性格不一致という表現が妥当だろう。
フォン・メック夫人は、長年にわたってチャイコフスキーを金銭面で支えていた富裕な未亡人。一度も会うことなく、厖大な手紙のやり取りを通じてチャイコフスキーの相談相手になっていた友人でもある。1881年以降、フォン・メック夫人は財政難にあったが、支援を打ち切ったり、返済を求めたりすることはなかった。この関係は1890年まで続いた。ちなみに、夫人が支えたのはチャイコフスキーだけではない。若きドビュッシーの援助もしていたことが知られている。
また、1877年といえば、ロシア・トルコ戦争が起こっていた時期とも重なる。チャイコフスキーの手紙には、この戦争に対する憤り、不安などが綴られていて、こんな時に「自分のことで涙を流すのは恥ずかしいことです」とまで書いている。交響曲第4番は、このような精神的、物理的状況下で生まれた。芸術家が生み出す作品に、実生活と分けて考えるべきものと分けては考えられないものがあるとすれば、交響曲第4番は間違いなく後者だろう。これはチャイコフスキーが当時抱え込んでいた真情がもろに噴出した作品といっていい。
この交響曲は、ベートーヴェンの交響曲第5番にヒントを得て書かれた。つまり、暗い運命との闘争から勝利へ、という図式に則っている。音楽に込められた意味も、チャイコフスキー自身によって明らかにされている。フォン・メック夫人のためだけに、「私たちの交響曲」の各楽章について手紙で説明しているのだ。
例えば、第1楽章の冒頭には次のようなテーマが込められているという。
「これは『運命』です。すなわち、幸福の追求を妨げる運命の力。平和と慰安が満ちあふれ晴れ渡らないように嫉妬深く監視している力です。そしてダモクレスの剣のように頭上に垂れ下がり、つねに魂に毒をもたらします」
悲劇的な暗さ、真摯な烈しさ、そして複雑な構成を持った第1楽章を書くにあたり、チャイコフスキーはかなり苦しんだようだが、最終的にその苦しみは凄絶な輝きに変容している。圧巻なのは、第2主題が現れてから「運命」の主題が復帰する第191小節まで。その筆運びには、構成という言葉も使いたくなくなるような閃きと、冷徹で強靭な意思の力がみなぎっている。
第2楽章は憂いに満ちた甘いメロディーが魅力的。チャイコフスキーは一人の詩人となり、こう綴っている。
「交響曲の第2楽章は、悲哀のもうひとつの相をあらわしています。仕事に疲れ、夜半にただ一人家の中に座っている時、彼を包み込む憂鬱な感情です。読もうと思っていた本が、手からすべり落ち、多くの思い出が湧いてきます。こんなにも多くのいろいろなことが、みんな過ぎ去ってしまったというのは、なんと悲しいことでしょう」
第3楽章のスケルツォは、弦楽器のピッツィカートに彩られ、独特の音楽的効果をもたらしている。
「ここにあるのは気まぐれな唐草模様。酩酊の最初の段階で、われわれの脳裏にすべりこんでくるぼんやりとした姿です」
このピッツィカートはトリオで中断され、今度は木管が活躍するが、まもなく金管による軍隊の行進曲が聞こえてくる。最後はピッツィカートが再現され、木管、金管も一緒になってささやかなクライマックスを形成する。巧みな音の配色とリズムの展開で魅せる楽章である。
第4楽章は強烈なffではじまる。第2主題はロシア民謡の「野に立つ白樺」をモチーフにしたもので、この美しいメロディーが様々な形にほぐされ、絡まりながら進行する。緩むことのない緊張感、めまぐるしく変転する喜怒哀楽。その果てに、嵐のような大団円を迎える。この楽章についてチャイコフスキーは、「民衆の祭りの日の描写」という言葉を残している。祭りの日に、その喜びを民衆と共にすることができるか。その一体感を味わうことができるか。
「あなたが自分自身の中に歓喜を見出せなかったら、ほかの人々をごらんなさい。民衆の中に入りなさい。民衆がどんなに生を楽しみ、歓びの感情に浸っているかをご覧なさい」
むろん、作曲者の語る言葉が全てではない。作品の解釈は自由である。標題性を抜きにして、音楽的内容の濃さ、音楽的効果のめざましさを味わうだけでも良い。第5交響曲や第6交響曲のような語り口の巧さとはまた違う、自分を押しつぶそうとするものに抵抗し、逆巻き、燃え上がる創作意欲の発露がここにはある。
これはチャイコフスキーが己の全存在を賭して書いた、彼の作品中でも屈指の力作である。「これまで自分の作品で、こんなに苦心したことはありませんが、これほどの愛情を感じたこともありません」という言葉も、そのことを裏付けている。
録音では、ウィレム・メンゲルベルク指揮、アムステルダム・コンセルトヘボウ管による1929年の演奏が、抜群に素晴らしい。楽譜に込められたニュアンスの細かいところまで、丁寧かつ大胆に紡ぎ出し、豊饒な旋律のドラマを形成している。ほかの指揮者では聴き流してしまうようなところも、この人はおろそかにしない。メンゲルベルクというとデフォルメ指揮者のようにいう人もあるが、少なくともチャイコフスキーの第4番に関してはその評言はあたらない。かつてこれほどの理解を以て、しかも美しく演奏された第4番があっただろうか、といいたくなるほどの指揮ぶりだ。録音状態も、年代から考えるとかなり良好である。

1960年に録音された、エフゲニー・ムラヴィンスキー&レニングラード・フィルの演奏も、昔から名盤として知られてきたもの。贅肉のない引き締まったアンサンブルで、感傷の介入を拒みながら、作品の核心にぐいぐい迫ろうとする。体を貫くような冒頭の金管には恐怖すら覚えてしまう。厳格すぎて近づきがたいと感じる人もいるだろう。ただ、個人的には、ムラヴィンスキー盤の真の魅力は第2楽章の高潔な表現にこそあるように思われる。私は何度聴いても、この第2楽章で寒気にも似た感動に襲われる。
カラヤン盤、バーンスタイン盤、マルケヴィチ盤、ザンデルリンク盤、アルヘンタ盤、ドラティ盤など人によって評価の高い演奏を挙げはじめたらキリがないが、先に紹介した3種の録音を超えるものではない。ヴィルヘルム・フルトヴェングラー&ウィーン・フィルの1951年盤は別格。フルトヴェングラーらしい熱狂よりもむしろ格調を感じさせる演奏である。ピエール・モントゥー&ボストン響の1959年盤も不滅の名演。覇気を漂わせながらも感情に流されず、旋律を歌わせながらも骨格を崩さない。その匠の技に魅了され、聴き飽きることがない。
(阿部十三)
【関連サイト】
チャイコフスキー:交響曲第4番
ピョートル・イリイッチ・チャイコフスキー
[1840.5.7-1893.11.6]
交響曲第4番ヘ短調 作品36
【お薦めディスク】(掲載ジャケット:上から)
アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団
ウィレム・メンゲルベルク指揮
録音:1929年
ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー指揮
レニングラード・フィルハーモニー
録音:1971年9月9日
[1840.5.7-1893.11.6]
交響曲第4番ヘ短調 作品36
【お薦めディスク】(掲載ジャケット:上から)
アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団
ウィレム・メンゲルベルク指揮
録音:1929年
ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー指揮
レニングラード・フィルハーモニー
録音:1971年9月9日
月別インデックス
- January 2026 [1]
- November 2025 [1]
- September 2025 [1]
- July 2025 [1]
- March 2025 [1]
- February 2025 [1]
- January 2025 [1]
- December 2024 [1]
- November 2024 [1]
- October 2024 [1]
- September 2024 [1]
- August 2024 [1]
- July 2024 [1]
- May 2024 [1]
- April 2024 [1]
- March 2024 [1]
- January 2024 [1]
- December 2023 [1]
- November 2023 [1]
- October 2023 [1]
- September 2023 [1]
- July 2023 [1]
- June 2023 [1]
- May 2023 [1]
- March 2023 [1]
- January 2023 [1]
- December 2022 [1]
- October 2022 [1]
- September 2022 [1]
- August 2022 [1]
- July 2022 [1]
- May 2022 [1]
- March 2022 [1]
- February 2022 [1]
- December 2021 [1]
- November 2021 [1]
- October 2021 [1]
- September 2021 [1]
- July 2021 [1]
- June 2021 [1]
- May 2021 [1]
- March 2021 [1]
- February 2021 [1]
- December 2020 [1]
- November 2020 [1]
- October 2020 [1]
- July 2020 [1]
- June 2020 [1]
- May 2020 [1]
- April 2020 [1]
- February 2020 [1]
- January 2020 [1]
- December 2019 [1]
- October 2019 [1]
- September 2019 [2]
- August 2019 [1]
- June 2019 [1]
- April 2019 [1]
- March 2019 [1]
- February 2019 [1]
- December 2018 [1]
- November 2018 [1]
- October 2018 [1]
- September 2018 [1]
- July 2018 [1]
- June 2018 [1]
- April 2018 [1]
- March 2018 [2]
- February 2018 [1]
- December 2017 [5]
- November 2017 [1]
- October 2017 [1]
- September 2017 [1]
- August 2017 [1]
- June 2017 [1]
- May 2017 [2]
- April 2017 [2]
- February 2017 [1]
- January 2017 [2]
- November 2016 [2]
- September 2016 [2]
- August 2016 [2]
- July 2016 [1]
- June 2016 [1]
- May 2016 [1]
- April 2016 [1]
- February 2016 [2]
- January 2016 [1]
- December 2015 [1]
- November 2015 [2]
- October 2015 [1]
- September 2015 [2]
- August 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- May 2015 [1]
- April 2015 [1]
- February 2015 [2]
- January 2015 [1]
- December 2014 [1]
- November 2014 [2]
- October 2014 [1]
- September 2014 [1]
- August 2014 [2]
- July 2014 [1]
- June 2014 [2]
- May 2014 [2]
- April 2014 [1]
- March 2014 [2]
- February 2014 [2]
- January 2014 [2]
- December 2013 [1]
- November 2013 [2]
- October 2013 [2]
- September 2013 [1]
- August 2013 [2]
- July 2013 [2]
- June 2013 [2]
- May 2013 [2]
- March 2013 [2]
- February 2013 [1]
- January 2013 [2]
- December 2012 [2]
- November 2012 [1]
- October 2012 [2]
- September 2012 [1]
- August 2012 [1]
- July 2012 [3]
- June 2012 [1]
- May 2012 [2]
- April 2012 [2]
- March 2012 [2]
- February 2012 [3]
- January 2012 [2]
- December 2011 [2]
- November 2011 [2]
- October 2011 [2]
- September 2011 [3]
- August 2011 [2]
- July 2011 [3]
- June 2011 [4]
- May 2011 [4]
- April 2011 [5]
- March 2011 [5]
- February 2011 [4]