
フリッツ・ブッシュ 〜音楽の生命力〜 その1
2011.09.08
フリッツ・ブッシュのキャリアの全盛期は戦前である。残された音源は当然モノラルで、キズもある。極端に古い音源は、現代のテクノロジーを駆使しても大した改善は望めない。下手に加工しても音が不自然にツルツルしてしまい、興ざめするだけだ。だから結局古いままで聴くほかない。にもかかわらず、演奏があまりに魅力的なために、聴いているうちに音質のハンデを忘れてしまう。1930年代半ばの古い録音でも、あたかも目の前で歌われ、演奏されているかのような錯覚を抱かせるほど、声や楽器の音に生彩があるのだ。こちらが想像力で補完しようとしなくても、そこで聴くことの出来る音楽がすべてを語っている。「名演奏はどんな音質でも聴く者の胸に響く」と言う人もいるが、それは間違っている。ただ、ブッシュのオペラ録音に関して言えば、それは当たっている。これほど生命力をたたえた音楽はなかなか聴けない。
ブッシュは、1890年3月13日、ドイツのジーゲン生まれ。ヴァイオリニストのアドルフ・ブッシュ、チェリストのヘルマン・ブッシュはフリッツの弟である。1906年、ケルン音楽院に入学し、フリッツ・シュタインバッハのクラスで指揮を学ぶ。1909年、リガの劇場でデビュー。アーヘン市立歌劇場の音楽監督、シュトゥットガルトのヴュルテンブルク国立歌劇場の音楽監督を経て、1922年にフリッツ・ライナーの後任としてドレスデン国立歌劇場の音楽監督に就任。ドレスデンではR.シュトラウスの『インテルメッツォ』『エジプトのヘレナ』、ブゾーニの『ファウスト博士』、ヒンデミットの『カルディヤック』などを初演している。
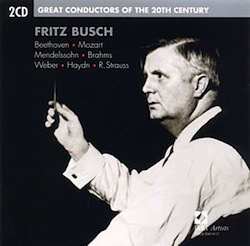 1933年にナチス政権が誕生すると、ブッシュは音楽監督を解任される。ユダヤ人でもなく、政治的発言をしたわけでもなかったが、ナチスに対して嫌悪と不信の念を抱いていたために解雇されたらしい。ブッシュの才能を高く評価していたヒトラーとゲーリングが復職させるよう命じたのに、ドレスデン支部がその命令を無視した、という興味深い説もある。ドイツを去ったブッシュはブエノスアイレスのコロン劇場と契約。さらに、イギリスのグラインドボーン音楽祭の音楽監督にも就任。水準の高い公演が話題になる。グラインドボーン音楽祭のメンバーを起用した『フィガロの結婚』(1934年録音)、『コジ・ファン・トゥッテ』(1935年録音)、『ドン・ジョヴァンニ』(1936年録音)の録音は、オペラ史に残る名盤として知られている。その間、トスカニーニの後任としてニューヨーク・フィルハーモニックの指揮者のポストを打診されるが辞退。戦争中は主に南米で指揮活動を行っていた。
1933年にナチス政権が誕生すると、ブッシュは音楽監督を解任される。ユダヤ人でもなく、政治的発言をしたわけでもなかったが、ナチスに対して嫌悪と不信の念を抱いていたために解雇されたらしい。ブッシュの才能を高く評価していたヒトラーとゲーリングが復職させるよう命じたのに、ドレスデン支部がその命令を無視した、という興味深い説もある。ドイツを去ったブッシュはブエノスアイレスのコロン劇場と契約。さらに、イギリスのグラインドボーン音楽祭の音楽監督にも就任。水準の高い公演が話題になる。グラインドボーン音楽祭のメンバーを起用した『フィガロの結婚』(1934年録音)、『コジ・ファン・トゥッテ』(1935年録音)、『ドン・ジョヴァンニ』(1936年録音)の録音は、オペラ史に残る名盤として知られている。その間、トスカニーニの後任としてニューヨーク・フィルハーモニックの指揮者のポストを打診されるが辞退。戦争中は主に南米で指揮活動を行っていた。
1945年からはメトロポリタン歌劇場で指揮。1950年にはグラインドボーン音楽祭に復帰。デンマーク国立放送局交響楽団を率いてエディンバラ音楽祭に出演し、ウィーン国立歌劇場にも登場。ヨーロッパでの名声が再び蘇るが、1951年9月、エディンバラ音楽祭で『運命の力』『ドン・ジョヴァンニ』を指揮した後、同月14日にロンドンで急逝した。
フリッツ・ブッシュの指揮でモーツァルトのオペラを聴いていると、指揮棒の動きをほとんど感じない。そこには指揮者が介在していないかのような自然発生的な音楽の生命力と解放感がある。かといってブッシュが何もしていないのかというと、全く逆で、歌詞に綴られた心理の綾をあぶり出すためにアンサンブルの細部に神経を注ぎ、それでいて神経質になりすぎず、中庸の力加減で指揮をしている。例えば、『フィガロの結婚』の伯爵夫人のアリア「どこへ行ったの、あの頃の喜びと嬉しさは」。オーケストラの演奏にはこれみよがしの主張はなく、淡々と歌手を支えることに徹しているように聞こえるが、よく耳を傾けてみると弦楽器も管楽器も後半へと進むにつれて音色の艶が増していることが分かる。そういう表情の付け方を、作為や細工の跡を一切残さずにやる人なのだ。
【関連サイト】
フリッツ・ブッシュ(CD)
ブッシュは、1890年3月13日、ドイツのジーゲン生まれ。ヴァイオリニストのアドルフ・ブッシュ、チェリストのヘルマン・ブッシュはフリッツの弟である。1906年、ケルン音楽院に入学し、フリッツ・シュタインバッハのクラスで指揮を学ぶ。1909年、リガの劇場でデビュー。アーヘン市立歌劇場の音楽監督、シュトゥットガルトのヴュルテンブルク国立歌劇場の音楽監督を経て、1922年にフリッツ・ライナーの後任としてドレスデン国立歌劇場の音楽監督に就任。ドレスデンではR.シュトラウスの『インテルメッツォ』『エジプトのヘレナ』、ブゾーニの『ファウスト博士』、ヒンデミットの『カルディヤック』などを初演している。
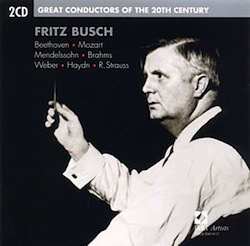
1945年からはメトロポリタン歌劇場で指揮。1950年にはグラインドボーン音楽祭に復帰。デンマーク国立放送局交響楽団を率いてエディンバラ音楽祭に出演し、ウィーン国立歌劇場にも登場。ヨーロッパでの名声が再び蘇るが、1951年9月、エディンバラ音楽祭で『運命の力』『ドン・ジョヴァンニ』を指揮した後、同月14日にロンドンで急逝した。
フリッツ・ブッシュの指揮でモーツァルトのオペラを聴いていると、指揮棒の動きをほとんど感じない。そこには指揮者が介在していないかのような自然発生的な音楽の生命力と解放感がある。かといってブッシュが何もしていないのかというと、全く逆で、歌詞に綴られた心理の綾をあぶり出すためにアンサンブルの細部に神経を注ぎ、それでいて神経質になりすぎず、中庸の力加減で指揮をしている。例えば、『フィガロの結婚』の伯爵夫人のアリア「どこへ行ったの、あの頃の喜びと嬉しさは」。オーケストラの演奏にはこれみよがしの主張はなく、淡々と歌手を支えることに徹しているように聞こえるが、よく耳を傾けてみると弦楽器も管楽器も後半へと進むにつれて音色の艶が増していることが分かる。そういう表情の付け方を、作為や細工の跡を一切残さずにやる人なのだ。
(続く)
【関連サイト】
フリッツ・ブッシュ(CD)
月別インデックス
- March 2012 [1]
- January 2012 [1]
- December 2011 [1]
- November 2011 [2]
- October 2011 [1]
- September 2011 [2]
- August 2011 [2]
- July 2011 [2]
- June 2011 [3]
- May 2011 [3]
- April 2011 [3]
- March 2011 [3]
- February 2011 [3]