2011年6月アーカイブ

ベートーヴェンも愛した「短調のモーツァルト」 明るく、無邪気なモーツァルトしか知らない人は、悲しみ悶え苦しむ「短調のモーツァルト」の存在を知った時、少なからず驚くに違いない。生活の匂いを感じさせない、まるで天使が書いたような長調の作品は、モーツァルトが〈神の子〉であったことを伝えているが、暗い情熱が波打つ短調の作品は、モーツァルトがまぎれもなく苦悩する〈人間...
[続きを読む](2011.06.29)
2人の女優 『女は二度生まれる』は若尾文子主演作。無欲でお人よしの芸者、小えんが様々な男たちと関係を結ぶことで少しずつ女として変化してゆくプロセスを描く。諸行無常の人間模様をこまやかに映し出す川島雄三の演出がすばらしい。若尾の魅力も十二分に引き出されており、難役にぴったりとはまっている。 撮影現場での川島について、若尾は川本三郎との対談でこう語っている。「ダ...
[続きを読む](2011.06.26)
映画界の戯作者として 川島雄三は45年の短い人生で51本の作品を撮ったが、そのうち傑作と呼べるものは僅かしかない。しかし、その数少ない傑作には、誇張を抜きにして、観た人の価値観や人生観までも変えてしまうくらいの磁場が広がっている。残りの困った作品群も、見方によっては斬新で、捨てがたい味わいがあり、一部のカルト映画ファンから支持されている。 具体的に書くと、一...
[続きを読む](2011.06.26)
実用性の観点からすれば全く理に適っていない選択肢、道具に愛着を持ってしまうタイプの人間が世の中には存在する。全くもって非能率的で非生産的! ナンセンス! ダカラモテナイノサ! そう罵られたとしても寂しげな笑いを浮かべ、静かに頭を下げるしかないコダワリの持ち主達。それは例えば1000円くらいで売っているクォーツやデジタル時計の方が遥かに正確なのに、わざわざ数...
[続きを読む](2011.06.25)
テレヴィジョン『マーキー・ムーン』1977年発表 NYパンクの重要バンドの一つ、テレヴィジョンは1973年に結成され、74年からライヴ活動をスタートした。後にリチャード・ヘル&ザ・ヴォイドイズを結成し、ロンドン・パンクに影響を及ぼすリチャード・ヘルがベーシストだった頃は、ガレージ・ロック的な音楽性を持っていたらしいが、徐々にフリージャズの影響を反映したサウン...
[続きを読む](2011.06.24)
果たしてそれは「革命」なのか 国内最大規模のクラシック音楽祭「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン」で、もしテーマがショスタコーヴィチになったらどうなるのだろう、と時々想像することがある。異様な熱気に覆われている会場内。モーツァルトやショパンの時は家族や恋人たちの憩いの場だったのに、「政治と芸術」「革命」を論じ合う場と化す屋外の休憩所。平年の数倍の割合を占める...
[続きを読む](2011.06.22)
1955年に公開された『暴力教室』(原題『BLACKBOARD JUNGLE』)は、非行が横行する学校の現実をリアルに描いた作品で、各地で上映禁止騒動を起こした。不良たちによって荒らされる授業、女教師への暴行未遂、教師の妻への嫌がらせ、そして「当校には非行問題はない」と言い張る校長。教師たちは聖職者でも何でもない。獣ばかりがいるジャングルで孤軍奮闘する使い...
[続きを読む](2011.06.20)
ひとつ忘れられない思い出がある。2006年11月、サントリーホールでモーツァルトの交響曲第39番、第40番、第41番を聴いた時のことだ。3作とも有名すぎるほど有名な作品である。それをウィーンフィルが演奏する。こちらはさぞ魅惑的なモーツァルトが聴けるのだろうと期待する。しかし指揮者はアーノンクール。普通の演奏はしないだろう、という不安にも似た予感がふと脳裏を...
[続きを読む](2011.06.18)
春風の吹く日本のとある町。長い階段を数えながらのぼっている一人の少年の姿がある。「88、89、90......」 そこへ赤い麦わら帽子が風に飛ばされてくる。少年はジャンプして帽子をつかむ。すると、階段の上の方から声が聞こえてくる。「ナイスキャッチ」 少年が見上げるとそこには少女が立っている。 転校生・春日恭介と鮎川まどかの出会いのシーンだ。 恭介は階段をの...
[続きを読む](2011.06.18)
1年以上前のこと、あるコンサートの告知に目が釘付けになった。ニコラウス・アーノンクール指揮、ウィーン・コンツェントゥス・ムジクスによるJ.S.バッハの『ミサ曲ロ短調』。会場はNHKホール。公演は2010年10月に行われるという。私はチケットの発売日を確認し、発売初日に購入した。 キャッチコピーは「アーノンクール最後の来日公演!」ーーこういう類の宣伝文句は(...
[続きを読む](2011.06.17)
ルキーノ・ヴィスコンティの映画はしばしば「絢爛たる」とか「格調高い」と形容される。しかし、クラシカルな雰囲気を漂わせた外観の内側には、秩序のないエネルギーが散乱している。多くの古典がそうであるように、彼の映画もまた現代的な「おさまりの良さ」を知らない。そこが魅力である。 その作品は、全体のまとまり具合や演出の巧みさで語られるより、美学の観点から語られる方が...
[続きを読む](2011.06.15)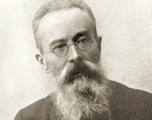
音楽で愉しむアラビアン・ナイト 昔々、ペルシアの王様シャハリアールは、妃の浮気がもとで女性不信に陥ってしまいました。王様は妃を殺してしまうと、それ以来、毎日のように城下から娘を連れてこさせました。一晩だけ過ごして、殺すためです。ある日、大臣の娘シェヘラザードが差し出されることになりました。しかし、彼女はほかの娘とは違いました。知性に富んだ彼女は、王様の寝室で...
[続きを読む](2011.06.12)
高橋愛率いるモーニング娘。が著しい成長を遂げたのは、それだけ場数を踏んできたからだろう。観客の反応がダイレクトに返ってくる空間で、メンバー同士なれ合うことなく何年も真剣勝負をしていれば、おのずから集中力もつき、見せ方も聴かせ方もグレードアップする。 とはいえ、やはり実際に観ないことには確信が持てないので、コンサートへ行ってみることにした。メンバーの卒業を控...
[続きを読む](2011.06.11)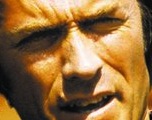
画面一杯に広がる黄金色の麦畑と鮮やかな青い空。アイダホ州の片田舎の、のどかな風景を映し出し、『サンダーボルト』はスタートする。続いて画面が切り替わり、小さな教会から賛美歌が聞こえてくる。教会の中に入ると、人々が神妙な面持ちで牧師の説教に耳を傾けている。長身でスリムな牧師が目を引く......クリント・イーストウッド! 本作が公開されたのは1974年。イース...
[続きを読む](2011.06.10)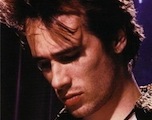
ジェフ・バックリィ『グレース』1994年発表 90年代の音楽シーンを振り返ると、ブリットポップでもグランジでもエレクトロニカでもなく、累々と死体が横たわる戦場のような光景を目に浮かべてしまう。というのも、90年代を代表する才能豊かなミュージシャンたちーーカート・コバーン、リッチー・エドワーズ、トゥーパック・シャクール、ノートリアスB.I.G.、レイン・ステイ...
[続きを読む](2011.06.09)
戦前から戦中にかけて海外でその実力を認められ、高い評価を得ていた世界的ヴァイオリニスト、諏訪根自子(すわ・ねじこ)。おそらく彼女の名前を見て胸を熱くするのはかなり上の世代だろう。 諏訪のファンだった城山三郎は「日本が初めて生んだ知的な美人という気がした」と述べていたそうだ。たしかに綺麗な顔立ちである。一目でそれと分かる美人ヴァイオリニスト。ただ、音楽的には...
[続きを読む](2011.06.07)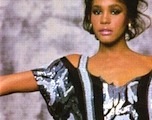
ホイットニー・ヒューストン「すべてをあなたに」(1985年/全米No.1、全英No.1) そのスレンダーな肢体を活かしてモデル業に身を投じたホイットニー・ヒューストンは、言わばショウ・ビジネス界におけるサラブレッド的存在だった。ゴスペル・シンガーのシシー・ヒューストンを母に持ち、往年の人気シンガー、ディオンヌ・ワーウィックは従姉妹という血統書付き。幼少の頃か...
[続きを読む](2011.06.05)
内田吐夢ほど浮き沈みの激しい人生を送った映画監督がいるだろうか。その歩みを追うだけでも劇的な長編小説を読むような思いがする。 高等小学校中退後、ピアノ屋で丁稚奉公し、こき使われた少年時代。やがて映画に興味を持った彼は、谷崎潤一郎の『アマチュア倶楽部』の製作現場に飛び込むが、そのまま映画界に進むことなく、旅芸人の一座に入りドサ回りを体験。さらに、震災直後は浅...
[続きを読む](2011.06.05)
モーニング娘。ブームとはいつ頃のことを指すのか。そうきかれた時、多くの人が思い浮かべるのは「LOVEマシーン」以降の数年間だろう。そのブームがいつ過ぎたのかは、何事につけ前倒しで「終わった」と書きたがるマスコミの傾向もあるので分からないが、ここ数年のことではないはず。おそらくもっと前である。そして、現在のモーニング娘。はというと、魅力的な個性と豊かな才能に...
[続きを読む](2011.06.04)
アメリカで成功したロシアン・ピアノ・コンチェルト チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番といえば、あらゆるピアノ協奏曲の中で最も有名な作品ではないだろうか。冒頭でホルンが奏でる主題を聴いたことがないという人はおそらく一人もいないはずだ。いかにもロシア的なスケールの大きさを感じさせる名旋律である。序奏部のクライマックスで、グランドピアノとオーケストラが一体化して...
[続きを読む](2011.06.03)