
ジョセフ・ロージー 〜儀式の問題〜
2015.04.16
反骨精神の人
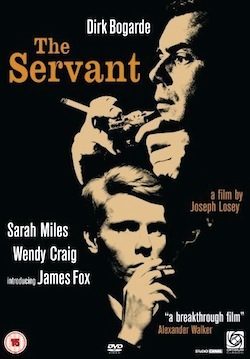 ジョセフ・ロージーは赤狩りの時代にアメリカを追われ、イギリスで問題作を次々と発表した監督である。いわば反骨精神の塊のような人。マッカーシズムの犠牲者というレッテルは似合わない。その作品は、観る者をスカッとさせるタイプのものではなく、毒に満ちている。とにかく後味の悪い映画が多い。にもかかわらず、観たくなる。言ってみれば、その毒には偽善的な社会や微温的な人間関係に飼いならされた者を正気に戻す力がある。それを味わいたくて観てしまうのだ。
ジョセフ・ロージーは赤狩りの時代にアメリカを追われ、イギリスで問題作を次々と発表した監督である。いわば反骨精神の塊のような人。マッカーシズムの犠牲者というレッテルは似合わない。その作品は、観る者をスカッとさせるタイプのものではなく、毒に満ちている。とにかく後味の悪い映画が多い。にもかかわらず、観たくなる。言ってみれば、その毒には偽善的な社会や微温的な人間関係に飼いならされた者を正気に戻す力がある。それを味わいたくて観てしまうのだ。
主従関係の逆転とアイデンティティーの崩壊を描いた『召使』(1963年)を観ても分かるように、ロージーは支配層にも被支配層にも与しない。彼の関心は、私たちが身を置いている社会の仮面を剥ぎ取り、日々の生活の中で腐敗しゆく人間の真実を暴くことに注がれている。この姿勢を貫く意志の強さを、ロージーは敬愛する劇作家ベルトルト・ブレヒトから継承した。
初めて手がけた長編映画『緑色の髪の少年』(1948年)では、戦争で両親を失った少年ピーター(ディーン・ストックウェル)の髪の毛がある日突然緑色になる。小さな町のことなので、噂はすぐに広まり、ピーターは奇異の目で見られる。しかし彼は変色した髪を戦争の悲惨さを象徴するものとしてあえて切らず、周囲の威圧的な雰囲気に抵抗する。この少年はロージーそのものと見ていいだろう。映画の中では、ピーターは信頼していた老人(パット・オブライエン)に裏切られ、髪を切ることになるが、ロージー自身は気骨の人として緑色の髪のままアメリカを離れ、イギリスに渡ったのである。1967年、ニューヨークで記者会見を開いた彼は、赤狩りの時代を振り返り、次のように語っている。
「全てをマッカーシーの罪にするのは、あまりにも安易です。あれはマッカーシーではなく、みんなだったのです。あの時、沈黙を守っていた全ての人々だったのです。私は昨日ラジオに出演しました。そこで誰かが言いました、『今あの事件について話し合えるのは素晴らしいじゃないですか』と。しかし私はちっとも素晴らしいとは思わない。これが大きな自由だとも思えません。あの時だってこのくらいの自由はあった。それでも誰も話さなかったのです」
1960年代の作品の儀式
ロージーの映画には必ずと言っていいほど儀式やゲームが登場する。それは無意味で子供じみたものに見えなくもないが、実は大きな意味を持っており、登場人物の運命を変えたり、場合によっては死を招くこともある。この一種の様式的展開は、すでに『緑色の髪の少年』から存在する。老人が「緑は希望の色だよ」と言った後、同居している少年ピーターが、ふと思いついたように植木を食卓に置く。まるで緑を尊ぶ儀式のようである。その翌日、ピーターの髪の毛が緑色になるのだ。
『召使』では裕福な青年トニー(ジェームズ・フォックス)と召使バレット(ダーク・ボガード)がボールのぶつけ合いをしたり、かくれんぼをしたりする。以降、主従関係が明確な形で転換する。『銃殺』(1964年)では、兵隊たちが憂さ晴らしでネズミ狩りを行う。死んだ馬の肉を食べているネズミを捕まえて、裁判の後、皆で石を投げて殺すのである。それと同時進行で、脱走の容疑をかけられた兵士ハンプ(トム・コートネイ)が茶番にすぎない非公式の裁判にかけられ、銃殺刑を宣告される。『できごと』(1967年)では、大学で哲学を教えている中年男スティーブン(ダーク・ボガード)が学校伝統のゲームに参加させられる。ラグビーみたいな遊びで、ボールとして使われるのは長細い筒状のものだ。いざ実際にゲームが始まると、スティーブンの中に若者への対抗心が芽生え、教え子のウィリアム(マイケル・ヨーク)の挑戦的なタックルを真っ向から受ける。そこからほとんど2人の個人的な取っ組み合いのような様相を呈するが、結果、ウィリアムは鼻血を出し、頬にみみず腫れを作り、何者かに殴られてダウンする。このイメージがそのままウィリアムの死に直結する。
1970年代の作品の儀式
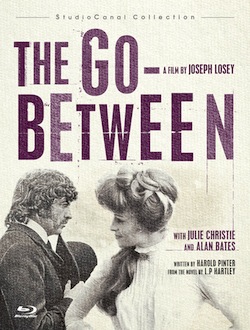 カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞した『恋』(1970年)では黒魔術そのものが登場する。憧れの女性マリアン(ジュリー・クリスティ)のために使いっ走りをさせられる少年レオ(ドミニク・ガード)が、小作人(アラン・ベイツ)とマリアンの関係を知り、怒りに我を忘れ、毒花を使って呪いをかけるのだ。『暗殺者のメロディ』(1972年)の儀式も、意味深長である。スターリンの命令でトロツキー(リチャード・バートン)を殺害するタイミングを狙う男(アラン・ドロン)が、人気のない僧院で仲間と会い、自分一人で殺してみせると息巻く。そして鐘を鳴らそうとして、鐘の舌についている紐をつかもうとする。しかし紐は上の方にあり、届かない。それを象徴するかのように、1回目のチャンスではトロツキーの威厳に気圧され、手を出せなくなる。まもなく2回目のチャンスが訪れる。トロツキーを訪ねる前、男は僧院へ行き、煙草を吸い、気持ちを高ぶらせる。彼はふと鐘の舌についている紐が垂れているのを目にする。この前はジャンプして届かなかったが、今は下まで垂れている。男は煙草を捨てて、その紐に勢いよく飛びつく。子供じみた行為だが、男にとっては重要な儀式なのである。その後、男はトロツキー暗殺を遂行する。
カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞した『恋』(1970年)では黒魔術そのものが登場する。憧れの女性マリアン(ジュリー・クリスティ)のために使いっ走りをさせられる少年レオ(ドミニク・ガード)が、小作人(アラン・ベイツ)とマリアンの関係を知り、怒りに我を忘れ、毒花を使って呪いをかけるのだ。『暗殺者のメロディ』(1972年)の儀式も、意味深長である。スターリンの命令でトロツキー(リチャード・バートン)を殺害するタイミングを狙う男(アラン・ドロン)が、人気のない僧院で仲間と会い、自分一人で殺してみせると息巻く。そして鐘を鳴らそうとして、鐘の舌についている紐をつかもうとする。しかし紐は上の方にあり、届かない。それを象徴するかのように、1回目のチャンスではトロツキーの威厳に気圧され、手を出せなくなる。まもなく2回目のチャンスが訪れる。トロツキーを訪ねる前、男は僧院へ行き、煙草を吸い、気持ちを高ぶらせる。彼はふと鐘の舌についている紐が垂れているのを目にする。この前はジャンプして届かなかったが、今は下まで垂れている。男は煙草を捨てて、その紐に勢いよく飛びつく。子供じみた行為だが、男にとっては重要な儀式なのである。その後、男はトロツキー暗殺を遂行する。
例を挙げていくとキリがないが、このような趣向は、社会制度と人間の腐敗の関係性にメスを入れ続けたロージーの強面なイメージだけでは捉えにくい神秘主義的傾向を示すものだ。確固たる人間関係、不安定さのない人生のように見えても、それは表面上のことで、人間ないし人生の本質はどこまでいっても安定し得ない。歯車がおかしくなる瞬間、すなわち危機は必ず訪れる。その象徴として、たわいのない儀式やゲームを好んで用いたのだろう。
儀式のほかにも、鏡を使ったショットなど、ロージーの映画には彼なりの決まった様式がある。そう考えると、『ガリレオ』(1974年)で様式化への志向をはっきりと示すようになったのは、ある意味自然な流れと言える。ちなみに、『ガリレオ』の原作はブレヒト。公開当時、トポルが演じるガリレオは不評だったようだが、それよりも映画全体のテンポが良くないことの方が気になる。
『エヴァの匂い』について
 ロージーの作品は、男優たちの醸し出す雰囲気が濃厚で、可愛い女優が出ていても単なるお飾りにしか見えない。目と心の保養になるような女優の扱い方が、ぶっきらぼうに感じられることさえある。その代わり、毒のあるヒロインたちが精彩を放つ。中でも『エヴァの匂い』(1962年)のジャンヌ・モロー、『召使』のサラ・マイルズ、『秘密の儀式』(1968年)のエリザベス・テイラーとミア・ファロー、『恋』のジュリー・クリスティが示す毒性は、トラウマレベルと言っても過言ではない。演出のタッチが奇怪なほどコミカルな『唇からナイフ』(1966年)のモニカ・ヴィッティとロッセラ・フォークも、やはり有毒だ(モニカ・ヴィッティの太腿にある刺青はサソリである)。これはロージーの女性観を表しているのだろうか。
ロージーの作品は、男優たちの醸し出す雰囲気が濃厚で、可愛い女優が出ていても単なるお飾りにしか見えない。目と心の保養になるような女優の扱い方が、ぶっきらぼうに感じられることさえある。その代わり、毒のあるヒロインたちが精彩を放つ。中でも『エヴァの匂い』(1962年)のジャンヌ・モロー、『召使』のサラ・マイルズ、『秘密の儀式』(1968年)のエリザベス・テイラーとミア・ファロー、『恋』のジュリー・クリスティが示す毒性は、トラウマレベルと言っても過言ではない。演出のタッチが奇怪なほどコミカルな『唇からナイフ』(1966年)のモニカ・ヴィッティとロッセラ・フォークも、やはり有毒だ(モニカ・ヴィッティの太腿にある刺青はサソリである)。これはロージーの女性観を表しているのだろうか。
ロージーの手にかかると恋愛映画も毒と化す。『エヴァの匂い』はその好例。ここではワケありの新進作家タイヴィアン(スタンリー・ベイカー)が、美しい婚約者フランチェスカ(ヴィルナ・リージ)を裏切り、エヴァ(ジャンヌ・モロー)の魅力に溺れて破滅する。若さも美しさもフランチェスカの方が勝っているのに、なぜエヴァなのか。それは彼女が自分と同類だから、もっと言えば、嘘や裏切りを重ねて底辺から這い上がり上流の仮面をかぶっている、醜い魂を持つ人間だからである。フランチェスカは自分のことを愛してくれてはいるものの、同類の人間ではない。だからタイヴィアンは満たされない。その哀れなフランチェスカはというと、映画プロデューサーのブランコ(ジョルジョ・アルベルタッツィ)に深く愛されながらも、タイヴィアンと結婚する。そして、エヴァの好みはというと、ブランコのようなタイプの上流人なのである。ここに一種の四角関係が成立する。ハッピーな展開が望めるわけがない。ロマンティックな要素も皆無だ。不幸な人間関係からひたすら目が痛くなるほどの悪の匂いが放たれる。しかし、これを他人事だと誰に言い切れるだろうか。恋愛は人をこれ以上ないほど美しくすることもあれば、これ以上ないほど醜くすることもあるのだ。
【関連サイト】
Joseph Losey
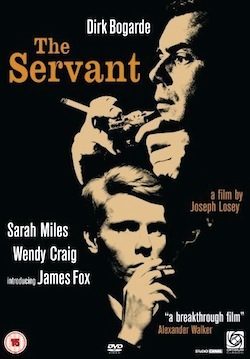
主従関係の逆転とアイデンティティーの崩壊を描いた『召使』(1963年)を観ても分かるように、ロージーは支配層にも被支配層にも与しない。彼の関心は、私たちが身を置いている社会の仮面を剥ぎ取り、日々の生活の中で腐敗しゆく人間の真実を暴くことに注がれている。この姿勢を貫く意志の強さを、ロージーは敬愛する劇作家ベルトルト・ブレヒトから継承した。
初めて手がけた長編映画『緑色の髪の少年』(1948年)では、戦争で両親を失った少年ピーター(ディーン・ストックウェル)の髪の毛がある日突然緑色になる。小さな町のことなので、噂はすぐに広まり、ピーターは奇異の目で見られる。しかし彼は変色した髪を戦争の悲惨さを象徴するものとしてあえて切らず、周囲の威圧的な雰囲気に抵抗する。この少年はロージーそのものと見ていいだろう。映画の中では、ピーターは信頼していた老人(パット・オブライエン)に裏切られ、髪を切ることになるが、ロージー自身は気骨の人として緑色の髪のままアメリカを離れ、イギリスに渡ったのである。1967年、ニューヨークで記者会見を開いた彼は、赤狩りの時代を振り返り、次のように語っている。
「全てをマッカーシーの罪にするのは、あまりにも安易です。あれはマッカーシーではなく、みんなだったのです。あの時、沈黙を守っていた全ての人々だったのです。私は昨日ラジオに出演しました。そこで誰かが言いました、『今あの事件について話し合えるのは素晴らしいじゃないですか』と。しかし私はちっとも素晴らしいとは思わない。これが大きな自由だとも思えません。あの時だってこのくらいの自由はあった。それでも誰も話さなかったのです」
1960年代の作品の儀式
ロージーの映画には必ずと言っていいほど儀式やゲームが登場する。それは無意味で子供じみたものに見えなくもないが、実は大きな意味を持っており、登場人物の運命を変えたり、場合によっては死を招くこともある。この一種の様式的展開は、すでに『緑色の髪の少年』から存在する。老人が「緑は希望の色だよ」と言った後、同居している少年ピーターが、ふと思いついたように植木を食卓に置く。まるで緑を尊ぶ儀式のようである。その翌日、ピーターの髪の毛が緑色になるのだ。
『召使』では裕福な青年トニー(ジェームズ・フォックス)と召使バレット(ダーク・ボガード)がボールのぶつけ合いをしたり、かくれんぼをしたりする。以降、主従関係が明確な形で転換する。『銃殺』(1964年)では、兵隊たちが憂さ晴らしでネズミ狩りを行う。死んだ馬の肉を食べているネズミを捕まえて、裁判の後、皆で石を投げて殺すのである。それと同時進行で、脱走の容疑をかけられた兵士ハンプ(トム・コートネイ)が茶番にすぎない非公式の裁判にかけられ、銃殺刑を宣告される。『できごと』(1967年)では、大学で哲学を教えている中年男スティーブン(ダーク・ボガード)が学校伝統のゲームに参加させられる。ラグビーみたいな遊びで、ボールとして使われるのは長細い筒状のものだ。いざ実際にゲームが始まると、スティーブンの中に若者への対抗心が芽生え、教え子のウィリアム(マイケル・ヨーク)の挑戦的なタックルを真っ向から受ける。そこからほとんど2人の個人的な取っ組み合いのような様相を呈するが、結果、ウィリアムは鼻血を出し、頬にみみず腫れを作り、何者かに殴られてダウンする。このイメージがそのままウィリアムの死に直結する。
1970年代の作品の儀式
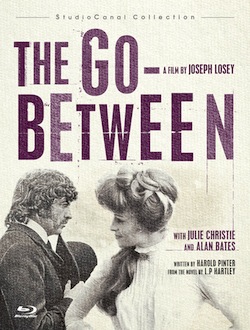
例を挙げていくとキリがないが、このような趣向は、社会制度と人間の腐敗の関係性にメスを入れ続けたロージーの強面なイメージだけでは捉えにくい神秘主義的傾向を示すものだ。確固たる人間関係、不安定さのない人生のように見えても、それは表面上のことで、人間ないし人生の本質はどこまでいっても安定し得ない。歯車がおかしくなる瞬間、すなわち危機は必ず訪れる。その象徴として、たわいのない儀式やゲームを好んで用いたのだろう。
儀式のほかにも、鏡を使ったショットなど、ロージーの映画には彼なりの決まった様式がある。そう考えると、『ガリレオ』(1974年)で様式化への志向をはっきりと示すようになったのは、ある意味自然な流れと言える。ちなみに、『ガリレオ』の原作はブレヒト。公開当時、トポルが演じるガリレオは不評だったようだが、それよりも映画全体のテンポが良くないことの方が気になる。
『エヴァの匂い』について

ロージーの手にかかると恋愛映画も毒と化す。『エヴァの匂い』はその好例。ここではワケありの新進作家タイヴィアン(スタンリー・ベイカー)が、美しい婚約者フランチェスカ(ヴィルナ・リージ)を裏切り、エヴァ(ジャンヌ・モロー)の魅力に溺れて破滅する。若さも美しさもフランチェスカの方が勝っているのに、なぜエヴァなのか。それは彼女が自分と同類だから、もっと言えば、嘘や裏切りを重ねて底辺から這い上がり上流の仮面をかぶっている、醜い魂を持つ人間だからである。フランチェスカは自分のことを愛してくれてはいるものの、同類の人間ではない。だからタイヴィアンは満たされない。その哀れなフランチェスカはというと、映画プロデューサーのブランコ(ジョルジョ・アルベルタッツィ)に深く愛されながらも、タイヴィアンと結婚する。そして、エヴァの好みはというと、ブランコのようなタイプの上流人なのである。ここに一種の四角関係が成立する。ハッピーな展開が望めるわけがない。ロマンティックな要素も皆無だ。不幸な人間関係からひたすら目が痛くなるほどの悪の匂いが放たれる。しかし、これを他人事だと誰に言い切れるだろうか。恋愛は人をこれ以上ないほど美しくすることもあれば、これ以上ないほど醜くすることもあるのだ。
(阿部十三)
【関連サイト】
Joseph Losey
[ジョセフ・ロージー略歴]
1909年1月14日、アメリカのウィスコンシン州生まれ。ダートマス大学で医学を専攻後、ハーバード大学で文学を専攻。学業と平行して演劇活動にのめり込む。1937年から映画の編集に従事。1939年にマリオネット映画『石油とそのいとこたち』(短編)で初監督を務め、1945年にはMGMで短編『手の中の拳銃』を撮り、評判を呼ぶ。1948年、長編映画『緑色の髪の少年』を発表、1950年には『無法者』を撮り、病めるアメリカに焦点を当てる。当時から非米活動委員会にマークされていたロージーは、1951年9月、脚本家レオ・タウンゼントの証言により「赤」とみなされ、ブラックリストに載る。アメリカで職を失ったロージーは渡欧し、アンドレア・フォルツァーノの名前で『拳銃を売る男』(1952年)、ヴィクター・ハンブリーの名前で『眠れる虎』(1954年)、ジョセフ・ウォルトンの名前で『身近な見知らぬ人』(1955年)を監督。栄光のキャリアは1960年代に始まり、『コンクリート・ジャングル』『エヴァの匂い』『地獄に堕ちた人々』『召使』『銃殺』と問題作を連発。1967年に『できごと』でカンヌ国際映画祭審査員特別グランプリ、1970年には『恋』でカンヌ国際映画祭パルム・ドールを受賞。後年はオペラの演出も手がけ、『ドン・ジョヴァンニ』(1979年)も製作された。1984年6月22日、ロンドンで死去。
1909年1月14日、アメリカのウィスコンシン州生まれ。ダートマス大学で医学を専攻後、ハーバード大学で文学を専攻。学業と平行して演劇活動にのめり込む。1937年から映画の編集に従事。1939年にマリオネット映画『石油とそのいとこたち』(短編)で初監督を務め、1945年にはMGMで短編『手の中の拳銃』を撮り、評判を呼ぶ。1948年、長編映画『緑色の髪の少年』を発表、1950年には『無法者』を撮り、病めるアメリカに焦点を当てる。当時から非米活動委員会にマークされていたロージーは、1951年9月、脚本家レオ・タウンゼントの証言により「赤」とみなされ、ブラックリストに載る。アメリカで職を失ったロージーは渡欧し、アンドレア・フォルツァーノの名前で『拳銃を売る男』(1952年)、ヴィクター・ハンブリーの名前で『眠れる虎』(1954年)、ジョセフ・ウォルトンの名前で『身近な見知らぬ人』(1955年)を監督。栄光のキャリアは1960年代に始まり、『コンクリート・ジャングル』『エヴァの匂い』『地獄に堕ちた人々』『召使』『銃殺』と問題作を連発。1967年に『できごと』でカンヌ国際映画祭審査員特別グランプリ、1970年には『恋』でカンヌ国際映画祭パルム・ドールを受賞。後年はオペラの演出も手がけ、『ドン・ジョヴァンニ』(1979年)も製作された。1984年6月22日、ロンドンで死去。
[主な監督作品]
1948年『緑色の髪の少年』/1950年『無法者』/1951年『M』/1960年『コンクリート・ジャングル』/1962年『エヴァの匂い』/1963年『地獄に堕ちた人々』『召使』/1964年『銃殺』/1966年『唇からナイフ』1967年『できごと』/1968年『秘密の儀式』『夕なぎ』/1970年『恋』/1972年『暗殺者のメロディ』/1973年『人形の家』/1974年『ガリレオ』/1976年『パリの灯は遠く』/1979年『ドン・ジョヴァンニ』
1948年『緑色の髪の少年』/1950年『無法者』/1951年『M』/1960年『コンクリート・ジャングル』/1962年『エヴァの匂い』/1963年『地獄に堕ちた人々』『召使』/1964年『銃殺』/1966年『唇からナイフ』1967年『できごと』/1968年『秘密の儀式』『夕なぎ』/1970年『恋』/1972年『暗殺者のメロディ』/1973年『人形の家』/1974年『ガリレオ』/1976年『パリの灯は遠く』/1979年『ドン・ジョヴァンニ』
月別インデックス
- May 2024 [1]
- January 2023 [1]
- November 2021 [1]
- April 2021 [1]
- September 2020 [2]
- May 2020 [1]
- April 2020 [1]
- January 2020 [1]
- July 2019 [1]
- March 2019 [1]
- January 2019 [1]
- November 2018 [3]
- June 2018 [1]
- April 2018 [1]
- October 2017 [2]
- September 2017 [1]
- June 2017 [2]
- March 2017 [2]
- November 2016 [1]
- August 2016 [1]
- July 2016 [2]
- February 2016 [1]
- October 2015 [1]
- August 2015 [1]
- June 2015 [1]
- April 2015 [1]
- February 2015 [1]
- January 2015 [2]
- September 2014 [1]
- July 2014 [2]
- May 2014 [1]
- March 2014 [1]
- January 2014 [2]
- December 2013 [1]
- September 2013 [2]
- July 2013 [2]
- June 2013 [1]
- May 2013 [1]
- February 2013 [1]
- December 2012 [2]
- October 2012 [2]
- August 2012 [2]
- June 2012 [1]
- April 2012 [2]
- March 2012 [1]
- February 2012 [1]
- January 2012 [1]
- November 2011 [2]
- October 2011 [1]
- September 2011 [2]
- August 2011 [2]
- July 2011 [3]
- June 2011 [4]
- May 2011 [3]
- April 2011 [3]
- March 2011 [3]
- February 2011 [3]