
ウィリアム・ワイラー 〜その階段でドラマが起こる〜
2015.10.01
ワイラーとヒューマニズム
 ウィリアム・ワイラーは1930年代から1960年代にかけて多くの傑作を手がけ、アカデミー賞をはじめとする数々の名誉に輝いた監督である。『ローマの休日』(1953年)と『ベン・ハー』(1959年)の監督というだけでも映画史におけるその存在感の大きさは格別だ。
ウィリアム・ワイラーは1930年代から1960年代にかけて多くの傑作を手がけ、アカデミー賞をはじめとする数々の名誉に輝いた監督である。『ローマの休日』(1953年)と『ベン・ハー』(1959年)の監督というだけでも映画史におけるその存在感の大きさは格別だ。
しかし彼の映画にみられるいくつかのパターンは、必ずしも万人受けするものとは言えない。そのうちの一つは、明るい雰囲気で幕を開けて、次第にトーンが暗くなり、シリアスになるストーリー展開を印象付ける演出で、ベティ・デイヴィスが主演を務めた『黒蘭の女』(1938年)や『偽りの花園』(1941年)はその好例と言える。オープニングの雰囲気がラストでは雲散霧消している。
何が人間らしく、何が人間らしくないかを問うヒューマニズムをめぐる葛藤も、ワイラー作品おなじみのテーマである。そのヒューマニズムの表現はいささか説教臭く、それは極端な信条や感情に溺れている人物に対して、ややお節介な第三者が意見するパターンを用いることにより、余計強調されることになる。例えば『探偵物語』(1951年)では、いかなる犯罪もいかなる虚偽も許容できないマクラウド刑事(カーク・ダグラス)に同僚たちがあれこれ差し出がましく忠告し、『ベン・ハー』(1959年)では、復讐心に燃えるベン・ハー(チャールトン・ヘストン)の人間性にエスター(ハイヤ・ハラリート)が疑問を投げかける。このような形でのヒューマニズムの提示にはほとんど意味が感じられない。『ローマの休日』(1953年)でアン王女(オードリー・ヘプバーン)が堅苦しい風習や過密なスケジュールに堪えきれずヒステリーを起こす場面の方がよほど効果的である。
ワイラー自身が紋切り型のヒューマニズムを盲信していなかったことは、多数の作品が証明している。『デッド・エンド』(1937年)のマーティン(ハンフリー・ボガート)も、『西部の男』(1940年)のロイ・ビーン(ウォルター・ブレナン)も、『偽りの花園』のレジーナ(ベティ・デイヴィス)も、『女相続人』(1949年)のキャサリン(オリヴィア・デ・ハビランド)も、ヒューマニズムに目覚めるわけではない。ワイラーが二度も映画化したリリアン・ヘルマン原作の『子供の時間』ーーつまり『この三人』(1936年)と『噂の二人』(1961年)に登場し、大人たちの人生を滅茶苦茶にする邪悪な少女メアリー(ボニータ・グランヴィル、カレン・バルキン)も、決して改心することはないだろう。凡百のヒューマニストが描くような子供はそこにはいない。このメアリーを創造したのはヘルマンだが、肉付けして視覚化させたのはワイラーなのだ。こういった作品を観ると、ワイラーがヒューマニズムそのものよりも、むしろ人間と人間とのぶつかり合いから生まれる新しい関係性、ないし、崩壊する関係性の方に関心を寄せていたことがはっきりと分かる。
ドラマの場としての階段
そして重要なのは、これらの人間ドラマが演じられる場面に、必ず階段が使われていることである。おそらくワイラーは『この三人』から『我等の生涯の最良の年』(1946年)までたびたびコンビを組んだ名カメラマン、グレッグ・トーランドとの共同作業を経て、階段という舞台装置を意識的にとりいれるようになったのだろう。パン・フォーカスを駆使して奥行きの構図の美しさや明晰さを打ち出す上で、階段は何かと重宝される。それにしても、その見せ方は舞台装置の一つという枠を超えて、ほとんど偏愛の境地に達していると考えざるを得ない。緊張感を出すドラマの見せ場、登場人物たちの関係性や運命を決定づける大事な場面には階段(もしくは階段のある場所)が不可欠である、と言わんばかりに執着しているのだ。
まずワイラーの出世作とも言うべき『この三人』では、マーサ(ミリアム・ホプキンス)とカレン(マール・オベロン)が決別する場面で階段を印象的に使っている。こういった例を挙げればきりがない。『デッド・エンド』では犯罪者マーティンが母親に拒絶されるドラマティックな場面、『黒蘭の女』では改心したジュリー(ベティ・デイヴィス)が愛する男のために命を賭けた決断をする場面、『偽りの花園』では冷酷なレジーナに娘アレクサンドラ(テレサ・ライト)が初めて反抗する場面や心臓を患っているホレース(ハーバート・マーシャル)が倒れる場面などが、まさに階段で繰り広げられる。後期の作品『コレクター』(1965年)でミランダ(サマンサ・エッガー)を監禁する病的な青年フレディ(テレンス・スタンプ)の邸宅にも立派な階段があり、最初に観客を緊張させる場面(ミランダが風呂の水を溢れさせる場面)でこの舞台装置を活用している。ミランダにとって唯一最大の脱出のチャンスが訪れるのも、フレディが外の監禁部屋への階段を下りたときである(結局捕まったことで、ミランダの運命は決する)。
不幸な出来事ばかりではなく、幸福な出来事も階段で起こる。『ミニヴァー夫人』(1942年)を例に挙げるなら、やがて戦争によって失われる家族の幸せの絶頂を示す場面(終盤、幸せだった頃のミニヴァー家を観る者に思い出させる場面が同じアングルで撮られる)、『我等の生涯の最良の年』なら、戦争で両手を失った新郎ホーマー(ハロルド・ラッセル)を愛する幼なじみのウィルマ(キャシー・オドネル)がウェディングドレスで現れる場面、『ベン・ハー』なら、奇跡によって困難を乗り越えた家族が身を寄せあうラスト・シーンがそれに該当する。
シンボルとしての階段
身も蓋もないことを言えば、そこが階段である必然性はないはずなのだが、ワイラーは階段にこだわる。その重用ぶりは尋常ではない。『黄昏』(1952年)でも、汽車のステップでキャリー(ジェニファー・ジョーンズ)が妻子あるジョージ(ローレンス・オリヴィエ)と駆け落ちすることを決断するが、ほかにも、キャリーが女優として第一歩を踏み出すオーディションの場面や、落魄したジョージが出世したキャリーに物乞いする場面で階段をしっかりと映している。
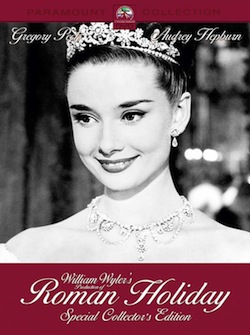 むろん、ワイラーと階段について語るなら、『ローマの休日』を外すことはできない。人間らしい生活に憧れるアン王女がスペイン広場でジェラートを食べているとき、特ダネを手に入れたい新聞記者のジョー(グレゴリー・ペック)が再会を装って階段をおりてくる。このあまりにも有名な場面から、アンとジョーの冒険が本格的にスタートするのだ。ただし、大使館を抜け出す場面、ジョーの住まいから街へ出る場面、船上ダンスパーティに向かう場面などで階段をおりるシーンが繰り返されているのも重要である。これらが市井におりていくことを意味しているのは言うまでもない。その積み重ねの後、王女が記者会見に応じるラスト・シーンが用意される。王女は王室で決められた言葉を自分自身の言葉に変えて述べると、自らの意志で階段をおりて記者団に挨拶をする。階段の高さにすればわずかだが、王女にとっては大きな決断である。映画の文法として完璧としか言いようがない。
むろん、ワイラーと階段について語るなら、『ローマの休日』を外すことはできない。人間らしい生活に憧れるアン王女がスペイン広場でジェラートを食べているとき、特ダネを手に入れたい新聞記者のジョー(グレゴリー・ペック)が再会を装って階段をおりてくる。このあまりにも有名な場面から、アンとジョーの冒険が本格的にスタートするのだ。ただし、大使館を抜け出す場面、ジョーの住まいから街へ出る場面、船上ダンスパーティに向かう場面などで階段をおりるシーンが繰り返されているのも重要である。これらが市井におりていくことを意味しているのは言うまでもない。その積み重ねの後、王女が記者会見に応じるラスト・シーンが用意される。王女は王室で決められた言葉を自分自身の言葉に変えて述べると、自らの意志で階段をおりて記者団に挨拶をする。階段の高さにすればわずかだが、王女にとっては大きな決断である。映画の文法として完璧としか言いようがない。
階段とは通過する場所であり、安定しない場所である。そこには段差があり、すなわち平坦ではない。上と下をつなぐもの、別々の空間をつなぐものであり、水平でもない。それがワイラー作品の中では舞台装置以上の意味を持ち、緊張の高まりや感情の激しい揺らぎ、人間関係の悲劇的なぶつかり合いや幸福なつながり合い、身分の差の広がりや狭まりを示すシンボルとして多方向に機能している。換言すると、ワイラーは階段そのものを「ドラマ的な存在」と見立てて、階段をのぼる、階段をおりるという人間の日常的行為に、その行為以上の劇的ニュアンスを付与し、登場人物の運命にまで影響を及ぼさせているのである。
確固たる批判精神
ウィリアム・ワイラーほどハリウッドの栄光に包まれた監督もそうそういないが、彼は単なる古き良き時代の監督でもなければ、上っ面のヒューマニズムを謳った監督でもない。賞レースに強く、メジャーな存在であるがゆえに「無難」「穏健」「良心的」「正統派」といったイメージを抱かれがちだが、その作品をよく観れば、意味深い構図に瞠目させられるし、そうそうたる名優たちの実力を引き出す手腕においても卓越したものを感じさせる(ワイラーは何度も撮り直すことで有名だった)。そして何より、人生に向ける温かい視線のみならず、厳しい視線も伝わってくる。
彼自身、確固たる批判精神を持った人間であり、ハリウッドを巻き込んだ「赤狩り」に対しては一切の協力を拒んだ(『ローマの休日』の脚本家は赤狩りで追放されたダルトン・トランボである)。1930年代に撮った『この三人』ではレズビアンの要素が排除されたが、25年後の『噂の二人』でリベンジし、トップスターのオードリー・ヘプバーンとシャーリー・マクレーンを起用してこのテーマに挑んでいる。ちなみに、原作者リリアン・ヘルマンも赤狩りで干された人である。黒人差別問題にも敏感で、『黒蘭の女』では南部の白人女性が黒人たちと分け隔てなく接して合唱する場面を描き、それから32年後の『L・B・ジョーンズの解放』(1970年)ではより明確に人種差別に焦点を当てている。戦後まだ1年しか経っていない1946年に公開された『我等の生涯の最良の年』では、アメリカに帰還したアル軍曹(フレドリック・マーチ)の息子ロブ(マイケル・ホール)の口を通して、原爆の放射能がもたらす深刻な影響を語らせ、「JAP」と言う父親に対して、「JAPANESE」と言わせている。大衆の好みへの迎合や甘ったるいヒューマニズムで撮ることができるような映画は、ワイラーのフィルモグラフィにはないのである。
【関連サイト】
William Wyler(IMDb)

しかし彼の映画にみられるいくつかのパターンは、必ずしも万人受けするものとは言えない。そのうちの一つは、明るい雰囲気で幕を開けて、次第にトーンが暗くなり、シリアスになるストーリー展開を印象付ける演出で、ベティ・デイヴィスが主演を務めた『黒蘭の女』(1938年)や『偽りの花園』(1941年)はその好例と言える。オープニングの雰囲気がラストでは雲散霧消している。
何が人間らしく、何が人間らしくないかを問うヒューマニズムをめぐる葛藤も、ワイラー作品おなじみのテーマである。そのヒューマニズムの表現はいささか説教臭く、それは極端な信条や感情に溺れている人物に対して、ややお節介な第三者が意見するパターンを用いることにより、余計強調されることになる。例えば『探偵物語』(1951年)では、いかなる犯罪もいかなる虚偽も許容できないマクラウド刑事(カーク・ダグラス)に同僚たちがあれこれ差し出がましく忠告し、『ベン・ハー』(1959年)では、復讐心に燃えるベン・ハー(チャールトン・ヘストン)の人間性にエスター(ハイヤ・ハラリート)が疑問を投げかける。このような形でのヒューマニズムの提示にはほとんど意味が感じられない。『ローマの休日』(1953年)でアン王女(オードリー・ヘプバーン)が堅苦しい風習や過密なスケジュールに堪えきれずヒステリーを起こす場面の方がよほど効果的である。
ワイラー自身が紋切り型のヒューマニズムを盲信していなかったことは、多数の作品が証明している。『デッド・エンド』(1937年)のマーティン(ハンフリー・ボガート)も、『西部の男』(1940年)のロイ・ビーン(ウォルター・ブレナン)も、『偽りの花園』のレジーナ(ベティ・デイヴィス)も、『女相続人』(1949年)のキャサリン(オリヴィア・デ・ハビランド)も、ヒューマニズムに目覚めるわけではない。ワイラーが二度も映画化したリリアン・ヘルマン原作の『子供の時間』ーーつまり『この三人』(1936年)と『噂の二人』(1961年)に登場し、大人たちの人生を滅茶苦茶にする邪悪な少女メアリー(ボニータ・グランヴィル、カレン・バルキン)も、決して改心することはないだろう。凡百のヒューマニストが描くような子供はそこにはいない。このメアリーを創造したのはヘルマンだが、肉付けして視覚化させたのはワイラーなのだ。こういった作品を観ると、ワイラーがヒューマニズムそのものよりも、むしろ人間と人間とのぶつかり合いから生まれる新しい関係性、ないし、崩壊する関係性の方に関心を寄せていたことがはっきりと分かる。
ドラマの場としての階段
そして重要なのは、これらの人間ドラマが演じられる場面に、必ず階段が使われていることである。おそらくワイラーは『この三人』から『我等の生涯の最良の年』(1946年)までたびたびコンビを組んだ名カメラマン、グレッグ・トーランドとの共同作業を経て、階段という舞台装置を意識的にとりいれるようになったのだろう。パン・フォーカスを駆使して奥行きの構図の美しさや明晰さを打ち出す上で、階段は何かと重宝される。それにしても、その見せ方は舞台装置の一つという枠を超えて、ほとんど偏愛の境地に達していると考えざるを得ない。緊張感を出すドラマの見せ場、登場人物たちの関係性や運命を決定づける大事な場面には階段(もしくは階段のある場所)が不可欠である、と言わんばかりに執着しているのだ。
まずワイラーの出世作とも言うべき『この三人』では、マーサ(ミリアム・ホプキンス)とカレン(マール・オベロン)が決別する場面で階段を印象的に使っている。こういった例を挙げればきりがない。『デッド・エンド』では犯罪者マーティンが母親に拒絶されるドラマティックな場面、『黒蘭の女』では改心したジュリー(ベティ・デイヴィス)が愛する男のために命を賭けた決断をする場面、『偽りの花園』では冷酷なレジーナに娘アレクサンドラ(テレサ・ライト)が初めて反抗する場面や心臓を患っているホレース(ハーバート・マーシャル)が倒れる場面などが、まさに階段で繰り広げられる。後期の作品『コレクター』(1965年)でミランダ(サマンサ・エッガー)を監禁する病的な青年フレディ(テレンス・スタンプ)の邸宅にも立派な階段があり、最初に観客を緊張させる場面(ミランダが風呂の水を溢れさせる場面)でこの舞台装置を活用している。ミランダにとって唯一最大の脱出のチャンスが訪れるのも、フレディが外の監禁部屋への階段を下りたときである(結局捕まったことで、ミランダの運命は決する)。
不幸な出来事ばかりではなく、幸福な出来事も階段で起こる。『ミニヴァー夫人』(1942年)を例に挙げるなら、やがて戦争によって失われる家族の幸せの絶頂を示す場面(終盤、幸せだった頃のミニヴァー家を観る者に思い出させる場面が同じアングルで撮られる)、『我等の生涯の最良の年』なら、戦争で両手を失った新郎ホーマー(ハロルド・ラッセル)を愛する幼なじみのウィルマ(キャシー・オドネル)がウェディングドレスで現れる場面、『ベン・ハー』なら、奇跡によって困難を乗り越えた家族が身を寄せあうラスト・シーンがそれに該当する。
シンボルとしての階段
身も蓋もないことを言えば、そこが階段である必然性はないはずなのだが、ワイラーは階段にこだわる。その重用ぶりは尋常ではない。『黄昏』(1952年)でも、汽車のステップでキャリー(ジェニファー・ジョーンズ)が妻子あるジョージ(ローレンス・オリヴィエ)と駆け落ちすることを決断するが、ほかにも、キャリーが女優として第一歩を踏み出すオーディションの場面や、落魄したジョージが出世したキャリーに物乞いする場面で階段をしっかりと映している。
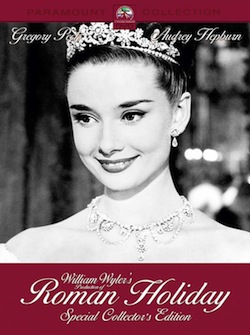
階段とは通過する場所であり、安定しない場所である。そこには段差があり、すなわち平坦ではない。上と下をつなぐもの、別々の空間をつなぐものであり、水平でもない。それがワイラー作品の中では舞台装置以上の意味を持ち、緊張の高まりや感情の激しい揺らぎ、人間関係の悲劇的なぶつかり合いや幸福なつながり合い、身分の差の広がりや狭まりを示すシンボルとして多方向に機能している。換言すると、ワイラーは階段そのものを「ドラマ的な存在」と見立てて、階段をのぼる、階段をおりるという人間の日常的行為に、その行為以上の劇的ニュアンスを付与し、登場人物の運命にまで影響を及ぼさせているのである。
確固たる批判精神
ウィリアム・ワイラーほどハリウッドの栄光に包まれた監督もそうそういないが、彼は単なる古き良き時代の監督でもなければ、上っ面のヒューマニズムを謳った監督でもない。賞レースに強く、メジャーな存在であるがゆえに「無難」「穏健」「良心的」「正統派」といったイメージを抱かれがちだが、その作品をよく観れば、意味深い構図に瞠目させられるし、そうそうたる名優たちの実力を引き出す手腕においても卓越したものを感じさせる(ワイラーは何度も撮り直すことで有名だった)。そして何より、人生に向ける温かい視線のみならず、厳しい視線も伝わってくる。
彼自身、確固たる批判精神を持った人間であり、ハリウッドを巻き込んだ「赤狩り」に対しては一切の協力を拒んだ(『ローマの休日』の脚本家は赤狩りで追放されたダルトン・トランボである)。1930年代に撮った『この三人』ではレズビアンの要素が排除されたが、25年後の『噂の二人』でリベンジし、トップスターのオードリー・ヘプバーンとシャーリー・マクレーンを起用してこのテーマに挑んでいる。ちなみに、原作者リリアン・ヘルマンも赤狩りで干された人である。黒人差別問題にも敏感で、『黒蘭の女』では南部の白人女性が黒人たちと分け隔てなく接して合唱する場面を描き、それから32年後の『L・B・ジョーンズの解放』(1970年)ではより明確に人種差別に焦点を当てている。戦後まだ1年しか経っていない1946年に公開された『我等の生涯の最良の年』では、アメリカに帰還したアル軍曹(フレドリック・マーチ)の息子ロブ(マイケル・ホール)の口を通して、原爆の放射能がもたらす深刻な影響を語らせ、「JAP」と言う父親に対して、「JAPANESE」と言わせている。大衆の好みへの迎合や甘ったるいヒューマニズムで撮ることができるような映画は、ワイラーのフィルモグラフィにはないのである。
(阿部十三)
【関連サイト】
William Wyler(IMDb)
[ウィリアム・ワイラー略歴]
1902年7月1日、ドイツのミュールハウゼン生まれ。パリでヴァイオリニストを志すが挫折し、母方の親戚であるユニバーサル・スタジオ社長カール・レムリを頼って渡米。同社で研鑽を積み、1926年に監督に昇進した。西部劇やコメディを数多く撮り、1936年にサミュエル・ゴールドウィンのプロダクションへ移籍。MGMで撮った『ミニヴァー夫人』(1942年)がアカデミー作品賞、監督賞を含む6部門で受賞し、監督の地位を確立。空軍に従軍後(片耳の聴力を失った)、『我等の生涯の最良の年』(1946年)でアカデミー賞9部門受賞。1950年代には『ローマの休日』(1953年)などの作品で大きな成功を収めた。『友情ある説得』(1956年)でカンヌ映画祭パルム・ドールを受賞し、『ベン・ハー』(1959年)でアカデミー賞11部門受賞。1960年代以降は、現代人の歪んだ愛の形にメスを入れた『コレクター』(1965年)などの問題作を発表する一方、コメディ『おしゃれ泥棒』(1966年)やミュージカル『ファニー・ガール』(1968年)をヒットさせた。1981年7月27日死去。
1902年7月1日、ドイツのミュールハウゼン生まれ。パリでヴァイオリニストを志すが挫折し、母方の親戚であるユニバーサル・スタジオ社長カール・レムリを頼って渡米。同社で研鑽を積み、1926年に監督に昇進した。西部劇やコメディを数多く撮り、1936年にサミュエル・ゴールドウィンのプロダクションへ移籍。MGMで撮った『ミニヴァー夫人』(1942年)がアカデミー作品賞、監督賞を含む6部門で受賞し、監督の地位を確立。空軍に従軍後(片耳の聴力を失った)、『我等の生涯の最良の年』(1946年)でアカデミー賞9部門受賞。1950年代には『ローマの休日』(1953年)などの作品で大きな成功を収めた。『友情ある説得』(1956年)でカンヌ映画祭パルム・ドールを受賞し、『ベン・ハー』(1959年)でアカデミー賞11部門受賞。1960年代以降は、現代人の歪んだ愛の形にメスを入れた『コレクター』(1965年)などの問題作を発表する一方、コメディ『おしゃれ泥棒』(1966年)やミュージカル『ファニー・ガール』(1968年)をヒットさせた。1981年7月27日死去。
[主な監督作品]
1936年『この三人』『孔雀夫人』/1937年『デッド・エンド』/1938年『黒蘭の女』/1939年『嵐が丘』/1940年『西部の人』/1941年『偽りの花園』/1942年『ミニヴァー夫人』/1946年『我等の生涯の最良の年』/1949年『女相続人』/1951年『探偵物語』/1952年『黄昏』/1953年『ローマの休日』/1955年『必死の逃亡者』/1956年『友情ある説得』/1958年『大いなる西部』/1959年『ベン・ハー』/1961年『噂の二人』/1965年『コレクター』/1966年『おしゃれ泥棒』/1968年『ファニー・ガール』/1970年『L・B・ジョーンズの解放』
1936年『この三人』『孔雀夫人』/1937年『デッド・エンド』/1938年『黒蘭の女』/1939年『嵐が丘』/1940年『西部の人』/1941年『偽りの花園』/1942年『ミニヴァー夫人』/1946年『我等の生涯の最良の年』/1949年『女相続人』/1951年『探偵物語』/1952年『黄昏』/1953年『ローマの休日』/1955年『必死の逃亡者』/1956年『友情ある説得』/1958年『大いなる西部』/1959年『ベン・ハー』/1961年『噂の二人』/1965年『コレクター』/1966年『おしゃれ泥棒』/1968年『ファニー・ガール』/1970年『L・B・ジョーンズの解放』
月別インデックス
- May 2024 [1]
- January 2023 [1]
- November 2021 [1]
- April 2021 [1]
- September 2020 [2]
- May 2020 [1]
- April 2020 [1]
- January 2020 [1]
- July 2019 [1]
- March 2019 [1]
- January 2019 [1]
- November 2018 [3]
- June 2018 [1]
- April 2018 [1]
- October 2017 [2]
- September 2017 [1]
- June 2017 [2]
- March 2017 [2]
- November 2016 [1]
- August 2016 [1]
- July 2016 [2]
- February 2016 [1]
- October 2015 [1]
- August 2015 [1]
- June 2015 [1]
- April 2015 [1]
- February 2015 [1]
- January 2015 [2]
- September 2014 [1]
- July 2014 [2]
- May 2014 [1]
- March 2014 [1]
- January 2014 [2]
- December 2013 [1]
- September 2013 [2]
- July 2013 [2]
- June 2013 [1]
- May 2013 [1]
- February 2013 [1]
- December 2012 [2]
- October 2012 [2]
- August 2012 [2]
- June 2012 [1]
- April 2012 [2]
- March 2012 [1]
- February 2012 [1]
- January 2012 [1]
- November 2011 [2]
- October 2011 [1]
- September 2011 [2]
- August 2011 [2]
- July 2011 [3]
- June 2011 [4]
- May 2011 [3]
- April 2011 [3]
- March 2011 [3]
- February 2011 [3]