2011年4月アーカイブ

シドニー・ルメットの代表作というと、大半の人は『十二人の怒れる男』を挙げるだろう。アル・パチーノが好きな人なら『狼たちの午後』や『セルピコ』を選ぶかもしれない。いずれも硬派な社会派作品として知られ、評価も高い。 ただ、身も蓋もないことを書くようだが、私自身はこの監督に何の思い入れもない。社会派と言われているわりにはシャープさが足りないし、そこまで社会の深層...
[続きを読む](2011.04.30)
高校3年生の時に大学受験に失敗してしまった僕は、1991年の4月から約1年間を代々木ゼミナール本校で過ごした。浪人、予備校生活に対しては、暗いイメージを持つ人が大半だろう。たしかに、浪人はひたすら勉強しなければいけないし、世間体も非常に悪いし、「来年も受からなかったらどうしよう!」というプレッシャーはズシリと心に絶えず重くのしかかる。しかし、「ちゃんと勉強...
[続きを読む](2011.04.30)
カイルベルトについて語る時に決まって出てくる言葉は「質実剛健」「無骨」といったものばかり。渋いと評する人もいるが、それも褒め言葉ではなく単に「地味」「色気がない」の裏返しとして言っているだけ。これには本人のジャガイモみたいな風采も少しは影響しているのかもしれない。 そのイメージが変わってきたのはワーグナーの『指環』のバイロイト・ライヴ音源が発売されてからで...
[続きを読む](2011.04.28)
2003年9月8日、101歳で亡くなったレニ・リーフェンシュタール。その劇的な生涯は、生前から様々な形で取り沙汰されてきたが、これからも決して明かされない秘密のようなものを包含したまま、否定的に、時に誇張され、人々に語り継がれてゆくことだろう。 舞踏家だったレニは、アーノルト・ファンク監督の山岳映画『聖山』で女優に転身した。初監督作は『青の光』。これを観て...
[続きを読む](2011.04.27)
ワルターからミンコフスキまで 名盤と呼ばれている録音は少なくない。長年、最高の「40番」とされてきたブルーノ・ワルター/コロンビア響の組み合わせを筆頭に、オットー・クレンペラー/フィルハーモニア管、カール・ベーム/ウィーン・フィル、ヨーゼフ・カイルベルト/バイエルン放送交響楽団(ライヴ)などなど、どれも素晴らしい出来である。 ワルターならコロンビア響よりウィ...
[続きを読む](2011.04.23)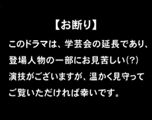
スケ番もののドラマの名作が数々生まれた1980年代だが、そのムーヴメントは1990年代に入るとピタリと止まる。最大の原因は現実世界でのスケ番カルチャーの衰退だろう。90年代に入ると少女達の反抗の仕方は、もっとファッショナブルに洗練されてゆく。スケ番の象徴的アイテムとも言うべき長いスカートやペシャンコの学生カバンはすっかり時代遅れとなり、プロレスの悪役のよう...
[続きを読む](2011.04.23)
ジョン・コルトレーン『ブルー・トレイン』1957年録音 金色に輝くテナー・サックスをスラリと構え、音域のギリギリの限りを縦横無尽に駆け巡り、暴れ馬のような野趣に溢れたトーンを心底優雅に乗りこなしてみせたプレイヤー、それがジョン・コルトレーンだ。彼の息遣いから生まれた全ての音は、今なお人々を虜にして止まない。楽器屋の店先でウィンドウにピッタリ貼り付き、店員に鬱...
[続きを読む](2011.04.23)
いかにも隙のない絶対的な美人の前では、男は往々にして無力になるものだ。口説きの対象というよりは憧れ、崇拝の対象。映画で観るグレタ・ガルボは、まさにそんなイメージの女だった。マスコミを徹底的に遠ざけ、私生活を明かさなかったことも、彼女の神秘性を高めるのに一役買っていた。 1905年9月18日、スウェーデン生まれ。本名グレタ・ロヴィーサ・グスタフソン。映画に初...
[続きを読む](2011.04.20)
モーツァルトの運命交響曲 交響曲第40番の第1楽章は、クラシック・ファンならずとも誰もが一度は耳にしたことがあるに違いない。あの哀愁漂う美しい主題は、モーツァルトの書いた数ある名旋律の中でも『アイネ・クライネ・ナハトムジーク』と並んで最も知られているものであり、世界中の人から愛されている。この曲をテーマにした文章がこれまでにいったいどれだけ書かれたことだろう...
[続きを読む](2011.04.18)
ジャン・ヴィゴが29年の短い生涯で撮った映画はわずか4作。全部の長さを合わせても160分に満たない。保存状態も良いとはいえず、フィルムにはキズがたくさんある。にもかかわらず、ヴィゴは今なお映画ファンの間で熱い談義の対象であり続けてきた。フランソワ・トリュフォーをはじめ、その作品から創作の啓示を受けた映画人も多い。一体ヴィゴの何がここまで人を夢中にさせるのか...
[続きを読む](2011.04.16)
みなさんはスケ番が好きですか? 僕は大好きです! と唐突に始めてみたが、「こんな原稿、誰も読まないかもなあ」と、早くも激しい孤独を感じている僕なのであった......。なにしろ「俺もスケ番が大好きなんだよ!」と同胞と手を握り合ったことは、僕の人生の中で一度もないのだから。しかし、スケ番が日本のエンタテインメントを語る上で決して無視出来ない存在であるのは、紛...
[続きを読む](2011.04.16)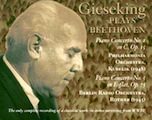
ワルター・ギーゼキングの「皇帝」といえば、ヘルベルト・フォン・カラヤン/フィルハーモニア管弦楽団と組んだ録音が有名である。昔から名演として知られているので、聴いたことがある人も多いだろう。アルチェオ・ガリエラ/フィルハーモニア管弦楽団との録音もあるが、こちらはカラヤン盤に比べると薄味すぎて物足りない。そこが自己主張の強いベートーヴェンらしくなくてかえって良...
[続きを読む](2011.04.13)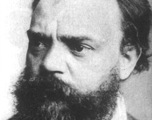
涸れることを知らぬ旋律の泉 アントニン・ドヴォルザークは、1841年9月8日、豊かな自然に囲まれたモルダウ河ほとりのネラホゼヴェス村で生まれた。家は肉屋兼居酒屋。彼は幼い頃から楽器に親しみ、音楽家として生きることを望むが、父親に言われるまま肉屋職人としての資格を取得した。しかし最終的に父親が折れ、18歳のドヴォルザークはプラハの小さな楽団のヴィオラ奏者となり...
[続きを読む](2011.04.11)
おお、運命の女神よ 生命の息吹あふれる春に、カール・オルフの『カルミナ・ブラーナ』ほどぴったりくる作品はない。この音楽に耳を傾けていると、肉体が開放され、奮い立ち、人生のさまざまな揉めごとや災いの山に向かって猛然と突き進んでいこう、という雄々しい気持ちになってくる。効果的に繰り返される劇的なメロディーや千変万化するリズム、声を限りに歌われる力強い合唱が、私た...
[続きを読む](2011.04.10)声が聞こえないなんて、と不満を漏らす人もいるだろうが、顔の表情、体の動作、仕草、字幕で全てを表現するサイレント映画は、意外なほど雄弁である。声を媒介としない分、登場人物の心情がそのまま画面から迫り伝わってくる。そして絵画でも見ているかのように想像力が刺激される。1920年代を〈映画の黄金時代〉と呼ぶ人がいるのも、いまだに先鋭的な作品でサイレント的手法が好ん...
[続きを読む](2011.04.10)
1990年9月、龍膽寺雄は「墓を造る」を執筆した。この作品は翌年4月の『湘南文学』創刊号に掲載、それから1年あまり経った1992年6月3日、心不全でこの世を去った。「墓を造る」にはその題名通り丹沢山の裾に墓を造ったことが記されている。ほかにも大好きだというギボウシの花にまつわる思い出、慶大生の頃にアインシュタインに会ったこと、神様に「貸し」を作る生き方など...
[続きを読む](2011.04.09)
シャルル・ミュンシュが遺した録音に接していると、しばしばライヴを目の当たりにしているような気分になる。そこには生々しい臨場感がある。彼はその著作『私は指揮者である』の中で、「コンサートは毎回頭脳と筋肉と神経のエネルギーを信じられないほど消耗させる」と書いているが、そうした全力投球の姿勢はレコーディングでも変わらなかったに違いない。 ミュンシュは1891年9...
[続きを読む](2011.04.08)
ジャン・コクトーはレオナルド・ダ・ヴィンチの系譜に属する最後の万能人である。詩、小説、戯曲、評論、絵画、陶芸、彫刻、舞台演出、映画監督、バレエ制作などなど、多方面で大きな功績を残した。人呼んで〈20の顔を持つ男〉。そんな彼にあえてひとつだけ肩書きを与えるとすれば、やはり詩人ということになるだろう。その溢れかえる才能から生まれたオブジェは、言ってみれば全て〈...
[続きを読む](2011.04.06)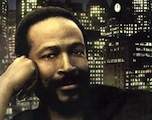
マーヴィン・ゲイ『ミッドナイト・ラヴ』1982年作品 R&B/ソウル・ミュージック界にその名を色濃くかつ深く刻むマーヴィン・ゲイの大復活作にして生前最後のオリジナル・アルバムという大看板を背負った作品にしては、このカヴァー写真の安っぽさに違和感を覚える人も少なくないのでは...? 低級な匂いを放つのは、何処かの都会の夜景を背景に、素肌にジャケット(実...
[続きを読む](2011.04.06)
再評価の動きが出始めたのは1970年代のことである。川端康成の死(1972年4月16日)から1年ほど経った1973年3月、中央大学の古俣裕介氏が論文「龍膽寺雄ノート」を発表。その辺りから見直しが進み、1980年代半ばには昭和書院から全集が出た(全集といっても完全なものではなく、いわゆる〈カストリ雑誌〉に書いたものは収録されていない)。 この全集の月報で、若...
[続きを読む](2011.04.02)
宗教と官能 ダンディ、ショーソン、デュパルクの師匠であり、近代フランス音楽の父と言われるセザール・フランク。ベルギー生まれだが、「フランスのブルックナー」と呼ばれていたこともある。 誠実温厚な人柄で、質素な生活を営み、信仰に篤く、教会音楽を数多く手がけ、教会のオルガン奏者として生涯を終えたということもあり、多くの研究者はフランクの作品について説明する際、まず...
[続きを読む](2011.04.02)