
『血みどろの入江』 〜スプラッターなのに、哀愁〜
2020.12.22
本格的なスプラッター映画
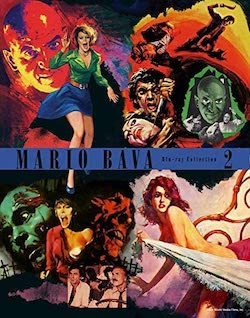
もともとは女優のラウラ・ベッティが、マリオ・バーヴァと夕食をとりながら話している時に、この映画の案が出たらしい。脚本は、バーヴァがダルダーノ・サチェッティと共に完成させた。サチェッティは、ダリオ・アルジェントの『わたしは目撃者』(1971年)で注目され始めたばかりの新鋭だ。
主演はボンドガールとして知名度のあるクローディーヌ・オージェだが、出演者それぞれに見せ場がある。その顔ぶれも多彩というか異色で、前述のラウラ・ベッティ、『二匹の流れ星』(1967年)の悪役クラウディオ・ヴォロンテ(クラウディオ・カマソ)、『鉄格子の彼方』(1949年)のイザ・ミランダも出演している。
入江の相続権をめぐって
裕福な老婦人フェデリカ(イザ・ミランダ)が窓辺で車椅子にすわり、雨降る入江を眺めている。甘く切ないメロディーが流れ、センチメンタルなムードが漂う。老婦人は一軒の家の灯に目を遣ると、窓辺から離れ、鏡に映った自分の老いた顔から目をそらして電気を消す。まるでこれから遠い過去の恋愛を回想するかのようなオープニング。往年の名女優の演技が光っている。
老婦人は、部屋から出ようとしたところで首にロープをかけられ、首吊りに見せかけて殺される。犯人は、彼女の夫である伯爵(ジョヴァンニ・ヌヴォレッティ)だ。しかし、伯爵もまた何者かによってナイフで刺され、息絶える。その後、伯爵の死体はどこかに隠される。警察はフェデリカの死を自殺と断定し、「失踪した」伯爵を捜索する。
ここから、フェデリカが所有していた入江の相続権をめぐり、様々な思惑が交錯する。主要人物は7人。フェデリカの義理の娘レナータ(クローディーヌ・オージェ)とその尻に敷かれている夫アルベルト(ルイジ・ピスティッリ)、入江を埋め立てて土地開発を行おうと企む建築家ヴェンチューラ(クリス・アヴラム)とその愛人兼秘書のローラ(アンナ・マリア・ロサティ)、昆虫研究家パオロ(レオポルド・トリエステ)と占いに凝っているその妻アンナ(ラウラ・ベッティ)、フェデリカの私生児サイモン(クラウディオ・ヴォロンテ)である。彼らに加えて、おバカな若者4人が入江に遊びに来たことで、殺しの舞台が整う。
若者のうちの一人、ヒルダ(ブリギッテ・スカイ)が入江で泳ぎ、水中に隠されていた伯爵の死体を見つけてしまったことから、惨劇の火蓋が切って落とされる。ほかの3人は留守中のヴェンチューラ邸に不法侵入し、酒を飲んだり、ベッドで抱き合ったりしていたため、死体を見つけたヒルダの悲鳴は聞こえない。
一部始終をうかがっていた犯人は、ヒルダを鉈で殺害する。喉元をえぐる描写がなんとも残酷だが、これは序の口で、残りの若者たちも鉈で顔面を割かれたり、性行為中に槍で串刺しにされたりする。ホラー映画では、聖域を侵したり不法侵入したりする輩はろくな死に方をしない。これは一種のお約束だ。なお、特殊メイクを担当したのはカルロ・ランバルディ。この人の名前を出すだけでも、ゴア描写のクオリティがどれだけ高いか想像できるだろう。後年、これらの描写は「13日の金曜日」シリーズなどで模倣されることになる。
入り乱れる殺人劇
フェデリカにはサイモンという婚外子がいて、彼が入江を相続することになっていた。レナータはそのことを事情通のアンナから聞かされ、愕然とする。いくら自分が義理の娘で、伯爵の連れ子であるとはいえ、納得がいかない。
彼女は夫アルベルトと共に、入江のそばに住むサイモンを訪ねるが、そこで水中から引きあげられた父親の亡骸を発見する。腐乱しかかった死体に蛸が吸い付くカットのグロテスクなことといったらない。変わり果てた実父の姿に、彼女はひどいショックを受ける。
夫婦はヴェンチューラの家に行くが、誰もいない。アルベルトが車を取りに行くのを待っている間、レナータは気分が悪くなって洗面台へ向かう。と、そこには4人の若者の死体が並べられている。おぞましい光景に絶句し、逃げ出そうとするレナータ。しかし目の前には斧を持ったヴェンチューラが立っていた......。
惨殺死体をグロテスクな絵画のように並べたショットといえば、J・リー・トンプソン監督の『誕生日はもう来ない』(1981年)やミケーレ・ソアヴィ監督の『アクエリアス』(1987年)が有名だが、これらの作品に影響を与えた可能性は十分にある。バーヴァはこれ以前にも『モデル連続殺人!』(1964年)で2人の女性の死体を重ねて鏡に映すショットを撮っている。
事の真相は......
殺人劇は徐々に入り乱れてくる。かろうじて危機を脱し、開き直ったレナータは、この際、邪魔者を全員殺してしまおうと考える。ホラー映画の中で女性が泣いて怯える時代は終わったのだ。レナータは余計なことに首を突っ込んできたパオロを夫に殺させ、自分はアンナを殺す。後ろから斧で首をばっさりである。次に狙うはサイモンだ。
ここからは事の真相にふれる。
実は、伯爵を殺したのも、4人の若者を殺したのもサイモンである。それを知った悪党のヴェンチューラは、見逃してやるかわりに入江の相続権をよこせとサイモンに迫り、譲渡契約にサインさせていた。
しかし、サイモンは気付いたのである。ヴェンチューラと秘書ローラが伯爵をそそのかし、母親を殺させたことを。伯爵はローラの色仕掛けに引っかかり、フェデリカを殺害すればローラと一緒になれるものと思い、凶行に及んだのだった。
ここからは事の真相にふれる。
実は、伯爵を殺したのも、4人の若者を殺したのもサイモンである。それを知った悪党のヴェンチューラは、見逃してやるかわりに入江の相続権をよこせとサイモンに迫り、譲渡契約にサインさせていた。
しかし、サイモンは気付いたのである。ヴェンチューラと秘書ローラが伯爵をそそのかし、母親を殺させたことを。伯爵はローラの色仕掛けに引っかかり、フェデリカを殺害すればローラと一緒になれるものと思い、凶行に及んだのだった。
怒りを爆発させたサイモンはローラを絞殺し、ヴェンチューラを殺しに行く。その姿はどこか切ない。途中、甘いメロディーが流れるのは、映画の隠しテーマを表面化させるためだろう。それは「母と子の愛」である。
オープニングで老婦人フェデリカが見ていた家は、サイモンが住む小屋である。母親は、ずっと我が子のことを見守っていたのだ。そしてサイモンは、愛する母親を殺した伯爵を葬り、その犯罪を隠すために若者たちを葬った。言ってみれば哀しい話である。スプラッター描写、莫大な遺産、そして切ない母子愛という要素だけを拾うと、この映画は市川崑監督の『犬神家の一族』(1976年)を連想させる。
この後、残りわずかとなった登場人物たちによる死闘が行われ、決着がついたところで、まさかのドンデン返しがあり、皮肉な結末を迎える。唖然必至のエンディングだが、13人(プラス2人の子供。1人は名子役レナート・チェスティだ)の人物を絡ませ、13件の殺人を敢行するという、84分の上映時間では無理があるとしか思えないプロットは、きっちりと消化されている。
チプリアーニの音楽
これは低予算、短期日程で製作された映画であり、子供用のワゴンで移動ショットを撮ったり、森の雰囲気を出すために小枝を調達してカメラの前に配置したりするなど、バーヴァのアイディアが逆境で爆発している。生前、才能と実績に見合う評価を得ていたとは言い難い巨匠の執念が生んだ力作なのだ。
もうひとつ、この映画を特別なものにしているのが、ステルヴィオ・チプリアーニの音楽。『ベニスの愛』、『ラストコンサート』などで知られる美メロの魔術士が、凄惨なスプラッターのために哀愁のメロディーを編んでいる。この音楽があることにより、冒頭でイザ・ミランダが小屋の灯を見遣る時の情愛に満ちた眼差しが印象付けられ、母子愛というテーマが単なる飾りに終わらず、深い意味を持つものとなった。
イタリア語の原題は『Ecologia del delitto(犯罪生態学)』。公開時はまともに評価されず、アメリカでは何度も改題され、一時は『Last House on the Left Part II』(ウェス・クレイヴン監督のデビュー作『鮮血の美学』の原題に2を付けたもの)という不名誉なタイトルを付けられたこともあった。しかし、そういったタイトルに惹かれて観た人たちが作品を支持し、その先駆性と影響力が見直されるようになったことを考えると、悪あがきのような改題も無駄ではなかったと言えるかもしれない。
(阿部十三)
【関連サイト】
月別インデックス
- October 2025 [1]
- March 2025 [1]
- January 2024 [1]
- September 2023 [1]
- May 2023 [1]
- September 2022 [1]
- July 2022 [1]
- April 2022 [1]
- January 2022 [1]
- October 2021 [1]
- August 2021 [1]
- June 2021 [1]
- February 2021 [1]
- January 2021 [1]
- December 2020 [1]
- November 2020 [1]
- July 2020 [1]
- March 2020 [1]
- December 2019 [1]
- November 2019 [1]
- October 2019 [1]
- August 2019 [1]
- May 2019 [1]
- April 2019 [1]
- February 2019 [1]
- December 2018 [2]
- October 2018 [1]
- September 2018 [3]
- August 2018 [3]
- April 2018 [2]
- January 2018 [2]
- November 2017 [1]
- August 2017 [2]
- April 2017 [1]
- February 2017 [1]
- December 2016 [1]
- October 2016 [1]
- July 2016 [1]
- May 2016 [1]
- April 2016 [1]
- January 2016 [1]
- December 2015 [1]
- October 2015 [1]
- July 2015 [1]
- May 2015 [1]
- March 2015 [1]
- December 2014 [1]
- November 2014 [1]
- October 2014 [1]
- September 2014 [1]
- August 2014 [1]
- June 2014 [2]
- April 2014 [2]
- February 2014 [2]
- November 2013 [2]
- October 2013 [2]
- August 2013 [2]
- May 2013 [1]
- April 2013 [1]
- March 2013 [1]
- February 2013 [1]
- January 2013 [1]
- November 2012 [2]
- September 2012 [3]
- August 2012 [1]
- July 2012 [1]
- June 2012 [1]
- May 2012 [4]
- April 2012 [1]
- March 2012 [3]
- February 2012 [1]
- January 2012 [3]
- December 2011 [2]
- November 2011 [2]
- October 2011 [2]
- September 2011 [1]
- August 2011 [2]
- July 2011 [3]
- June 2011 [2]
- May 2011 [3]
- April 2011 [3]
- March 2011 [3]
- February 2011 [3]