
『デカローグ』 〜人間の運命につきまとう神秘と皮肉〜
2013.04.10
クシシュトフ・キェシロフスキ監督の連作集『デカローグ』は、十戒をモチーフにした10篇の人間ドラマである。元々はテレビ用に撮られたものだが、あまりにも完成度が高く、1989年のヴェネチア国際映画祭で上映されて絶賛された。これによりキェシロフスキの名前は世界中に轟いた、といっても過言ではない。
作品は一話完結式である。一つの戒律をテーマにしたエピソードもあれば、そうでないエピソードもある。例えば、有名な『ある殺人に関する物語』と『ある愛に関する物語』だけを観ても、前者は第六戒「あなたは殺してはならない」をテーマにしているが、後者は第七戒「あなたは姦淫してはならない」だけをテーマにしているわけではない(ちなみに、この2作は劇場版『殺人に関する短いフィルム』、『愛に関する短いフィルム』も作られ、テレビ版より先に公開された)。
「十戒がモチーフ」というと鹿爪らしく見えるかもしれない。実際のところは、十戒がインスピレーションの源泉になっている、といった方が正確である。『ある〜に関する物語』も、日本用に加えられたサブタイトルで、原題には何話目かを示す数字が付いているのみ。つまるところ、どのように解釈しようが観る人の自由なのである。
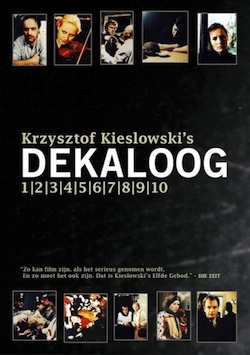 登場人物はエピソード毎に異なる。ただ、あるエピソードで主要な役割を演じたキャラクターが、別のエピソードでエキストラとして顔を見せるという、バルザックの人間喜劇の「人物再登場」が用いられている。
登場人物はエピソード毎に異なる。ただ、あるエピソードで主要な役割を演じたキャラクターが、別のエピソードでエキストラとして顔を見せるという、バルザックの人間喜劇の「人物再登場」が用いられている。
登場するのは、どこにでもいそうな、地味な生活を送っている人たちばかり。彼らの運命が、エピソード毎に異なるタッチで描かれ、大きな物語の層を形成していく。救いのある話もあれば、ない話もある。救いがないと思ったら最後に少しだけ救いがあったというパターンもある。物語の展開は運命のように推し量りがたく、登場人物たちはその微妙な配剤に翻弄され、苦悩する。
第1話のヴォイチェフ・クラタ(パヴェウ役)、第2話のクリスティナ・ヤンダ(ドロタ役)、第3話のダニエル・オルブリフスキー(ヤヌーシュ役)、第4話のアドリアンナ・ビェドジェインスカ(アンカ役)、第5話のミロスラフ・バカ(ヤツェック役)、第6話のグラジナ・シャポウォフスカ(マグダ役)......などキャストが魅力的なのも『デカローグ』の大きな強みである。その存在感や演技を前にしていると、思わず物語の世界に引き込まれ、時が経つのを忘れてしまう。
カメラマンをエピソード毎に替えて、作風に変化をつけたことも奏功したようだ。それは単に技術的な面にとどまらず、撮影現場の雰囲気にまで影響を及ぼした、とキェシロフスキは語っている。
「通常は撮影が始まると単調な繰り返しの作業にだんだん飽きてくるが、(『デカローグ』では)常に新しいメンバーが加わり、新鮮だった。退屈しがちな現場がそれまでより楽しくなった。おかげでこの連作を完成させることができたんだ」
初めて観た時、私が最も衝撃を受けたのは、第1話『ある運命に関する物語』である。人間の運命につきまとう神秘や皮肉は全てこの53分間の物語の中で端的に描かれているといっていい。ベースとなっている戒律は、第一戒「あなたは私の他になにものも神としてはならない」。主人公の大学教授クシシュトフは神の存在に背を向けている。息子パヴェウも父親の影響を受けて、コンピュータいじりに余念がない。しかし、そのコンピュータを過信したばかりに悲劇が起こる。不意に起動するコンピュータ、不気味に広がる青いインクのしみ、遠くから聞こえるサイレンの音......運命が悪い方向へ急転するサインに、少しずつ気付いていくクシシュトフ。その心臓の音まで聞こえそうなほどリアルな演出と演技に鳥肌が立つ。
凍った湖のそばで延々と焚き火をしている男の存在も無視することはできない。この謎の男は『デカローグ』のほとんどのエピソードにちょっとだけ登場し、物語の主人公たちを静観する役割を演じる。自分で何か直接手を下したり、相手の人生に影響を与えたりすることはない。常にイノセントな存在である。ただし、第1話に関してはイノセントではない。氷のそばで執拗に燃える火は、コンピュータを「神」とする者に向けられた、さりげない、かつ、確実な警告を意味している。その警告が悲劇の下地を作るのである。
父親と娘の危険な関係を描いた第4話『ある父と娘に関する物語』も忘れがたい。ここに登場する父親ミハウと娘アンカは、度が過ぎるほど仲が良い。ある日、父親が出張している間に、アンカは亡き母の手紙を見つける。「私の娘、アンカへ」と書かれた未開封の手紙を前に、アンカはどうすべきか迷う。以前から彼女は、もしかするとミハウとは血がつがなっていないのではないか、と感じていた。その疑念に対する答えが書かれているに違いない。間もなく出張から帰ってきた父親に手紙を開封したことを告げるアンカ。それをきっかけに父娘の関係が崩れていく。
予期できない運命を描いた『デカローグ』の中では異質な内容である。というのも、「シナリオ」を司っているのが運命ではなく、アンカだからである。結末も彼女の手に握られている。人間が神のように物語を動かしているという意味で、これは第五戒「あなたの父母を敬え」のみならず、「あなたは私の他になにものも神としてはならない」も含んでいるといえる。アンカがとった行動をやり過ぎと責めるのは簡単だが、母親の遺言を読めずにいたことを斟酌すれば、同情の余地がないわけではない。
アンカを演じているのはポーランドの人気女優で、歌手としても活動しているアドリアンナ・ビェドジェインスカ。猫っぽい雰囲気をたたえたフォトジェニックな美女である。『デカローグ』以外では、イシュトヴァン・サボーの『ハヌッセン』(1988年公開)、アンジェイ・ワイダの『鷲の指輪』(1993年公開)などに出演している。デビュー間もない頃に主演した『Miłość z listy przebojów』(1985年公開)も代表作。これは当時のポーランドの若者文化を知る上でも興味深いごった煮的な青春ミュージカルである。『天国への300マイル』(1989年公開)ではジャーナリストを演じているが、出番は少なく、執拗にシャッターを押している印象しか残っていない(主役はヴォイチェフ・クラタである)。アドリアンナはルックスが良いだけでなく、役の幅も広く、日本でもきちんと紹介されていれば人気が出たのではないかと思う。
既述したように、『デカローグ』はテレビ用に撮られた作品である。その質を高めるために、厳しい予算の中、キェシロフスキはもちろん、脚本家のクシシュトフ・ピエシェヴィチ(『デカローグ』の企画者はこの人)、各エピソードを担当したカメラマン、スタッフ、そしてポーランドの名優たちは、情熱と才能を存分に出してぶつかり合った。
私はこれまでいろいろな国のドラマを観てきたが、一生付き合っていける作品はごく一握りしかない。『デカローグ』はその中でも最高峰に位置するものである。「とはいえ10話は長い」と二の足を踏んでいる人は、まず第1話だけ観るといい。これだけでも『デカローグ』の世界観がどんなものかは十分伝わるだろうし、その研ぎすまされた美感と尋常ならざる暗示力に目を見張らされるに違いない。
【関連サイト】
クシシュトフ・キェシロフスキ『デカローグ』
作品は一話完結式である。一つの戒律をテーマにしたエピソードもあれば、そうでないエピソードもある。例えば、有名な『ある殺人に関する物語』と『ある愛に関する物語』だけを観ても、前者は第六戒「あなたは殺してはならない」をテーマにしているが、後者は第七戒「あなたは姦淫してはならない」だけをテーマにしているわけではない(ちなみに、この2作は劇場版『殺人に関する短いフィルム』、『愛に関する短いフィルム』も作られ、テレビ版より先に公開された)。
「十戒がモチーフ」というと鹿爪らしく見えるかもしれない。実際のところは、十戒がインスピレーションの源泉になっている、といった方が正確である。『ある〜に関する物語』も、日本用に加えられたサブタイトルで、原題には何話目かを示す数字が付いているのみ。つまるところ、どのように解釈しようが観る人の自由なのである。
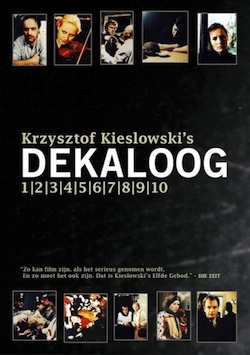
登場するのは、どこにでもいそうな、地味な生活を送っている人たちばかり。彼らの運命が、エピソード毎に異なるタッチで描かれ、大きな物語の層を形成していく。救いのある話もあれば、ない話もある。救いがないと思ったら最後に少しだけ救いがあったというパターンもある。物語の展開は運命のように推し量りがたく、登場人物たちはその微妙な配剤に翻弄され、苦悩する。
第1話のヴォイチェフ・クラタ(パヴェウ役)、第2話のクリスティナ・ヤンダ(ドロタ役)、第3話のダニエル・オルブリフスキー(ヤヌーシュ役)、第4話のアドリアンナ・ビェドジェインスカ(アンカ役)、第5話のミロスラフ・バカ(ヤツェック役)、第6話のグラジナ・シャポウォフスカ(マグダ役)......などキャストが魅力的なのも『デカローグ』の大きな強みである。その存在感や演技を前にしていると、思わず物語の世界に引き込まれ、時が経つのを忘れてしまう。
カメラマンをエピソード毎に替えて、作風に変化をつけたことも奏功したようだ。それは単に技術的な面にとどまらず、撮影現場の雰囲気にまで影響を及ぼした、とキェシロフスキは語っている。
「通常は撮影が始まると単調な繰り返しの作業にだんだん飽きてくるが、(『デカローグ』では)常に新しいメンバーが加わり、新鮮だった。退屈しがちな現場がそれまでより楽しくなった。おかげでこの連作を完成させることができたんだ」
(『キェシロフスキ監督に関する100の質問』)
初めて観た時、私が最も衝撃を受けたのは、第1話『ある運命に関する物語』である。人間の運命につきまとう神秘や皮肉は全てこの53分間の物語の中で端的に描かれているといっていい。ベースとなっている戒律は、第一戒「あなたは私の他になにものも神としてはならない」。主人公の大学教授クシシュトフは神の存在に背を向けている。息子パヴェウも父親の影響を受けて、コンピュータいじりに余念がない。しかし、そのコンピュータを過信したばかりに悲劇が起こる。不意に起動するコンピュータ、不気味に広がる青いインクのしみ、遠くから聞こえるサイレンの音......運命が悪い方向へ急転するサインに、少しずつ気付いていくクシシュトフ。その心臓の音まで聞こえそうなほどリアルな演出と演技に鳥肌が立つ。
凍った湖のそばで延々と焚き火をしている男の存在も無視することはできない。この謎の男は『デカローグ』のほとんどのエピソードにちょっとだけ登場し、物語の主人公たちを静観する役割を演じる。自分で何か直接手を下したり、相手の人生に影響を与えたりすることはない。常にイノセントな存在である。ただし、第1話に関してはイノセントではない。氷のそばで執拗に燃える火は、コンピュータを「神」とする者に向けられた、さりげない、かつ、確実な警告を意味している。その警告が悲劇の下地を作るのである。
父親と娘の危険な関係を描いた第4話『ある父と娘に関する物語』も忘れがたい。ここに登場する父親ミハウと娘アンカは、度が過ぎるほど仲が良い。ある日、父親が出張している間に、アンカは亡き母の手紙を見つける。「私の娘、アンカへ」と書かれた未開封の手紙を前に、アンカはどうすべきか迷う。以前から彼女は、もしかするとミハウとは血がつがなっていないのではないか、と感じていた。その疑念に対する答えが書かれているに違いない。間もなく出張から帰ってきた父親に手紙を開封したことを告げるアンカ。それをきっかけに父娘の関係が崩れていく。
予期できない運命を描いた『デカローグ』の中では異質な内容である。というのも、「シナリオ」を司っているのが運命ではなく、アンカだからである。結末も彼女の手に握られている。人間が神のように物語を動かしているという意味で、これは第五戒「あなたの父母を敬え」のみならず、「あなたは私の他になにものも神としてはならない」も含んでいるといえる。アンカがとった行動をやり過ぎと責めるのは簡単だが、母親の遺言を読めずにいたことを斟酌すれば、同情の余地がないわけではない。
アンカを演じているのはポーランドの人気女優で、歌手としても活動しているアドリアンナ・ビェドジェインスカ。猫っぽい雰囲気をたたえたフォトジェニックな美女である。『デカローグ』以外では、イシュトヴァン・サボーの『ハヌッセン』(1988年公開)、アンジェイ・ワイダの『鷲の指輪』(1993年公開)などに出演している。デビュー間もない頃に主演した『Miłość z listy przebojów』(1985年公開)も代表作。これは当時のポーランドの若者文化を知る上でも興味深いごった煮的な青春ミュージカルである。『天国への300マイル』(1989年公開)ではジャーナリストを演じているが、出番は少なく、執拗にシャッターを押している印象しか残っていない(主役はヴォイチェフ・クラタである)。アドリアンナはルックスが良いだけでなく、役の幅も広く、日本でもきちんと紹介されていれば人気が出たのではないかと思う。
既述したように、『デカローグ』はテレビ用に撮られた作品である。その質を高めるために、厳しい予算の中、キェシロフスキはもちろん、脚本家のクシシュトフ・ピエシェヴィチ(『デカローグ』の企画者はこの人)、各エピソードを担当したカメラマン、スタッフ、そしてポーランドの名優たちは、情熱と才能を存分に出してぶつかり合った。
私はこれまでいろいろな国のドラマを観てきたが、一生付き合っていける作品はごく一握りしかない。『デカローグ』はその中でも最高峰に位置するものである。「とはいえ10話は長い」と二の足を踏んでいる人は、まず第1話だけ観るといい。これだけでも『デカローグ』の世界観がどんなものかは十分伝わるだろうし、その研ぎすまされた美感と尋常ならざる暗示力に目を見張らされるに違いない。
(阿部十三)
【関連サイト】
クシシュトフ・キェシロフスキ『デカローグ』
月別インデックス
- October 2025 [1]
- March 2025 [1]
- January 2024 [1]
- September 2023 [1]
- May 2023 [1]
- September 2022 [1]
- July 2022 [1]
- April 2022 [1]
- January 2022 [1]
- October 2021 [1]
- August 2021 [1]
- June 2021 [1]
- February 2021 [1]
- January 2021 [1]
- December 2020 [1]
- November 2020 [1]
- July 2020 [1]
- March 2020 [1]
- December 2019 [1]
- November 2019 [1]
- October 2019 [1]
- August 2019 [1]
- May 2019 [1]
- April 2019 [1]
- February 2019 [1]
- December 2018 [2]
- October 2018 [1]
- September 2018 [3]
- August 2018 [3]
- April 2018 [2]
- January 2018 [2]
- November 2017 [1]
- August 2017 [2]
- April 2017 [1]
- February 2017 [1]
- December 2016 [1]
- October 2016 [1]
- July 2016 [1]
- May 2016 [1]
- April 2016 [1]
- January 2016 [1]
- December 2015 [1]
- October 2015 [1]
- July 2015 [1]
- May 2015 [1]
- March 2015 [1]
- December 2014 [1]
- November 2014 [1]
- October 2014 [1]
- September 2014 [1]
- August 2014 [1]
- June 2014 [2]
- April 2014 [2]
- February 2014 [2]
- November 2013 [2]
- October 2013 [2]
- August 2013 [2]
- May 2013 [1]
- April 2013 [1]
- March 2013 [1]
- February 2013 [1]
- January 2013 [1]
- November 2012 [2]
- September 2012 [3]
- August 2012 [1]
- July 2012 [1]
- June 2012 [1]
- May 2012 [4]
- April 2012 [1]
- March 2012 [3]
- February 2012 [1]
- January 2012 [3]
- December 2011 [2]
- November 2011 [2]
- October 2011 [2]
- September 2011 [1]
- August 2011 [2]
- July 2011 [3]
- June 2011 [2]
- May 2011 [3]
- April 2011 [3]
- March 2011 [3]
- February 2011 [3]