「ブラー」と一致するもの
-

成熟したヴィルトゥオーゾの遺産 ナタン・ミルシテインはバッハの「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」全曲を2度録音している。1967年に出版されたヨアヒム・ハルトナックの『二十世紀の名ヴァイオリニスト』には、ミルシテインが演奏した「シャコンヌ」について、「彼はこの作品の構築とポリフォニーを、透明な追跡可能なものにしている。旋律の内包するものは彼の...
[続きを読む](2015.03.24) -

衰えることを知らぬ人 演奏技術について語るとき、昔より今の方が格段に進歩しているとか、水準が上がっているという言い方をする人をよく見かける。しかし、全体の平均値が上がっても、突出した存在が現れるとは限らない。その証拠に、ナタン・ミルシテインやウラディミール・ホロヴィッツに匹敵するようなヴィルトゥオーゾは、ほとんど現代に存在しない。才能は平等なものではなく、分...
[続きを読む](2015.03.20) -
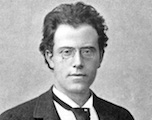
世界が未だかつて耳にしたことがないようなもの マーラーの交響曲第3番は全6楽章、演奏時間に90分以上を要する大作である。ただ、渋滞感や退屈な部分は皆無で聴きやすく、最終的には聴き手を大きな幸福感で包み込む。あらゆる雑念を吸収し、世界を高みへと押し上げるような第6楽章の美しさが、この作品に存在する全ての要素を肯定させ、悲しみも苦しみも疲れも忘れさせるのだ。これ...
[続きを読む](2015.02.25) -

魅力的なライヴ音源 1975年に椎間板の大手術を受け、1978年に指揮台から落ちて脳卒中に見舞われた後は、健康状態の悪化やベルリン・フィルとの関係悪化(1981年に勃発した「ザビーネ・マイヤー事件」をきっかけに、カラヤンとオーケストラの間には大きな溝が生じた)に悩まされ、それを反映するかのように、統率力が以前よりも緩み、オーケストラの自発性を重んじる傾向が強...
[続きを読む](2014.10.04) -

パルプ『コモン・ピープル』1995年作品 その感覚を「違和感」、もしくは「居心地悪さ」と評するべきなのか、パルプは枠からハミ出がちなバンドだった。間違いなく純英国的なセンスを備え、一般的にはブリット・ポップに括られることが多いものの、スウェードやブラーの面々と比べると世代的には少しばかり先輩。フロントマンでありリリシストのジャーヴィス・コッカーが前身バンドA...
[続きを読む](2014.09.15) -

指揮者の中の王 アルトゥーロ・トスカニーニは19世紀後半から20世紀半ばにかけて君臨したイタリアの大指揮者である。彼の登場により指揮者の地位、オペラの上演スタイル、オーケストラの演奏表現の在り方は大きく変わった。かのオットー・クレンペラーが「指揮者の中の王」と呼ぶほどその影響力は絶大だった。トスカニーニは単に指揮棒を振るだけの人ではなく、音楽監督ないし芸術監...
[続きを読む](2014.07.08) -

協奏曲の録音 ギレリスのピアニズムには確かな造形感があり、胸に響く重量感、輝かしいまでの明晰さがある。しかし、グリーグの『抒情小曲集』で聴くことが出来るしっとりとした味わいと甘美さ、プロコフィエフの「束の間の幻影」で聴くことが出来る胸のすくような跳躍感や諧謔的な表現の巧さもギレリスの特性である。 若い頃(1930年代から1940年代にかけて)の録音を聴くとテ...
[続きを読む](2014.04.23) -

ギレリスのプロフィール エミール・ギレリスは多面的な魅力を持ったピアニストである。かつては「鋼鉄のタッチ」と評され、それが彼のイメージを狭めていた節もあるが、遺された多くの録音に虚心坦懐に耳を傾ければ、強靭で決然たる打鍵や猛烈な疾走感だけでなく、音色の美しさやフレージングの柔らかさも持ち味であることが分かるはずだ。 若い頃からギレリスの技術は大きな注目の的と...
[続きを読む](2014.04.21) -

ブラー『パークライフ』1994年作品 音楽ムーヴメントの起点を定めるのは得てして難しいもの。1990年代英国のブリットポップがいつ始まったのかという議論も様々ある。中でも有力なふたつの説のうち、ひとつは1992年5月のスウェードのデビュー。そしてもうひとつが、1994年4月の、ブラーの傑作サード『パークライフ』のリリースだ。つまり後者をとるなら今年はちょうど...
[続きを読む](2014.04.16) -

テイク・ザット『エヴリシング・チェンジズ』1993年作品 まず最初に断らなくてはならないが、筆者はテイク・ザットの大ファンだ。なので贔屓目になるのは免れない。それにしても、数年ぶりにこうしてセカンド・アルバム『Everything Changes』(1993年)を聴いてみて、その完全無欠ぶりに仰天している。え、これってベストじゃないんだよね?と。そう感じたの...
[続きを読む](2013.12.16)