
マーラー 交響曲第3番
2015.02.25
世界が未だかつて耳にしたことがないようなもの
 マーラーの交響曲第3番は全6楽章、演奏時間に90分以上を要する大作である。ただ、渋滞感や退屈な部分は皆無で聴きやすく、最終的には聴き手を大きな幸福感で包み込む。あらゆる雑念を吸収し、世界を高みへと押し上げるような第6楽章の美しさが、この作品に存在する全ての要素を肯定させ、悲しみも苦しみも疲れも忘れさせるのだ。これがマーラーの書いた最も美しいアダージョと言われるのも納得である。だからといって、アダージョだけ聴けば良いというものでもなく、第1楽章から第5楽章までの長い道のりを経た上で、初めてその美しさを身にしみて味わうことが出来るのだ。
マーラーの交響曲第3番は全6楽章、演奏時間に90分以上を要する大作である。ただ、渋滞感や退屈な部分は皆無で聴きやすく、最終的には聴き手を大きな幸福感で包み込む。あらゆる雑念を吸収し、世界を高みへと押し上げるような第6楽章の美しさが、この作品に存在する全ての要素を肯定させ、悲しみも苦しみも疲れも忘れさせるのだ。これがマーラーの書いた最も美しいアダージョと言われるのも納得である。だからといって、アダージョだけ聴けば良いというものでもなく、第1楽章から第5楽章までの長い道のりを経た上で、初めてその美しさを身にしみて味わうことが出来るのだ。
当初、第3番の各楽章には標題がつけられていた。マックス・マルシャルク宛の手紙(1896年8月6日付)によると、それは次のようなものだった。
夏の真昼の夢
第1部
序奏 牧神(パン)が目覚める
第1楽章 夏が行進してくる(バッカスの行進)
第2部
第2楽章 野の花たちが私に語ること
第3楽章 森の動物たちが私に語ること
第4楽章 人間たちが私に語ること
第5楽章 天使たちが私に語ること
第6楽章 愛が私に語ること
第7楽章は「子どもが私に語ること」になる予定だったが、ここでは使われず、交響曲第4番の終楽章に回された。なお、第6楽章の「愛」は個人的・世俗的な愛ではなく、愛としてのみ把握出来る神のことである。それを踏まえた上で、作曲者は当時愛していた歌手アンナ・フォン・ミルデンブルクに宛てて、「この楽章を『神が私に語ること』と呼び変えてもよいくらいだ」(1896年7月1日付)と書いている。いずれにしても、これらの標題は出版時に全て削除されたので、作品への理解を補助する参考資料以上のものではない。
作曲期間は1895年夏から1896年8月の間だが(完成後も手を加えている)、当時マーラーはハンブルクの劇場で指揮者として多忙な日々を送っていた。いくら夏の休暇があるとはいえ、作曲の時間は限られていたはずである。そんな状況下で、誰も書いたことのないような独創的な大作を書き上げたのだ。忙しさで抑えられれば抑えられるほど創作意欲がふくらんでいたことの証だろう。
第1楽章は8本のホルンによるユニゾンで始まる。この主題はブラームスの交響曲第1番の終楽章の主題に酷似しているが、これは元々「歓喜の歌」に似ていると指摘されたものである。マーラーはこの旋律を高らかに奏することで、ベートーヴェン、ブラームスに次ぐ交響曲作曲家は自分であると宣言したのかもしれない。第1楽章はソナタ形式の一種とみてよいが、「既成のパターンの各部分に、どのくらい予期せざるメッセージを託することが可能か、という実験のようなもの」(柴田南雄)で、何が起こるか分からない緊張感の中、放埒な音とリズムの豪雨が耳を覆う。なだれ込むようなコーダは爽快そのもので、長大な楽章を締めくくるのに相応しい。
第2楽章はテンポ・ディ・メヌエット。のどかな雰囲気の中、テンポが速まるところが2回ある。あたかも突風が起こり、音の草花が揺れる様を見るようである。続く第3楽章はコーモド・スケルツァンド。「コーモド」は気楽に、という意味である。歌曲集『若き日の歌』の「夏に小鳥はかわり」を編曲したものだが、トリオでは遠くからポストホルンが鳴り響き、幻想的な空気に満たされる。この主題はリストの『スペイン狂詩曲』のホタ・アラゴネーゼ(民謡が題材)を彷彿させる。ポストホルン・ソロの後、テンポが躍動する。音の色彩は狂おしさを秘めているようだ。再度ポストホルンが登場し、静かになった後、その狂おしさが爆発する。
第4楽章から第6楽章までは続けて演奏される。第4楽章は「きわめてゆるやかに、神秘的に」。第1楽章で使われた主題の断片が漂う中、アルトの独唱により、ニーチェの『ツァラトストラはかく語りき』の酔歌(真夜中の歌)が歌われる。「すべての快楽は深い永遠を欲する」が出てくる有名な箇所である。第5楽章は「快活な速度で、表出は大胆に」。児童合唱が「ビム、バム」と鐘の音を模し、女声合唱が「3人の天使がすてきな歌を歌い、その声は幸いに満ちて天上に響き......」と歌う。ペテロのエピソードに基づく『少年の魔法の角笛』から採られた詩である。アルトの歌詞は深刻で、清澄な合唱と対比をなしている。ここではヴァイオリンは登場しない。
第6楽章は「ゆるやかに、平静に、感情をこめて」。弦の合奏が静かに、ゆっくりと主題を奏で、徐々に波紋を広げてゆき、壮大なクライマックスを形成する。この上なく美しいアダージョで、そこに一度身を委ねたら、ずっと鳴り止まないでほしいと願わずにいられない。マーラーは「僕のこの交響曲は、世界が未だかつて耳にしたことのないようなものだ。そこでは自然界全体が一つの声を得て、人が夢の中で予感することしか出来ないほどの奥深い秘密を物語るのだ」とフォン・ミルデンブルクに書き送っているが、このような音楽を生み出した以上、そう明言したくなるのは当然の心理と言える。
リヒャルト・バトカ宛の手紙(1896年11月18日)によると、マーラーの頭の中には、音楽の進行をそのまま進化論的展開につなげる構想があったようだ。先に紹介したマルシャルク宛の手紙でも示唆されているように、植物、動物、人間、天使、愛(神)という進化である。そういう解釈の縛りをなくして、正解だったと思う。私がこの音楽を聴いてイメージするのは、人生のイデアである。人生に起こる出来事はさまざまで、一見脈絡のないように見えるが、実はどこかに繋がりがあり、最後は大きな力によって包括される。人生は突然断ち切られることもあるし、綺麗な終わり方をするとも限らないわけだが、第3番を聴くと、この音楽のように生を全うしたいという気持ちが芽生えてくる。そんな風に思わせる音楽が私にはいくつかある。
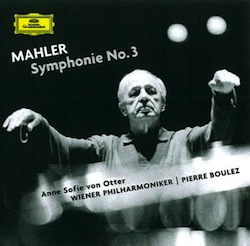 こういう大作は、その内容に相応しい理想的な演奏で聴きたいものだが、私にとって「これさえあれば十分」と言い切れる演奏はなく、特にこだわらずあれこれ聴いている。とはいえ、やたら情感をこめすぎると音楽の流れがよどみ、健康的だと物足りなくなり、幸福感が強すぎると白々しくなるので、私の好みはそのどれでもない演奏ということになる。あと、両端楽章のコーダでのティンパニが頼りない演奏は、聴く気が起こらない(単に騒々しいのは論外)。「結局、理想を求めているではないか」と言われても仕方ない。私に言わせれば、この作品自体が求めている理想の演奏が、相当高いところにあるのだ。
こういう大作は、その内容に相応しい理想的な演奏で聴きたいものだが、私にとって「これさえあれば十分」と言い切れる演奏はなく、特にこだわらずあれこれ聴いている。とはいえ、やたら情感をこめすぎると音楽の流れがよどみ、健康的だと物足りなくなり、幸福感が強すぎると白々しくなるので、私の好みはそのどれでもない演奏ということになる。あと、両端楽章のコーダでのティンパニが頼りない演奏は、聴く気が起こらない(単に騒々しいのは論外)。「結局、理想を求めているではないか」と言われても仕方ない。私に言わせれば、この作品自体が求めている理想の演奏が、相当高いところにあるのだ。
今私が聴いているのは、クラウス・テンシュテット指揮、ロンドン・フィルによる1986年のライヴである。ややくぐもった音質だが、この指揮者ならではの情感のにじみ具合がたまらないし、オケの鳴りっぷりも良いので、これは充実感が欲しいときに聴く。楽章単位で言うと、第3楽章はジョン・バルビローリとハレ管による1969年のライヴ、終楽章はヘルベルト・ケーゲルが1984年にドレスデン・フィルを指揮したライヴが、私の考える理想に近い。ピエール・ブーレーズとウィーン・フィルによる2001年の録音も名演奏で、見通しが良く、かといって機能的になりすぎず、初めて聴く人にもおすすめなのだが(1974年にBBC響を振ったときの演奏も私は好きである)、第3楽章に不自然な編集箇所があるのが惜しい。
【関連サイト】
マーラー:交響曲第3番 ニ短調(CD)

当初、第3番の各楽章には標題がつけられていた。マックス・マルシャルク宛の手紙(1896年8月6日付)によると、それは次のようなものだった。
夏の真昼の夢
第1部
序奏 牧神(パン)が目覚める
第1楽章 夏が行進してくる(バッカスの行進)
第2部
第2楽章 野の花たちが私に語ること
第3楽章 森の動物たちが私に語ること
第4楽章 人間たちが私に語ること
第5楽章 天使たちが私に語ること
第6楽章 愛が私に語ること
第7楽章は「子どもが私に語ること」になる予定だったが、ここでは使われず、交響曲第4番の終楽章に回された。なお、第6楽章の「愛」は個人的・世俗的な愛ではなく、愛としてのみ把握出来る神のことである。それを踏まえた上で、作曲者は当時愛していた歌手アンナ・フォン・ミルデンブルクに宛てて、「この楽章を『神が私に語ること』と呼び変えてもよいくらいだ」(1896年7月1日付)と書いている。いずれにしても、これらの標題は出版時に全て削除されたので、作品への理解を補助する参考資料以上のものではない。
作曲期間は1895年夏から1896年8月の間だが(完成後も手を加えている)、当時マーラーはハンブルクの劇場で指揮者として多忙な日々を送っていた。いくら夏の休暇があるとはいえ、作曲の時間は限られていたはずである。そんな状況下で、誰も書いたことのないような独創的な大作を書き上げたのだ。忙しさで抑えられれば抑えられるほど創作意欲がふくらんでいたことの証だろう。
第1楽章は8本のホルンによるユニゾンで始まる。この主題はブラームスの交響曲第1番の終楽章の主題に酷似しているが、これは元々「歓喜の歌」に似ていると指摘されたものである。マーラーはこの旋律を高らかに奏することで、ベートーヴェン、ブラームスに次ぐ交響曲作曲家は自分であると宣言したのかもしれない。第1楽章はソナタ形式の一種とみてよいが、「既成のパターンの各部分に、どのくらい予期せざるメッセージを託することが可能か、という実験のようなもの」(柴田南雄)で、何が起こるか分からない緊張感の中、放埒な音とリズムの豪雨が耳を覆う。なだれ込むようなコーダは爽快そのもので、長大な楽章を締めくくるのに相応しい。
第2楽章はテンポ・ディ・メヌエット。のどかな雰囲気の中、テンポが速まるところが2回ある。あたかも突風が起こり、音の草花が揺れる様を見るようである。続く第3楽章はコーモド・スケルツァンド。「コーモド」は気楽に、という意味である。歌曲集『若き日の歌』の「夏に小鳥はかわり」を編曲したものだが、トリオでは遠くからポストホルンが鳴り響き、幻想的な空気に満たされる。この主題はリストの『スペイン狂詩曲』のホタ・アラゴネーゼ(民謡が題材)を彷彿させる。ポストホルン・ソロの後、テンポが躍動する。音の色彩は狂おしさを秘めているようだ。再度ポストホルンが登場し、静かになった後、その狂おしさが爆発する。
第4楽章から第6楽章までは続けて演奏される。第4楽章は「きわめてゆるやかに、神秘的に」。第1楽章で使われた主題の断片が漂う中、アルトの独唱により、ニーチェの『ツァラトストラはかく語りき』の酔歌(真夜中の歌)が歌われる。「すべての快楽は深い永遠を欲する」が出てくる有名な箇所である。第5楽章は「快活な速度で、表出は大胆に」。児童合唱が「ビム、バム」と鐘の音を模し、女声合唱が「3人の天使がすてきな歌を歌い、その声は幸いに満ちて天上に響き......」と歌う。ペテロのエピソードに基づく『少年の魔法の角笛』から採られた詩である。アルトの歌詞は深刻で、清澄な合唱と対比をなしている。ここではヴァイオリンは登場しない。
第6楽章は「ゆるやかに、平静に、感情をこめて」。弦の合奏が静かに、ゆっくりと主題を奏で、徐々に波紋を広げてゆき、壮大なクライマックスを形成する。この上なく美しいアダージョで、そこに一度身を委ねたら、ずっと鳴り止まないでほしいと願わずにいられない。マーラーは「僕のこの交響曲は、世界が未だかつて耳にしたことのないようなものだ。そこでは自然界全体が一つの声を得て、人が夢の中で予感することしか出来ないほどの奥深い秘密を物語るのだ」とフォン・ミルデンブルクに書き送っているが、このような音楽を生み出した以上、そう明言したくなるのは当然の心理と言える。
リヒャルト・バトカ宛の手紙(1896年11月18日)によると、マーラーの頭の中には、音楽の進行をそのまま進化論的展開につなげる構想があったようだ。先に紹介したマルシャルク宛の手紙でも示唆されているように、植物、動物、人間、天使、愛(神)という進化である。そういう解釈の縛りをなくして、正解だったと思う。私がこの音楽を聴いてイメージするのは、人生のイデアである。人生に起こる出来事はさまざまで、一見脈絡のないように見えるが、実はどこかに繋がりがあり、最後は大きな力によって包括される。人生は突然断ち切られることもあるし、綺麗な終わり方をするとも限らないわけだが、第3番を聴くと、この音楽のように生を全うしたいという気持ちが芽生えてくる。そんな風に思わせる音楽が私にはいくつかある。
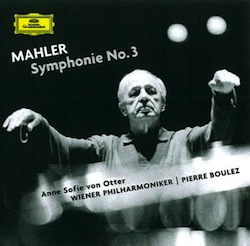
今私が聴いているのは、クラウス・テンシュテット指揮、ロンドン・フィルによる1986年のライヴである。ややくぐもった音質だが、この指揮者ならではの情感のにじみ具合がたまらないし、オケの鳴りっぷりも良いので、これは充実感が欲しいときに聴く。楽章単位で言うと、第3楽章はジョン・バルビローリとハレ管による1969年のライヴ、終楽章はヘルベルト・ケーゲルが1984年にドレスデン・フィルを指揮したライヴが、私の考える理想に近い。ピエール・ブーレーズとウィーン・フィルによる2001年の録音も名演奏で、見通しが良く、かといって機能的になりすぎず、初めて聴く人にもおすすめなのだが(1974年にBBC響を振ったときの演奏も私は好きである)、第3楽章に不自然な編集箇所があるのが惜しい。
(阿部十三)
【関連サイト】
マーラー:交響曲第3番 ニ短調(CD)
グスタフ・マーラー
[1860.7.7-1911.5.18]
交響曲第3番 ニ短調
【お薦めディスク】(掲載CDジャケット:上から)
ヴァルトラウト・マイアー(アルト)
クラウス・テンシュテット指揮
ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団
録音:1986年10月5日(ライヴ)
アンネ・ゾフィー・フォン・オッター(メゾ・ソプラノ)
ピエール・ブーレーズ指揮
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
録音:2001年2月
[1860.7.7-1911.5.18]
交響曲第3番 ニ短調
【お薦めディスク】(掲載CDジャケット:上から)
ヴァルトラウト・マイアー(アルト)
クラウス・テンシュテット指揮
ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団
録音:1986年10月5日(ライヴ)
アンネ・ゾフィー・フォン・オッター(メゾ・ソプラノ)
ピエール・ブーレーズ指揮
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
録音:2001年2月
月別インデックス
- January 2026 [1]
- November 2025 [1]
- September 2025 [1]
- July 2025 [1]
- March 2025 [1]
- February 2025 [1]
- January 2025 [1]
- December 2024 [1]
- November 2024 [1]
- October 2024 [1]
- September 2024 [1]
- August 2024 [1]
- July 2024 [1]
- May 2024 [1]
- April 2024 [1]
- March 2024 [1]
- January 2024 [1]
- December 2023 [1]
- November 2023 [1]
- October 2023 [1]
- September 2023 [1]
- July 2023 [1]
- June 2023 [1]
- May 2023 [1]
- March 2023 [1]
- January 2023 [1]
- December 2022 [1]
- October 2022 [1]
- September 2022 [1]
- August 2022 [1]
- July 2022 [1]
- May 2022 [1]
- March 2022 [1]
- February 2022 [1]
- December 2021 [1]
- November 2021 [1]
- October 2021 [1]
- September 2021 [1]
- July 2021 [1]
- June 2021 [1]
- May 2021 [1]
- March 2021 [1]
- February 2021 [1]
- December 2020 [1]
- November 2020 [1]
- October 2020 [1]
- July 2020 [1]
- June 2020 [1]
- May 2020 [1]
- April 2020 [1]
- February 2020 [1]
- January 2020 [1]
- December 2019 [1]
- October 2019 [1]
- September 2019 [2]
- August 2019 [1]
- June 2019 [1]
- April 2019 [1]
- March 2019 [1]
- February 2019 [1]
- December 2018 [1]
- November 2018 [1]
- October 2018 [1]
- September 2018 [1]
- July 2018 [1]
- June 2018 [1]
- April 2018 [1]
- March 2018 [2]
- February 2018 [1]
- December 2017 [5]
- November 2017 [1]
- October 2017 [1]
- September 2017 [1]
- August 2017 [1]
- June 2017 [1]
- May 2017 [2]
- April 2017 [2]
- February 2017 [1]
- January 2017 [2]
- November 2016 [2]
- September 2016 [2]
- August 2016 [2]
- July 2016 [1]
- June 2016 [1]
- May 2016 [1]
- April 2016 [1]
- February 2016 [2]
- January 2016 [1]
- December 2015 [1]
- November 2015 [2]
- October 2015 [1]
- September 2015 [2]
- August 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- May 2015 [1]
- April 2015 [1]
- February 2015 [2]
- January 2015 [1]
- December 2014 [1]
- November 2014 [2]
- October 2014 [1]
- September 2014 [1]
- August 2014 [2]
- July 2014 [1]
- June 2014 [2]
- May 2014 [2]
- April 2014 [1]
- March 2014 [2]
- February 2014 [2]
- January 2014 [2]
- December 2013 [1]
- November 2013 [2]
- October 2013 [2]
- September 2013 [1]
- August 2013 [2]
- July 2013 [2]
- June 2013 [2]
- May 2013 [2]
- March 2013 [2]
- February 2013 [1]
- January 2013 [2]
- December 2012 [2]
- November 2012 [1]
- October 2012 [2]
- September 2012 [1]
- August 2012 [1]
- July 2012 [3]
- June 2012 [1]
- May 2012 [2]
- April 2012 [2]
- March 2012 [2]
- February 2012 [3]
- January 2012 [2]
- December 2011 [2]
- November 2011 [2]
- October 2011 [2]
- September 2011 [3]
- August 2011 [2]
- July 2011 [3]
- June 2011 [4]
- May 2011 [4]
- April 2011 [5]
- March 2011 [5]
- February 2011 [4]