
『ノストラダムスの大予言』 〜禁じられた環境映画〜
2012.02.10
大真面目に環境汚染を告発したエンターテイメント大作である。これを「名画」と呼ぶことには躊躇を覚えるが、当時、ここまで大々的かつ直接的に環境問題を取り上げた作品はほとんどなかったのではないか。ただし、後に述べる理由により、今ではなかなか観ることができない。放射能の問題が深刻化している中、今後ますます封印され、観られなくなることが予想される。
上映されたのは1974年8月。文部省推薦というお墨付きである。併映は『ルパン三世 念力珍作戦』。映画は大ヒットしたものの、同年12月、一部団体の抗議を受け、原水爆で被害を受けた方々に対する配慮と認識が足りなかったと謝罪し、高濃度の放射能に汚染された人々が映るシーンがカットされた。公開から4ヶ月後のことである。抗議のタイミングが遅かったのか、会社側の対応が遅かったのか、私にはわからない。ここからわかるのは、かなりのロングラン・ヒットだったということである。1974年の興行収入では『日本沈没』に次いで2位を記録。80年代には問題のシーンをカットしてビデオ化する話が出ていたようだが、実現せず、ソフトは市販されていない。
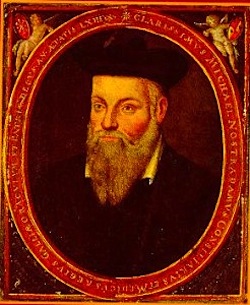 おもちゃにしか見えない巨大ナメクジ、発狂して木の上で「どんぐりころころ」を歌いだす開発大臣、明らかに人形でしかないニューギニアのコウモリ、「赤ちゃんができたの」と砂丘で喜びの舞を踊る由美かおる、核戦争後の人類のグロテスクなメイクなどなど、突っ込みどころは沢山あるが、映画のテーマ自体はハードで、笑えるところはない。現代を生きる私たちにも(というか、むしろ私たちにこそ)響く深刻な調子が脈打っている。
おもちゃにしか見えない巨大ナメクジ、発狂して木の上で「どんぐりころころ」を歌いだす開発大臣、明らかに人形でしかないニューギニアのコウモリ、「赤ちゃんができたの」と砂丘で喜びの舞を踊る由美かおる、核戦争後の人類のグロテスクなメイクなどなど、突っ込みどころは沢山あるが、映画のテーマ自体はハードで、笑えるところはない。現代を生きる私たちにも(というか、むしろ私たちにこそ)響く深刻な調子が脈打っている。
ノストラダムスはあくまでも方便である。環境問題、人口問題、食料問題に対して意識の低い国民にわかりやすく問いかけるべく、当時のノストラダムス・ブームに乗っかったにすぎない。しかし、前述の抗議を受け、人目にふれる機会が減り、現在では上映の場は皆無に等しくなり、キワモノのカルト映画のようなイメージが付着している。私自身も、実際に観るまでは、映画斜陽期にヤケクソで作られた壮大な駄作だろうと思っていた。
学生時代に初めて観た時は、冨田勲による雰囲気満点の音楽と岸田今日子の不気味なナレーションにゾクゾクし、西山(丹波哲郎)が放つ痛快な台詞に胸を熱くしたものだが、終盤の「もし、ひとたび核兵器が用いられたなら......」からの長々しい仮定シーンには、失笑を通り越して退屈してしまった。今もその印象は変わらない。それまでの迫真性を台無しにしかねないB級SF以下の映像表現に陥っている。それよりは、東京から脱出しようと急ぐ男が高速道路で車を暴走させて横転し、その爆発によってほかの車が巻き添えを食う、火炎地獄のシーンの方が数倍怖い。火薬馬鹿、中野昭慶ならではのド派手な爆破っぷりに圧倒される。
ニューギニアのシーンも本当に必要なのか疑問である。「成層圏に蓄積した原子の灰がジェット気流に乗り、何らかの要因でこの奥地に集中的に落ちたのではないか」ということで、西山の後輩が調査に行くわけだが、まもなく音信不通となる。その行方を西山や中川(黒沢年男)たちが追うのだが、これがもう「川口浩探検隊」にしかみえない。おまけに放射能汚染をまともに受けた人間が脳を破壊され、獣のようになって人肉を貪るシーンは、いたずらに猟奇的で、ニューギニアだからそういう展開にしたのか、という安直な思惑まで透けてみえる。
ニューギニアのシーンや核戦争の仮定シーンがなかったとしても(インパクトは弱まるが)この映画は立派に成立する。これらのシーンがスケープゴートにされ、作品全体が葬られているのは残念としかいいようがない。
科学者の西山は、環境問題について次のような考えを持っている。これは映画の本編開始後まもなく提示される、この物語の要点だ。本編を観ることができない人も多いと思うので、なるべく正確に本人の言葉を紹介していきたい。
「やれ農業革命だ、緑の革命だ、なんていったってだね、人間がかつてやったことは農薬と肥料とをぶち撒いてだよ、土地をメチャメチャにしてしまったことだけじゃないか。自然には自然の摂理ってものがあるんだよ。人間が思い上がってだね、安易に改造しようとした結果が、今のこの地球のザマなんだ」
西山は周囲の理解をなかなか得られない。方々から圧力を受け、脅迫されている。環境庁での会議では、ある政治家がこういって西山に反論する。
「ここまで高度に発達した文明は後戻りすることはできない。人間の飽くなき欲望追求、これは本能的なものだ」
それに対し、西山はこう応じる。
「しかし、かつて文明の頂点まで栄えた数々の都市は、ひとつの例外もなしに滅亡している。万物の霊長などと思い上がった人間が、闇雲に科学技術を発達させて、自然のバランスを破壊し、愚かにも自分たちの生存のための最高条件を満たしたと思った時、その時、決定的な破滅が訪れるのです」
原発についても完全に反対派である。国会議事堂でも西山は熱弁をふるう。
「原子力発電所には許容安全度というものはあり得ないし、地震に対しても絶対に安全とはいえないのであります。だとすれば、これは言語を絶する公害である」
子供が原発や放射能に恐怖を抱くには十分な映画だ。ただ、警告はあくまでも警告である。未曾有の危機を回避するにはどうすればいいか。劇中では、ラストの演説シーンで山村聰演じる首相がこういうだけである。
「今からでも決して遅くはないと思います。私はたとい世界の終末が明日訪れようとも、なおかつ1本の苗木をこの大地に植えつけたい。我々に必要なのは勇気であります。今こそ全人類は物質文明の欲望に終止符を打たなければならない。さもなければ、欲望が人間生存に終止符を打つであろう。この事実を正しく認識し、全世界の人々と一緒になって、同じ窮乏生活にたえてみせる、その勇気であります」
いわんとしていることはわからなくもないが、これでは誰も納得しないだろう。窮乏生活にたえる勇気。そこには具体的なビジョンはない。結局そんなことしかいえないのか、と鼻で笑う人がいても不思議はない。率直にいって、私も初めてこれを観た時は、「お前らがメチャメチャにしてきたのに、なんで俺らの世代が窮乏しなければいけないんだ」と思ったものである。
正義の側にみえる西山にも偏向したところがある。彼は人口抑制のために「弱き者、能力なき者は......」と口走るのだ。こういう人間はほぼ例外なく自分のことを「強き者、能力ある者」と考えている。この発言に対し、政治家は血相を変え、「君のいうことはナチスを思わせる」と批判する。
すると、西山は激しい口吻でこう応戦する。
「キレイごとばかり並べているから、すべてのことがメチャメチャになってしまうんだ」
それゆえ、ラストシーンには違和感を覚える。こんな人物が首相の演説に感動するわけがないのだ。以前は「総理、もっと具体的にお願いします」と噛みついていた男なのである。それなのに、しみじみ感動の面持ちで聞き入っている。自分に孫が生まれることを知って丸くなったのか、「これですべて良くなる」といわんばかりの表情だ。なんとも強引なエンディング。結末のつけようがなくなった話をまとめるために、丹波哲郎と山村聰の熱演に頼り、無理やり感動の場面に仕立て上げようとしている風にしかみえない。
科学者なのに「ノストラダムスの予言などというキワモノ」を吹聴しているのはなぜか、と詰め寄られるシーンも印象的だ。西山は威厳を漂わせ、身を乗り出してこう反論する。
「残念ながら、公害の問題はいくら理屈ではわかっていても、その身がひっかぶらないとピンとこない。だが、そうなってはもう遅いんです。だから、私は理論と共にノストラダムスの詩のイメージを借りて警告してるんです」
わかるようなわからないような説明である。これは西山の、というより、映画自体の弁明とみた方がいい。ノストラダムスの名前を使わなければ、この映画はヒットしなかった。大衆が夏休みにこぞって環境汚染を考える映画を観に行くなんてことは考えられない。『ノストラダムスの大予言』だから観に行ったのだ。ただ、皮肉なことに、今はそのノストラダムスが足かせとなっている。キワモノ的イメージでとらえられ、怪しい宗教の映画ではないかとさえ思われている。ソフトが市販されていない以上、誤解を解く方法はない。一皮むけば、ただの環境映画なのに。
2012年になっても、ノストラダムスの予言はまだ有効らしい。彼が考えていた終末は1999年ではなく、2012年だという説がある。まあ、そう信じたい人は、他人に迷惑をかけない範囲で信じていればいい。マヤ文明でも人類は2012年12月に滅亡すると考えられていたという。人類は滅亡するのではなく、新しいステージに進むのだ、と主張する人もいる。
そういえば、先日、近所のファストフード店で中学生たちが「人類は滅亡するわけじゃない。ただブラックホールの向こう側に行くから、その途中で生き残れる人とそうじゃない人が出てくる」と真面目な口調で語り合っていた。スポーツ新聞にはしょっちゅう「まもなく大地震」の見出しが躍っている。この混迷の時代にどう対処すればいいか、『ノストラダムスの大予言』は特に何も教えてはくれないが、観た後、「何が起こってもおかしくはない」という妙にさっぱりした気持ちにはなれる。この映画を上映しても、日本がパニックに陥ることはないだろう。
映画を封印したところで、放射能汚染の現実から逃れることはできない。前述のニューギニアのシーンと核戦争の仮定シーンが本当にそこまで問題視されているのなら、それらをカットしてでも、解禁すべきではないかと思う。教育映画ではなくエンターテイメント作品だからこそ伝わることもあるのだ。
上映されたのは1974年8月。文部省推薦というお墨付きである。併映は『ルパン三世 念力珍作戦』。映画は大ヒットしたものの、同年12月、一部団体の抗議を受け、原水爆で被害を受けた方々に対する配慮と認識が足りなかったと謝罪し、高濃度の放射能に汚染された人々が映るシーンがカットされた。公開から4ヶ月後のことである。抗議のタイミングが遅かったのか、会社側の対応が遅かったのか、私にはわからない。ここからわかるのは、かなりのロングラン・ヒットだったということである。1974年の興行収入では『日本沈没』に次いで2位を記録。80年代には問題のシーンをカットしてビデオ化する話が出ていたようだが、実現せず、ソフトは市販されていない。
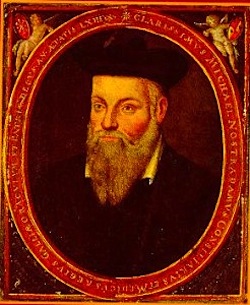
ノストラダムスはあくまでも方便である。環境問題、人口問題、食料問題に対して意識の低い国民にわかりやすく問いかけるべく、当時のノストラダムス・ブームに乗っかったにすぎない。しかし、前述の抗議を受け、人目にふれる機会が減り、現在では上映の場は皆無に等しくなり、キワモノのカルト映画のようなイメージが付着している。私自身も、実際に観るまでは、映画斜陽期にヤケクソで作られた壮大な駄作だろうと思っていた。
学生時代に初めて観た時は、冨田勲による雰囲気満点の音楽と岸田今日子の不気味なナレーションにゾクゾクし、西山(丹波哲郎)が放つ痛快な台詞に胸を熱くしたものだが、終盤の「もし、ひとたび核兵器が用いられたなら......」からの長々しい仮定シーンには、失笑を通り越して退屈してしまった。今もその印象は変わらない。それまでの迫真性を台無しにしかねないB級SF以下の映像表現に陥っている。それよりは、東京から脱出しようと急ぐ男が高速道路で車を暴走させて横転し、その爆発によってほかの車が巻き添えを食う、火炎地獄のシーンの方が数倍怖い。火薬馬鹿、中野昭慶ならではのド派手な爆破っぷりに圧倒される。
ニューギニアのシーンも本当に必要なのか疑問である。「成層圏に蓄積した原子の灰がジェット気流に乗り、何らかの要因でこの奥地に集中的に落ちたのではないか」ということで、西山の後輩が調査に行くわけだが、まもなく音信不通となる。その行方を西山や中川(黒沢年男)たちが追うのだが、これがもう「川口浩探検隊」にしかみえない。おまけに放射能汚染をまともに受けた人間が脳を破壊され、獣のようになって人肉を貪るシーンは、いたずらに猟奇的で、ニューギニアだからそういう展開にしたのか、という安直な思惑まで透けてみえる。
ニューギニアのシーンや核戦争の仮定シーンがなかったとしても(インパクトは弱まるが)この映画は立派に成立する。これらのシーンがスケープゴートにされ、作品全体が葬られているのは残念としかいいようがない。
科学者の西山は、環境問題について次のような考えを持っている。これは映画の本編開始後まもなく提示される、この物語の要点だ。本編を観ることができない人も多いと思うので、なるべく正確に本人の言葉を紹介していきたい。
「やれ農業革命だ、緑の革命だ、なんていったってだね、人間がかつてやったことは農薬と肥料とをぶち撒いてだよ、土地をメチャメチャにしてしまったことだけじゃないか。自然には自然の摂理ってものがあるんだよ。人間が思い上がってだね、安易に改造しようとした結果が、今のこの地球のザマなんだ」
西山は周囲の理解をなかなか得られない。方々から圧力を受け、脅迫されている。環境庁での会議では、ある政治家がこういって西山に反論する。
「ここまで高度に発達した文明は後戻りすることはできない。人間の飽くなき欲望追求、これは本能的なものだ」
それに対し、西山はこう応じる。
「しかし、かつて文明の頂点まで栄えた数々の都市は、ひとつの例外もなしに滅亡している。万物の霊長などと思い上がった人間が、闇雲に科学技術を発達させて、自然のバランスを破壊し、愚かにも自分たちの生存のための最高条件を満たしたと思った時、その時、決定的な破滅が訪れるのです」
原発についても完全に反対派である。国会議事堂でも西山は熱弁をふるう。
「原子力発電所には許容安全度というものはあり得ないし、地震に対しても絶対に安全とはいえないのであります。だとすれば、これは言語を絶する公害である」
子供が原発や放射能に恐怖を抱くには十分な映画だ。ただ、警告はあくまでも警告である。未曾有の危機を回避するにはどうすればいいか。劇中では、ラストの演説シーンで山村聰演じる首相がこういうだけである。
「今からでも決して遅くはないと思います。私はたとい世界の終末が明日訪れようとも、なおかつ1本の苗木をこの大地に植えつけたい。我々に必要なのは勇気であります。今こそ全人類は物質文明の欲望に終止符を打たなければならない。さもなければ、欲望が人間生存に終止符を打つであろう。この事実を正しく認識し、全世界の人々と一緒になって、同じ窮乏生活にたえてみせる、その勇気であります」
いわんとしていることはわからなくもないが、これでは誰も納得しないだろう。窮乏生活にたえる勇気。そこには具体的なビジョンはない。結局そんなことしかいえないのか、と鼻で笑う人がいても不思議はない。率直にいって、私も初めてこれを観た時は、「お前らがメチャメチャにしてきたのに、なんで俺らの世代が窮乏しなければいけないんだ」と思ったものである。
正義の側にみえる西山にも偏向したところがある。彼は人口抑制のために「弱き者、能力なき者は......」と口走るのだ。こういう人間はほぼ例外なく自分のことを「強き者、能力ある者」と考えている。この発言に対し、政治家は血相を変え、「君のいうことはナチスを思わせる」と批判する。
すると、西山は激しい口吻でこう応戦する。
「キレイごとばかり並べているから、すべてのことがメチャメチャになってしまうんだ」
それゆえ、ラストシーンには違和感を覚える。こんな人物が首相の演説に感動するわけがないのだ。以前は「総理、もっと具体的にお願いします」と噛みついていた男なのである。それなのに、しみじみ感動の面持ちで聞き入っている。自分に孫が生まれることを知って丸くなったのか、「これですべて良くなる」といわんばかりの表情だ。なんとも強引なエンディング。結末のつけようがなくなった話をまとめるために、丹波哲郎と山村聰の熱演に頼り、無理やり感動の場面に仕立て上げようとしている風にしかみえない。
科学者なのに「ノストラダムスの予言などというキワモノ」を吹聴しているのはなぜか、と詰め寄られるシーンも印象的だ。西山は威厳を漂わせ、身を乗り出してこう反論する。
「残念ながら、公害の問題はいくら理屈ではわかっていても、その身がひっかぶらないとピンとこない。だが、そうなってはもう遅いんです。だから、私は理論と共にノストラダムスの詩のイメージを借りて警告してるんです」
わかるようなわからないような説明である。これは西山の、というより、映画自体の弁明とみた方がいい。ノストラダムスの名前を使わなければ、この映画はヒットしなかった。大衆が夏休みにこぞって環境汚染を考える映画を観に行くなんてことは考えられない。『ノストラダムスの大予言』だから観に行ったのだ。ただ、皮肉なことに、今はそのノストラダムスが足かせとなっている。キワモノ的イメージでとらえられ、怪しい宗教の映画ではないかとさえ思われている。ソフトが市販されていない以上、誤解を解く方法はない。一皮むけば、ただの環境映画なのに。
2012年になっても、ノストラダムスの予言はまだ有効らしい。彼が考えていた終末は1999年ではなく、2012年だという説がある。まあ、そう信じたい人は、他人に迷惑をかけない範囲で信じていればいい。マヤ文明でも人類は2012年12月に滅亡すると考えられていたという。人類は滅亡するのではなく、新しいステージに進むのだ、と主張する人もいる。
そういえば、先日、近所のファストフード店で中学生たちが「人類は滅亡するわけじゃない。ただブラックホールの向こう側に行くから、その途中で生き残れる人とそうじゃない人が出てくる」と真面目な口調で語り合っていた。スポーツ新聞にはしょっちゅう「まもなく大地震」の見出しが躍っている。この混迷の時代にどう対処すればいいか、『ノストラダムスの大予言』は特に何も教えてはくれないが、観た後、「何が起こってもおかしくはない」という妙にさっぱりした気持ちにはなれる。この映画を上映しても、日本がパニックに陥ることはないだろう。
映画を封印したところで、放射能汚染の現実から逃れることはできない。前述のニューギニアのシーンと核戦争の仮定シーンが本当にそこまで問題視されているのなら、それらをカットしてでも、解禁すべきではないかと思う。教育映画ではなくエンターテイメント作品だからこそ伝わることもあるのだ。
(阿部十三)
月別インデックス
- October 2025 [1]
- March 2025 [1]
- January 2024 [1]
- September 2023 [1]
- May 2023 [1]
- September 2022 [1]
- July 2022 [1]
- April 2022 [1]
- January 2022 [1]
- October 2021 [1]
- August 2021 [1]
- June 2021 [1]
- February 2021 [1]
- January 2021 [1]
- December 2020 [1]
- November 2020 [1]
- July 2020 [1]
- March 2020 [1]
- December 2019 [1]
- November 2019 [1]
- October 2019 [1]
- August 2019 [1]
- May 2019 [1]
- April 2019 [1]
- February 2019 [1]
- December 2018 [2]
- October 2018 [1]
- September 2018 [3]
- August 2018 [3]
- April 2018 [2]
- January 2018 [2]
- November 2017 [1]
- August 2017 [2]
- April 2017 [1]
- February 2017 [1]
- December 2016 [1]
- October 2016 [1]
- July 2016 [1]
- May 2016 [1]
- April 2016 [1]
- January 2016 [1]
- December 2015 [1]
- October 2015 [1]
- July 2015 [1]
- May 2015 [1]
- March 2015 [1]
- December 2014 [1]
- November 2014 [1]
- October 2014 [1]
- September 2014 [1]
- August 2014 [1]
- June 2014 [2]
- April 2014 [2]
- February 2014 [2]
- November 2013 [2]
- October 2013 [2]
- August 2013 [2]
- May 2013 [1]
- April 2013 [1]
- March 2013 [1]
- February 2013 [1]
- January 2013 [1]
- November 2012 [2]
- September 2012 [3]
- August 2012 [1]
- July 2012 [1]
- June 2012 [1]
- May 2012 [4]
- April 2012 [1]
- March 2012 [3]
- February 2012 [1]
- January 2012 [3]
- December 2011 [2]
- November 2011 [2]
- October 2011 [2]
- September 2011 [1]
- August 2011 [2]
- July 2011 [3]
- June 2011 [2]
- May 2011 [3]
- April 2011 [3]
- March 2011 [3]
- February 2011 [3]