「ブラー」と一致するもの
-

ウィレム・メンゲルベルクは19世紀末から20世紀半ばにかけて活躍したオランダの大指揮者であり、トスカニーニ、ワルター、フルトヴェングラーを含むいわゆる「四大巨匠」の一人である。彼は必要とあらば楽譜上の指示を自己流に変更し、お馴染みの作品から瞠目すべきニュアンスを引き出して音楽的効果を上げる達人だった。そのロマン主義的なスタイルと、細部の表現に徹底してこだわ...
[続きを読む](2013.12.11) -
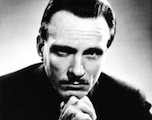
アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリは、同じ作品を徹底的に繰り返し練習し、表現の細かい部分まで磨き上げ、精巧無比な技術と強靭な理性をもって感情の抑揚を統御し、コンサートや録音に臨んでいた。1971年にドイツ・グラモフォンと契約してからの一連の録音は、まさにそんなミケランジェリの美学の結晶といえる。そこには一回性の感情表現はなく、完璧なアーティキュレー...
[続きを読む](2013.10.04) -
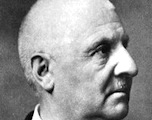
巨人の創造物 交響曲第8番は1884年7月から1887年8月10日の間に作曲された。1884年といえば、ブルックナーが交響曲第7番で大成功をおさめ、キャリアの絶頂期を迎えた年である。彼は60歳になっていたが、その創作意欲は衰えることを知らず、ますます横溢していた。それは同年に完成した『テ・デウム』を聴いてもはっきりと分かるだろう。そして3年後、彼は生涯最大規...
[続きを読む](2013.09.16) -

比類なき至芸の結晶 作品の美質を引き出す術は、オーケストラの美質を引き出す術と無関係ではあり得ない。シューリヒトはそのことを心得ていた。彼は固定スタイルを団員たちに押しつけるタイプの指揮者ではなかった。オーケストラが変われば演奏も変わる。ただ、いかなる方向からでも作品の核へと迫ろうとする、その姿勢は変わらない。 ウィーン・フィルとの組み合わせでは、1960年...
[続きを読む](2013.07.19) -
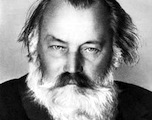
歳月の重さと理念の重さ ヨハネス・ブラームスが交響曲第1番を完成させたのは1876年。「2台のピアノのためのソナタ」を交響曲に改作しようとして挫折したのが1855年頃なので、20年越しの念願成就ということになる。むろん、その間ずっと交響曲にかかりきりだったわけではないが、自らが世に出す最初の交響曲のことをブラームスはかなり重く考えていたようである。ベートーヴ...
[続きを読む](2013.07.01) -

「ジダーノフ批判」の時期に生まれた傑作 ショスタコーヴィチのヴァイオリン協奏曲第1番は1947年夏から1948年3月24日の間に作曲された。この時期(1948年以降)、彼はいわゆる「ジダーノフ批判」にさらされていて、作品が演奏禁止になったり、教職を解かれたり、自己批判を強要されたりしていた。 「ジダーノフ批判」というのは、アンドレイ・ジダーノフ主導による言論...
[続きを読む](2013.06.10) -

ジノ・フランチェスカッティのヴァイオリンは聴く者を幸福な気分にさせる。その音は豊潤で、艶やかで、屈託がない。深刻ぶったところもない。心地よさを伴いながら耳の中にすべりこみ、鼓膜に浸透し、全身に行き渡る。深みが足りないとか、精神性に欠けるという人もいるが、根が明るく解放感に満ちたヴァイオリンにそんなものを求めるのは野暮というものである。 1902年8月9日、...
[続きを読む](2013.05.14) -

2004年にグリゴリー・ソコロフのコンサート映像がDVD化された時、日本では知名度が高いとはいえないこの大ピアニストについて、私は次のように書いたことがある。「現在は西欧を中心にマイペースの活動を行ない、その名声はすでに不動の高みに達している。にもかかわらず、日本で目立つかたちで紹介される機会はなく、情報が増えない。はっきりいえばマイナー扱いされている節す...
[続きを読む](2013.04.16) -

スウェード『スウェード』1993年作品 2012年7月、再結成してから2回目の来日を果たしたスウェードを、妙齢女性4人で勇んで観に行った時のこと。年甲斐もなく最前ブロックに押しかけてもみくちゃになって、若い頃と変わらぬルックスを保つブレット・アンダーソン(vo)に見惚れた我々は、「散々歌っちゃったけど、ほんと、ドラッグとセックスの曲ばっかだよね」と、大笑いし...
[続きを読む](2013.03.24) -

チェボターリの後継者 美貌と美声と才能に恵まれ、究極の才色兼備を体現した名歌手である。早世したマリア・チェボターリの正当な後継者といってもいい。その声は艶があって美しいだけでなく、清潔感があり、しかも聴き手の耳を威圧することなく、ホールの隅々にまで響くような浸透性を備えている。レガートのなめらかさも特筆もので、歌い口に気品がある。そして歌詞の世界を、理智的な...
[続きを読む](2012.11.28)