2011年7月アーカイブ

その日、財布はいつになく膨れていた。ターゲットはモンブランの限定万年筆「ヘミングウェイ・モデル」。武者震いしつつ、いざ鎌倉! のはずだったのだが......。 あれは7月の暑い日だったと記憶している。あの日あの時の、自分の行動の由って来るところを、今以て説明できない。というのも、行きつけの文房具屋(Y堂本店)がかつて万年筆売場を設けていた馬車道のビルを目指...
[続きを読む](2011.07.30)
天才は最後にキレた メンデルスゾーンが紡ぎ出す旋律は流麗で、親しみやすく、時折情熱的な力強さや憂鬱な表情を見せることはあっても、取り乱した叫び声となることはない。音楽的な冒険をしても、それは「カッコいい」と思える範囲にとどまり、節度は保たれている。だから紳士淑女が顔をしかめることもない。そういうところをあげつらい、「メンデルスゾーンの作品はお上品で中身が薄い...
[続きを読む](2011.07.29)
クラフトワーク『アウトバーン』1974年作品 クラフトワークの原型は、1968年にドイツのデュッセルドルフでラルフ・ヒュッターとフローリアン・シュナイダーによって始動された。1970年にグループ名を「クラフトワーク」とし、同年に1stアルバム『KRAFTWERK』をリリース。電子音楽のパイオニアである彼らの本格的な第一歩はここから始まった。しかし、無数の電子...
[続きを読む](2011.07.24)
万年筆。何と魅惑的な響きだろうか。どうせなら旧字体の萬年筆と表記したいところだ。それほど、この筆記具には崇高な佇まいを感じる。英語でいうなら〈fountain pen〉。〈fountain〉はご存知のように「噴水、泉、原水」という意味。万年筆には「長く(=万年)使っても使いべりがしない」という意味が込められているだろうし、〈fountain pen〉には「...
[続きを読む](2011.07.23)
有馬稲子の美貌は宝塚時代から有名だった。ただ、その美しさには翳があり、笑顔の中にも愁いが漂っていて、それが単なる美人女優にはない複雑な魅力を彼女に付与している。東宝専属女優としての第1回主演作『ひまわり娘』を手がけた千葉泰樹監督も、有馬稲子の印象をこう語っていたという。「明るい感じの娘だと思っていたが、撮影が始まり、彼女を見つめていると、むしろ哀愁が濃いこ...
[続きを読む](2011.07.23)
アンドレ・クリュイタンスはフランス音楽のスペシャリストとして知られている。その指揮棒から生み出される音楽は、エレガント、粋、エスプリ、洗練、色彩感、香り高い、といった言葉を並べて説明されることが多い。しかし、それらの言葉はどこまで本質をついているのだろうか。使いようによってはどうにでも使える言葉を、日本人が抱いている「フランス」のイメージに絡めて使っている...
[続きを読む](2011.07.21)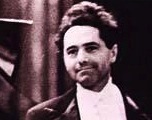
湖の月光、波にゆらぐ小舟 ベートーヴェンの3大ピアノ・ソナタといえば「悲愴」「月光」「熱情」。この中で最も広く知られ、人気が高いのは「月光」だろう。元のタイトルは「幻想曲風ソナタ」だが、詩人のルートヴィヒ・レルシュタープがゆるやかでロマンティックなムードをたたえた第1楽章を「スイスのルツェルン湖の月光の波に揺らぐ小舟のよう」と評したことから、この愛称がついた...
[続きを読む](2011.07.17)
「住んでいた部屋にお化けが出た」というような話はよく聞くが、僕はお化けなんかちっとも怖くない。僕が悩まされたアレに較べれば......。 僕がかつて暮らしていたのは、松本零士の漫画にでも出てきそうな昭和臭ムンムンのアパートであった。築40年は経っている木造モルタルの2階。昇り降りには錆が浮きまくった鉄製の階段を使った。誰かがやって来るとカンカンカン〜という...
[続きを読む](2011.07.16)
21世紀の今もドクトル・マブゼは生きている。 先日、文庫化された平野啓一郎の長編『決壊』を読んだが、この前半に〈悪魔〉と称する男がカラオケボックスで中学生の北崎友哉を唆す重要な場面がある。そこで放たれる言葉は、バウム教授に託されたマブゼのメッセージを思い出させる。 〈悪魔〉は、「純化された殺意として、まったく無私の、匿名の観念として殺人を行う」ことを奨励し...
[続きを読む](2011.07.16)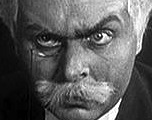
『ドクトル・マブゼ』で華々しい成功を収めた後、フリッツ・ラングはテア・フォン・ハルボウと結婚した。しかし漁色家のラングは多くの女性と関係を持ち、夫婦仲が冷却化。1930年代に入ると別居し、今度はハルボウがインド人青年と恋愛関係を結ぶ。『ドクトル・マブゼ』の続編は、そんな状況の中で製作された。 『怪人マブゼ博士(マブゼ博士の遺言)』が完成したのは1933年頭...
[続きを読む](2011.07.15)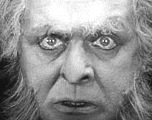
オーストリアが生んだ天才監督フリッツ・ラングは、戦前から戦後にかけて誇張抜きに「傑作」と呼ぶに値する作品を多く撮った。普通の監督が1本でも完成させれば歴史に名を残せるような映画を何本も作っているのだ。その代表作を数本に絞ることは不可能に等しい。 ただ、それぞれ好みはあるにせよ、観る者をひれ伏させるようなラングの演出力と魔術的なビジュアル・センスが確かな強度...
[続きを読む](2011.07.14)
ボビー・ヘブ「サニー」(1966年/全米No.2、全英No.12) 一度、耳にしたら忘れられないメロディ。幼少時代、FEN(現AFN)からこの曲が頻繁に流れていたのを記憶している。歌い出しの♪Sunny...も、まだ英語の聞き取りができない年齢だったが、そこだけはずっと耳に残っていた。今もどこかしらで耳にする機会が決して少なくないこの「サニー」(R&...
[続きを読む](2011.07.13)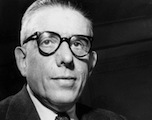
完全燃焼するオルガン フランシス・プーランクのオルガン協奏曲は、正式には「オルガン、弦楽、ティンパニのための協奏曲」という。つまり、管楽器が使われていない。それらの音色はオルガンが一手に担っている。その多彩な音にティンパニの打音と弦楽器の重厚な響きが重なり合う。そこから生まれるアンサンブルは驚くほど陰翳が深い。管楽器がなくて物足りない、という印象が与えられる...
[続きを読む](2011.07.10)
特に期待していたわけではなかった。「へえ〜。AKB48ってこういうこともやっていたんだね」という参考資料程度のつもりで観たのが、AKB歌劇団『∞・Infinity』のDVDであった。しかし、僕は自分でも驚く程の感銘を受けたのだ。 AKB歌劇団『∞・Infinity』は、AKB48のメンバーによるミュージカル。2009年10月30日〜11月8日、シアターGロ...
[続きを読む](2011.07.09)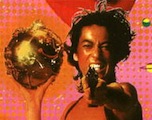
『太陽を盗んだ男』(1979年)は中学の理科教師が自宅アパートで原子爆弾を製造し、日本政府を脅迫する物語。つまり、テロリストを描いた映画だ。とはいえ、主人公・城戸誠(沢田研二)の要求には、政治的な色合いは一切ない。彼が突きつけるのは、「ナイター中継を最後まで放送しろ!」「ローリング・ストーンズの来日公演を実現しろ!」など......国家を揺るがし得る兵器を...
[続きを読む](2011.07.08)
ジャッキー・ウィルソン『ハイヤー・アンド・ハイヤー』1967年作品 R&B史、延いてはポピュラー音楽史上において、過去の栄光と現在の受け止められ方がこれほどまでに乖離しているアーティストは、ジャッキー・ウィルソンをおいて他にはいないのではないか。亡くなるまでの数年間、病床にあったとは言え、1984年1月21日、遂に力尽きたジャッキーが49歳の若さでこ...
[続きを読む](2011.07.07)
R.シュトラウスとカラヤンの理想 マリア・チェボターリはリヒャルト・シュトラウスのお気に入りだった。ヘルベルト・フォン・カラヤンによると、シュトラウスが理想としていた〈サロメ〉はチェボターリだったという。1970年代半ば、カラヤンもまたサロメ役に亡きチェボターリの声を求めていた。そうして見つけた歌手がヒルデガルト・ベーレンスである。カラヤンはリチャード・オズ...
[続きを読む](2011.07.02)
場当たり的な政策、米価の高騰、米騒動、度重なる不況、コレラの蔓延、都市部への人口の流入、木造建築密集地帯で多発する火災......と悪化の一途をたどっていた貧民問題は、世論においても多少の関心を集めていた。特に明治10年以降は、数多くの社会主義思想関連の書籍が翻訳出版され、単に「自己責任」としてとらえられていた貧民観も、社会問題的側面から論じられるようにな...
[続きを読む](2011.07.02)
昭和20年5月24日、東京大空襲の夜に出会った男と女。2人は名を告げることなく、数寄屋橋の上で半年後に会うことを約束する。それが長く険しい悲恋の道の始まりとも知らずに......。 やがて戦争が終わり、約束の11月24日を迎えた。橋の上では男が女を待っている。同じ頃、女は佐渡で不本意な結婚を迫られていた。ようやく2人が会えたのは、さらに1年が経ってからのこ...
[続きを読む](2011.07.01)