
ダフネ・デュ・モーリア 聖地に挑む人々 [続き]
2012.01.14
デュ・モーリアのファンの間で神品と評されている「モンテ・ヴェリタ」(1952年、『林檎の木』収録)も、2人の男とファム・ファタールの話である。
主人公「わたし」の親友で登山仲間のヴィクターが、不思議な魅力を持つ女性アンナと結婚する。登山に興味を持ったアンナは、ある日、ヴィクターを置き去りにしてモンテ・ヴェリタの山へ向かい、それきり戻ってこなくなる。村人たちの話によると、モンテ・ヴェリタの住人サセルドテッサは特別な力を持ち、13才以上の女子を招き寄せ、山に住まわせているのだという。
心配するヴィクターがモンテ・ヴェリタに登り、待ち続けて数日後、アンナが姿を現す。深い奈落に隔てられた岩壁を背に立つ彼女は、すでにサセルドテッサの一員になっていた。
「ここはわたしにとって天国なの。モンテ・ヴェリタからふつうの世界に戻るくらいなら、いますぐ何百フィートも下の岩に身を投げて死ぬわ」
と言われ、絶望するヴィクター。彼は下山し、「わたし」にこれまでの経緯を打ち明ける。
それから20年以上の年月を経た後、ヴィクターと再会した「わたし」は、重病を患う親友のため、そしてアンナに惹かれている自分自身のために、モンテ・ヴェリタに登ることを決意する。
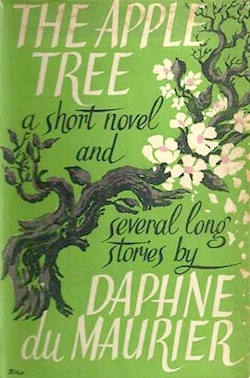 モンテ・ヴェリタ(真実の山)は、デュ・モーリア版シャングリラである。モンテ・ヴェリタに住めば永遠の若さが得られるし、精神的にも満たされる。デュ・モーリアはフランク・キャプラ監督の『失はれた地平線』を観ていたか、ジェームズ・ヒルトンの原作を読んでいたに違いない。「わたし」が乗っている飛行機をアンナがモンテ・ヴェリタの近くに不時着させるくだりは、『失はれた地平線』へのオマージュだろう。ただし、シャングリラとモンテ・ヴェリタの間には決定的な相違点がある。モンテ・ヴェリタは人間的な愛情を受けつけないのだ。
モンテ・ヴェリタ(真実の山)は、デュ・モーリア版シャングリラである。モンテ・ヴェリタに住めば永遠の若さが得られるし、精神的にも満たされる。デュ・モーリアはフランク・キャプラ監督の『失はれた地平線』を観ていたか、ジェームズ・ヒルトンの原作を読んでいたに違いない。「わたし」が乗っている飛行機をアンナがモンテ・ヴェリタの近くに不時着させるくだりは、『失はれた地平線』へのオマージュだろう。ただし、シャングリラとモンテ・ヴェリタの間には決定的な相違点がある。モンテ・ヴェリタは人間的な愛情を受けつけないのだ。
少女たちが岩山で行方不明になる話で思い出すのは、ピーター・ウィアー監督の映画『ピクニック at ハンギング・ロック』である。原作はジョーン・リンジーで、実際に起こった事件に基づいていると言われているが、現在証拠となる資料が存在しないため、フィクション説が優勢である。「モンテ・ヴェリタ」が何らかの影響を与えた可能性もあるかもしれない。
『レベッカ』にも『レイチェル』にも「モンテ・ヴェリタ」にも共通していることがある。聖地によそ者がやってくるという図式だ。聖地とは、『レベッカ』なら「マンダレイ」、『レイチェル』なら「コーンウォール」、「モンテ・ヴェリタ」なら「モンテ・ヴェリタ」である。よそ者は、『レベッカ』の「わたし」、『レイチェル』の「レイチェル」、「モンテ・ヴェリタ」の「わたし」である。いずれもよそ者たちの目的や希望や企みは果たされずに終わる。
「皇女」(1959年、『破局』収録)にも、ロンダ公国という聖地が登場する。ロンダは「歓楽と癒しと平和の国」である。宗教はない。必要がないからである。女性たちも美しい。このシャングリラのような国の最大の資産は、泉から湧き出る水だ。「この水をある種の薬品と調合して用いると、永遠の若さを保つ効能」があるのだ。その秘法は大公だけが知っている。
ロンダ公国に不協和音を起こすのは、マーコイとグランドスである。2人は厳密にいうと「よそ者」ではないが、陰湿で、貪欲で、外国文化に影響されている。ヨーロッパを旅した2人は、半年後、「胸に不満の種を宿して帰国し、そのときは意識していなかったが、それはやがて熟し、芽生えんばかりとな」る。
新聞記者となったマーコイは〈ロンダ・ニューズ〉にこう書く。
「われわれは、老いも若きもひっくるめ、なにゆえわれわれ自身の所有物をわれわれから奪い上げている政府に唯々諾々として支配されているのか。われわれみんなが支配者たりうるのだ。それなのに、われわれは支配されている」
こうした記事を読み続けるうちに、国民はそれまで感じたことのなかった不満を感じるようになる。そして、幾世紀にもわたり平和統治してきた王家に対し、こんな不満を抱くようになる。
「なんの権利があって、あいつはおれたちを支配しているんだ」
ここからはマーコイとグランドスの思惑通りに事が進む。彼らはいわばスヴェンガリである。スヴェンガリとは、デュ・モーリアの祖父ジョージ・デュ・モーリアの小説『トリルビー』に出てくる催眠術師。国民は、革命家の仮面をつけたスヴェンガリによって催眠状態に陥る。まもなく革命が起こり、大公は虐殺され、ロンダ公国はロンダ共和国に変わる。
地球上にいる誰もがシャングリラやモンテ・ヴェリタを望んでいるわけではない。人間には獣性があり、嫉妬心があり、所有欲があり、闘争本能がある。そこを突かれたらどうなるか。デュ・モーリアはそういう人間性を踏まえた上で、革命を描く。肯定的にも否定的に扱わない。その筆致は常にクールだ。そこもまた読者に冷え冷えとした恐怖を催させる。
しかし、マーコイとグランドスの目的は本当に達せられたのだろうか。否である。彼らは「革命の真の目的」だった泉の水の秘密を知ることができなかった。革命家たちはその秘密を握る唯一の存在である皇女を捕え、「追従からはじまり、強姦、拷問、監禁、飢餓、疫病に至るあらゆる手段」を用いて聞き出そうとしたが、皇女は口を割らなかった。そのためにマーコイとグランドスは不老長寿を手にすることなく世を去る。かくして聖地への侵犯は失敗に終わるのだ。
繰り返すが、デュ・モーリアは『レベッカ』だけの作家ではない。彼女は様々なジャンルで才能を発揮し、小説のみならず戯曲やノンフィクションも手がけていた。現在、それらの作品のうち何作が国内で入手できるのだろう。昔、三笠書房から出ていた『デュ・モーリア作品集』が復刊すればいいのだが、そんな気配はなさそうだ。伝記や研究本も国内ではみかけない(マーガレット・フォースターが書いた伝記を海外から取り寄せることは可能である)。英国文学史を扱った書籍などを読んでも、デュ・モーリアの名前が飛ばされているケースが多々ある。無神経な話だ。今後、ジェーン・オースティンやエミリー・ブロンテやヴァージニア・ウルフを生んだイギリスの天才作家として、その真価が知られる日は来るのだろうか。
【関連サイト】
ダフネ・デュ・モーリア 聖地に挑む人々
Daphne Du Maurier
ダフネ・デュ・モーリア(書籍)
主人公「わたし」の親友で登山仲間のヴィクターが、不思議な魅力を持つ女性アンナと結婚する。登山に興味を持ったアンナは、ある日、ヴィクターを置き去りにしてモンテ・ヴェリタの山へ向かい、それきり戻ってこなくなる。村人たちの話によると、モンテ・ヴェリタの住人サセルドテッサは特別な力を持ち、13才以上の女子を招き寄せ、山に住まわせているのだという。
心配するヴィクターがモンテ・ヴェリタに登り、待ち続けて数日後、アンナが姿を現す。深い奈落に隔てられた岩壁を背に立つ彼女は、すでにサセルドテッサの一員になっていた。
「ここはわたしにとって天国なの。モンテ・ヴェリタからふつうの世界に戻るくらいなら、いますぐ何百フィートも下の岩に身を投げて死ぬわ」
と言われ、絶望するヴィクター。彼は下山し、「わたし」にこれまでの経緯を打ち明ける。
それから20年以上の年月を経た後、ヴィクターと再会した「わたし」は、重病を患う親友のため、そしてアンナに惹かれている自分自身のために、モンテ・ヴェリタに登ることを決意する。
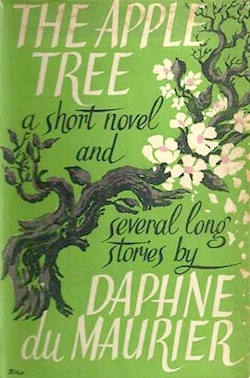
少女たちが岩山で行方不明になる話で思い出すのは、ピーター・ウィアー監督の映画『ピクニック at ハンギング・ロック』である。原作はジョーン・リンジーで、実際に起こった事件に基づいていると言われているが、現在証拠となる資料が存在しないため、フィクション説が優勢である。「モンテ・ヴェリタ」が何らかの影響を与えた可能性もあるかもしれない。
『レベッカ』にも『レイチェル』にも「モンテ・ヴェリタ」にも共通していることがある。聖地によそ者がやってくるという図式だ。聖地とは、『レベッカ』なら「マンダレイ」、『レイチェル』なら「コーンウォール」、「モンテ・ヴェリタ」なら「モンテ・ヴェリタ」である。よそ者は、『レベッカ』の「わたし」、『レイチェル』の「レイチェル」、「モンテ・ヴェリタ」の「わたし」である。いずれもよそ者たちの目的や希望や企みは果たされずに終わる。
「皇女」(1959年、『破局』収録)にも、ロンダ公国という聖地が登場する。ロンダは「歓楽と癒しと平和の国」である。宗教はない。必要がないからである。女性たちも美しい。このシャングリラのような国の最大の資産は、泉から湧き出る水だ。「この水をある種の薬品と調合して用いると、永遠の若さを保つ効能」があるのだ。その秘法は大公だけが知っている。
ロンダ公国に不協和音を起こすのは、マーコイとグランドスである。2人は厳密にいうと「よそ者」ではないが、陰湿で、貪欲で、外国文化に影響されている。ヨーロッパを旅した2人は、半年後、「胸に不満の種を宿して帰国し、そのときは意識していなかったが、それはやがて熟し、芽生えんばかりとな」る。
新聞記者となったマーコイは〈ロンダ・ニューズ〉にこう書く。
「われわれは、老いも若きもひっくるめ、なにゆえわれわれ自身の所有物をわれわれから奪い上げている政府に唯々諾々として支配されているのか。われわれみんなが支配者たりうるのだ。それなのに、われわれは支配されている」
こうした記事を読み続けるうちに、国民はそれまで感じたことのなかった不満を感じるようになる。そして、幾世紀にもわたり平和統治してきた王家に対し、こんな不満を抱くようになる。
「なんの権利があって、あいつはおれたちを支配しているんだ」
ここからはマーコイとグランドスの思惑通りに事が進む。彼らはいわばスヴェンガリである。スヴェンガリとは、デュ・モーリアの祖父ジョージ・デュ・モーリアの小説『トリルビー』に出てくる催眠術師。国民は、革命家の仮面をつけたスヴェンガリによって催眠状態に陥る。まもなく革命が起こり、大公は虐殺され、ロンダ公国はロンダ共和国に変わる。
地球上にいる誰もがシャングリラやモンテ・ヴェリタを望んでいるわけではない。人間には獣性があり、嫉妬心があり、所有欲があり、闘争本能がある。そこを突かれたらどうなるか。デュ・モーリアはそういう人間性を踏まえた上で、革命を描く。肯定的にも否定的に扱わない。その筆致は常にクールだ。そこもまた読者に冷え冷えとした恐怖を催させる。
しかし、マーコイとグランドスの目的は本当に達せられたのだろうか。否である。彼らは「革命の真の目的」だった泉の水の秘密を知ることができなかった。革命家たちはその秘密を握る唯一の存在である皇女を捕え、「追従からはじまり、強姦、拷問、監禁、飢餓、疫病に至るあらゆる手段」を用いて聞き出そうとしたが、皇女は口を割らなかった。そのためにマーコイとグランドスは不老長寿を手にすることなく世を去る。かくして聖地への侵犯は失敗に終わるのだ。
繰り返すが、デュ・モーリアは『レベッカ』だけの作家ではない。彼女は様々なジャンルで才能を発揮し、小説のみならず戯曲やノンフィクションも手がけていた。現在、それらの作品のうち何作が国内で入手できるのだろう。昔、三笠書房から出ていた『デュ・モーリア作品集』が復刊すればいいのだが、そんな気配はなさそうだ。伝記や研究本も国内ではみかけない(マーガレット・フォースターが書いた伝記を海外から取り寄せることは可能である)。英国文学史を扱った書籍などを読んでも、デュ・モーリアの名前が飛ばされているケースが多々ある。無神経な話だ。今後、ジェーン・オースティンやエミリー・ブロンテやヴァージニア・ウルフを生んだイギリスの天才作家として、その真価が知られる日は来るのだろうか。
(阿部十三)
【関連サイト】
ダフネ・デュ・モーリア 聖地に挑む人々
Daphne Du Maurier
ダフネ・デュ・モーリア(書籍)
月別インデックス
- April 2025 [1]
- November 2024 [1]
- October 2024 [1]
- September 2024 [1]
- March 2024 [1]
- February 2024 [1]
- November 2023 [1]
- August 2023 [7]
- March 2023 [1]
- February 2023 [1]
- December 2022 [1]
- October 2022 [1]
- August 2022 [1]
- May 2022 [1]
- February 2022 [1]
- December 2021 [1]
- September 2021 [2]
- August 2021 [1]
- July 2021 [1]
- May 2021 [1]
- March 2021 [1]
- January 2021 [1]
- December 2020 [1]
- October 2020 [1]
- August 2020 [1]
- June 2020 [1]
- May 2020 [2]
- March 2020 [1]
- February 2020 [1]
- January 2020 [1]
- December 2019 [1]
- November 2019 [2]
- October 2019 [1]
- September 2019 [1]
- August 2019 [1]
- July 2019 [1]
- June 2019 [1]
- May 2019 [1]
- March 2019 [1]
- January 2019 [1]
- December 2018 [1]
- November 2018 [1]
- October 2018 [1]
- September 2018 [1]
- July 2018 [1]
- June 2018 [2]
- May 2018 [1]
- February 2018 [1]
- December 2017 [2]
- October 2017 [1]
- September 2017 [1]
- August 2017 [1]
- July 2017 [3]
- June 2017 [1]
- May 2017 [1]
- April 2017 [1]
- February 2017 [1]
- January 2017 [1]
- December 2016 [2]
- October 2016 [1]
- September 2016 [1]
- August 2016 [1]
- July 2016 [1]
- June 2016 [2]
- April 2016 [2]
- March 2016 [1]
- January 2016 [1]
- December 2015 [2]
- November 2015 [1]
- October 2015 [1]
- September 2015 [2]
- August 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- May 2015 [2]
- April 2015 [1]
- March 2015 [1]
- February 2015 [1]
- January 2015 [1]
- December 2014 [1]
- November 2014 [2]
- October 2014 [1]
- September 2014 [2]
- August 2014 [1]
- July 2014 [1]
- June 2014 [2]
- May 2014 [2]
- April 2014 [1]
- March 2014 [1]
- February 2014 [1]
- January 2014 [3]
- December 2013 [3]
- November 2013 [2]
- October 2013 [1]
- September 2013 [2]
- August 2013 [1]
- July 2013 [2]
- June 2013 [2]
- May 2013 [2]
- April 2013 [3]
- March 2013 [2]
- February 2013 [2]
- January 2013 [1]
- December 2012 [3]
- November 2012 [2]
- October 2012 [3]
- September 2012 [3]
- August 2012 [3]
- July 2012 [3]
- June 2012 [3]
- May 2012 [2]
- April 2012 [3]
- March 2012 [2]
- February 2012 [3]
- January 2012 [4]
- December 2011 [5]
- November 2011 [4]
- October 2011 [5]
- September 2011 [4]
- August 2011 [4]
- July 2011 [5]
- June 2011 [4]
- May 2011 [4]
- April 2011 [5]
- March 2011 [4]
- February 2011 [5]