
〈少将滋幹の母〉をめぐる色道
2017.07.01
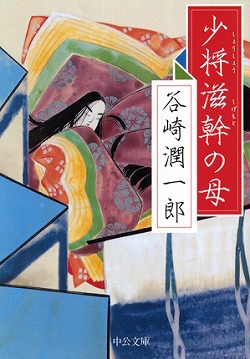
物語中盤の重要な場面ーー左大臣の時平が大納言の国経を泥酔させ、さらに権力で圧迫し、さも国経がすすんで献上したようにして、その美貌の若妻を自分のものにする場面の大筋は、谷崎の創作ではなく、『今昔物語』の巻第二十二「時平の大臣国経の大納言の妻を取る語第八」をもとにしている。ただし、時平による謀略が着々と進行して実行されるまでの迫真の描写は、あくまでも谷崎の筆のなせるわざだ。
史実のあらましは次の通りである。大納言国経は、七十歳過ぎの老齢でありながら、やっと20歳を越えたくらいの美しい妻(北の方)を迎え、子宝(滋幹)にも恵まれ、穏やかに暮らしていた。その噂を聞いて興味を抱いた左大臣時平は、すでに北の方と密通している色男の平中から情報を聞き出すと、情欲を燃やし、伯父とはいえ自分より格下の大納言を丁重に扱うようにした。そして年の暮れが近づいた頃、使者をやり、正月の三が日のうちに大納言の邸に行く由を告げた。国経が喜び、ぬかりなく饗応の支度をしたことは言うまでもない。
正月三日、大納言邸で宴が始まった。杯が重ねられ、歌が歌われ、座は盛り上がったが、その最中、時平は簾の向こうにいる北の方に流し目を使っていた。やがて夜も更け、時平が帰ろうとすると、国経は引出物として見事な馬2頭を用意させた。しかし、ここで時平が本性を見せる。普段から大納言のことを気にかけ、このように左大臣の方からわざわざ出向いてきたことを恩に着せ、その程度の引出物では物足りないと言い、もっと特別な物を要求したのである。時平が露骨に御簾の方を見ていることに気付いた国経は、どうにも引っ込みがつかなくなり、また、泥酔していた勢いも手伝って、北の方を引出物にすると言ってしまった。時平は来た甲斐があったと、女の袖をとらえ、車に乗せて去った。明け方、目を覚ました国経は己の行為を悔やんだが、もう遅い。今さら妻を取り返すこともできず、ただ恋しく思うのであった。
『今昔物語』はこの後が欠落しているが、『世継物語』には続きが記されている。それによると、北の方は左大臣邸の対屋に住み、時平の子(敦忠)を生み、何不自由なく暮らしていた。国経の妻であった当時密通していた平中は、今や手が届かなくなったことを口惜しく思い、色々画策して歌を交わしていたという。後撰集の「昔せし我かねごとの悲しきはいかに契りし名残なるらん」はその時の歌である。『今昔物語』に、北の方が老人の妻である己が身の上を情けなく思い、左大臣になびいていたという意味のことが書かれているのは、後世の解釈なのだろうが、平中と関係していたことを考えると、本当らしく思える。
平安貴族の恋愛観は現代のモラルでは到底測れないが、左大臣の行いはさすがに当時でも目に余るものだったようだ。だからこそ事件として書き遺されたのだろう。この手の話は、武士の時代ならいざ知らず、平安の世には似つかわしくない。谷崎は『少将滋幹の母』で、平中の心情を次のように綴り、色道の仁義を以て時平を非難している。
「彼に云はせれば、妻は夫の眼を掠め、夫は妻の眼を掠めて、無理な首尾をし、危い瀬戸を渡り、こつそりと切ない逢ふ瀬を樂しむところにこそ戀の面白味は存するのである。地位や權勢を利用して他人の所有物を強奪するのでは、身も蓋もない野暮な話で、自慢にも何もなりはしない。左大臣のやり方は、他人の面目や世間の掟を蹈み躙つた傍若無人な行爲であるのみか、色道の方でも仲間の仁義を無視した仕方で、あれでは色事師の資格はないと云ふべきである」
時平については、『大鏡』に「大和魂などは、いみじくおはしましたるものを」と書かれている。つまり、知恵と才覚に富み、実務能力があった。笑癖がひどく、一度笑い出すと止まらなかったとも言われている。一方、すこぶる好色であり、国経のように泣きを見る者もいた。何よりも、時平の名は、菅公すなわち菅原道真公を陥れ、大宰府へと追いやったために呪われた人物として、今は知られている。
その死にざまは救いがない。菅公の死後、陰謀に加担した藤原定国、藤原菅根といった人物が相次いで亡くなり、いよいよ時平が病に倒れた。その死が近づいてきた時、三善清行の子、浄蔵が呼ばれた。世に聞こえた浄蔵の法力にすがるほか術がなくなったのである。しかし、加持祈祷が始まると、青龍と化した菅公が時平の両耳から出現し、清行を説き伏せた。清行は浄蔵に祈祷を止めさせ、時平はまもなく絶命した。享年三十九歳。
無念の死を遂げた霊が、多くの高貴な人々を死に至らしめ、時の政権に甚大な被害を及ぼし、怖れられた有名な例としては、菅公のほかに大津皇子や長屋王などが挙げられる。権勢をほしいままにする者が邪魔な人間を陥れ、御霊神に祟られる話には、慈悲の概念はない。その思想は霊を重んじる日本人の自然な気質のあらわれであると同時に、驕れる権力者に対する批判も多分に含んでいるように感じられる。時平の場合も、因果応報の色合いが非常に濃い。
言うまでもなく、このような話は日本史に数多く見られるが、武士の時代以降は、非業の死を遂げた者は無数にいるのに、平安期の菅公の話よりも広まった例はあまりない。民衆の宗教が変化してきたことも影響しているのだろう。しかし、我々日本人は御霊信仰から完全に脱することはない。慈悲や許しなどという、ともすると生者の都合で濫用される考えが、全然通用しない場合があることを知っている。大津皇子も菅公も怒れる龍になったが、それは誇張の表現ではない。
『少将滋幹の母』では、妻を奪われた国経も、不浄観を会得しようとしてかなわず、愛欲と妄執に悶えて亡くなったことになっている。だとすると、(谷崎はそこまでは書いていないが)やはり時平に祟ったのではないか。老人の愛欲の恨みはなかなか烈しそうである。実際、時平が北の方に生ませた敦忠も三十代で亡くなっている。
平中はというと、左大臣邸に仕えていた侍従の君に翻弄され、煩悶して死んだと『今昔物語』に書かれている(芥川龍之介の「好色」はこれを題材にしている)。それについて谷崎は、時平が侍従を裏で操り、平中を苦しめていたという仮説を立てているが、平中の没年は時平の死のだいぶ後なので肯んじがたい。
先にふれたように、〈少将滋幹の母〉は在原業平の孫娘である。業平も平中も色好みで知られた人物であった。しかしながら両者は、『伊勢物語』や『平中物語』を読めばわかるように、笑える話はあっても、あまり批判的には描かれていない。色道の仁義にかなった人物だったのだろう。まさか、自分の孫娘が色道にもとる時平の獲物にされようとは、業平の霊も思い及ばなかったにちがいない。
(阿部十三)
【関連サイト】
谷崎潤一郎(書籍)
谷崎潤一郎『少将滋幹の母』(書籍)
月別インデックス
- February 2026 [1]
- April 2025 [1]
- November 2024 [1]
- October 2024 [1]
- September 2024 [1]
- March 2024 [1]
- February 2024 [1]
- November 2023 [1]
- August 2023 [7]
- March 2023 [1]
- February 2023 [1]
- December 2022 [1]
- October 2022 [1]
- August 2022 [1]
- May 2022 [1]
- February 2022 [1]
- December 2021 [1]
- September 2021 [2]
- August 2021 [1]
- July 2021 [1]
- May 2021 [1]
- March 2021 [1]
- January 2021 [1]
- December 2020 [1]
- October 2020 [1]
- August 2020 [1]
- June 2020 [1]
- May 2020 [2]
- March 2020 [1]
- February 2020 [1]
- January 2020 [1]
- December 2019 [1]
- November 2019 [2]
- October 2019 [1]
- September 2019 [1]
- August 2019 [1]
- July 2019 [1]
- June 2019 [1]
- May 2019 [1]
- March 2019 [1]
- January 2019 [1]
- December 2018 [1]
- November 2018 [1]
- October 2018 [1]
- September 2018 [1]
- July 2018 [1]
- June 2018 [2]
- May 2018 [1]
- February 2018 [1]
- December 2017 [2]
- October 2017 [1]
- September 2017 [1]
- August 2017 [1]
- July 2017 [3]
- June 2017 [1]
- May 2017 [1]
- April 2017 [1]
- February 2017 [1]
- January 2017 [1]
- December 2016 [2]
- October 2016 [1]
- September 2016 [1]
- August 2016 [1]
- July 2016 [1]
- June 2016 [2]
- April 2016 [2]
- March 2016 [1]
- January 2016 [1]
- December 2015 [2]
- November 2015 [1]
- October 2015 [1]
- September 2015 [2]
- August 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- May 2015 [2]
- April 2015 [1]
- March 2015 [1]
- February 2015 [1]
- January 2015 [1]
- December 2014 [1]
- November 2014 [2]
- October 2014 [1]
- September 2014 [2]
- August 2014 [1]
- July 2014 [1]
- June 2014 [2]
- May 2014 [2]
- April 2014 [1]
- March 2014 [1]
- February 2014 [1]
- January 2014 [3]
- December 2013 [3]
- November 2013 [2]
- October 2013 [1]
- September 2013 [2]
- August 2013 [1]
- July 2013 [2]
- June 2013 [2]
- May 2013 [2]
- April 2013 [3]
- March 2013 [2]
- February 2013 [2]
- January 2013 [1]
- December 2012 [3]
- November 2012 [2]
- October 2012 [3]
- September 2012 [3]
- August 2012 [3]
- July 2012 [3]
- June 2012 [3]
- May 2012 [2]
- April 2012 [3]
- March 2012 [2]
- February 2012 [3]
- January 2012 [4]
- December 2011 [5]
- November 2011 [4]
- October 2011 [5]
- September 2011 [4]
- August 2011 [4]
- July 2011 [5]
- June 2011 [4]
- May 2011 [4]
- April 2011 [5]
- March 2011 [4]
- February 2011 [5]