
名前を呼ぶということ 〜フェードルとジュリエットの場合〜
2020.08.12
フェードルの場合
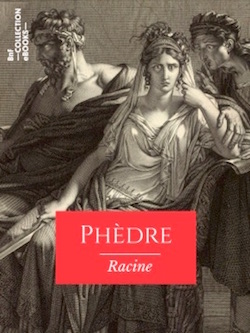
フェードルはギリシャ神話に出てくるクレタ島の王ミノスの娘であり、アテナイの王テーゼの妻である。テーゼにはアマゾン(女性だけの部族)の女王アンティオペーとの間に子供がいる。それが立派な青年となったイポリートだ。これまでフェードルは、血の繋がりのない彼に対して冷たく振る舞ってきた。それは己の恋心を隠すためである。
やがて彼女は己の秘めた恋に苦しみ、死を望む。その理由をまったく知らない乳母のエレーヌは、生きる気力を与えようと励ます。しかし会話を進めていくうちに、エレーヌはフェードルが恋煩いをしているのではないかと考える。その相手を尋ねると、フェードルはついに我慢できず、打ち明ける。
フェードル:お前は身の毛もよだつようなことを聞くのだよ。私が愛しているのは......呪わしいあの名前、言おうとすると、身が震え、わななく。私が愛しているのは......
エレーヌ:誰です?
フェードル:知っておいでだろう、あのアマゾンの女王の息子を。長い間、この私が虐げてきた王子のことを。
エレーヌ:イポリート!ああ、なんという!
フェードル:お前だよ、その名前を口に出したのは。
(『フェードル』)
この2人の長いダイアローグには大きな起伏がある。会話の最初の方でエレーヌが「イポリート」の名を口に出した時も、フェードルは動揺している。そして、そこからやりとりが続き、「私が愛しているのは......呪わしいあの名前」で劇的緊張がピークに達する。しかし、彼女は直接名前を口にすることができない。かわりに、エレーヌが軽々しく口にするのだ。
フランスの批評家ロラン・バルトは『ラシーヌ論』の中で『フェードル』に言及し、この劇では「言葉の意味よりは、言葉の出現そのものに重きが置かれている」と指摘した。バルトによると、言葉が恐ろしいのは、「一度発したら取り返しがつかない」からである。言葉とは生命の代替物であり、発された言葉は、巻き戻すことのできない時間の中にある。
言葉の中でも、人の名前は特に重い。真に「生命の代替物」と呼ぶに値するのは名前である。名前を口にすれば実体を喚び起こすことになるという考え方は大昔からあった。古代ギリシャの劇作家エウリピデスもそのように考えていた一人で、発された名前が深刻な影響をもたらす場面を『ヒッポリュトス』に盛り込んでいる。ラシーヌはこれを踏まえて『フェードル』を書いたのだ。
『ヒッポリュトス』は紀元前428年に上演された悲劇で、やはりパイドラ(フェードル)がヒッポリュトス(イポリート)に禁断の恋心を抱く。その後の展開は1677年に上演された『フェードル』と大きく異なるが、パイドラが胸の内を明かす場面はほぼ同じである。ラシーヌは言葉(名前)が出現する瞬間を重く見て、ここだけは変えるべきではないと判断したのだろう。
乳母:姫様、あなたは恋をしておいででございますの? それはまた一体どのお方に?
パイドラ:どういう方と言ってよいか、それはあのアマゾンの御子の......。
乳母:と申すと、ヒッポリュトス様?
パイドラ:(両手で顔を隠し、床の上に崩れ伏す)それを言ったのは婆やよ。私ではありませんよ。
(『ヒッポリュトス』)
愛する人の名前は神聖なものだが、時として素手で直接肉体に触れるような生々しい響きを持つ。本来気位の高いヒロインは、愛してはいけない男の名前を聞いたり、自ら口にしたりすることを恐れ、潔癖とも言える態度をとりながら、恐れの中にある甘美な感情に悶えているのだ。
ジュリエットの場合
「ああ、ロミオ様、ロミオ様、あなたはなぜロミオ様なの?」
このバルコニーの場面で、ジュリエットはロミオの名前を連呼し、「名前を捨ててほしい」と願う。しかし、それは無効になるどころか、名前の力をより強めて、甘美な空気を醸成することになる。ジュリエット自身、愛しい人の名を口にすることで、はからずもバラ色の恋心に胸を膨らませているのだ。そして、客席にいる私たちはというと、この場面でジュリエットが「ロミオ」と言うたびに、生々しい響きにドキドキしたり、照れ臭い気持ちになったりする。
現代のラブソングの歌詞にも、好きな人の名前を呼ぶと愛しさが増す、あるいは切ない気持ちになるといったものが少なからずある。通常の話し言葉とはまた別に、名前の中に含まれている言霊は相当重い。それをジュリエットのように何度も口にするか、フェードルのように避けようとするかの違いはあれ、人の名前ほど心理に影響を及ぼすものは稀である。
これが嫌いな人の名前だと、どうなるのか。嫌いな人の名前なんか言うのも聞くのも避けたいと思うのが普通だろう。クラシック音楽のファンには有名なエピソードだが、かつてヴィルヘルム・フルトヴェングラーは、年下のヘルベルト・フォン・カラヤンの名前を呼ぶことを避け、「K」と呼んでいた。ピエール・ブーレーズは、インタビュアーがショスタコーヴィチの名前を出すと、「その名前は禁句です」と拒否反応を示した。クラシックの世界に限らず、そんな話はざらにある。名前には実体を喚び起こす力があるから、相手の名前を忌避するのは当然である。名前とは生々しいものなのだ。
日本や中国には諱(忌み名)というものがある。辞書には、「(1)人の死後尊敬しておくる敬称。(2)死んだ人の生前の名前。(3)身分の高い人の実名」とある。重要なのは(3)だ。貴人や目上の人を実名で呼ぶのをはばかることを「避諱(ひき)」という。これは今でも根強く残っている風習である。
諱を避ける理由は諸説あり、相手の存在を支配する行為だからとも、呪術に利用されるからとも言われる。どの説が正しいにしても、「名前はその人の精神、肉体と切り離せない」という前提がなければならない。もっと言えば、人間とは精神と肉体と名前で構成されるという考えに基づいている。
英語圏の名前には短縮形や愛称がある。例えば、エリザベスは「リズ、イライザ、リリアン、ベス、ベティー」、ロバートは「ロビン、ロブ、ボブ、ボビー」という具合に。その方が親しみやすいとか、呼びやすいということなのだろうが、日本人である私の目にはこれも一種の「避諱」のように見える。ミドルネームを略して呼ぶのも然りで、フルネームで呼ぶのは親が子供を本気で叱る時だという話を聞いたことがある。
名前を呼ぶことを重くみる感覚は、洋の東西でどこか通じるものがあるのだろう。モーゼの十戒には、「神の名をみだりに唱えてはならない」とある。神の名は尊い。貴人の名も尊い。愛する人の名も尊い。好きな芸能人、アイドルの名も然りだ。その名前を目にしたり、呼んだりする時のドキドキ感は、古代のタブーを破る感覚を味わうことで生じているのかもしれない。
(阿部十三)
【関連サイト】
月別インデックス
- April 2025 [1]
- November 2024 [1]
- October 2024 [1]
- September 2024 [1]
- March 2024 [1]
- February 2024 [1]
- November 2023 [1]
- August 2023 [7]
- March 2023 [1]
- February 2023 [1]
- December 2022 [1]
- October 2022 [1]
- August 2022 [1]
- May 2022 [1]
- February 2022 [1]
- December 2021 [1]
- September 2021 [2]
- August 2021 [1]
- July 2021 [1]
- May 2021 [1]
- March 2021 [1]
- January 2021 [1]
- December 2020 [1]
- October 2020 [1]
- August 2020 [1]
- June 2020 [1]
- May 2020 [2]
- March 2020 [1]
- February 2020 [1]
- January 2020 [1]
- December 2019 [1]
- November 2019 [2]
- October 2019 [1]
- September 2019 [1]
- August 2019 [1]
- July 2019 [1]
- June 2019 [1]
- May 2019 [1]
- March 2019 [1]
- January 2019 [1]
- December 2018 [1]
- November 2018 [1]
- October 2018 [1]
- September 2018 [1]
- July 2018 [1]
- June 2018 [2]
- May 2018 [1]
- February 2018 [1]
- December 2017 [2]
- October 2017 [1]
- September 2017 [1]
- August 2017 [1]
- July 2017 [3]
- June 2017 [1]
- May 2017 [1]
- April 2017 [1]
- February 2017 [1]
- January 2017 [1]
- December 2016 [2]
- October 2016 [1]
- September 2016 [1]
- August 2016 [1]
- July 2016 [1]
- June 2016 [2]
- April 2016 [2]
- March 2016 [1]
- January 2016 [1]
- December 2015 [2]
- November 2015 [1]
- October 2015 [1]
- September 2015 [2]
- August 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- May 2015 [2]
- April 2015 [1]
- March 2015 [1]
- February 2015 [1]
- January 2015 [1]
- December 2014 [1]
- November 2014 [2]
- October 2014 [1]
- September 2014 [2]
- August 2014 [1]
- July 2014 [1]
- June 2014 [2]
- May 2014 [2]
- April 2014 [1]
- March 2014 [1]
- February 2014 [1]
- January 2014 [3]
- December 2013 [3]
- November 2013 [2]
- October 2013 [1]
- September 2013 [2]
- August 2013 [1]
- July 2013 [2]
- June 2013 [2]
- May 2013 [2]
- April 2013 [3]
- March 2013 [2]
- February 2013 [2]
- January 2013 [1]
- December 2012 [3]
- November 2012 [2]
- October 2012 [3]
- September 2012 [3]
- August 2012 [3]
- July 2012 [3]
- June 2012 [3]
- May 2012 [2]
- April 2012 [3]
- March 2012 [2]
- February 2012 [3]
- January 2012 [4]
- December 2011 [5]
- November 2011 [4]
- October 2011 [5]
- September 2011 [4]
- August 2011 [4]
- July 2011 [5]
- June 2011 [4]
- May 2011 [4]
- April 2011 [5]
- March 2011 [4]
- February 2011 [5]