タグ「ベートーヴェン」が付けられているもの
-

ベートーヴェンの「月光」をアナトリー・ヴェデルニコフほど美しく奏でた人はほとんどいない。この格調高く、内省的な第1楽章を聴いていると、時間や空間の動きが止まって音楽だけがなめらかに流れているような気持ちにさせられる。テクニックは申し分ないが、機械的な冷たさはなく、わざとらしいアクセントもない。演奏者がただ者でないことはすぐに分かる。 かつて名教師・名ピア...
[続きを読む](2019.05.10) -

名は体を表す ベートーヴェンのピアノ・ソナタ第23番は1804年から1805年にかけて作曲されたとみられている。「熱情(Appassionata)」という題は作曲者の死後、ハンブルクの出版社クランツによって付けられたものだが、まさに熱情をそのまま音楽に置き換えたような作品なので、おそらく今日でも、この作品を初めて聴く人は、オブラートに包まれていない激しい感情...
[続きを読む](2019.02.04) -

スイス出身の大ピアニスト、エドウィン・フィッシャーの著書に『音楽の考察』というエッセイ集がある。邦訳もあり、『音楽を愛する友へ』と題されて新潮社から出ていた(1958年初版)。 フィッシャーはこの本の中で、演奏家の心得を述べ、「作曲家が作品を懐胎した時に彼が霊感を受けていた状態に、われわれ自身の身を置くこと」の大切さを説き、合理主義に傾いている音楽表現や音...
[続きを読む](2019.01.26) -

アレルヤとジュピター ヨハン・ネポムク・フンメルは1778年にプレスブルク(現ブラチスラヴァ)に生まれた。ベートーヴェンの8歳下である。神童だったフンメルは、アウフ・デア・ヴィーデン劇場の音楽監督になった父親と共にウィーンに移住、モーツァルトにピアノを教わった。フンメルのことを気に入ったモーツァルトは、1787年に自身が主催した演奏会でピアニストとしてデビュ...
[続きを読む](2018.03.04) -

「皇帝」と呼ばれる協奏曲 ベートーヴェンが完成させた最後の協奏曲である。作曲年は1809年。いわゆる「傑作の森」の時期に書かれた大作で、「皇帝」の異名にふさわしいスケールと風格を備えているが、これは作曲家自身による命名ではなく、出版人のJ.B.クラマーによるものである。作品はルドルフ大公に献呈された。 1809年といえば、ウィーンがフランス軍に占領されていた...
[続きを読む](2017.12.05) -

もう一人の巨人 ベートーヴェンの交響曲第4番は1806年に作曲され、1807年3月に初演された。かつてシューマンは、有名な第3番と第5番の間に生まれたこの作品を、「北欧の2人の巨人に挟まれた清楚可憐なギリシャの乙女」と呼んだ。美しい呼称である。しかし、第2楽章はともかく、全体的にはベートーヴェンらしい力強さと緊張感をたたえた力作で、その構成も(第5番以上とは...
[続きを読む](2017.05.29) -

次の世代の作曲家として ベートーヴェンの交響曲第1番は、遅くとも1800年3月までに書かれ、同年4月2日に作曲者自身の指揮により初演された。30歳を迎える前にようやく最初の交響曲を完成させたわけだが、これが嚆矢となり、ベートーヴェンは30代の間に第2番から第6番「田園」まで書き上げることになる。 第1番の作風については、ハイドン、モーツァルトの影響から脱し切...
[続きを読む](2017.05.12) -

短調の眠り アントニオ・ヴィヴァルディの『四季』は、1725年に出版された『和声と創意への試み』の中に収録されている最初の4曲、「春」「夏」「秋」「冬」を指す。それぞれの曲は、作者不明のソネットをもとにした一種の「標題音楽」で、春の喜び、夏のけだるさと激しい嵐、秋の収穫の祝いと狩猟、冬の寒さと暖炉がある室内での安らぎなどが描写される。 バロック期の標題音楽の...
[続きを読む](2017.04.02) -

ベートーヴェン弾きとして ベートーヴェンのピアノ・ソナタ全集は、モノラルとステレオの2種類ある。前者は1950年から1954年、後者は1959年から1969年にかけて録音された(「ハンマークラヴィーア・ソナタ」は除く)。演奏に関しては、モノラル盤の方が構築的である。ピアニッシモの美しい音色や聴き手に違和感を与えないアゴーギクの妙技も、神経質すぎない程度に磨か...
[続きを読む](2017.03.13) -

何もかもが音楽的 ヴィルヘルム・バックハウスは「鍵盤の獅子王」と呼ばれたドイツのピアニストで、ベートーヴェンやブラームスを得意としていた。質実剛健、謹厳実直と言われることが多いが、その音楽性は決して堅苦しいものではなく、聴き手に息詰まるような緊張を強いるものでもない。むしろ、すぐれた音楽作品に封じ込められた神秘をあっさりと解き放ち、難解さやいかめしさとは異な...
[続きを読む](2017.03.10) -

変化と創造への意思 ベートーヴェンの交響曲第3番は1803年5月から1804年にかけて作曲された。公開初演日は1805年4月7日。作曲のきっかけは定かでないが、ベートーヴェンが完成した作品をナポレオン・ボナパルトに献呈するつもりでいたところ、皇帝に即位したニュースを聞いて失望したという逸話は有名だ。 第2番を作曲したのは1802年のことなので、この第3番の完...
[続きを読む](2016.11.01) -
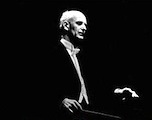
一回勝負に賭ける演奏 ヴィルヘルム・フルトヴェングラーが没入を重んじた指揮者だったことは、遺された録音や映像に接すればすぐに分かる。その手記にも、集中と没頭なき芸術が「芸術全般の悲劇の始まり」であると書かれている。彼にとって、単に楽譜に忠実なだけの演奏は非創造的であり、個性的な審美観を振り回す指揮は疑わしいものであった。「私にとって重要なのは、魂に訴えるか否...
[続きを読む](2016.10.19) -

円熟前の傑作 ベートーヴェンの交響曲第2番は、第8番と並び、語られることの少ない作品だ。しかし、ここには第3番「英雄」以降の作品にはない円熟前の魅力があり、青年らしい生気がある。端的に言えば、円熟した人間には書けない傑作である。「私はこの作品の中に、誰一人取り戻すことのできない快活な青春時代を、そして、欠点を除去しようとすればたちまちのうちに逃げ去ってしまう...
[続きを読む](2016.07.10) -
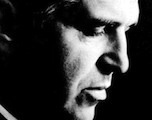
ハンス・リヒター=ハーザーはかつてヨーロッパでもアメリカでも称賛されたドイツのピアニストである。遺された音源が限られているせいか、今では地味な存在になっているが、実際の音楽性は地味と言われるようなものでは全くない。 生まれたのは1912年1月6日。13歳でドレスデン・アカデミーに入学し、ピアノだけでなくヴァイオリン、打楽器、指揮法も学んだ。1928年にデビ...
[続きを読む](2016.05.29) -

クレンペラーの音楽 木管を強調させるやり方は、クレンペラーが意識して行っていたことである。何しろ「木管がきこえるということがもっとも重要なのです」とまで言い切っているのだ。その傾向が昔からあったことは、1928年に録音されたR.シュトラウスの「7つのヴェールの踊り」を聴くとわかる。これは極めて貴重な音源だ。録音年代を忘れるほど音質が良いこともあり、ぞくぞくす...
[続きを読む](2016.03.21) -

マーラーの影響 若い頃、オットー・クレンペラーはマーラーの交響曲第2番「復活」をピアノ用に編曲して暗譜で演奏し、作曲者に認められた。そして、そのとき書いてもらった推薦状のおかげで、プラハの歌劇場の指揮者になることができた。1907年のことである。「すぐれた音楽家クレンペラー氏をご推薦申し上げます。氏はまだ若年にもかかわらず、すでに経験豊かであり、指揮者の職に...
[続きを読む](2016.03.19) -

完全無欠 ベートーヴェンの交響曲第5番は、1804年から1808年の間に作曲された。キンスキー=ハルムの作品目録によると、交響曲第3番「英雄」完成後に着手したが、交響曲第4番、ピアノ協奏曲第4番、ヴァイオリン協奏曲などの創作のため中断、1807年に再び取りかかり、1808年の早い時期に書き上げたという。作曲に費やした時間が実質的にどれくらいなのかは不明だが、...
[続きを読む](2015.08.13) -
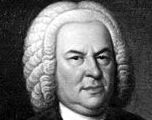
音楽の冒険 J.S.バッハの「ゴルトベルク変奏曲」は、『クラヴィーア練習曲集』の第4部として1741年(1742年とも言われる)に出版された作品で、元々は「2段の手鍵盤をもつチェンバロのためのアリアとさまざまな変奏」と題されていた。「ゴルトベルク変奏曲」と呼ばれるようになったのは、ヨハン・ニコラウス・フォルケルが『バッハ小伝』の中で、あの有名なエピソードを伝...
[続きを読む](2015.07.09) -

ピアノ・ソナタの詩情 シューベルトのピアノ・ソナタの中で最高傑作と評されることが多いのは、第21番である。これに対して異論を唱える人はほとんどいないだろう。私自身も最初はこの晩年の作品に魅了され、シューベルトのピアノ・ソナタを聴くようになった。ただ、私が無性に惹かれたのは第21番の第1楽章であり、ほかの楽章がそこまで自分の心に深く浸潤したかというと、やや疑わ...
[続きを読む](2015.04.10) -

楽想は深淵の傍に シューベルトの音楽を聴いていると、必ずと言っていいほど楽想というものに考えが及ぶ。彼はひとつの作品の中にさまざまな楽想を織り込み、それらを有機的につなげることで、えもいわれぬ美の世界と独創的な構成を獲得した。その作品では、次から次へと美しい楽想があらわれ、こともなげに連鎖する。たとえそれが理論上異質な要素であっても、同じ空気の中で結合し、包...
[続きを読む](2015.01.09)