
J.S.バッハ ゴルトベルク変奏曲
2015.07.09
音楽の冒険
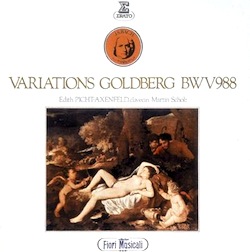 J.S.バッハの「ゴルトベルク変奏曲」は、『クラヴィーア練習曲集』の第4部として1741年(1742年とも言われる)に出版された作品で、元々は「2段の手鍵盤をもつチェンバロのためのアリアとさまざまな変奏」と題されていた。「ゴルトベルク変奏曲」と呼ばれるようになったのは、ヨハン・ニコラウス・フォルケルが『バッハ小伝』の中で、あの有名なエピソードを伝えてからである。すなわち、カイザーリンク伯爵が不眠症に悩んでいた頃、眠れない夜に気持ちを慰めてくれるような作品をバッハに依頼し、それを伯爵に仕えていたヨハン・ゴットリープ・ゴルトベルクに弾かせたという話だ。当時ゴルトベルクは14歳か15歳。これだけの変化に富んだ変奏曲を満足のいくように弾きこなせたとすれば、相当の才能の持ち主だったのだろうが、このエピソード自体の信憑性を疑う人は多い。
J.S.バッハの「ゴルトベルク変奏曲」は、『クラヴィーア練習曲集』の第4部として1741年(1742年とも言われる)に出版された作品で、元々は「2段の手鍵盤をもつチェンバロのためのアリアとさまざまな変奏」と題されていた。「ゴルトベルク変奏曲」と呼ばれるようになったのは、ヨハン・ニコラウス・フォルケルが『バッハ小伝』の中で、あの有名なエピソードを伝えてからである。すなわち、カイザーリンク伯爵が不眠症に悩んでいた頃、眠れない夜に気持ちを慰めてくれるような作品をバッハに依頼し、それを伯爵に仕えていたヨハン・ゴットリープ・ゴルトベルクに弾かせたという話だ。当時ゴルトベルクは14歳か15歳。これだけの変化に富んだ変奏曲を満足のいくように弾きこなせたとすれば、相当の才能の持ち主だったのだろうが、このエピソード自体の信憑性を疑う人は多い。
冒頭で32小節の美しいアリアが奏でられた後、その低音主題に基づく30の変奏曲が披露され、最後に再びアリアで締めくくられる。全32曲。ト長調が29曲、残り3曲はト短調である。30の異なる変奏は3曲ごとにカノンによって区切られ、一つの小さなまとまりを成している。バッハは数字に大きな意味を持たせた作曲家だが、ここでは3と32が支配しているようだ。
数字が支配しているといっても、そこに溢れる楽想は窮屈さとは無縁で、驚くほど大胆で斬新だ。創作アリアに基づく32の変奏曲「ラ・カプリツィオーザ」(これもト長調)を書いた先輩作曲家ブクステフーデからの影響も感じられるが、バッハの作品が革新的であることに変わりはない。快活な第1変奏だけでも意外性に富んでいるし、暗く幻想的な第25変奏にいたっては各曲との連関性のきわどさを見せつけるかのようで、そこまでやるかと言いたくなる。こういう作品を聴くにつけ、クラシック音楽が保守の歴史ではなく、革新の歴史であることを改めて痛感させられる。一つ一つの変奏を作曲している間のバッハの頭の中がどんな風だったのか、どの変奏から着手したのか、変奏の順番は何を意味しているのか、これは推理小説のテーマにもなり得る謎だ。約80年後に「ディアベリ変奏曲」を書くことになるベートーヴェンだったら、どのようにバッハの楽譜を読み解くだろう。
30の変奏曲がもたらすのは、汲めども尽きぬ魅力に満ちた音楽の冒険である。民謡を用いた最後の「クォドリベット」は、その到達感のあらわれだ。いかにも大団円という趣がある。伯爵の不眠症を癒すために書かれた(らしい)というエピソードに反論する気はないし、私自身、昔は第15変奏、第21変奏、第25変奏に配された短調の曲を聴くと必ず眠くなったものだが、一度作品全体を把握した者にとっては、何度通っても面白みのある道が続いている。
「ゴルトベルク変奏曲」を語る上で欠かせない演奏家は2人いる。ワンダ・ランドフスカとグレン・グールドだ。前者は言わずと知れたチェンバロ復興の立役者。1933年にこの作品を録音し、しばらくの間、決定盤とみなされていた。後者はこれまた超有名なカナダ出身のピアニストで、1956年に弱冠23歳で「ゴルトベルク変奏曲」を発表してデビュー(録音時は22歳)。そこでセンセーショナルな成功を収めたことが、今日の「ゴルトベルク変奏曲」の人気につながっていると言っても過言ではない。総じてテンポが速く、反復も無く、「ジャズのようだ」とも評されたこの演奏に違和感を覚えた人は多いようだが、これによって重々しいバッハ像が払拭されたことは間違いない。
 かくいう私はこの演奏を好みながらも、録音の音質が生理的に受けつけられず、自ら率先して聴くことはほとんどない。グールドに関して言えば、2度目の録音、彼が世を去る前年(1981年)の演奏をよく聴いている。ゆるやかなテンポで、なおかつ旋律の一つ一つを浮き上がらせ、主張させ、各変奏の連関性を印象づけるように弾いているので、音の動きがつかみやすい。作品に対する深い理解と愛情が伝わってくる演奏だ。ただ、もう少し自然な音楽の流れを好む人には、ザルツブルク音楽祭で弾いたときの演奏(1959年ライヴ録音)が向いているかもしれない。
かくいう私はこの演奏を好みながらも、録音の音質が生理的に受けつけられず、自ら率先して聴くことはほとんどない。グールドに関して言えば、2度目の録音、彼が世を去る前年(1981年)の演奏をよく聴いている。ゆるやかなテンポで、なおかつ旋律の一つ一つを浮き上がらせ、主張させ、各変奏の連関性を印象づけるように弾いているので、音の動きがつかみやすい。作品に対する深い理解と愛情が伝わってくる演奏だ。ただ、もう少し自然な音楽の流れを好む人には、ザルツブルク音楽祭で弾いたときの演奏(1959年ライヴ録音)が向いているかもしれない。
「ピアノによるゴルトベルク」は、グールドが先駆者であるわけではなく、ランドフスカとグールドの録音の間にはクラウディオ・アラウの演奏が存在する。これは1942年に録音されたもののお蔵入りとなり、1988年になって発売された。また、1920年代には若き日のルドルフ・ゼルキンがアンコールで全曲弾いたというエピソードも残っている。とはいえ「グールド以後」にピアノで録音した人は、程度の差こそあれ、この天才をいやでも意識せざるを得なくなっている。常に比較されるのだから、そうなるのも仕方ない。結果的に、深い音楽性よりも理知や才気で武装した頭でっかちの演奏が多くなっている。
その点、1969年に録音されたヴィルムヘルム・ケンプの演奏は、年の功とでも言うべきか、グールドの影響を全く感じさせない。装飾音を最小限に削り、音楽自体がリラックスして流れているような開放的な雰囲気に覆われている。ほかのピアニストと同じ作品を弾いているとは思えない、と言うと大袈裟だが、そう言いたくなるほど独自に確立された世界の中で悠然とピアノを奏でている。
 本来「ゴルトベルク変奏曲」は嗜好性が著しく異なる作品で、人によって好みが細かく分かれるのが普通なのではないかと思う。どんな歴史的名盤もそこまでアテにならず、自分に合う演奏を簡単に見つけることはできないのだ。私の場合、グールド、ケンプ、ランドフスカ、ロザリン・テューレック(1988年録音)の順に好きになったが、完璧に自分にフィットする音楽を見出したわけではなかった。私が初めて「ゴルトベルク変奏曲をのみこめた」と感じて、さわやかな感動を覚えたのは、エディト・ピヒト=アクセンフェルトのチェンバロ(1965年頃の録音)を聴いたときである。アリアの演奏中、やたら耳につく鳥のさえずりには苦笑させられたものだが、第1変奏から第30変奏まで意匠を凝らした表現に魅せられ、集中力を保ったまま楽しむことができた。バッハの奥深い世界を分かりやすく伝えるチェンバロである。そして、もう一人忘れてはならないのがマリア・ティーポによるピアノ版(1986年録音)。独特の重心を持つフレージングと凝り固まったところのない音色の美しさが印象的な彼女の演奏も愛聴盤である。
本来「ゴルトベルク変奏曲」は嗜好性が著しく異なる作品で、人によって好みが細かく分かれるのが普通なのではないかと思う。どんな歴史的名盤もそこまでアテにならず、自分に合う演奏を簡単に見つけることはできないのだ。私の場合、グールド、ケンプ、ランドフスカ、ロザリン・テューレック(1988年録音)の順に好きになったが、完璧に自分にフィットする音楽を見出したわけではなかった。私が初めて「ゴルトベルク変奏曲をのみこめた」と感じて、さわやかな感動を覚えたのは、エディト・ピヒト=アクセンフェルトのチェンバロ(1965年頃の録音)を聴いたときである。アリアの演奏中、やたら耳につく鳥のさえずりには苦笑させられたものだが、第1変奏から第30変奏まで意匠を凝らした表現に魅せられ、集中力を保ったまま楽しむことができた。バッハの奥深い世界を分かりやすく伝えるチェンバロである。そして、もう一人忘れてはならないのがマリア・ティーポによるピアノ版(1986年録音)。独特の重心を持つフレージングと凝り固まったところのない音色の美しさが印象的な彼女の演奏も愛聴盤である。
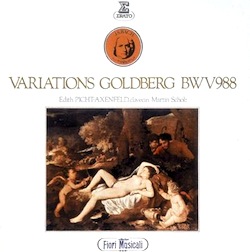
冒頭で32小節の美しいアリアが奏でられた後、その低音主題に基づく30の変奏曲が披露され、最後に再びアリアで締めくくられる。全32曲。ト長調が29曲、残り3曲はト短調である。30の異なる変奏は3曲ごとにカノンによって区切られ、一つの小さなまとまりを成している。バッハは数字に大きな意味を持たせた作曲家だが、ここでは3と32が支配しているようだ。
数字が支配しているといっても、そこに溢れる楽想は窮屈さとは無縁で、驚くほど大胆で斬新だ。創作アリアに基づく32の変奏曲「ラ・カプリツィオーザ」(これもト長調)を書いた先輩作曲家ブクステフーデからの影響も感じられるが、バッハの作品が革新的であることに変わりはない。快活な第1変奏だけでも意外性に富んでいるし、暗く幻想的な第25変奏にいたっては各曲との連関性のきわどさを見せつけるかのようで、そこまでやるかと言いたくなる。こういう作品を聴くにつけ、クラシック音楽が保守の歴史ではなく、革新の歴史であることを改めて痛感させられる。一つ一つの変奏を作曲している間のバッハの頭の中がどんな風だったのか、どの変奏から着手したのか、変奏の順番は何を意味しているのか、これは推理小説のテーマにもなり得る謎だ。約80年後に「ディアベリ変奏曲」を書くことになるベートーヴェンだったら、どのようにバッハの楽譜を読み解くだろう。
30の変奏曲がもたらすのは、汲めども尽きぬ魅力に満ちた音楽の冒険である。民謡を用いた最後の「クォドリベット」は、その到達感のあらわれだ。いかにも大団円という趣がある。伯爵の不眠症を癒すために書かれた(らしい)というエピソードに反論する気はないし、私自身、昔は第15変奏、第21変奏、第25変奏に配された短調の曲を聴くと必ず眠くなったものだが、一度作品全体を把握した者にとっては、何度通っても面白みのある道が続いている。
「ゴルトベルク変奏曲」を語る上で欠かせない演奏家は2人いる。ワンダ・ランドフスカとグレン・グールドだ。前者は言わずと知れたチェンバロ復興の立役者。1933年にこの作品を録音し、しばらくの間、決定盤とみなされていた。後者はこれまた超有名なカナダ出身のピアニストで、1956年に弱冠23歳で「ゴルトベルク変奏曲」を発表してデビュー(録音時は22歳)。そこでセンセーショナルな成功を収めたことが、今日の「ゴルトベルク変奏曲」の人気につながっていると言っても過言ではない。総じてテンポが速く、反復も無く、「ジャズのようだ」とも評されたこの演奏に違和感を覚えた人は多いようだが、これによって重々しいバッハ像が払拭されたことは間違いない。

「ピアノによるゴルトベルク」は、グールドが先駆者であるわけではなく、ランドフスカとグールドの録音の間にはクラウディオ・アラウの演奏が存在する。これは1942年に録音されたもののお蔵入りとなり、1988年になって発売された。また、1920年代には若き日のルドルフ・ゼルキンがアンコールで全曲弾いたというエピソードも残っている。とはいえ「グールド以後」にピアノで録音した人は、程度の差こそあれ、この天才をいやでも意識せざるを得なくなっている。常に比較されるのだから、そうなるのも仕方ない。結果的に、深い音楽性よりも理知や才気で武装した頭でっかちの演奏が多くなっている。
その点、1969年に録音されたヴィルムヘルム・ケンプの演奏は、年の功とでも言うべきか、グールドの影響を全く感じさせない。装飾音を最小限に削り、音楽自体がリラックスして流れているような開放的な雰囲気に覆われている。ほかのピアニストと同じ作品を弾いているとは思えない、と言うと大袈裟だが、そう言いたくなるほど独自に確立された世界の中で悠然とピアノを奏でている。

(阿部十三)
ヨハン・セバスチャン・バッハ
[1685.3.31-1750.7.28]
ゴルトベルク変奏曲 ト長調 BWV988
【お薦めの録音】(掲載ジャケット:上から)
エディト・ピヒト=アクセンフェルト(cemb)
録音:1965年頃
グレン・グールド(p)
録音:1981年4月〜5月
マリア・ティーポ(p)
録音:1986年
[1685.3.31-1750.7.28]
ゴルトベルク変奏曲 ト長調 BWV988
【お薦めの録音】(掲載ジャケット:上から)
エディト・ピヒト=アクセンフェルト(cemb)
録音:1965年頃
グレン・グールド(p)
録音:1981年4月〜5月
マリア・ティーポ(p)
録音:1986年
月別インデックス
- January 2026 [1]
- November 2025 [1]
- September 2025 [1]
- July 2025 [1]
- March 2025 [1]
- February 2025 [1]
- January 2025 [1]
- December 2024 [1]
- November 2024 [1]
- October 2024 [1]
- September 2024 [1]
- August 2024 [1]
- July 2024 [1]
- May 2024 [1]
- April 2024 [1]
- March 2024 [1]
- January 2024 [1]
- December 2023 [1]
- November 2023 [1]
- October 2023 [1]
- September 2023 [1]
- July 2023 [1]
- June 2023 [1]
- May 2023 [1]
- March 2023 [1]
- January 2023 [1]
- December 2022 [1]
- October 2022 [1]
- September 2022 [1]
- August 2022 [1]
- July 2022 [1]
- May 2022 [1]
- March 2022 [1]
- February 2022 [1]
- December 2021 [1]
- November 2021 [1]
- October 2021 [1]
- September 2021 [1]
- July 2021 [1]
- June 2021 [1]
- May 2021 [1]
- March 2021 [1]
- February 2021 [1]
- December 2020 [1]
- November 2020 [1]
- October 2020 [1]
- July 2020 [1]
- June 2020 [1]
- May 2020 [1]
- April 2020 [1]
- February 2020 [1]
- January 2020 [1]
- December 2019 [1]
- October 2019 [1]
- September 2019 [2]
- August 2019 [1]
- June 2019 [1]
- April 2019 [1]
- March 2019 [1]
- February 2019 [1]
- December 2018 [1]
- November 2018 [1]
- October 2018 [1]
- September 2018 [1]
- July 2018 [1]
- June 2018 [1]
- April 2018 [1]
- March 2018 [2]
- February 2018 [1]
- December 2017 [5]
- November 2017 [1]
- October 2017 [1]
- September 2017 [1]
- August 2017 [1]
- June 2017 [1]
- May 2017 [2]
- April 2017 [2]
- February 2017 [1]
- January 2017 [2]
- November 2016 [2]
- September 2016 [2]
- August 2016 [2]
- July 2016 [1]
- June 2016 [1]
- May 2016 [1]
- April 2016 [1]
- February 2016 [2]
- January 2016 [1]
- December 2015 [1]
- November 2015 [2]
- October 2015 [1]
- September 2015 [2]
- August 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- May 2015 [1]
- April 2015 [1]
- February 2015 [2]
- January 2015 [1]
- December 2014 [1]
- November 2014 [2]
- October 2014 [1]
- September 2014 [1]
- August 2014 [2]
- July 2014 [1]
- June 2014 [2]
- May 2014 [2]
- April 2014 [1]
- March 2014 [2]
- February 2014 [2]
- January 2014 [2]
- December 2013 [1]
- November 2013 [2]
- October 2013 [2]
- September 2013 [1]
- August 2013 [2]
- July 2013 [2]
- June 2013 [2]
- May 2013 [2]
- March 2013 [2]
- February 2013 [1]
- January 2013 [2]
- December 2012 [2]
- November 2012 [1]
- October 2012 [2]
- September 2012 [1]
- August 2012 [1]
- July 2012 [3]
- June 2012 [1]
- May 2012 [2]
- April 2012 [2]
- March 2012 [2]
- February 2012 [3]
- January 2012 [2]
- December 2011 [2]
- November 2011 [2]
- October 2011 [2]
- September 2011 [3]
- August 2011 [2]
- July 2011 [3]
- June 2011 [4]
- May 2011 [4]
- April 2011 [5]
- March 2011 [5]
- February 2011 [4]