
ヴィヴァルディ 協奏曲集『四季』
2017.04.02
短調の眠り
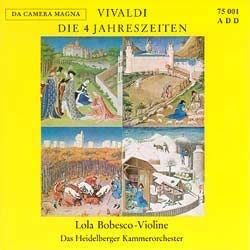 アントニオ・ヴィヴァルディの『四季』は、1725年に出版された『和声と創意への試み』の中に収録されている最初の4曲、「春」「夏」「秋」「冬」を指す。それぞれの曲は、作者不明のソネットをもとにした一種の「標題音楽」で、春の喜び、夏のけだるさと激しい嵐、秋の収穫の祝いと狩猟、冬の寒さと暖炉がある室内での安らぎなどが描写される。
アントニオ・ヴィヴァルディの『四季』は、1725年に出版された『和声と創意への試み』の中に収録されている最初の4曲、「春」「夏」「秋」「冬」を指す。それぞれの曲は、作者不明のソネットをもとにした一種の「標題音楽」で、春の喜び、夏のけだるさと激しい嵐、秋の収穫の祝いと狩猟、冬の寒さと暖炉がある室内での安らぎなどが描写される。
バロック期の標題音楽の多くが、解説を要するものであるのに対し、『四季』の場合は、ソネットや解説を読まなくても、「春」のこの部分では鳥たちが歌っているとか、嵐が起こっているとか、陽気に踊っている、ということが即座に伝わってくる。これは描写の対象を写実的に表現すると同時に、自然に対する人間の感情を重んじた表現をとり入れた成果である。
たとえば、「冬」の第2楽章で「炉端で静かに満ち足りた日々を送る。家の外では雨が降っている」という場面を描くにあたり、ヴィヴァルディは己の卓抜した描写力のみに頼るのではなく、寒さを避けている安心感や穏やかな感情の表現を盛り込むことによって、鮮明に「冬」を感じさせる音楽に仕上げている。しかも、協奏曲の形式を崩すことなく、絶対音楽として聴いても十分魅力的なものにした上で、そのバランスを(いとも簡単そうに)保っているのだ。これが『四季』の驚異である。このような作品が、ベートーヴェンがあえて「絵画的描写ではなく感情の表出」だと宣言した「田園」の約80年前に生まれていたことを忘れてはならない。
「春」はホ長調、「夏」はト短調、「秋」はヘ長調、「冬」はヘ短調。このうち、「春」「夏」「秋」の第2楽章は短調であり、「春」「秋」はそれぞれの平行調にあたる嬰ハ短調、ニ短調で書かれている。無数の蝿、雷鳴、癒えようのない体の疲れを表す「夏」の第2楽章はともかく、心地よくまどろんでいるはずの「春」と「秋」も短調なのは面白い。いずれも緩やかなラルゴ、アダージョだが、甘い夢を見ているようには思えない。これは、ヴィヴァルディが司祭である点を踏まえると、聖書の「眠りを愛してはならない」という言葉を思い出させるし、しょせん眠りは束の間の憩いにすぎないと言っているようでもある。
『四季』の中でも一、二を争う聴きどころである「夏」の第3楽章の嵐や「冬」の第1楽章の吹雪のように苛烈な音楽は、当時の聴き手にとって衝撃的だったのではないかと思われる。ヴィヴァルディは、形式から逸れることなく、季節を描くという名目で、より直截的かつ革新的な音楽表現を目論んでいたのかもしれない。
誰もが知る人気作品になったのは、第二次世界大戦後のこと。その嚆矢となったのは、カール・ミュンヒンガーが指揮し、ラインホルト・バルヒェットがソロを務めた1951年の録音、フェリックス・アーヨがソロを務めたイ・ムジチ合奏団による1955年の録音である。その後、ミュンヒンガーは1958年に、イ・ムジチは1959年にステレオ録音を行い、両者ともにヒットしたことで、『四季』の人気が定着した。
 今も変わらず愛聴されているのは、アーヨが弾いた1959年の録音。これは、誇張抜きで、ぞくぞくするほど美しい演奏だ。ヴァイオリンの音色はみずみずしく、アンサンブルは磨き抜かれていて、まるで古さを感じさせない。オリジナル楽器による演奏でショッキングなのは、ニコラウス・アーノンクールが指揮した1977年の録音。アーノンクールは表面的な美しさをえぐらんばかりに排除し、一つ一つのフレーズの意味を吟味した上で、楽器の音がもはや動物や虫の鳴き声にしか聞こえないような『四季』を体験させる。ここまでやってくれたらあっぱれと言うべきだろう。シモン・ゴールドベルクとオランダ室内管弦楽団による1973年録音は、絶対音楽的なアプローチで、楽器の純粋な響きと室内楽曲のように精緻なアンサンブルが味わえる。徹底して統制されたこの『四季』は、アーノンクールとは異なる意味で、聴き手を驚かせるはずだ。
今も変わらず愛聴されているのは、アーヨが弾いた1959年の録音。これは、誇張抜きで、ぞくぞくするほど美しい演奏だ。ヴァイオリンの音色はみずみずしく、アンサンブルは磨き抜かれていて、まるで古さを感じさせない。オリジナル楽器による演奏でショッキングなのは、ニコラウス・アーノンクールが指揮した1977年の録音。アーノンクールは表面的な美しさをえぐらんばかりに排除し、一つ一つのフレーズの意味を吟味した上で、楽器の音がもはや動物や虫の鳴き声にしか聞こえないような『四季』を体験させる。ここまでやってくれたらあっぱれと言うべきだろう。シモン・ゴールドベルクとオランダ室内管弦楽団による1973年録音は、絶対音楽的なアプローチで、楽器の純粋な響きと室内楽曲のように精緻なアンサンブルが味わえる。徹底して統制されたこの『四季』は、アーノンクールとは異なる意味で、聴き手を驚かせるはずだ。
弾丸が楽器をぶち抜いているジャケットが笑えるイル・ジャルディーノ・アルモニコの演奏(1993年録音)は、発売当時、過激と言われたもの。たしかに威勢が良いし、「なんでこんな楽器が登場するの」という突っ込みどころもあって新鮮ではある。ただ、演奏自体が上手いかというとそうとは言えず、ジャケットほどバイオレントでもない。それよりは、やや手垢のついてきた『四季』に新風を吹き込んだファビオ・ビオンディ/エウローパ・ガランテの演奏(1991年録音)の方が、五感を貫くような快感に満ちている。特に、鋭く爽快なスピード感と手の込んだアーティキュレーションでワクワクさせる「夏」の嵐は聴きものだ。もっとも、快速のフレーズに魅力が集中していて、全体的には満足できる出来ではない。
ローラ・ボベスコがソロを務めたハイデルベルク室内管の演奏(1967年録音)は素晴らしい。アーヨ以上に、と言ったら大げさかもしれないが、みずみずしい音色を持ち、何よりも艶やかな歌心にあふれていて、聴いていると心が満たされる。ただ美しいだけでなく、楽章によっては枯淡の味わい深い趣もある。ラルゴやアダージョの演奏も丁寧だし、ここぞというときの表現の濃厚さにも不足がない。これが入っていない名盤カタログの類は、私には何の意味もない、と言いたくなるほどの『四季』だ(CDも持っているが、レコードの方が音がいい)。21世紀以降では、植物園で演奏されたユリア・フィッシャーの映像版(2001年収録)が良い。ただし、鳥のさえずりなどが結構入っているため、神経質な人には向かない。
最後にもう一つ、シェドヴィルが編曲した『四季』は、「春」だけは楽しめる。やたらと鳴り響いているハーディ・ガーディにだんだん耳が飽きてきて、「ここまでしなくてもいいのに」と言いたくなるし、「春」以外の季節の編曲も全くピンとこないが、話のネタとして聴く価値はある。
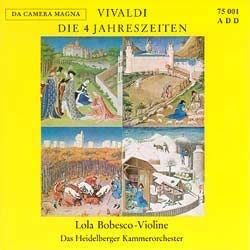
バロック期の標題音楽の多くが、解説を要するものであるのに対し、『四季』の場合は、ソネットや解説を読まなくても、「春」のこの部分では鳥たちが歌っているとか、嵐が起こっているとか、陽気に踊っている、ということが即座に伝わってくる。これは描写の対象を写実的に表現すると同時に、自然に対する人間の感情を重んじた表現をとり入れた成果である。
たとえば、「冬」の第2楽章で「炉端で静かに満ち足りた日々を送る。家の外では雨が降っている」という場面を描くにあたり、ヴィヴァルディは己の卓抜した描写力のみに頼るのではなく、寒さを避けている安心感や穏やかな感情の表現を盛り込むことによって、鮮明に「冬」を感じさせる音楽に仕上げている。しかも、協奏曲の形式を崩すことなく、絶対音楽として聴いても十分魅力的なものにした上で、そのバランスを(いとも簡単そうに)保っているのだ。これが『四季』の驚異である。このような作品が、ベートーヴェンがあえて「絵画的描写ではなく感情の表出」だと宣言した「田園」の約80年前に生まれていたことを忘れてはならない。
「春」はホ長調、「夏」はト短調、「秋」はヘ長調、「冬」はヘ短調。このうち、「春」「夏」「秋」の第2楽章は短調であり、「春」「秋」はそれぞれの平行調にあたる嬰ハ短調、ニ短調で書かれている。無数の蝿、雷鳴、癒えようのない体の疲れを表す「夏」の第2楽章はともかく、心地よくまどろんでいるはずの「春」と「秋」も短調なのは面白い。いずれも緩やかなラルゴ、アダージョだが、甘い夢を見ているようには思えない。これは、ヴィヴァルディが司祭である点を踏まえると、聖書の「眠りを愛してはならない」という言葉を思い出させるし、しょせん眠りは束の間の憩いにすぎないと言っているようでもある。
『四季』の中でも一、二を争う聴きどころである「夏」の第3楽章の嵐や「冬」の第1楽章の吹雪のように苛烈な音楽は、当時の聴き手にとって衝撃的だったのではないかと思われる。ヴィヴァルディは、形式から逸れることなく、季節を描くという名目で、より直截的かつ革新的な音楽表現を目論んでいたのかもしれない。
誰もが知る人気作品になったのは、第二次世界大戦後のこと。その嚆矢となったのは、カール・ミュンヒンガーが指揮し、ラインホルト・バルヒェットがソロを務めた1951年の録音、フェリックス・アーヨがソロを務めたイ・ムジチ合奏団による1955年の録音である。その後、ミュンヒンガーは1958年に、イ・ムジチは1959年にステレオ録音を行い、両者ともにヒットしたことで、『四季』の人気が定着した。

弾丸が楽器をぶち抜いているジャケットが笑えるイル・ジャルディーノ・アルモニコの演奏(1993年録音)は、発売当時、過激と言われたもの。たしかに威勢が良いし、「なんでこんな楽器が登場するの」という突っ込みどころもあって新鮮ではある。ただ、演奏自体が上手いかというとそうとは言えず、ジャケットほどバイオレントでもない。それよりは、やや手垢のついてきた『四季』に新風を吹き込んだファビオ・ビオンディ/エウローパ・ガランテの演奏(1991年録音)の方が、五感を貫くような快感に満ちている。特に、鋭く爽快なスピード感と手の込んだアーティキュレーションでワクワクさせる「夏」の嵐は聴きものだ。もっとも、快速のフレーズに魅力が集中していて、全体的には満足できる出来ではない。
ローラ・ボベスコがソロを務めたハイデルベルク室内管の演奏(1967年録音)は素晴らしい。アーヨ以上に、と言ったら大げさかもしれないが、みずみずしい音色を持ち、何よりも艶やかな歌心にあふれていて、聴いていると心が満たされる。ただ美しいだけでなく、楽章によっては枯淡の味わい深い趣もある。ラルゴやアダージョの演奏も丁寧だし、ここぞというときの表現の濃厚さにも不足がない。これが入っていない名盤カタログの類は、私には何の意味もない、と言いたくなるほどの『四季』だ(CDも持っているが、レコードの方が音がいい)。21世紀以降では、植物園で演奏されたユリア・フィッシャーの映像版(2001年収録)が良い。ただし、鳥のさえずりなどが結構入っているため、神経質な人には向かない。
最後にもう一つ、シェドヴィルが編曲した『四季』は、「春」だけは楽しめる。やたらと鳴り響いているハーディ・ガーディにだんだん耳が飽きてきて、「ここまでしなくてもいいのに」と言いたくなるし、「春」以外の季節の編曲も全くピンとこないが、話のネタとして聴く価値はある。
(阿部十三)
アントニオ・ヴィヴァルディ
[1678.3.4-1741.7.28]
協奏曲集『四季』 〜『和声と創意への試み』作品8から
【お薦めディスク】(掲載ジャケット:上から)
ローラ・ボベスコ(vn)
ハイデルベルク室内管弦楽団
録音:1967年8月
フェリックス・アーヨ(vn)
イ・ムジチ合奏団
録音:1959年
[1678.3.4-1741.7.28]
協奏曲集『四季』 〜『和声と創意への試み』作品8から
【お薦めディスク】(掲載ジャケット:上から)
ローラ・ボベスコ(vn)
ハイデルベルク室内管弦楽団
録音:1967年8月
フェリックス・アーヨ(vn)
イ・ムジチ合奏団
録音:1959年
月別インデックス
- January 2026 [1]
- November 2025 [1]
- September 2025 [1]
- July 2025 [1]
- March 2025 [1]
- February 2025 [1]
- January 2025 [1]
- December 2024 [1]
- November 2024 [1]
- October 2024 [1]
- September 2024 [1]
- August 2024 [1]
- July 2024 [1]
- May 2024 [1]
- April 2024 [1]
- March 2024 [1]
- January 2024 [1]
- December 2023 [1]
- November 2023 [1]
- October 2023 [1]
- September 2023 [1]
- July 2023 [1]
- June 2023 [1]
- May 2023 [1]
- March 2023 [1]
- January 2023 [1]
- December 2022 [1]
- October 2022 [1]
- September 2022 [1]
- August 2022 [1]
- July 2022 [1]
- May 2022 [1]
- March 2022 [1]
- February 2022 [1]
- December 2021 [1]
- November 2021 [1]
- October 2021 [1]
- September 2021 [1]
- July 2021 [1]
- June 2021 [1]
- May 2021 [1]
- March 2021 [1]
- February 2021 [1]
- December 2020 [1]
- November 2020 [1]
- October 2020 [1]
- July 2020 [1]
- June 2020 [1]
- May 2020 [1]
- April 2020 [1]
- February 2020 [1]
- January 2020 [1]
- December 2019 [1]
- October 2019 [1]
- September 2019 [2]
- August 2019 [1]
- June 2019 [1]
- April 2019 [1]
- March 2019 [1]
- February 2019 [1]
- December 2018 [1]
- November 2018 [1]
- October 2018 [1]
- September 2018 [1]
- July 2018 [1]
- June 2018 [1]
- April 2018 [1]
- March 2018 [2]
- February 2018 [1]
- December 2017 [5]
- November 2017 [1]
- October 2017 [1]
- September 2017 [1]
- August 2017 [1]
- June 2017 [1]
- May 2017 [2]
- April 2017 [2]
- February 2017 [1]
- January 2017 [2]
- November 2016 [2]
- September 2016 [2]
- August 2016 [2]
- July 2016 [1]
- June 2016 [1]
- May 2016 [1]
- April 2016 [1]
- February 2016 [2]
- January 2016 [1]
- December 2015 [1]
- November 2015 [2]
- October 2015 [1]
- September 2015 [2]
- August 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- May 2015 [1]
- April 2015 [1]
- February 2015 [2]
- January 2015 [1]
- December 2014 [1]
- November 2014 [2]
- October 2014 [1]
- September 2014 [1]
- August 2014 [2]
- July 2014 [1]
- June 2014 [2]
- May 2014 [2]
- April 2014 [1]
- March 2014 [2]
- February 2014 [2]
- January 2014 [2]
- December 2013 [1]
- November 2013 [2]
- October 2013 [2]
- September 2013 [1]
- August 2013 [2]
- July 2013 [2]
- June 2013 [2]
- May 2013 [2]
- March 2013 [2]
- February 2013 [1]
- January 2013 [2]
- December 2012 [2]
- November 2012 [1]
- October 2012 [2]
- September 2012 [1]
- August 2012 [1]
- July 2012 [3]
- June 2012 [1]
- May 2012 [2]
- April 2012 [2]
- March 2012 [2]
- February 2012 [3]
- January 2012 [2]
- December 2011 [2]
- November 2011 [2]
- October 2011 [2]
- September 2011 [3]
- August 2011 [2]
- July 2011 [3]
- June 2011 [4]
- May 2011 [4]
- April 2011 [5]
- March 2011 [5]
- February 2011 [4]