
リチャード・ウィドマーク 〜悪役出世譚〜
2019.08.26
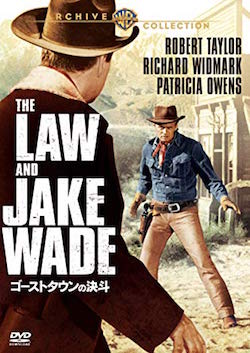
魅力的な悪役は時に主役を食うものだが、ウィドマークはデビュー作『死の接吻』(1947年)のトミー役で、すでに主役のヴィクター・マチュアを完全に食っていた。ラスト近く、殺し屋トミーが自分のことを密告したビアンコ(ヴィクター・マチュア)をカーテンの隙間から睨みつける時の鋭い眼光は、思い出すだけでゾッとする。この作品でアカデミー助演男優賞賞にノミネートされたウィドマークは、その後、『廃墟の群盗』(1948年)でもグレゴリー・ペックを押しのける存在感を示し、さらに評価を高めた。
もともとは法律家を目指していた人で、レイク・フォレスト大学で演劇に熱中し、卒業後は同大学の弁論、演劇の講師を務めていた。知性に富み、家庭を大事にする人だった。俳優の中には、自分自身とは真逆の役の方が演じやすいと言う人が少なからずいるが、ウィドマークはまさにそのタイプだったのではないかと思われる。
性格俳優らしい演技力を見せつけたのは、ジュールス・ダッシン監督の『街の野獣』(1950年)。ウィドマークが演じたハリーは極悪人ではないが、運も才能もないのに大きな夢ばかり見ているアウトロー的な山師だ。持ち前の敏捷さと強引な手口でプロレス興行に首を突っ込んだ彼は、様々なトラブルを招き、自滅してゆく。興行を仕切る一味に追い詰められたハリーの動揺ぶり、汗ばんだ顔が忘れられない。ウィドマークは完璧なハマり役で、どうしようもないけど人間味があり、憎めない男をしっかりと造型し、屈折したところ、ナイーブなところを感じさせる。暗くて後味の悪い映画だが、サスペンスとして面白いし、特に理性を失ったレスラーたちの格闘の場面(ここでハリーの運命が決まる)はスリリングだ。
『ワーロック』(1959年)では、それまで善玉が多かったヘンリー・フォンダと悪玉が多かったウィドマークのパートが入れ替わる。この辺りがターニングポイントだろう。以後、ウィドマークは物語の目線から見て「カウンター」的な立場でなく、『アラモ』(1960年)の英雄ジム・ボウイ、『ニュールンベルグ裁判』(1961年)の検察官タッド・ローソン、『長い船団』(1964年)のロルフ、『シャイアン』(1964年)のアーチャー大尉といった役を務め、重厚な演技を見せるようになる。
『駆逐艦ベッドフォード作戦』(1965年)のエリック艦長役は、ウィドマークのために書かれたのではないかと思えるほど適役だ。好戦的で、常にイライラしていて、威圧感があり、パワハラで部下を精神的に追い込む役どころで、本領発揮している。ドン・シーゲル監督の『刑事マディガン』(1968年)のマディガンは掟破りのスゴ腕刑事という設定だが、開始早々拳銃を奪われ、良いところがない。上司からの理解もなく、夫婦関係も微妙で、刑事という仕事の悲哀が色濃く出ている。同年公開されたフランク・シナトラ主演の『刑事』とあわせて観ておきたい。ちなみに、マディガンはテレビシリーズにもなり、テレビ嫌いだったウィドマークが主役を演じている。
1970年代には貫禄も出てきて、『大統領のスキャンダル』(1971年)の大統領役、『合衆国最後の日』(1977年)の将軍役を好演。役者として大物になっただけでなく、大物を演じる役者になったのである。往年のファンは「あのハイエナが大統領に......」と感慨深かったことだろう。ただ一方では、『オリエント急行殺人事件』(1974年)で殺害される実業家役(どんな役かは周知の通り)も演じており、演じ分けは自由自在、文字通りどんな役でも演じられる名優になった感がある。
悪役出世譚として、ウィドマークほどの成功例は稀である。英国のジェームズ・メイスン、米国のウィドマークといったところか。むろん、その成功はウィドマーク自身の魅力と実力あってこそのものだが、単なる二枚目ヒーローが飽きられつつあった風潮も追い風になったと思う。戦後のヒーローは、見せかけでない生々しい怒りや憎しみ、人間味と冷酷さの表裏一体感、反抗心の内側にあるナイーブな心理、夢を叶えられない挫折感や屈折感も表現することが出来なければならなかった。ウィドマークがその先陣を切り、多くの若者の共感を得たことは想像に難くない。
(阿部十三)
【関連サイト】
Richard Widmark
[リチャード・ウィドマーク略歴]
1914年12月26日、アメリカ・ミネソタ州生まれ。法律家を目指していたが、レイク・フォレスト大学在学中に演劇に夢中になり、1938年にニューヨークへ。ラジオ、舞台の仕事を経て、ダリル・F・ザナックに気に入られて、『死の接吻』(1947年)の殺し屋役でデビュー。アカデミー助演男優賞にノミネートされた。以後、主役クラスの悪役、アウトロー役として高い評価を受けていたが、1950年代から徐々に善玉も演じるようになり、演技の幅を広げた。最後の映画出演は『トゥルー・カラーズ』(1991年)。私生活では、脚本家のジーン・ヘイズルウッドと1942年に結婚し、1997年に死別。1999年にヘンリー・フォンダの元夫人と再婚した。2008年3月24日、93歳で死去。
1914年12月26日、アメリカ・ミネソタ州生まれ。法律家を目指していたが、レイク・フォレスト大学在学中に演劇に夢中になり、1938年にニューヨークへ。ラジオ、舞台の仕事を経て、ダリル・F・ザナックに気に入られて、『死の接吻』(1947年)の殺し屋役でデビュー。アカデミー助演男優賞にノミネートされた。以後、主役クラスの悪役、アウトロー役として高い評価を受けていたが、1950年代から徐々に善玉も演じるようになり、演技の幅を広げた。最後の映画出演は『トゥルー・カラーズ』(1991年)。私生活では、脚本家のジーン・ヘイズルウッドと1942年に結婚し、1997年に死別。1999年にヘンリー・フォンダの元夫人と再婚した。2008年3月24日、93歳で死去。
月別インデックス
- October 2025 [1]
- March 2025 [1]
- January 2024 [1]
- September 2023 [1]
- May 2023 [1]
- September 2022 [1]
- July 2022 [1]
- April 2022 [1]
- January 2022 [1]
- October 2021 [1]
- August 2021 [1]
- June 2021 [1]
- February 2021 [1]
- January 2021 [1]
- December 2020 [1]
- November 2020 [1]
- July 2020 [1]
- March 2020 [1]
- December 2019 [1]
- November 2019 [1]
- October 2019 [1]
- August 2019 [1]
- May 2019 [1]
- April 2019 [1]
- February 2019 [1]
- December 2018 [2]
- October 2018 [1]
- September 2018 [3]
- August 2018 [3]
- April 2018 [2]
- January 2018 [2]
- November 2017 [1]
- August 2017 [2]
- April 2017 [1]
- February 2017 [1]
- December 2016 [1]
- October 2016 [1]
- July 2016 [1]
- May 2016 [1]
- April 2016 [1]
- January 2016 [1]
- December 2015 [1]
- October 2015 [1]
- July 2015 [1]
- May 2015 [1]
- March 2015 [1]
- December 2014 [1]
- November 2014 [1]
- October 2014 [1]
- September 2014 [1]
- August 2014 [1]
- June 2014 [2]
- April 2014 [2]
- February 2014 [2]
- November 2013 [2]
- October 2013 [2]
- August 2013 [2]
- May 2013 [1]
- April 2013 [1]
- March 2013 [1]
- February 2013 [1]
- January 2013 [1]
- November 2012 [2]
- September 2012 [3]
- August 2012 [1]
- July 2012 [1]
- June 2012 [1]
- May 2012 [4]
- April 2012 [1]
- March 2012 [3]
- February 2012 [1]
- January 2012 [3]
- December 2011 [2]
- November 2011 [2]
- October 2011 [2]
- September 2011 [1]
- August 2011 [2]
- July 2011 [3]
- June 2011 [2]
- May 2011 [3]
- April 2011 [3]
- March 2011 [3]
- February 2011 [3]