
ベートーヴェン 三重協奏曲
2025.11.29
威風凛然
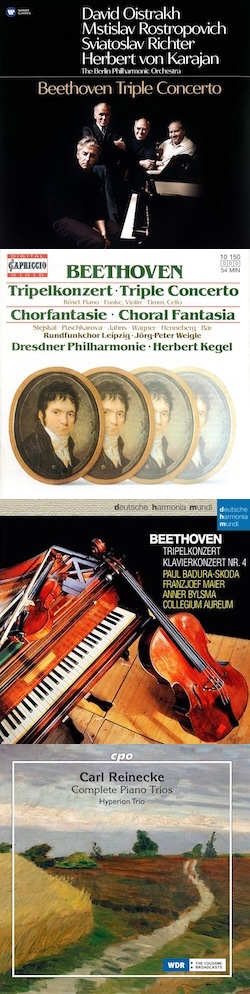 ベートーヴェンのピアノ、ヴァイオリン、チェロのための協奏曲は1803年から1804年にかけて作曲された。通称、三重協奏曲(トリプル・コンチェルト)。初演は1808年5月、ウィーンの演奏会で行われた。ウィーン初演以前にライプツィヒで行われていたとする説、パトロンだったルドルフ大公の邸宅で非公式に披露されたとする説もある。作曲を終えてから初演までに時間がかかった理由は定かでない。
ベートーヴェンのピアノ、ヴァイオリン、チェロのための協奏曲は1803年から1804年にかけて作曲された。通称、三重協奏曲(トリプル・コンチェルト)。初演は1808年5月、ウィーンの演奏会で行われた。ウィーン初演以前にライプツィヒで行われていたとする説、パトロンだったルドルフ大公の邸宅で非公式に披露されたとする説もある。作曲を終えてから初演までに時間がかかった理由は定かでない。
複数の楽器が独奏を担う協奏曲はすでにあり、シュターミツ、ハイドン、モーツァルトらによって協奏交響曲(サンフォニー・コンセルタンテ)という形式で世に送られていた。それ以前にも、バロック期に合奏協奏曲(コンチェルト・グロッソ)という形式で多くの作品が書かれている。ただ、ベートーヴェンの三重協奏曲はそれらと趣が異なる。協奏交響曲等にみられる融和性は影をひそめ、独奏パートの活躍度がより高くなり、それぞれ独立して動き、主役級の存在感を発揮しているのだ。個性の強いピアノ・トリオにオーケストラを組み合わせたような新味がある。
同時代には存在しなかった異形の傑作だが、ベートーヴェンの作品の中では特に人気があるわけではない。そもそもオーケストラのほかに3人のソリスト(もしくはピアノ・トリオ)を用意しなければいけない事情もあり、演奏される機会が少ない。楽想の展開に乏しく繰り返しが多いとか、構想自体は意欲的だが音楽表現として物足りないといった批判的な声もある。しかし虚心坦懐に耳を傾ければ、創造意欲に溢れた魅力的な作品であることがわかるはずだ。これは高邁なる大志の音楽。スケールが大きく、ロマンティックで、威風凛然として、冒険に出る前のような高揚感に満ちている。聴いていると、ポジティブな気持ちになる。
第1楽章はアレグロ。ハ長調の美しい第1主題が低音で響き、徐々に盛り上がり、華々しく強奏される。その後静かになり、優美な第2主題が登場。2つの主題から派生した経過句を経て、まず独奏チェロが第1主題を奏でる。次いで独奏ヴァイオリン、独奏ピアノの順に現れ、第114小節で2つの主題から派生したロマンティックな旋律がトゥッティで堂々と響きわたる。展開部はチェロによる第1主題で始まり、この主題を軸に進んでいく。ピアノ・トリオ風の掛け合いの間に、第114小節の旋律が挟まれる。やがて愁いのある旋律がチェロ、ヴァイオリンに現れた後、再現部に。提示部冒頭を繰り返した後、3つの独奏楽器の掛け合いが始まり、第114小節の旋律が登場。緩急強弱の変化に富み、最後はピウ・アレグロで勇壮に締め括られる。
第2楽章はラルゴ。弦楽合奏による短い前奏の後、独奏チェロがのびやかで抒情的な主題を奏で、第20小節まで独壇場が続く。ここはチェロ協奏曲のような趣がある。その後、木管が前奏部分を、チェロとヴァイオリンが主題を奏で、それをピアノの分散和音が支える。チェロとヴァイオリンによる睦まじいやりとりが終わると、木管が前奏部分を再現し、3つの楽器が弱音で幻想的な雰囲気を作り出す。そこからアタッカで第3楽章へと進む。
第3楽章はロンド・アラ・ポラッカ。まず独奏チェロがロンド主題を提示、ヴァイオリンがそれを引き継ぎ、ピアノとオーケストラも加わり、全奏でロンド主題が鳴り響く。その後、第76小節でチェロが跳ねるような第2主題を奏で、情熱的な走句に入る。これが繰り返され、冒頭のロンド主題に回帰。やがてリズミカルな第3主題が現れ、3つの楽器によって奏でられる。第203小節からの美しい経過句の余韻も冷めやらぬうちに、ロンド主題が再現され、美しい経過句も再現される。その後、ロンド主題の動機を用いて独奏ヴァイオリンがアレグロで駆け始め、チェロとピアノが加わり、さらにオーケストラ全体で盛り上げる。そこから再び元のテンポに戻り、独奏楽器とオーケストラが掛け合う形でロンド主題を響かせ、華々しく締め括られる。
最初に主題を提示するのは、ほとんど場合、独奏チェロである。演奏技術の面でも、ピアノが平易であるのと比べて、独奏チェロのパートは極めて難しい。ベートーヴェンがこの作品で独奏チェロに大きな役割を持たせようとしていたことは間違いない。もっとも、演奏効果の面ではピアノが目立っており、チェロの働きはあまり報われていない。第3楽章の第104小節や第297小節など独奏チェロの音が浮いているように感じられるところもある。
オイストラフ・トリオ(ダヴィッド・オイストラフ、スヴャトスラフ・クヌシェヴィツキー、レフ・オボーリン)、マルコム・サージェント、フィルハーモニア管の演奏(1958年録音)は穏健で、押し出しが強くない。指揮者は3人のソリストを尊重し、3人の掛け合いも調和的で、対話しているような感じがある。第3楽章はソリストとオーケストラが所々で微妙に合っていないが、第104小節や第297小節でのチェロの音を抑えているところは好ましい。音質はあまり良くない。
クリスティアン・フンケ(vn)、ユルンヤコプ・ティム(vc)、ペーター・レーゼル(p)、ヘルベルト・ケーゲル、ドレスデン・フィル(1986年録音)は名演。冒頭のリズムの刻み方から生き生きしている。オーケストラの響きは淡麗で、無駄な華美さがなく、凡手ならざる3人のソリストからも誠実な歌心が感じられる。全体のアンサンブルが引き締まっていて、ソリストとオーケストラとの掛け合いに隙がなく、指揮者の目が細部にまで光っていることがわかる。
ウルフ・ヘルシャー(vn)、ハインリヒ・シフ(vc)、クリスティアン・ツァハリアス(p)、クルト・マズア、ゲヴァントハウス管の演奏(1984年録音)は、シフの独奏チェロに熱がこもっていて、耳をひく。ツァハリアスやヘルシャーの演奏もみずみずしいが、オケの音が空疎である。フランツヨーゼフ・マイアー(vn)、アンナー・ビルスマ(vc)、パウル・バドゥラ=スコダ(fp)、コレギウム・アウレウムの演奏(1974年録音)は、3つの独奏楽器のせめぎ合いが凄まじく、白熱している。低音部のアクセントも苛烈なほど力強い。
他にもフェレンツ・フリッチャイ盤(1960年録音)、ユージン・オーマンディ盤(1964年録音)、エリアフ・インバル盤(1970年録音)、カラヤンの再録盤(1979年録音)があり、それぞれ豪華なソリストを揃えている。この中ではオーマンディ盤が一番良い。古いところでは、アルトゥーロ・トスカニーニ(1933年録音)やフェリックス・ワインガルトナー(1937年録音)、ブルーノ・ワルター(1949年録音)が指揮したものもある。比較的新しいところでは、デイヴィッド・ジンマン盤(2004年録音)、ネーメ・ヤルヴィ盤(2007年録音)が良い。ヴィルジングやライネッケが編曲したピアノ・トリオ版の録音もある。
【関連サイト】
Triple Concerto for Violin, Cello and Piano in C Major Op.56
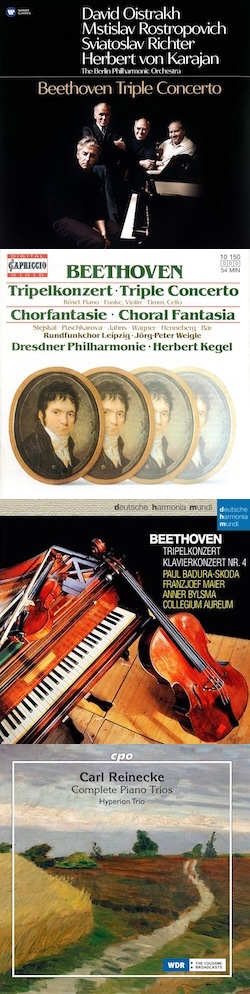
複数の楽器が独奏を担う協奏曲はすでにあり、シュターミツ、ハイドン、モーツァルトらによって協奏交響曲(サンフォニー・コンセルタンテ)という形式で世に送られていた。それ以前にも、バロック期に合奏協奏曲(コンチェルト・グロッソ)という形式で多くの作品が書かれている。ただ、ベートーヴェンの三重協奏曲はそれらと趣が異なる。協奏交響曲等にみられる融和性は影をひそめ、独奏パートの活躍度がより高くなり、それぞれ独立して動き、主役級の存在感を発揮しているのだ。個性の強いピアノ・トリオにオーケストラを組み合わせたような新味がある。
同時代には存在しなかった異形の傑作だが、ベートーヴェンの作品の中では特に人気があるわけではない。そもそもオーケストラのほかに3人のソリスト(もしくはピアノ・トリオ)を用意しなければいけない事情もあり、演奏される機会が少ない。楽想の展開に乏しく繰り返しが多いとか、構想自体は意欲的だが音楽表現として物足りないといった批判的な声もある。しかし虚心坦懐に耳を傾ければ、創造意欲に溢れた魅力的な作品であることがわかるはずだ。これは高邁なる大志の音楽。スケールが大きく、ロマンティックで、威風凛然として、冒険に出る前のような高揚感に満ちている。聴いていると、ポジティブな気持ちになる。
第1楽章はアレグロ。ハ長調の美しい第1主題が低音で響き、徐々に盛り上がり、華々しく強奏される。その後静かになり、優美な第2主題が登場。2つの主題から派生した経過句を経て、まず独奏チェロが第1主題を奏でる。次いで独奏ヴァイオリン、独奏ピアノの順に現れ、第114小節で2つの主題から派生したロマンティックな旋律がトゥッティで堂々と響きわたる。展開部はチェロによる第1主題で始まり、この主題を軸に進んでいく。ピアノ・トリオ風の掛け合いの間に、第114小節の旋律が挟まれる。やがて愁いのある旋律がチェロ、ヴァイオリンに現れた後、再現部に。提示部冒頭を繰り返した後、3つの独奏楽器の掛け合いが始まり、第114小節の旋律が登場。緩急強弱の変化に富み、最後はピウ・アレグロで勇壮に締め括られる。
第2楽章はラルゴ。弦楽合奏による短い前奏の後、独奏チェロがのびやかで抒情的な主題を奏で、第20小節まで独壇場が続く。ここはチェロ協奏曲のような趣がある。その後、木管が前奏部分を、チェロとヴァイオリンが主題を奏で、それをピアノの分散和音が支える。チェロとヴァイオリンによる睦まじいやりとりが終わると、木管が前奏部分を再現し、3つの楽器が弱音で幻想的な雰囲気を作り出す。そこからアタッカで第3楽章へと進む。
第3楽章はロンド・アラ・ポラッカ。まず独奏チェロがロンド主題を提示、ヴァイオリンがそれを引き継ぎ、ピアノとオーケストラも加わり、全奏でロンド主題が鳴り響く。その後、第76小節でチェロが跳ねるような第2主題を奏で、情熱的な走句に入る。これが繰り返され、冒頭のロンド主題に回帰。やがてリズミカルな第3主題が現れ、3つの楽器によって奏でられる。第203小節からの美しい経過句の余韻も冷めやらぬうちに、ロンド主題が再現され、美しい経過句も再現される。その後、ロンド主題の動機を用いて独奏ヴァイオリンがアレグロで駆け始め、チェロとピアノが加わり、さらにオーケストラ全体で盛り上げる。そこから再び元のテンポに戻り、独奏楽器とオーケストラが掛け合う形でロンド主題を響かせ、華々しく締め括られる。
最初に主題を提示するのは、ほとんど場合、独奏チェロである。演奏技術の面でも、ピアノが平易であるのと比べて、独奏チェロのパートは極めて難しい。ベートーヴェンがこの作品で独奏チェロに大きな役割を持たせようとしていたことは間違いない。もっとも、演奏効果の面ではピアノが目立っており、チェロの働きはあまり報われていない。第3楽章の第104小節や第297小節など独奏チェロの音が浮いているように感じられるところもある。
ただ、それも瑣末に思えるほど、音楽作品として素晴らしい。名旋律の宝庫である。特に、第1楽章の第114小節の旋律は、スケール感があり、明るく、いかにもヒロイックで雄々しい。後年書かれたリストのピアノ協奏曲第2番の主題に通じるものがある。それ以外にも、第1楽章の愁いのある旋律や第3楽章の抒情的な旋律など、主題以外にも美しい音楽がちりばめられている。「三重協奏曲」という構想に注意を奪われがちだが、まずはただ音楽の流れに身を委ね、旋律や展開を楽しみたい。
最もポピュラーな録音は、ダヴィド・オイストラフ(vn)、ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(vc)、スヴャトスラフ・リヒテル(p)とヘルベルト・フォン・カラヤン率いるベルリン・フィルによる演奏(1969年録音)である。レコーディングはスムーズに進まなかったようだが、結果的にはスケール感と高揚感のある音楽に仕上がっている。カラヤンらしくメリハリの付け方もうまい。第1楽章の第114小節の旋律なども豪壮かつロマンティックに鳴り響いている。
オイストラフ・トリオ(ダヴィッド・オイストラフ、スヴャトスラフ・クヌシェヴィツキー、レフ・オボーリン)、マルコム・サージェント、フィルハーモニア管の演奏(1958年録音)は穏健で、押し出しが強くない。指揮者は3人のソリストを尊重し、3人の掛け合いも調和的で、対話しているような感じがある。第3楽章はソリストとオーケストラが所々で微妙に合っていないが、第104小節や第297小節でのチェロの音を抑えているところは好ましい。音質はあまり良くない。
クリスティアン・フンケ(vn)、ユルンヤコプ・ティム(vc)、ペーター・レーゼル(p)、ヘルベルト・ケーゲル、ドレスデン・フィル(1986年録音)は名演。冒頭のリズムの刻み方から生き生きしている。オーケストラの響きは淡麗で、無駄な華美さがなく、凡手ならざる3人のソリストからも誠実な歌心が感じられる。全体のアンサンブルが引き締まっていて、ソリストとオーケストラとの掛け合いに隙がなく、指揮者の目が細部にまで光っていることがわかる。
ウルフ・ヘルシャー(vn)、ハインリヒ・シフ(vc)、クリスティアン・ツァハリアス(p)、クルト・マズア、ゲヴァントハウス管の演奏(1984年録音)は、シフの独奏チェロに熱がこもっていて、耳をひく。ツァハリアスやヘルシャーの演奏もみずみずしいが、オケの音が空疎である。フランツヨーゼフ・マイアー(vn)、アンナー・ビルスマ(vc)、パウル・バドゥラ=スコダ(fp)、コレギウム・アウレウムの演奏(1974年録音)は、3つの独奏楽器のせめぎ合いが凄まじく、白熱している。低音部のアクセントも苛烈なほど力強い。
他にもフェレンツ・フリッチャイ盤(1960年録音)、ユージン・オーマンディ盤(1964年録音)、エリアフ・インバル盤(1970年録音)、カラヤンの再録盤(1979年録音)があり、それぞれ豪華なソリストを揃えている。この中ではオーマンディ盤が一番良い。古いところでは、アルトゥーロ・トスカニーニ(1933年録音)やフェリックス・ワインガルトナー(1937年録音)、ブルーノ・ワルター(1949年録音)が指揮したものもある。比較的新しいところでは、デイヴィッド・ジンマン盤(2004年録音)、ネーメ・ヤルヴィ盤(2007年録音)が良い。ヴィルジングやライネッケが編曲したピアノ・トリオ版の録音もある。
(阿部十三)
【関連サイト】
Triple Concerto for Violin, Cello and Piano in C Major Op.56
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
[1770.12.16頃-1827.3.26]
ピアノ、ヴァイオリン、チェロのための協奏曲(三重協奏曲) ハ長調 作品56
【お薦めの録音】(掲載ジャケット:上から)
ダヴィド・オイストラフ(vn)、ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(vc)、スヴャトスラフ・リヒテル(p)
ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
録音:1969年
クリスティアン・フンケ(vn)、ユルンヤコプ・ティム(vc)、ペーター・レーゼル(p)
ヘルベルト・ケーゲル指揮
ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団
録音:1986年
フランツヨーゼフ・マイアー(vn)、アンナー・ビルスマ(vc)、パウル・バドゥラ=スコダ(fp)
コレギウム・アウレウム
録音:1974年
ハイペリオン・トリオ
録音:2019年
※カール・ライネッケ編曲のピアノ・トリオ版
[1770.12.16頃-1827.3.26]
ピアノ、ヴァイオリン、チェロのための協奏曲(三重協奏曲) ハ長調 作品56
【お薦めの録音】(掲載ジャケット:上から)
ダヴィド・オイストラフ(vn)、ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(vc)、スヴャトスラフ・リヒテル(p)
ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
録音:1969年
クリスティアン・フンケ(vn)、ユルンヤコプ・ティム(vc)、ペーター・レーゼル(p)
ヘルベルト・ケーゲル指揮
ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団
録音:1986年
フランツヨーゼフ・マイアー(vn)、アンナー・ビルスマ(vc)、パウル・バドゥラ=スコダ(fp)
コレギウム・アウレウム
録音:1974年
ハイペリオン・トリオ
録音:2019年
※カール・ライネッケ編曲のピアノ・トリオ版
月別インデックス
- January 2026 [1]
- November 2025 [1]
- September 2025 [1]
- July 2025 [1]
- March 2025 [1]
- February 2025 [1]
- January 2025 [1]
- December 2024 [1]
- November 2024 [1]
- October 2024 [1]
- September 2024 [1]
- August 2024 [1]
- July 2024 [1]
- May 2024 [1]
- April 2024 [1]
- March 2024 [1]
- January 2024 [1]
- December 2023 [1]
- November 2023 [1]
- October 2023 [1]
- September 2023 [1]
- July 2023 [1]
- June 2023 [1]
- May 2023 [1]
- March 2023 [1]
- January 2023 [1]
- December 2022 [1]
- October 2022 [1]
- September 2022 [1]
- August 2022 [1]
- July 2022 [1]
- May 2022 [1]
- March 2022 [1]
- February 2022 [1]
- December 2021 [1]
- November 2021 [1]
- October 2021 [1]
- September 2021 [1]
- July 2021 [1]
- June 2021 [1]
- May 2021 [1]
- March 2021 [1]
- February 2021 [1]
- December 2020 [1]
- November 2020 [1]
- October 2020 [1]
- July 2020 [1]
- June 2020 [1]
- May 2020 [1]
- April 2020 [1]
- February 2020 [1]
- January 2020 [1]
- December 2019 [1]
- October 2019 [1]
- September 2019 [2]
- August 2019 [1]
- June 2019 [1]
- April 2019 [1]
- March 2019 [1]
- February 2019 [1]
- December 2018 [1]
- November 2018 [1]
- October 2018 [1]
- September 2018 [1]
- July 2018 [1]
- June 2018 [1]
- April 2018 [1]
- March 2018 [2]
- February 2018 [1]
- December 2017 [5]
- November 2017 [1]
- October 2017 [1]
- September 2017 [1]
- August 2017 [1]
- June 2017 [1]
- May 2017 [2]
- April 2017 [2]
- February 2017 [1]
- January 2017 [2]
- November 2016 [2]
- September 2016 [2]
- August 2016 [2]
- July 2016 [1]
- June 2016 [1]
- May 2016 [1]
- April 2016 [1]
- February 2016 [2]
- January 2016 [1]
- December 2015 [1]
- November 2015 [2]
- October 2015 [1]
- September 2015 [2]
- August 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- May 2015 [1]
- April 2015 [1]
- February 2015 [2]
- January 2015 [1]
- December 2014 [1]
- November 2014 [2]
- October 2014 [1]
- September 2014 [1]
- August 2014 [2]
- July 2014 [1]
- June 2014 [2]
- May 2014 [2]
- April 2014 [1]
- March 2014 [2]
- February 2014 [2]
- January 2014 [2]
- December 2013 [1]
- November 2013 [2]
- October 2013 [2]
- September 2013 [1]
- August 2013 [2]
- July 2013 [2]
- June 2013 [2]
- May 2013 [2]
- March 2013 [2]
- February 2013 [1]
- January 2013 [2]
- December 2012 [2]
- November 2012 [1]
- October 2012 [2]
- September 2012 [1]
- August 2012 [1]
- July 2012 [3]
- June 2012 [1]
- May 2012 [2]
- April 2012 [2]
- March 2012 [2]
- February 2012 [3]
- January 2012 [2]
- December 2011 [2]
- November 2011 [2]
- October 2011 [2]
- September 2011 [3]
- August 2011 [2]
- July 2011 [3]
- June 2011 [4]
- May 2011 [4]
- April 2011 [5]
- March 2011 [5]
- February 2011 [4]