
ブルックナー 交響曲第7番
2012.06.11
60歳の出世作
 ブルックナーがワーグナーを信奉していたことはよく知られている。交響曲を献呈し、バイロイト音楽祭にも足を運んだ。ワーグナー協会の名誉会員にもなった。当然、音楽的にも大きな影響を受けた。ただ、そのおかげで、ある評論家から執拗に攻撃されることになる。それが、アンチ・ワーグナーとして知られたエドゥアルト・ハンスリックだ。ブラームス派だったハンスリックは、「ワーグナー派の最新の偶像」であるブルックナーの交響曲を批判し続け、一流の作曲家と認めようとしなかった。あげくの果てに、ブルックナーの交響曲をこのように評した。
ブルックナーがワーグナーを信奉していたことはよく知られている。交響曲を献呈し、バイロイト音楽祭にも足を運んだ。ワーグナー協会の名誉会員にもなった。当然、音楽的にも大きな影響を受けた。ただ、そのおかげで、ある評論家から執拗に攻撃されることになる。それが、アンチ・ワーグナーとして知られたエドゥアルト・ハンスリックだ。ブラームス派だったハンスリックは、「ワーグナー派の最新の偶像」であるブルックナーの交響曲を批判し続け、一流の作曲家と認めようとしなかった。あげくの果てに、ブルックナーの交響曲をこのように評した。
「ひと言でいえば、ワーグナーの劇的様式を交響曲に移しかえたものである」
これは交響曲第8番に向けられた批評だが、以後、ブルックナーのシンフォニーを「ワーグナーの楽劇の交響曲版」と解する人が増えてしまった。『ヘンゼルとグレーテル』の作曲家、フンパーディンクは、そういう見方に対してはっきりと疑問を呈している。
「私たちにとって不可解なのは、人々がアントン・ブルックナーについて、ワーグナーの芸術原理を交響曲に移しかえたと語っていることである。実際は、ワーグナー・チューバと大胆な和声進行の使用は外面的なものにすぎないし、ワーグナーの芸術とはなんら関わるものではない」
ブルックナーに最も近い作曲家とは誰か。それはワーグナーではなく、シューベルトではないだろうか。ブルックナーの交響曲には様々な楽想が溢れている。ある旋律が突如出現したかと思えば、すぐに違う旋律が現れ、自由に、大きな弧を描いて波打つ。それらはお互いにつながりがなさそうにみえるが、有機的に連鎖することによって時に神韻縹渺たる響きを生み出す。こういう配剤は、シューベルトが得意としていたことでもあった。19世紀後半にも、「ブルックナーは我々の時代のシューベルトである」と指摘した人がいる。これは交響曲第4番「ロマンティック」の初演後に書かれた評で、執筆者はエドゥアルト・クレムザー。この評を読んだ時、私は我が意を得たりと思ったものだ。
交響曲第7番は、1881年9月23日から1883年9月5日にかけて作曲された。初演は1884年12月30日、ライプツィヒ市立歌劇場で、若きアルトゥール・ニキシュが指揮を務めた。
初演にこぎつけるまで、師のために尽力したのがヨーゼフ・シャルクである。シャルクは当初ゲヴァントハウスの指揮者、カール・ライネッケに指揮してもらうつもりでいたが、理解を得られず、かつてヴァイオリン奏者としてブルックナーの交響曲第2番の演奏をしたことがあるニキシュに初演を依頼した。ニキシュは第7番の楽譜を見て、音楽的内容に驚嘆し、初演を快諾したという。この朗報を受けたブルックナーは、ニキシュに感謝の手紙を送っている。
「あなたは今私を救うことができる、そして、ありがたいことに、救おうという気持ちのある唯一の人です」
初演は圧倒的な成功に終わり、しばらくの間、拍手が鳴り止まなかった。交響曲第4番で作曲家として認められたブルックナーだが、その名声はまだ限られた範囲のものでしかなかった。彼が真に栄光を勝ち取るのは第7番によってである。当時、ブルックナーはすでに60歳になっていた。
60歳の出世作だが、その楽想には年齢相応の枯れた味わいはなく、それよりもみずみずしさと輝かしさ、そして深みのある美しさをたたえている。その霊感に満ちた楽想の交錯と有機的な統合感は、既述したように、シューベルトを思わせるものがある。
第1楽章はアレグロ・モデラート。弦のトレモロによる「ブルックナー開始」から、仰ぎたくなるほど荘厳なコーダまで、性格の異なる楽想が明滅し、随所で波動を呼び起こすが、散漫な印象を与えない。第2楽章はブルックナーが書いた最も美しいアダージョのひとつで、彼はこれをワーグナーの死を予感しながら書いた。コーダの「葬送音楽」は、ワーグナーの訃報に接した後に書き加えられたという。第3楽章はアグレッシヴで勢いに満ちたスケルツォ。この主題は、雄鶏の鳴き声から着想を得て書かれたものである。第4楽章のフィナーレは、第1楽章冒頭の主題から派生した楽句で始まる。以後、調性の移り変わりを経て、展開部を通過。再現部は第3主題、第2主題、第1主題の順で構成されている。ただ、この落ち着きのない終楽章については、批判的な声も少なくない。ブルックナーの交響曲のフィナーレにしては軽い、というのだ。たしかに、第1楽章と第2楽章の重量感と比べると、そういう批判が出るのも無理はない。
録音では、1967年のロヴロ・フォン・マタチッチとチェコ・フィルによる演奏が大変美しい。とくに第1楽章は絶品で、それぞれの楽器の音色に内側から膨らむような生気を感じる。オイゲン・ヨッフムが晩年にロイヤル・コンセルトヘボウを率いて来日した時のライヴ音源も素晴らしい(映像も残っている)。身を包むようなスケール感と、どこまでも続く崇高な響きーーブルックナー演奏のひとつの理想をステージで実現した例といえる。ヘルベルト・フォン・カラヤンにとって最後の録音となった1989年の演奏は、第1楽章のコーダの降り注ぐような音響にまず耳を奪われるが、カラヤンの特性が発揮されているのは第3楽章。ほかの指揮者では、細かなリズムの処理がぎこちなかったり、渋滞しているように感じられるところも、カラヤンの手にかかるときれいに解消される。簡単にやっているようにすら聞こえるから、かえって驚異である。カール・シューリヒト、ハーグ・フィルによる1964年の録音は、過去に絶賛されてきた名盤。オーケストラは弱いが、それでも、この素朴で味わい深いブルックナーに愛着を覚える人は多いだろう。
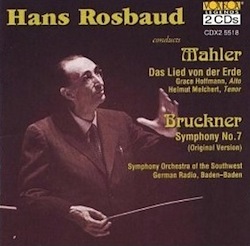 ハインツ・レーグナーが1983年にベルリン交響楽団を指揮した演奏は、大言壮語しない美学に貫かれている。スケール感たっぷりに音を響かせることだけがブルックナー演奏の在り方ではないのだ。ハンス・ロスバウト、南西ドイツ放送交響楽団の組み合わせによる演奏は終楽章が名演。この作品のアキレス腱といわれる楽章に明晰なメスを入れ、崇高な歌を引き出している。ほかに、カルロ・マリア・ジュリーニがフィルハーモニア管弦楽団を指揮した1982年のライヴ音源、エドゥアルト・ファン・ベイヌム、コンセルトヘボウによる1953年の録音も一聴の価値がある。
ハインツ・レーグナーが1983年にベルリン交響楽団を指揮した演奏は、大言壮語しない美学に貫かれている。スケール感たっぷりに音を響かせることだけがブルックナー演奏の在り方ではないのだ。ハンス・ロスバウト、南西ドイツ放送交響楽団の組み合わせによる演奏は終楽章が名演。この作品のアキレス腱といわれる楽章に明晰なメスを入れ、崇高な歌を引き出している。ほかに、カルロ・マリア・ジュリーニがフィルハーモニア管弦楽団を指揮した1982年のライヴ音源、エドゥアルト・ファン・ベイヌム、コンセルトヘボウによる1953年の録音も一聴の価値がある。
【関連サイト】
ブルックナー:交響曲第7番(CD)

「ひと言でいえば、ワーグナーの劇的様式を交響曲に移しかえたものである」
これは交響曲第8番に向けられた批評だが、以後、ブルックナーのシンフォニーを「ワーグナーの楽劇の交響曲版」と解する人が増えてしまった。『ヘンゼルとグレーテル』の作曲家、フンパーディンクは、そういう見方に対してはっきりと疑問を呈している。
「私たちにとって不可解なのは、人々がアントン・ブルックナーについて、ワーグナーの芸術原理を交響曲に移しかえたと語っていることである。実際は、ワーグナー・チューバと大胆な和声進行の使用は外面的なものにすぎないし、ワーグナーの芸術とはなんら関わるものではない」
ブルックナーに最も近い作曲家とは誰か。それはワーグナーではなく、シューベルトではないだろうか。ブルックナーの交響曲には様々な楽想が溢れている。ある旋律が突如出現したかと思えば、すぐに違う旋律が現れ、自由に、大きな弧を描いて波打つ。それらはお互いにつながりがなさそうにみえるが、有機的に連鎖することによって時に神韻縹渺たる響きを生み出す。こういう配剤は、シューベルトが得意としていたことでもあった。19世紀後半にも、「ブルックナーは我々の時代のシューベルトである」と指摘した人がいる。これは交響曲第4番「ロマンティック」の初演後に書かれた評で、執筆者はエドゥアルト・クレムザー。この評を読んだ時、私は我が意を得たりと思ったものだ。
交響曲第7番は、1881年9月23日から1883年9月5日にかけて作曲された。初演は1884年12月30日、ライプツィヒ市立歌劇場で、若きアルトゥール・ニキシュが指揮を務めた。
初演にこぎつけるまで、師のために尽力したのがヨーゼフ・シャルクである。シャルクは当初ゲヴァントハウスの指揮者、カール・ライネッケに指揮してもらうつもりでいたが、理解を得られず、かつてヴァイオリン奏者としてブルックナーの交響曲第2番の演奏をしたことがあるニキシュに初演を依頼した。ニキシュは第7番の楽譜を見て、音楽的内容に驚嘆し、初演を快諾したという。この朗報を受けたブルックナーは、ニキシュに感謝の手紙を送っている。
「あなたは今私を救うことができる、そして、ありがたいことに、救おうという気持ちのある唯一の人です」
初演は圧倒的な成功に終わり、しばらくの間、拍手が鳴り止まなかった。交響曲第4番で作曲家として認められたブルックナーだが、その名声はまだ限られた範囲のものでしかなかった。彼が真に栄光を勝ち取るのは第7番によってである。当時、ブルックナーはすでに60歳になっていた。
60歳の出世作だが、その楽想には年齢相応の枯れた味わいはなく、それよりもみずみずしさと輝かしさ、そして深みのある美しさをたたえている。その霊感に満ちた楽想の交錯と有機的な統合感は、既述したように、シューベルトを思わせるものがある。
第1楽章はアレグロ・モデラート。弦のトレモロによる「ブルックナー開始」から、仰ぎたくなるほど荘厳なコーダまで、性格の異なる楽想が明滅し、随所で波動を呼び起こすが、散漫な印象を与えない。第2楽章はブルックナーが書いた最も美しいアダージョのひとつで、彼はこれをワーグナーの死を予感しながら書いた。コーダの「葬送音楽」は、ワーグナーの訃報に接した後に書き加えられたという。第3楽章はアグレッシヴで勢いに満ちたスケルツォ。この主題は、雄鶏の鳴き声から着想を得て書かれたものである。第4楽章のフィナーレは、第1楽章冒頭の主題から派生した楽句で始まる。以後、調性の移り変わりを経て、展開部を通過。再現部は第3主題、第2主題、第1主題の順で構成されている。ただ、この落ち着きのない終楽章については、批判的な声も少なくない。ブルックナーの交響曲のフィナーレにしては軽い、というのだ。たしかに、第1楽章と第2楽章の重量感と比べると、そういう批判が出るのも無理はない。
録音では、1967年のロヴロ・フォン・マタチッチとチェコ・フィルによる演奏が大変美しい。とくに第1楽章は絶品で、それぞれの楽器の音色に内側から膨らむような生気を感じる。オイゲン・ヨッフムが晩年にロイヤル・コンセルトヘボウを率いて来日した時のライヴ音源も素晴らしい(映像も残っている)。身を包むようなスケール感と、どこまでも続く崇高な響きーーブルックナー演奏のひとつの理想をステージで実現した例といえる。ヘルベルト・フォン・カラヤンにとって最後の録音となった1989年の演奏は、第1楽章のコーダの降り注ぐような音響にまず耳を奪われるが、カラヤンの特性が発揮されているのは第3楽章。ほかの指揮者では、細かなリズムの処理がぎこちなかったり、渋滞しているように感じられるところも、カラヤンの手にかかるときれいに解消される。簡単にやっているようにすら聞こえるから、かえって驚異である。カール・シューリヒト、ハーグ・フィルによる1964年の録音は、過去に絶賛されてきた名盤。オーケストラは弱いが、それでも、この素朴で味わい深いブルックナーに愛着を覚える人は多いだろう。
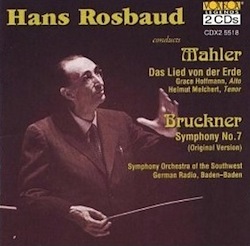
(阿部十三)
【関連サイト】
ブルックナー:交響曲第7番(CD)
アントン・ブルックナー
[1824.9.4-1896.10.11]
交響曲第7番 ホ長調
【お薦めディスク】(掲載ジャケット:上から)
チェコ・フィルハーモニー管弦楽団
ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮
録音:1967年3月
南西ドイツ放送交響楽団
ハンス・ロスバウト指揮
録音:1959年
[1824.9.4-1896.10.11]
交響曲第7番 ホ長調
【お薦めディスク】(掲載ジャケット:上から)
チェコ・フィルハーモニー管弦楽団
ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮
録音:1967年3月
南西ドイツ放送交響楽団
ハンス・ロスバウト指揮
録音:1959年
月別インデックス
- January 2026 [1]
- November 2025 [1]
- September 2025 [1]
- July 2025 [1]
- March 2025 [1]
- February 2025 [1]
- January 2025 [1]
- December 2024 [1]
- November 2024 [1]
- October 2024 [1]
- September 2024 [1]
- August 2024 [1]
- July 2024 [1]
- May 2024 [1]
- April 2024 [1]
- March 2024 [1]
- January 2024 [1]
- December 2023 [1]
- November 2023 [1]
- October 2023 [1]
- September 2023 [1]
- July 2023 [1]
- June 2023 [1]
- May 2023 [1]
- March 2023 [1]
- January 2023 [1]
- December 2022 [1]
- October 2022 [1]
- September 2022 [1]
- August 2022 [1]
- July 2022 [1]
- May 2022 [1]
- March 2022 [1]
- February 2022 [1]
- December 2021 [1]
- November 2021 [1]
- October 2021 [1]
- September 2021 [1]
- July 2021 [1]
- June 2021 [1]
- May 2021 [1]
- March 2021 [1]
- February 2021 [1]
- December 2020 [1]
- November 2020 [1]
- October 2020 [1]
- July 2020 [1]
- June 2020 [1]
- May 2020 [1]
- April 2020 [1]
- February 2020 [1]
- January 2020 [1]
- December 2019 [1]
- October 2019 [1]
- September 2019 [2]
- August 2019 [1]
- June 2019 [1]
- April 2019 [1]
- March 2019 [1]
- February 2019 [1]
- December 2018 [1]
- November 2018 [1]
- October 2018 [1]
- September 2018 [1]
- July 2018 [1]
- June 2018 [1]
- April 2018 [1]
- March 2018 [2]
- February 2018 [1]
- December 2017 [5]
- November 2017 [1]
- October 2017 [1]
- September 2017 [1]
- August 2017 [1]
- June 2017 [1]
- May 2017 [2]
- April 2017 [2]
- February 2017 [1]
- January 2017 [2]
- November 2016 [2]
- September 2016 [2]
- August 2016 [2]
- July 2016 [1]
- June 2016 [1]
- May 2016 [1]
- April 2016 [1]
- February 2016 [2]
- January 2016 [1]
- December 2015 [1]
- November 2015 [2]
- October 2015 [1]
- September 2015 [2]
- August 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- May 2015 [1]
- April 2015 [1]
- February 2015 [2]
- January 2015 [1]
- December 2014 [1]
- November 2014 [2]
- October 2014 [1]
- September 2014 [1]
- August 2014 [2]
- July 2014 [1]
- June 2014 [2]
- May 2014 [2]
- April 2014 [1]
- March 2014 [2]
- February 2014 [2]
- January 2014 [2]
- December 2013 [1]
- November 2013 [2]
- October 2013 [2]
- September 2013 [1]
- August 2013 [2]
- July 2013 [2]
- June 2013 [2]
- May 2013 [2]
- March 2013 [2]
- February 2013 [1]
- January 2013 [2]
- December 2012 [2]
- November 2012 [1]
- October 2012 [2]
- September 2012 [1]
- August 2012 [1]
- July 2012 [3]
- June 2012 [1]
- May 2012 [2]
- April 2012 [2]
- March 2012 [2]
- February 2012 [3]
- January 2012 [2]
- December 2011 [2]
- November 2011 [2]
- October 2011 [2]
- September 2011 [3]
- August 2011 [2]
- July 2011 [3]
- June 2011 [4]
- May 2011 [4]
- April 2011 [5]
- March 2011 [5]
- February 2011 [4]