
ベルク 歌劇『ヴォツェック』
2014.04.11
「人間は深い淵だ。底をのぞくと目が回るようだ」
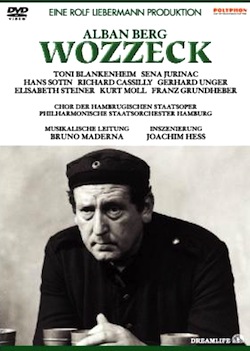 アルバン・ベルクの歌劇『ヴォツェック』は1914年に着手され、幾度かの中断を経て1922年に完成した。台本のベースとなっているのは、23歳で夭折した天才劇作家ゲオルク・ビューヒナーの『ヴォイツェック』。この舞台を観たベルクが、オペラ化するために自ら筆をとったのである。
アルバン・ベルクの歌劇『ヴォツェック』は1914年に着手され、幾度かの中断を経て1922年に完成した。台本のベースとなっているのは、23歳で夭折した天才劇作家ゲオルク・ビューヒナーの『ヴォイツェック』。この舞台を観たベルクが、オペラ化するために自ら筆をとったのである。
ビューヒナーの劇は、実際にあった出来事から着想を得ている。1821年6月21日、精神状態に異常を来していた(と思われる)貧しい兵士ヨハン・クリスティアン・ヴォイツェックが愛人を殺害した事件である。劇は未完に終わり、断片的な形で遺ったが、今でも『ダントンの死』と共にビューヒナーの代表作として知られている。なお、劇中では、主人公の名前は「フランツ・ヴォイツェック」、ベルクのオペラでは「フランツ・ヴォツェック」となっている。
ベルクはこの劇をオペラ化するにあたり、断片を15場にまとめ、5場ずつ3幕の構成に編集した。さらに驚くべきことに、全15場に異なる音楽形式を与えながら、それらが有機的に移行するように工夫を凝らし、ばらついた印象が生じないように配慮した。そのような手法をとったことについて、ベルク自身は「音楽的変化を得るため、また、ワーグナー以来慣例となってきた性格描写によって多くの場面を通作する手法を避けるため」と述べている。
彼が紡いだ15の音楽形式は次のようなものである。
第1幕「5つの性格的小品」
第1場「組曲」、第2場「3つの和音によるラプソディ」、第3場「軍隊行進曲、子守唄」、第4場「パッサカリア」、第5場「アンダンテ・アフェットゥオーゾ・クワジ・ロンド」
第2幕「5楽章の交響曲」
第1場「ソナタ楽章」、第2場「3つの主題によるインヴェンションとフーガ」、第3場「ラルゴ」、第4場「スケルツォ」、第5場「序奏とロンド・マルツィアーレ」
第3幕「6つのインヴェンション」
第1場「1つの主題によるインヴェンション」、第2場「H音によるインヴェンション」、第3場「1つのリズムによるインヴェンション」、第4場「六音和音によるインヴェンション」、管弦楽の間奏曲「1つの調性によるインヴェンション」、第5場「8分音符によるインヴェンション」
『ヴォツェック』は十二音技法、無調音楽、調性音楽、古典的な形式を融合させたオペラで、ここには「音楽的感性ーー音楽的連関ーーを現実化するためにどうしても必要と思われる音以外、1音たりとも、1パートたりともよけいなものがない」(テオドール・W・アドルノ)。兵役や病気や別仕事で中断を余儀なくされながら、このような作品を書き上げることが出来たベルクの異常な才能と強い意思には驚嘆するほかない。
話の内容は、観る者の心理の襞をかき乱すような悲劇である。かつて床屋だった兵士フランツ・ヴォツェックは、内縁の妻マリーとの間に子供をもうけているが、教会で洗礼を受けさせていないため非難される。ヴォツェックの日常は惨めで、過酷な労働と貧乏暮らしに加え、大尉にはこき使われ、医者には人体実験の道具にされ、精神状態が危うくなっている。フリーメイスンが何かを企んでいるとか、地面が揺れるといった錯覚を起こして取り乱すこともある。そんな中、マリーが鼓手長と浮気し、動転したヴォツェックはマリーを刺殺。凶器のナイフを池に投げるが、「あそこでは近すぎて誰かに見つかる」と危惧し、ナイフを探そうとして池に入り、最後には溺れ死ぬ。
なんとも救いのない話で、まともな人間は一人も出てこない。「まとも」という言葉自体が虚ろなもの、無意味なものに感じられる。劇中、「人間は深い淵だ。底をのぞくと目が回るようだ」という台詞があるが、まさにその暗い底をのぞいているような気分にさせられる。目に見えない枷をはめられ、「人間の本性の中にある、避けることの出来ない凶暴な力」(ゲオルク・ビューヒナー)に蓋をし、激しい抑圧を受けて己を失うヴォツェックのことを、誰も赤の他人とは思えないだろう。
オペラは髭剃りの場面からはじまり、次に薮を刈る場面に移行する。劇中のヴォツェックの仕事は、刃物のイメージと密接に結びついている。精神状態の不安定な人間が刃物を扱う危うさ。その刃物はまもなく殺人の凶器へと転じる。ひとつのイメージを変容させる構成は、巧みとしかいいようがない。
冒頭に出てくる旋律がベートーヴェンの「田園」の主題に似ているのも面白い。まるで「田舎に到着したときの愉快な感情の目ざめ」が裏返しにされたような印象がある。第3幕第2場、マリーを刺殺した後の「ロ音」のクレッシェンドも音楽的見せ場の一つ。それまであちこちに漂っていた「ロ音」の不吉な妖気が集まり、徐々に巨大化して爆発する。この瞬間にベルクの緻密な作曲技法のエッセンスが詰まっている。
世界初演は1925年12月14日に行われ、大成功を収めた。指揮を務めたのは、当時ベルリン国立歌劇場の音楽監督だったエーリヒ・クライバーである。妨害工作も行われたが、それを吹き飛ばすほどの喝采が起こった。1928年、ベルクは「オペラの問題」という題でこのように書いている。
「私は『ヴォツェック』を作曲することでオペラという芸術形態を改革しようなどとは夢にも思っていなかった」
一方で、作品に対する自信も表明している。
「このオペラの中に見出される音楽形式について、それらがいかに厳格に論理的に構築されているか、細部に至るまでいかに技術的に精巧に作られているかを知っていただけたらと思う。......しかもひとたび幕が開くや、最後の幕がおりる瞬間まで、観客の中の誰一人として様々なフーガやインヴェンション、組曲やソナタの楽章、変奏曲やパッサカリアのことなど気が付かないーー誰一人としてヴォツェックの個人的な運命から広がり出て行くこのオペラのイデー以外のものによって満たされることはないのである。そのことにーー私は成功したーーと信じている!」
結果的にこのオペラは、ワーグナー以降、真に新しい芸術として認められた。あのピエール・ブーレーズもこんな風に評している。
「『ヴォツェック』はオペラそのものの総括であり、おそらく『ヴォツェック』をもってこのジャンルの歴史が最終的に幕を閉じたのである。このような作品の後では、劇音楽は全く新しい表現形式を探さねばならないように思われる」
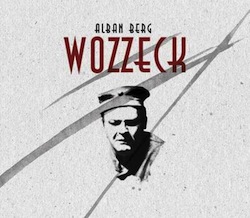 エーリヒ・クライバー、ディミトリ・ミトロプーロス、カール・ベーム、ピエール・ブーレーズ、カルロス・クライバー、ヘルベルト・ケーゲルが指揮した音源が遺っているので、鑑賞アイテムには困らないが、まずお薦めしたいのは、ロルフ・リーバーマン・プロの映像作品である。ブルーノ・マデルナ指揮、バイエルン・フィルによる演奏で、トニ・ブランケンハイムがヴォツェック役を、セーナ・ユリナッチがマリー役を演じている。何の希望も生命力も感じられないブランケンハイムの表情が良いし、殺伐とした映像も作品の雰囲気に合っている。
エーリヒ・クライバー、ディミトリ・ミトロプーロス、カール・ベーム、ピエール・ブーレーズ、カルロス・クライバー、ヘルベルト・ケーゲルが指揮した音源が遺っているので、鑑賞アイテムには困らないが、まずお薦めしたいのは、ロルフ・リーバーマン・プロの映像作品である。ブルーノ・マデルナ指揮、バイエルン・フィルによる演奏で、トニ・ブランケンハイムがヴォツェック役を、セーナ・ユリナッチがマリー役を演じている。何の希望も生命力も感じられないブランケンハイムの表情が良いし、殺伐とした映像も作品の雰囲気に合っている。
【関連サイト】
ベルク:歌劇『ヴォツェック』(CD)
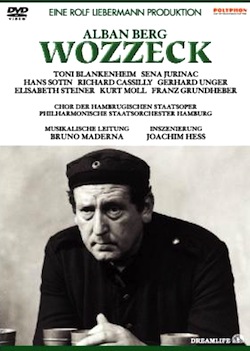
ビューヒナーの劇は、実際にあった出来事から着想を得ている。1821年6月21日、精神状態に異常を来していた(と思われる)貧しい兵士ヨハン・クリスティアン・ヴォイツェックが愛人を殺害した事件である。劇は未完に終わり、断片的な形で遺ったが、今でも『ダントンの死』と共にビューヒナーの代表作として知られている。なお、劇中では、主人公の名前は「フランツ・ヴォイツェック」、ベルクのオペラでは「フランツ・ヴォツェック」となっている。
ベルクはこの劇をオペラ化するにあたり、断片を15場にまとめ、5場ずつ3幕の構成に編集した。さらに驚くべきことに、全15場に異なる音楽形式を与えながら、それらが有機的に移行するように工夫を凝らし、ばらついた印象が生じないように配慮した。そのような手法をとったことについて、ベルク自身は「音楽的変化を得るため、また、ワーグナー以来慣例となってきた性格描写によって多くの場面を通作する手法を避けるため」と述べている。
彼が紡いだ15の音楽形式は次のようなものである。
第1幕「5つの性格的小品」
第1場「組曲」、第2場「3つの和音によるラプソディ」、第3場「軍隊行進曲、子守唄」、第4場「パッサカリア」、第5場「アンダンテ・アフェットゥオーゾ・クワジ・ロンド」
第2幕「5楽章の交響曲」
第1場「ソナタ楽章」、第2場「3つの主題によるインヴェンションとフーガ」、第3場「ラルゴ」、第4場「スケルツォ」、第5場「序奏とロンド・マルツィアーレ」
第3幕「6つのインヴェンション」
第1場「1つの主題によるインヴェンション」、第2場「H音によるインヴェンション」、第3場「1つのリズムによるインヴェンション」、第4場「六音和音によるインヴェンション」、管弦楽の間奏曲「1つの調性によるインヴェンション」、第5場「8分音符によるインヴェンション」
『ヴォツェック』は十二音技法、無調音楽、調性音楽、古典的な形式を融合させたオペラで、ここには「音楽的感性ーー音楽的連関ーーを現実化するためにどうしても必要と思われる音以外、1音たりとも、1パートたりともよけいなものがない」(テオドール・W・アドルノ)。兵役や病気や別仕事で中断を余儀なくされながら、このような作品を書き上げることが出来たベルクの異常な才能と強い意思には驚嘆するほかない。
話の内容は、観る者の心理の襞をかき乱すような悲劇である。かつて床屋だった兵士フランツ・ヴォツェックは、内縁の妻マリーとの間に子供をもうけているが、教会で洗礼を受けさせていないため非難される。ヴォツェックの日常は惨めで、過酷な労働と貧乏暮らしに加え、大尉にはこき使われ、医者には人体実験の道具にされ、精神状態が危うくなっている。フリーメイスンが何かを企んでいるとか、地面が揺れるといった錯覚を起こして取り乱すこともある。そんな中、マリーが鼓手長と浮気し、動転したヴォツェックはマリーを刺殺。凶器のナイフを池に投げるが、「あそこでは近すぎて誰かに見つかる」と危惧し、ナイフを探そうとして池に入り、最後には溺れ死ぬ。
なんとも救いのない話で、まともな人間は一人も出てこない。「まとも」という言葉自体が虚ろなもの、無意味なものに感じられる。劇中、「人間は深い淵だ。底をのぞくと目が回るようだ」という台詞があるが、まさにその暗い底をのぞいているような気分にさせられる。目に見えない枷をはめられ、「人間の本性の中にある、避けることの出来ない凶暴な力」(ゲオルク・ビューヒナー)に蓋をし、激しい抑圧を受けて己を失うヴォツェックのことを、誰も赤の他人とは思えないだろう。
オペラは髭剃りの場面からはじまり、次に薮を刈る場面に移行する。劇中のヴォツェックの仕事は、刃物のイメージと密接に結びついている。精神状態の不安定な人間が刃物を扱う危うさ。その刃物はまもなく殺人の凶器へと転じる。ひとつのイメージを変容させる構成は、巧みとしかいいようがない。
冒頭に出てくる旋律がベートーヴェンの「田園」の主題に似ているのも面白い。まるで「田舎に到着したときの愉快な感情の目ざめ」が裏返しにされたような印象がある。第3幕第2場、マリーを刺殺した後の「ロ音」のクレッシェンドも音楽的見せ場の一つ。それまであちこちに漂っていた「ロ音」の不吉な妖気が集まり、徐々に巨大化して爆発する。この瞬間にベルクの緻密な作曲技法のエッセンスが詰まっている。
世界初演は1925年12月14日に行われ、大成功を収めた。指揮を務めたのは、当時ベルリン国立歌劇場の音楽監督だったエーリヒ・クライバーである。妨害工作も行われたが、それを吹き飛ばすほどの喝采が起こった。1928年、ベルクは「オペラの問題」という題でこのように書いている。
「私は『ヴォツェック』を作曲することでオペラという芸術形態を改革しようなどとは夢にも思っていなかった」
一方で、作品に対する自信も表明している。
「このオペラの中に見出される音楽形式について、それらがいかに厳格に論理的に構築されているか、細部に至るまでいかに技術的に精巧に作られているかを知っていただけたらと思う。......しかもひとたび幕が開くや、最後の幕がおりる瞬間まで、観客の中の誰一人として様々なフーガやインヴェンション、組曲やソナタの楽章、変奏曲やパッサカリアのことなど気が付かないーー誰一人としてヴォツェックの個人的な運命から広がり出て行くこのオペラのイデー以外のものによって満たされることはないのである。そのことにーー私は成功したーーと信じている!」
結果的にこのオペラは、ワーグナー以降、真に新しい芸術として認められた。あのピエール・ブーレーズもこんな風に評している。
「『ヴォツェック』はオペラそのものの総括であり、おそらく『ヴォツェック』をもってこのジャンルの歴史が最終的に幕を閉じたのである。このような作品の後では、劇音楽は全く新しい表現形式を探さねばならないように思われる」
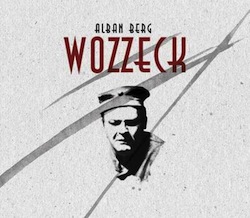
明晰な音響でスコアを浮き彫りにするピエール・ブーレーズ盤も、『ヴォツェック』の構造を知る上で外せない演奏である。それよりも不穏で、暗くて熱く、骨身にしみる演奏が好みの人には、ヴォツェックの生々しい心理の流れを汲み取ったヘルベルト・ケーゲル盤が向いている。
(阿部十三)
【関連サイト】
ベルク:歌劇『ヴォツェック』(CD)
アルバン・ベルク
[1885.2.9-1935.12.24]
歌劇『ヴォツェック』
【お薦めディスク】(掲載ジャケット:上から)
トニ・ブランケンハイム、セーナ・ユリナッチ
リチャード・カッシリー、ゲアハルト・ウンガー
ハンス・ゾーティン、エリザベート・シュタイナー
ブルーノ・マデルナ指揮
バイエルン・フィルハーモニー管弦楽団
収録:1970年
テオ・アダム、ギゼラ・シュレーター
ライナー・ゴルトベルク、ホルスト・ヒースターマン
コンラート・ルップ、ギゼラ・ポール
ヘルベルト・ケーゲル指揮
ライプツィヒ放送交響楽団
録音:1973年(ライヴ)
[1885.2.9-1935.12.24]
歌劇『ヴォツェック』
【お薦めディスク】(掲載ジャケット:上から)
トニ・ブランケンハイム、セーナ・ユリナッチ
リチャード・カッシリー、ゲアハルト・ウンガー
ハンス・ゾーティン、エリザベート・シュタイナー
ブルーノ・マデルナ指揮
バイエルン・フィルハーモニー管弦楽団
収録:1970年
テオ・アダム、ギゼラ・シュレーター
ライナー・ゴルトベルク、ホルスト・ヒースターマン
コンラート・ルップ、ギゼラ・ポール
ヘルベルト・ケーゲル指揮
ライプツィヒ放送交響楽団
録音:1973年(ライヴ)
月別インデックス
- January 2026 [1]
- November 2025 [1]
- September 2025 [1]
- July 2025 [1]
- March 2025 [1]
- February 2025 [1]
- January 2025 [1]
- December 2024 [1]
- November 2024 [1]
- October 2024 [1]
- September 2024 [1]
- August 2024 [1]
- July 2024 [1]
- May 2024 [1]
- April 2024 [1]
- March 2024 [1]
- January 2024 [1]
- December 2023 [1]
- November 2023 [1]
- October 2023 [1]
- September 2023 [1]
- July 2023 [1]
- June 2023 [1]
- May 2023 [1]
- March 2023 [1]
- January 2023 [1]
- December 2022 [1]
- October 2022 [1]
- September 2022 [1]
- August 2022 [1]
- July 2022 [1]
- May 2022 [1]
- March 2022 [1]
- February 2022 [1]
- December 2021 [1]
- November 2021 [1]
- October 2021 [1]
- September 2021 [1]
- July 2021 [1]
- June 2021 [1]
- May 2021 [1]
- March 2021 [1]
- February 2021 [1]
- December 2020 [1]
- November 2020 [1]
- October 2020 [1]
- July 2020 [1]
- June 2020 [1]
- May 2020 [1]
- April 2020 [1]
- February 2020 [1]
- January 2020 [1]
- December 2019 [1]
- October 2019 [1]
- September 2019 [2]
- August 2019 [1]
- June 2019 [1]
- April 2019 [1]
- March 2019 [1]
- February 2019 [1]
- December 2018 [1]
- November 2018 [1]
- October 2018 [1]
- September 2018 [1]
- July 2018 [1]
- June 2018 [1]
- April 2018 [1]
- March 2018 [2]
- February 2018 [1]
- December 2017 [5]
- November 2017 [1]
- October 2017 [1]
- September 2017 [1]
- August 2017 [1]
- June 2017 [1]
- May 2017 [2]
- April 2017 [2]
- February 2017 [1]
- January 2017 [2]
- November 2016 [2]
- September 2016 [2]
- August 2016 [2]
- July 2016 [1]
- June 2016 [1]
- May 2016 [1]
- April 2016 [1]
- February 2016 [2]
- January 2016 [1]
- December 2015 [1]
- November 2015 [2]
- October 2015 [1]
- September 2015 [2]
- August 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- May 2015 [1]
- April 2015 [1]
- February 2015 [2]
- January 2015 [1]
- December 2014 [1]
- November 2014 [2]
- October 2014 [1]
- September 2014 [1]
- August 2014 [2]
- July 2014 [1]
- June 2014 [2]
- May 2014 [2]
- April 2014 [1]
- March 2014 [2]
- February 2014 [2]
- January 2014 [2]
- December 2013 [1]
- November 2013 [2]
- October 2013 [2]
- September 2013 [1]
- August 2013 [2]
- July 2013 [2]
- June 2013 [2]
- May 2013 [2]
- March 2013 [2]
- February 2013 [1]
- January 2013 [2]
- December 2012 [2]
- November 2012 [1]
- October 2012 [2]
- September 2012 [1]
- August 2012 [1]
- July 2012 [3]
- June 2012 [1]
- May 2012 [2]
- April 2012 [2]
- March 2012 [2]
- February 2012 [3]
- January 2012 [2]
- December 2011 [2]
- November 2011 [2]
- October 2011 [2]
- September 2011 [3]
- August 2011 [2]
- July 2011 [3]
- June 2011 [4]
- May 2011 [4]
- April 2011 [5]
- March 2011 [5]
- February 2011 [4]