
チャイコフスキー 交響曲第6番「悲愴」
2015.10.07
「悲愴」と「幻想」
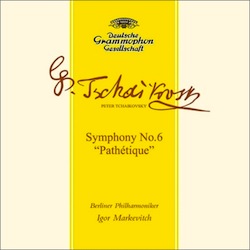 チャイコフスキーの「悲愴」は1893年に書かれた最後の交響曲である。初演は1893年10月28日、作曲者自身の指揮によって行われた。「悲愴」という言葉に込められた真意は分かっていないが、弟のモデストが伝えるところによると、初演の後、作品の標題をどうするか、兄から相談を受けたという。モデストがまず提案したのは「悲劇的」だったが、却下された。次に「悲愴」はどうかと言うと、チャイコフスキーは満足して受け入れた。
チャイコフスキーの「悲愴」は1893年に書かれた最後の交響曲である。初演は1893年10月28日、作曲者自身の指揮によって行われた。「悲愴」という言葉に込められた真意は分かっていないが、弟のモデストが伝えるところによると、初演の後、作品の標題をどうするか、兄から相談を受けたという。モデストがまず提案したのは「悲劇的」だったが、却下された。次に「悲愴」はどうかと言うと、チャイコフスキーは満足して受け入れた。
この有名なエピソードには誤りがある。そもそもモデストが提案したとされているのは「パテティーチェスキー」であり、これには「悲愴」の意味は含まれていない。ロシア語の辞書には「熱情的」「感動させる」と記されている。
それ以上に引っかかるのは、作曲を終えた9月の時点で、チャイコフスキーが出版者のピョートル・ユルゲンソン宛に「『第6悲愴交響曲』よりも『交響曲第6番 悲愴』とすべきだと思います」と書き送っていることである。その手紙でつかわれているのは、「悲壮な」「強く感動させる」を意味するフランス語「Pathétique」だ。つまり、チャイコフスキーは作品の標題をまずフランス語でイメージしていた。
もしモデストの証言に真実があるとするならば、ロシア語に置き換える際、どうすべきか相談されたのだろう。作曲者自身、「Pathétique」よりも「パテティーチェスキー」の方が良いと思ったのかもしれない。その手で「パテティーチェスカヤ(パテティーチェスキーの女性形)」とロシア語で自筆譜に記しているのも事実なのだ。
おそらくここには「悲愴」にとどまらない意味を持たせようという意図が込められている。が、初演から9日後の11月6日にチャイコフスキーが急逝したこともあり、交響曲第6番はまさに「悲愴」と呼ぶにふさわしい作品として浸透した。彼が旅先のフランスで構想を練りながら感動して泣いていたことや、作曲している間、「きっと私の最上の作となるだろう」と考えていたこと、作曲の筆をおいた後に「私の一生で一番良い曲だ」と断言していたことが、すべて辞世のムードにつながるエピソードとして紹介されるパターンも、すでに定石である。最新作を最高傑作とする芸術家は珍しくないと思うのだが。
第1楽章はアダージョで始まり、暗いため息の序奏が流れる。その後速度を増して第1主題の切迫感を印象付けると、ゆるやかなテンポになり、美しい第2主題が登場する。チャイコフスキーの作品の中でもとくに親しまれている名旋律の一つだ。この第2主題が繰り返され、木管がppppppの弱音にまで抑えられたところで、激情的な展開部へと突入する。嵐のような音楽は緩急をつけながら進行し、最終的にカタストロフのごとき終焉を迎える。やがて第2主題が回想され、静かに繰り返された後、あたかも死を弔うかのようにトランペットがやわらかく響き、木管がその旋律を受け継ぎ、穏やかに消えてゆく。
第2楽章は4分の5拍子の舞曲で、ニ長調からロ短調に転ずる中間部でメランコリックな影が広がる。不安定な揺らぎを感じさせる叙情の世界である。第3楽章は「タランテラ」の主題で始まり、楽器の音色で徐々に色付けされて厚みを持った後、行進曲風になる。この過程が繰り返されると、輝かしくも峻烈な響きが炸裂し、ほとんど威嚇的な面持ちでパレードが展開され、オーケストラが雪崩のような勢いで突進する。第4楽章はアダージョで、冒頭から悲痛な旋律が嘆息のように漏れる。中間部は感傷的な雰囲気に覆われるが、徐々に嘆きの色が濃くなり、慟哭に達する。しかしタム・タムが鳴ると、葛藤する気力も失ったかのように暗い淵に沈み込み、全曲が閉じられる。
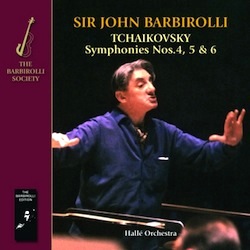 異様なまでに高潮する第3楽章を軸にして考えると、「悲愴」の構成にはどこかベルリオーズの「幻想交響曲」の影響を匂わせるものがある。第1楽章はただの悲劇という以上に死の宣告であり、その終わり方は宿命に抵抗することへの諦めを示している。とするならば、第2楽章は死への舞曲であり、第3楽章は「幻想」の「断頭台への行進」に相当する。もしくは、第1楽章は死そのものであり、第3楽章は「サバトの夜の夢」だ。いずれにしても第4楽章は、人生の最期を描いたものではなく、死してなお闇の中でたゆたう魂の嘆きを描いた音楽のように聴こえる。ちなみに、若い頃チャイコフスキーはベルリオーズと会っており、フランス語でスピーチして、この大作曲家を讃えている。「幻想」がベルリオーズの輝かしいキャリアの始まりを告げるものだったのに対し、「悲愴」がチャイコフスキーのキャリアの終わりを告げるものになったのは皮肉だが、両者に共通して言えるのは、これは芸術的昇華であって現実的な遺言の代替物ではないということだ。「悲愴」を聴いて、死を連想しないという人がいても別におかしくはない。なお、余談として、マーラーが最後に完成させた交響曲第9番も、「悲愴」のようにアダージョで静かに終わる。マーラー自身は大して意識していなかったかもしれないが、影響関係にあるとみてよいだろう。
異様なまでに高潮する第3楽章を軸にして考えると、「悲愴」の構成にはどこかベルリオーズの「幻想交響曲」の影響を匂わせるものがある。第1楽章はただの悲劇という以上に死の宣告であり、その終わり方は宿命に抵抗することへの諦めを示している。とするならば、第2楽章は死への舞曲であり、第3楽章は「幻想」の「断頭台への行進」に相当する。もしくは、第1楽章は死そのものであり、第3楽章は「サバトの夜の夢」だ。いずれにしても第4楽章は、人生の最期を描いたものではなく、死してなお闇の中でたゆたう魂の嘆きを描いた音楽のように聴こえる。ちなみに、若い頃チャイコフスキーはベルリオーズと会っており、フランス語でスピーチして、この大作曲家を讃えている。「幻想」がベルリオーズの輝かしいキャリアの始まりを告げるものだったのに対し、「悲愴」がチャイコフスキーのキャリアの終わりを告げるものになったのは皮肉だが、両者に共通して言えるのは、これは芸術的昇華であって現実的な遺言の代替物ではないということだ。「悲愴」を聴いて、死を連想しないという人がいても別におかしくはない。なお、余談として、マーラーが最後に完成させた交響曲第9番も、「悲愴」のようにアダージョで静かに終わる。マーラー自身は大して意識していなかったかもしれないが、影響関係にあるとみてよいだろう。
名録音のディスコグラフィーにもふれておく。まずその録音史を辿る上で、ウィレム・メンゲルベルクとコンセルトヘボウ管、ヴィルヘルム・フルトヴェングラーとベルリン・フィルの組み合わせによる1930年代の録音を無視することはできない。いわば戦前の双璧で、音質は古いが今なお心揺さぶり深い感銘をもたらす名演奏だ。その後、1950年代に入ると、エーリヒ・クライバーとパリ音楽院管、イーゴリ・マルケヴィッチとベルリン・フィル(超名演)、ジャン・マルティノンとウィーン・フィルの録音が登場し、高く評価された。1959年に録音され、お蔵入りとなっていたフェレンツ・フリッチャイ指揮、ベルリン放送響の演奏が1990年代に発売されると、これも絶賛された。ただ、フリッチャイ自身は第1楽章の録り直しを希望し、それを果たせぬまま世を去っている。
そして1960年、エフゲニー・ムラヴィンスキー指揮によるレニングラード・フィルの演奏が録音される。アンサンブルは鉄壁そのもの。当時聴いた人が受けた衝撃はいかばかりだったろう。しかも鋭く堅牢であるばかりでなく、フレージングは精緻かつ優美。今でも最高の「悲愴」と評する人が絶えないのも分かる。同じくソ連の勇将キリル・コンドラシンがモスクワ・フィルを指揮した1965年頃の録音は、ムラヴィンスキーに比べるとこまやかさに欠けるが、そのかわり心臓を圧迫するような緊張感がみなぎっている。心臓に悪い「悲愴」とでも言おうか。1971年にはヘルベルト・フォン・カラヤンがベルリン・フィルを指揮し、ムラヴィンスキーやコンドラシンとは異なるアプローチで作品の魅力を掘り下げることに成功している。カラヤンはとにかく「悲愴」に執着した人で、映像やライヴ録音を含めるとその数は10種類を超える。私は特にカラヤンの「悲愴」を好んでいるわけではないが、第3楽章になると、この指揮者ならではの華麗さや豪壮さが恋しくなる。
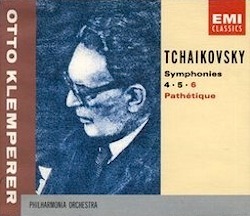 最新録音にこだわる必要は全くない。ここまで挙げてきた録音を聴けば、この作品の魅力は十分すぎるほど伝わる。ただ、私自身が最も圧倒された「悲愴」は、ジョン・バルビローリ指揮、ハレ管の演奏(1958年録音)だ。といっても、レニングラード・フィルやベルリン・フィルのように完璧な技術に裏打ちされた強靭かつ緊密なアンサンブルが聴けるわけではない。表現の仕方が素晴らしいのだ。とりわけ第1楽章の展開部を聴くと、作曲当時のチャイコフスキーを支配していた暗い情熱が自分に乗り移ってくるような感覚に陥り、ぞっとさせられる。テンポのとりかた、ティンパニによる効果の上げかた、各パートの音色の配合の絶妙さなど、アゴーギクとアーティキュレーションを駆使しながら、逃れようのない巨大な深淵を形成している。オットー・クレンペラーがフィルハーモニア管を指揮したもの(1961年録音)も、バルビローリとは違う意味で、聴き手を圧倒する。テンポは概して遅く、作品全体の細かな音の構造が透けて見えるほど明晰で、感傷に酔ったり衝動に駆られたりすることは一切ない。かといって無機的なのではなく、ゴツゴツしているわけでもなく、むしろその逆で、標題性に左右されない純然たる音楽の美が抽出されている。これほどまでに純器楽的で美しい「チャイコフスキーの交響曲第6番」はない。汗と涙と垢のついたメロディーの印象を、一度耳から洗い落とす演奏だ。音質も良く、1961年に録音されたものとはとても思えない。
最新録音にこだわる必要は全くない。ここまで挙げてきた録音を聴けば、この作品の魅力は十分すぎるほど伝わる。ただ、私自身が最も圧倒された「悲愴」は、ジョン・バルビローリ指揮、ハレ管の演奏(1958年録音)だ。といっても、レニングラード・フィルやベルリン・フィルのように完璧な技術に裏打ちされた強靭かつ緊密なアンサンブルが聴けるわけではない。表現の仕方が素晴らしいのだ。とりわけ第1楽章の展開部を聴くと、作曲当時のチャイコフスキーを支配していた暗い情熱が自分に乗り移ってくるような感覚に陥り、ぞっとさせられる。テンポのとりかた、ティンパニによる効果の上げかた、各パートの音色の配合の絶妙さなど、アゴーギクとアーティキュレーションを駆使しながら、逃れようのない巨大な深淵を形成している。オットー・クレンペラーがフィルハーモニア管を指揮したもの(1961年録音)も、バルビローリとは違う意味で、聴き手を圧倒する。テンポは概して遅く、作品全体の細かな音の構造が透けて見えるほど明晰で、感傷に酔ったり衝動に駆られたりすることは一切ない。かといって無機的なのではなく、ゴツゴツしているわけでもなく、むしろその逆で、標題性に左右されない純然たる音楽の美が抽出されている。これほどまでに純器楽的で美しい「チャイコフスキーの交響曲第6番」はない。汗と涙と垢のついたメロディーの印象を、一度耳から洗い落とす演奏だ。音質も良く、1961年に録音されたものとはとても思えない。
【関連サイト】
Tchaikovsky-Research
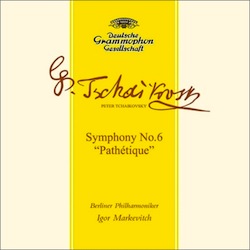
この有名なエピソードには誤りがある。そもそもモデストが提案したとされているのは「パテティーチェスキー」であり、これには「悲愴」の意味は含まれていない。ロシア語の辞書には「熱情的」「感動させる」と記されている。
それ以上に引っかかるのは、作曲を終えた9月の時点で、チャイコフスキーが出版者のピョートル・ユルゲンソン宛に「『第6悲愴交響曲』よりも『交響曲第6番 悲愴』とすべきだと思います」と書き送っていることである。その手紙でつかわれているのは、「悲壮な」「強く感動させる」を意味するフランス語「Pathétique」だ。つまり、チャイコフスキーは作品の標題をまずフランス語でイメージしていた。
もしモデストの証言に真実があるとするならば、ロシア語に置き換える際、どうすべきか相談されたのだろう。作曲者自身、「Pathétique」よりも「パテティーチェスキー」の方が良いと思ったのかもしれない。その手で「パテティーチェスカヤ(パテティーチェスキーの女性形)」とロシア語で自筆譜に記しているのも事実なのだ。
おそらくここには「悲愴」にとどまらない意味を持たせようという意図が込められている。が、初演から9日後の11月6日にチャイコフスキーが急逝したこともあり、交響曲第6番はまさに「悲愴」と呼ぶにふさわしい作品として浸透した。彼が旅先のフランスで構想を練りながら感動して泣いていたことや、作曲している間、「きっと私の最上の作となるだろう」と考えていたこと、作曲の筆をおいた後に「私の一生で一番良い曲だ」と断言していたことが、すべて辞世のムードにつながるエピソードとして紹介されるパターンも、すでに定石である。最新作を最高傑作とする芸術家は珍しくないと思うのだが。
第1楽章はアダージョで始まり、暗いため息の序奏が流れる。その後速度を増して第1主題の切迫感を印象付けると、ゆるやかなテンポになり、美しい第2主題が登場する。チャイコフスキーの作品の中でもとくに親しまれている名旋律の一つだ。この第2主題が繰り返され、木管がppppppの弱音にまで抑えられたところで、激情的な展開部へと突入する。嵐のような音楽は緩急をつけながら進行し、最終的にカタストロフのごとき終焉を迎える。やがて第2主題が回想され、静かに繰り返された後、あたかも死を弔うかのようにトランペットがやわらかく響き、木管がその旋律を受け継ぎ、穏やかに消えてゆく。
第2楽章は4分の5拍子の舞曲で、ニ長調からロ短調に転ずる中間部でメランコリックな影が広がる。不安定な揺らぎを感じさせる叙情の世界である。第3楽章は「タランテラ」の主題で始まり、楽器の音色で徐々に色付けされて厚みを持った後、行進曲風になる。この過程が繰り返されると、輝かしくも峻烈な響きが炸裂し、ほとんど威嚇的な面持ちでパレードが展開され、オーケストラが雪崩のような勢いで突進する。第4楽章はアダージョで、冒頭から悲痛な旋律が嘆息のように漏れる。中間部は感傷的な雰囲気に覆われるが、徐々に嘆きの色が濃くなり、慟哭に達する。しかしタム・タムが鳴ると、葛藤する気力も失ったかのように暗い淵に沈み込み、全曲が閉じられる。
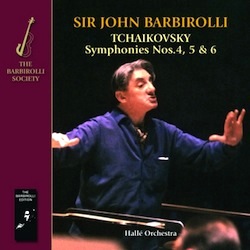
名録音のディスコグラフィーにもふれておく。まずその録音史を辿る上で、ウィレム・メンゲルベルクとコンセルトヘボウ管、ヴィルヘルム・フルトヴェングラーとベルリン・フィルの組み合わせによる1930年代の録音を無視することはできない。いわば戦前の双璧で、音質は古いが今なお心揺さぶり深い感銘をもたらす名演奏だ。その後、1950年代に入ると、エーリヒ・クライバーとパリ音楽院管、イーゴリ・マルケヴィッチとベルリン・フィル(超名演)、ジャン・マルティノンとウィーン・フィルの録音が登場し、高く評価された。1959年に録音され、お蔵入りとなっていたフェレンツ・フリッチャイ指揮、ベルリン放送響の演奏が1990年代に発売されると、これも絶賛された。ただ、フリッチャイ自身は第1楽章の録り直しを希望し、それを果たせぬまま世を去っている。
そして1960年、エフゲニー・ムラヴィンスキー指揮によるレニングラード・フィルの演奏が録音される。アンサンブルは鉄壁そのもの。当時聴いた人が受けた衝撃はいかばかりだったろう。しかも鋭く堅牢であるばかりでなく、フレージングは精緻かつ優美。今でも最高の「悲愴」と評する人が絶えないのも分かる。同じくソ連の勇将キリル・コンドラシンがモスクワ・フィルを指揮した1965年頃の録音は、ムラヴィンスキーに比べるとこまやかさに欠けるが、そのかわり心臓を圧迫するような緊張感がみなぎっている。心臓に悪い「悲愴」とでも言おうか。1971年にはヘルベルト・フォン・カラヤンがベルリン・フィルを指揮し、ムラヴィンスキーやコンドラシンとは異なるアプローチで作品の魅力を掘り下げることに成功している。カラヤンはとにかく「悲愴」に執着した人で、映像やライヴ録音を含めるとその数は10種類を超える。私は特にカラヤンの「悲愴」を好んでいるわけではないが、第3楽章になると、この指揮者ならではの華麗さや豪壮さが恋しくなる。
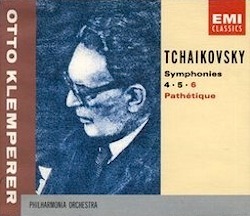
(阿部十三)
【関連サイト】
Tchaikovsky-Research
ピョートル・イリイッチ・チャイコフスキー
[1840.5.7-1893.11.6]
交響曲第6番 ロ短調 作品74
【お薦めの録音】(掲載ジャケット:上から)
イーゴリ・マルケヴィチ指揮
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
録音:1953年12月
ジョン・バルビローリ指揮
ハレ管弦楽団
録音:1958年8月
オットー・クレンペラー指揮
フィルハーモニア管弦楽団
録音:1961年10月
[1840.5.7-1893.11.6]
交響曲第6番 ロ短調 作品74
【お薦めの録音】(掲載ジャケット:上から)
イーゴリ・マルケヴィチ指揮
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
録音:1953年12月
ジョン・バルビローリ指揮
ハレ管弦楽団
録音:1958年8月
オットー・クレンペラー指揮
フィルハーモニア管弦楽団
録音:1961年10月
月別インデックス
- January 2026 [1]
- November 2025 [1]
- September 2025 [1]
- July 2025 [1]
- March 2025 [1]
- February 2025 [1]
- January 2025 [1]
- December 2024 [1]
- November 2024 [1]
- October 2024 [1]
- September 2024 [1]
- August 2024 [1]
- July 2024 [1]
- May 2024 [1]
- April 2024 [1]
- March 2024 [1]
- January 2024 [1]
- December 2023 [1]
- November 2023 [1]
- October 2023 [1]
- September 2023 [1]
- July 2023 [1]
- June 2023 [1]
- May 2023 [1]
- March 2023 [1]
- January 2023 [1]
- December 2022 [1]
- October 2022 [1]
- September 2022 [1]
- August 2022 [1]
- July 2022 [1]
- May 2022 [1]
- March 2022 [1]
- February 2022 [1]
- December 2021 [1]
- November 2021 [1]
- October 2021 [1]
- September 2021 [1]
- July 2021 [1]
- June 2021 [1]
- May 2021 [1]
- March 2021 [1]
- February 2021 [1]
- December 2020 [1]
- November 2020 [1]
- October 2020 [1]
- July 2020 [1]
- June 2020 [1]
- May 2020 [1]
- April 2020 [1]
- February 2020 [1]
- January 2020 [1]
- December 2019 [1]
- October 2019 [1]
- September 2019 [2]
- August 2019 [1]
- June 2019 [1]
- April 2019 [1]
- March 2019 [1]
- February 2019 [1]
- December 2018 [1]
- November 2018 [1]
- October 2018 [1]
- September 2018 [1]
- July 2018 [1]
- June 2018 [1]
- April 2018 [1]
- March 2018 [2]
- February 2018 [1]
- December 2017 [5]
- November 2017 [1]
- October 2017 [1]
- September 2017 [1]
- August 2017 [1]
- June 2017 [1]
- May 2017 [2]
- April 2017 [2]
- February 2017 [1]
- January 2017 [2]
- November 2016 [2]
- September 2016 [2]
- August 2016 [2]
- July 2016 [1]
- June 2016 [1]
- May 2016 [1]
- April 2016 [1]
- February 2016 [2]
- January 2016 [1]
- December 2015 [1]
- November 2015 [2]
- October 2015 [1]
- September 2015 [2]
- August 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- May 2015 [1]
- April 2015 [1]
- February 2015 [2]
- January 2015 [1]
- December 2014 [1]
- November 2014 [2]
- October 2014 [1]
- September 2014 [1]
- August 2014 [2]
- July 2014 [1]
- June 2014 [2]
- May 2014 [2]
- April 2014 [1]
- March 2014 [2]
- February 2014 [2]
- January 2014 [2]
- December 2013 [1]
- November 2013 [2]
- October 2013 [2]
- September 2013 [1]
- August 2013 [2]
- July 2013 [2]
- June 2013 [2]
- May 2013 [2]
- March 2013 [2]
- February 2013 [1]
- January 2013 [2]
- December 2012 [2]
- November 2012 [1]
- October 2012 [2]
- September 2012 [1]
- August 2012 [1]
- July 2012 [3]
- June 2012 [1]
- May 2012 [2]
- April 2012 [2]
- March 2012 [2]
- February 2012 [3]
- January 2012 [2]
- December 2011 [2]
- November 2011 [2]
- October 2011 [2]
- September 2011 [3]
- August 2011 [2]
- July 2011 [3]
- June 2011 [4]
- May 2011 [4]
- April 2011 [5]
- March 2011 [5]
- February 2011 [4]