
ブリジット・フォンテーヌ 『ラジオのように』
2012.05.02
ブリジット・フォンテーヌ
『ラジオのように』
1969年作品
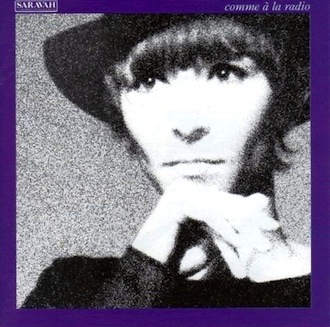 ノン・ジャンル、ミクスト・ミュージックなんていう言葉がまだ無かった時代に、大胆にジャンルの壁を越境してこそ得られる音楽がある、ということを強烈に意識させられたのが、このブリジット・フォンテーヌの1969年のアルバム『ラジオのように』だった。
ノン・ジャンル、ミクスト・ミュージックなんていう言葉がまだ無かった時代に、大胆にジャンルの壁を越境してこそ得られる音楽がある、ということを強烈に意識させられたのが、このブリジット・フォンテーヌの1969年のアルバム『ラジオのように』だった。
小鳥のさえずりにも似た歌声に絡み付くように調和と破綻を繰り返しながら腕利きのジャズ・プレイヤーたちが音を付加していく。現代ポピュラー音楽の魅力とは、いかに多くの要因を混ぜ合わせるかというところにこそあるのだろう、とつくづく思わせる演奏が続いていくアルバムである。
40年以上も前のフランスで発売されたこのアルバム、そしてブリジットというアーティストの魅力は、時を越え、現代の人々も刺激しまくる。1998年にはステレオラブとの共演シングル、そして2001年に発表されたアルバム『Kekeland』では、ソニック・ユースからアーチー・シェップまで含む多彩な顔ぶれを従え、少しも衰えることのないクリエイティヴィティを聴かせ、『ラジオのように』が伝説でも過去でもないことを再確認させてくれたのだった。
主人公のブリジット・フォンテーヌは、1939年6月フランスのブルターニュ地方のモルレーという町に生まれた。幼い頃からファンタジー小説や芝居を好む少女だったという。1957年にソルボンヌ大学に入学するが、彼女が夢中になったのはジャズと演劇で、前衛演劇を志すようになる。と同時にギターを手にクラブでも歌うようになった彼女の特異な個性は際立ち、ジャック・ブレルら大物シャンソン歌手を見出した名プロデューサー(ジャック・カネッティ)に認められ、1966年にレコード・デビューを飾っている。
同じく彼女の才能に魅せられたのが、前衛演劇家ジャック・イジュランで、彼と組んだパフォーマンスやデュエット・アルバムは大衆性とは無縁ながら、一部で熱烈な称賛を浴びることになる。1960年代後半に世界中で爆発したサブ・カルチャーの表現域拡大の流れとも一致したのだろう。そして、それらの作品に積極的な反応を示した一人が、映画『男と女』の大ヒットでスターになっていたピエール・バルーだった。
歌手・俳優・作曲家とマルチ・タレントぶりを見せていた彼が、自身の芸術的な野心を存分に展開するために設立したレコード・レーベルが、日本でも人気の高いサラヴァで、第1弾として1968年にリリースしたのが、アルバム『ブリジット・フォンテーヌは...』だった。シャンソンの伝統を備えながら、シュールな終末感を漂わすアルバムには、すでに既成の世界に収まることのない姿勢が見えている。
さらに創造意欲を燃やす彼女に、最良の共犯者たちが現れる。アート・アンサンブル・オブ・シカゴ(以下AEC)だ。オーネット・コールマン、セシル・テイラー、アルバート・アイラーといった人々が果敢に切り開いたフリー・ジャズを、さらにアグレッシヴな姿勢で追究したこのグループは、1960年代半ばシカゴで結成された。レスター・ボウイ、ロスコー・ミッチェルらが何種類もの楽器を操りながら、時に演劇性も含んだパフォーマンスを展開。ジャズの新時代を牽引した彼らだが、とくに1969年から約2年にわたってヨーロッパに滞在し、十数枚のアルバムを作った時代は充実した頃でもあった。
パリでブリジット、イジュランらが出演した前衛劇の音楽を担当したことから交友を深めた彼らが、自然に引き寄せられるように集まり生まれたのが『ラジオのように』であった。その魅力が集約されているのがタイトル曲で、AECと、ブリジットの公私のパートナーとなるアルジェリア人のパーカッショニスト、アレスキー・ベルセカムが複雑、自在にリズムを奏でる中、ブリジットが五月革命への情熱と虚無をあぶり出すように歌い綴っていく。
いまにも破綻しそうな歌は、軽やかなステップを踏みながら跳躍し、ギリギリのアンサンブルを描き出す。どこか醒めた呪術的な感触が、コケティッシュなブリジットの歌にぴったりと重なり、何とも魅惑的だ。ゴダールのモノクロ映画の風景が浮かんでは消えていったりもする。前衛的なアプローチであることは間違いないが、どこか人なつっこい彼女の歌声が、鋭い刃先のような表現に柔らかみを与えている。この鋭くもあたたかさを失わないところにも、『ラジオのように』がことのほか長年愛される秘密が隠されているのだろう。
アルバムには「短歌」と題されたトラックがあったりして日本人には親近感が持てるが、そのくせ演奏はアラブ/イスラム的な展開だったりするところも、誤解も含め、面白い。基本的には、アフリカン・リズムの濃厚なパーカッションとヴォイス、そしてフリー・ジャズを背景としながらも、アメリカのジャズ史まで俯瞰してみせるような音楽性を聴かせるAECの演奏によって展開されていくアルバムだが、過剰な言葉もなければ音楽的な装飾も、現代の耳からするととても少ない。
しかし、だからこそ断片的な言葉と、寓話的な世界を色づける音と音の間にパックリと空間が開き、その奥から思いがけない光景が次々と現れ、どんな音楽にも無い緊迫感を作り出すのである。それこそ、聴き手のイマジネーションが最高に刺激される瞬間と言ってもよい。多くの要素を持ったアーティストたちが、自分たちの表現を堅持しながら、他からインスパイアされたものに積極的に反応した結果、そういった刺激が生まれているのだ。
言いかえれば、ジャズ、シャンソン、ロックといったジャンル分けが全く無意味で、そんな呪縛から逃れたところにこそ、本当のスリルがあるというのを痛烈に証明したのがこのアルバムだったのである。その精神は、ソニック・ユースにまで伝わっているし、40年以上の月日が経ったというのに少しもその価値を下げてはいない。これを聴く前と後では、確実に音の聞こえる風景は変わるはずだ。
【関連サイト】
ブリジット・フォンテーヌ
サラヴァ
ブリジット・フォンテーヌ『ラジオのように』
『ラジオのように』
1969年作品
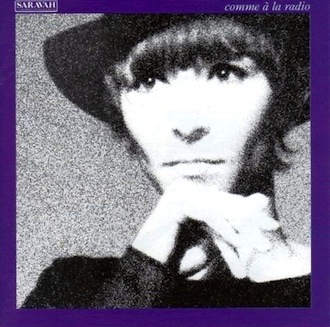
小鳥のさえずりにも似た歌声に絡み付くように調和と破綻を繰り返しながら腕利きのジャズ・プレイヤーたちが音を付加していく。現代ポピュラー音楽の魅力とは、いかに多くの要因を混ぜ合わせるかというところにこそあるのだろう、とつくづく思わせる演奏が続いていくアルバムである。
40年以上も前のフランスで発売されたこのアルバム、そしてブリジットというアーティストの魅力は、時を越え、現代の人々も刺激しまくる。1998年にはステレオラブとの共演シングル、そして2001年に発表されたアルバム『Kekeland』では、ソニック・ユースからアーチー・シェップまで含む多彩な顔ぶれを従え、少しも衰えることのないクリエイティヴィティを聴かせ、『ラジオのように』が伝説でも過去でもないことを再確認させてくれたのだった。
主人公のブリジット・フォンテーヌは、1939年6月フランスのブルターニュ地方のモルレーという町に生まれた。幼い頃からファンタジー小説や芝居を好む少女だったという。1957年にソルボンヌ大学に入学するが、彼女が夢中になったのはジャズと演劇で、前衛演劇を志すようになる。と同時にギターを手にクラブでも歌うようになった彼女の特異な個性は際立ち、ジャック・ブレルら大物シャンソン歌手を見出した名プロデューサー(ジャック・カネッティ)に認められ、1966年にレコード・デビューを飾っている。
同じく彼女の才能に魅せられたのが、前衛演劇家ジャック・イジュランで、彼と組んだパフォーマンスやデュエット・アルバムは大衆性とは無縁ながら、一部で熱烈な称賛を浴びることになる。1960年代後半に世界中で爆発したサブ・カルチャーの表現域拡大の流れとも一致したのだろう。そして、それらの作品に積極的な反応を示した一人が、映画『男と女』の大ヒットでスターになっていたピエール・バルーだった。
歌手・俳優・作曲家とマルチ・タレントぶりを見せていた彼が、自身の芸術的な野心を存分に展開するために設立したレコード・レーベルが、日本でも人気の高いサラヴァで、第1弾として1968年にリリースしたのが、アルバム『ブリジット・フォンテーヌは...』だった。シャンソンの伝統を備えながら、シュールな終末感を漂わすアルバムには、すでに既成の世界に収まることのない姿勢が見えている。
さらに創造意欲を燃やす彼女に、最良の共犯者たちが現れる。アート・アンサンブル・オブ・シカゴ(以下AEC)だ。オーネット・コールマン、セシル・テイラー、アルバート・アイラーといった人々が果敢に切り開いたフリー・ジャズを、さらにアグレッシヴな姿勢で追究したこのグループは、1960年代半ばシカゴで結成された。レスター・ボウイ、ロスコー・ミッチェルらが何種類もの楽器を操りながら、時に演劇性も含んだパフォーマンスを展開。ジャズの新時代を牽引した彼らだが、とくに1969年から約2年にわたってヨーロッパに滞在し、十数枚のアルバムを作った時代は充実した頃でもあった。
パリでブリジット、イジュランらが出演した前衛劇の音楽を担当したことから交友を深めた彼らが、自然に引き寄せられるように集まり生まれたのが『ラジオのように』であった。その魅力が集約されているのがタイトル曲で、AECと、ブリジットの公私のパートナーとなるアルジェリア人のパーカッショニスト、アレスキー・ベルセカムが複雑、自在にリズムを奏でる中、ブリジットが五月革命への情熱と虚無をあぶり出すように歌い綴っていく。
いまにも破綻しそうな歌は、軽やかなステップを踏みながら跳躍し、ギリギリのアンサンブルを描き出す。どこか醒めた呪術的な感触が、コケティッシュなブリジットの歌にぴったりと重なり、何とも魅惑的だ。ゴダールのモノクロ映画の風景が浮かんでは消えていったりもする。前衛的なアプローチであることは間違いないが、どこか人なつっこい彼女の歌声が、鋭い刃先のような表現に柔らかみを与えている。この鋭くもあたたかさを失わないところにも、『ラジオのように』がことのほか長年愛される秘密が隠されているのだろう。
アルバムには「短歌」と題されたトラックがあったりして日本人には親近感が持てるが、そのくせ演奏はアラブ/イスラム的な展開だったりするところも、誤解も含め、面白い。基本的には、アフリカン・リズムの濃厚なパーカッションとヴォイス、そしてフリー・ジャズを背景としながらも、アメリカのジャズ史まで俯瞰してみせるような音楽性を聴かせるAECの演奏によって展開されていくアルバムだが、過剰な言葉もなければ音楽的な装飾も、現代の耳からするととても少ない。
しかし、だからこそ断片的な言葉と、寓話的な世界を色づける音と音の間にパックリと空間が開き、その奥から思いがけない光景が次々と現れ、どんな音楽にも無い緊迫感を作り出すのである。それこそ、聴き手のイマジネーションが最高に刺激される瞬間と言ってもよい。多くの要素を持ったアーティストたちが、自分たちの表現を堅持しながら、他からインスパイアされたものに積極的に反応した結果、そういった刺激が生まれているのだ。
言いかえれば、ジャズ、シャンソン、ロックといったジャンル分けが全く無意味で、そんな呪縛から逃れたところにこそ、本当のスリルがあるというのを痛烈に証明したのがこのアルバムだったのである。その精神は、ソニック・ユースにまで伝わっているし、40年以上の月日が経ったというのに少しもその価値を下げてはいない。これを聴く前と後では、確実に音の聞こえる風景は変わるはずだ。
(大鷹俊一)
【関連サイト】
ブリジット・フォンテーヌ
サラヴァ
ブリジット・フォンテーヌ『ラジオのように』
『ラジオのように』収録曲
01. ラジオのように/02. 短歌2/03. 霧/04. 私は26才/05. 夏、夏/06. アンコール/07. レオ/08. 小馬/09. 短歌1/10. キャロル塔の駅長さんへの手紙
01. ラジオのように/02. 短歌2/03. 霧/04. 私は26才/05. 夏、夏/06. アンコール/07. レオ/08. 小馬/09. 短歌1/10. キャロル塔の駅長さんへの手紙
月別インデックス
- January 2026 [1]
- December 2025 [1]
- November 2025 [1]
- October 2025 [1]
- September 2025 [1]
- August 2025 [1]
- July 2025 [1]
- June 2025 [1]
- May 2025 [1]
- March 2025 [1]
- February 2025 [1]
- January 2025 [1]
- December 2024 [1]
- November 2024 [1]
- October 2024 [1]
- September 2024 [1]
- August 2024 [1]
- July 2024 [1]
- June 2024 [1]
- May 2024 [1]
- April 2024 [1]
- March 2024 [1]
- February 2024 [1]
- January 2024 [1]
- December 2023 [1]
- November 2023 [1]
- October 2023 [1]
- September 2023 [1]
- August 2023 [1]
- July 2023 [1]
- June 2023 [1]
- May 2023 [1]
- April 2023 [1]
- March 2023 [1]
- February 2023 [1]
- January 2023 [1]
- December 2022 [1]
- November 2022 [1]
- October 2022 [1]
- September 2022 [1]
- August 2022 [1]
- July 2022 [1]
- June 2022 [1]
- May 2022 [1]
- April 2022 [1]
- March 2022 [1]
- February 2022 [1]
- January 2022 [1]
- December 2021 [1]
- November 2021 [1]
- October 2021 [1]
- September 2021 [1]
- August 2021 [1]
- July 2021 [1]
- June 2021 [1]
- May 2021 [1]
- April 2021 [1]
- March 2021 [1]
- February 2021 [1]
- January 2021 [1]
- December 2020 [1]
- November 2020 [1]
- October 2020 [1]
- September 2020 [1]
- August 2020 [1]
- July 2020 [1]
- June 2020 [1]
- May 2020 [1]
- April 2020 [1]
- March 2020 [1]
- February 2020 [1]
- January 2020 [1]
- December 2019 [1]
- November 2019 [1]
- October 2019 [1]
- September 2019 [1]
- August 2019 [1]
- July 2019 [1]
- June 2019 [1]
- May 2019 [1]
- April 2019 [2]
- February 2019 [1]
- December 2018 [1]
- November 2018 [1]
- October 2018 [1]
- September 2018 [1]
- August 2018 [1]
- July 2018 [1]
- June 2018 [1]
- May 2018 [1]
- April 2018 [1]
- March 2018 [1]
- February 2018 [1]
- January 2018 [2]
- November 2017 [1]
- October 2017 [1]
- September 2017 [1]
- August 2017 [1]
- July 2017 [1]
- June 2017 [1]
- May 2017 [1]
- April 2017 [1]
- March 2017 [1]
- February 2017 [1]
- January 2017 [1]
- December 2016 [1]
- November 2016 [1]
- October 2016 [1]
- September 2016 [1]
- August 2016 [1]
- July 2016 [1]
- June 2016 [1]
- May 2016 [1]
- April 2016 [1]
- March 2016 [1]
- February 2016 [1]
- January 2016 [1]
- December 2015 [2]
- October 2015 [1]
- September 2015 [1]
- August 2015 [1]
- July 2015 [1]
- June 2015 [1]
- May 2015 [1]
- April 2015 [1]
- March 2015 [1]
- February 2015 [1]
- January 2015 [1]
- December 2014 [1]
- November 2014 [1]
- October 2014 [1]
- September 2014 [1]
- August 2014 [1]
- July 2014 [2]
- June 2014 [1]
- May 2014 [1]
- April 2014 [1]
- March 2014 [1]
- February 2014 [1]
- January 2014 [1]
- December 2013 [2]
- November 2013 [1]
- October 2013 [1]
- September 2013 [2]
- August 2013 [2]
- July 2013 [1]
- June 2013 [1]
- May 2013 [2]
- April 2013 [1]
- March 2013 [2]
- February 2013 [1]
- January 2013 [1]
- December 2012 [1]
- November 2012 [2]
- October 2012 [1]
- September 2012 [1]
- August 2012 [2]
- July 2012 [1]
- June 2012 [2]
- May 2012 [1]
- April 2012 [2]
- March 2012 [1]
- February 2012 [2]
- January 2012 [2]
- December 2011 [1]
- November 2011 [2]
- October 2011 [1]
- September 2011 [1]
- August 2011 [1]
- July 2011 [2]
- June 2011 [2]
- May 2011 [2]
- April 2011 [2]
- March 2011 [2]
- February 2011 [3]